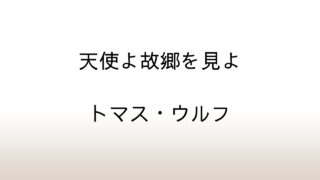林芙美子「風琴と魚の町」読了。
本作「風琴と魚の町」は、1931年(昭和6年)に書かれた短編小説である。
尾道で暮らした13歳の少女時代
主人公は、13歳の女の子である。
行商の両親と一緒に旅暮らしをしているが、尾道で汽車を降りた三人は、その町が気に入る。
貧しい暮らしゆえ、主人公の<まさこ>はいつでも腹を空かせているが、あまり食べ物をねだると母にビンタを張られる。
お腹いっぱいにモノを食べるということが、育ち盛りの少女にとって、何よりの憧れだったのだ。
座蒲団を二つに折って私の裾にさしあってはいると、父はこう云った。私は、白かまんまと云う言葉を聞くと、ポロポロと涙があふれた。「背丈が伸びる頃ちゅうて、あぎゃん食いたかものじゃろうかなア」(林芙美子「風琴と魚の町」)
父の行商もうまくいって、三人は尾道で暮らし始める。
そこは貧しい人たちが暮らす二階の部屋で、階下には五十位の夫婦者が住んでいた。
若い頃に船乗りだった階下のおじさんは、仕事で怪我をしてから働くことができない。
おばさんが内職で作る昆布巻きで生計を立てていたが、ある日、このおばさんが井戸の中へ落ちてしまう。
どうやら、おばさんは質屋へ向かおうとしていたところだったらしい。
尾道に暮らしに慣れた頃、まさこは小学校へ通い始める。
もっとも、学校では「オイチニイの新馬鹿大将の娘じゃ」といじめられた(オイチニイは父が行商で売っている薬の商品名)。
まさこは、魚屋の男の子が好きだった。
魚屋の前を通ったとき、男の子が魚をくれた。
あるいは、それが、まさこの初恋だったのかもしれない。
父が、どこからか美しい化粧水を仕入れてきた。
それは安価ではあったが、早く売ってしまわないと腐ると言われていたらしい。
間もなく、インチキな商売がバレて、父は警察に連れていかれた。
私は裏側へ廻って、水色のペンキ塗りの歪んだ窓へよじ登って下を覗いて見た。電気が煌々とついていた。部屋の隅に母が鼠よりも小さく私の眼に写った。父が、その母の前で、巡査にぴしぴしビンタを殴られていた。(林芙美子「風琴と魚の町」)
巡査に殴られながら、父は風琴を鳴らして歌を歌った。
それは、あの美しい化粧水を売るための宣伝歌であった。
貧乏な暮らしを美しく描く
本作は、貧しい少女時代の体験を回想した物語である。
行商暮らしの父と母に連れられて、主人公の少女は大変な苦労を強いられている。
本作の特徴は、困窮を極めるような生活なのに、境遇に対する恨みのようなものがまるで感じられないことである。
まるで貧乏だった暮らしが、楽しい経験であったかのように、爽やかに綴られている。
プロレタリア文学(例えば、佐多稲子「キャラメル工場から」)のような攻撃性がどこにもない。
貧しい暮らしを社会に転嫁することなく、自然体で受け入れているのだ。
爽やかに感じられるのは、詩情豊かな文章に由来するものだろう。
まさこが海で小便をする場面がある。
私は、あんまり長い小便にあいそをつかしながら、うんと力んで自分の股間を覗いてみた。白いプクプクした小山の向うに、空と船が逆さに写っていた。私は首筋が痛くなる程身を曲めた。白い小山の向うから霧を散らした尿(いばり)が、キラキラ光って桟橋をぬらしている。(林芙美子「風琴と魚の町」)
少女の小便の場面を美しく再現している原動力は、貧しい暮らしを美しく描いているものと、おそらく同じエネルギーであっただろう。
負を美しく表現することができる、それが、林芙美子という小説家だったのかもしれない。
そこには、人生を前向きに明るく生きていこうとする、たくましい生命力がある。
だから「風琴と魚の町」は、生き生きとした生命力に満ちた作品ということができるのである。
作品名:風琴と魚の町
著者:林芙美子
書名:風琴と魚の町・清貧の書
発行:1953/5/30
出版社:新潮文庫