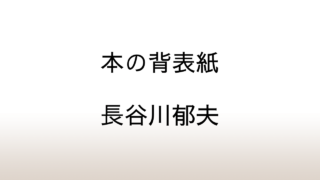和田芳恵「ひとつの文壇史」読了。
本作「ひとつの文壇史」は、「東京新聞」はじめ「中日新聞」「北海道新聞」などに発表され、1967年(昭和42年)7月に新潮社から刊行された回想録である。
この年、著者は61歳だった。
大衆雑誌『日の出』の創刊と大衆作家たち
和田芳恵は、中央大学法学部を卒業後、新潮社へ入社した人である。
最初『日本文学大辞典』の編集を担当した後で、大衆雑誌『日の出』の編集者となった。
だから、本作『ひとつの文壇史』は、大衆雑誌『日の出』の編集者が見た文壇の回顧録ということになる。
普通、文壇史と言えば純文学の作家が中心になるところ、そのため、本作では大衆文学の作家の名前が次々に登場する。
文壇史として、本書を新鮮と感じさせる理由の一つだろう。
和田芳恵は、昭和16年に新潮社を退社して作家へと転身しているから、この回想録は、昭和6年から昭和16年まで、つまり、戦前の大衆文学の世界を描いた物語ということができそうである。
大衆雑誌『日の出』が創刊した昭和7年8月当時、大衆雑誌といえば講談社の『キング』が圧倒的に人気だった時代で、新潮社の目標も、もちろん打倒『キング』にあった。
著者が最初に訪ねた作家の一人に長谷川海太郎がいる。
長谷川海太郎は、牧逸馬・林不忘・谷譲次と、一人で三つのペンネームを持つ流行作家だった。
『日の出』に発表する「都会の怪異 七時〇三分」の執筆中に、長谷川海太郎は急死した。
目を泣きはらした和子夫人から受取った原稿の最後の文字が、長谷川さんの体の重みをかけたように、原稿用紙に食い込んで、ぷつりと切れていた。(和田芳恵「ひとつの文壇史」)
あらかじめ、小説の筋書きを長谷川海太郎から聞いていた著者は、未完の部分を書き足して印刷へ送り込んだという。
作家と戦わなければならない編集者の厳しい立場について、触れられている部分も多い。
長谷川伸とは、頼んだ原稿を返したことからまずい関係になっていたし、山岡荘八に紹介された梶野悳三の作品を『日の出』に掲載するまでには、かなりの時間を要した。
「山岡のやつの気持ちがわかるような気がしたな。あの男は”日の出”から返された原稿をふところに入れて、家に帰る前におれのところへ寄り、よく屋台で飲んだものさ。そのあとで、和田の野郎とわめきながら、きっと屋台店を引っくりかえしたものだ」(和田芳恵「ひとつの文壇史」)
流行作家・山岡荘八が誕生するまでにも、人並ならぬ苦労のあったことが偲ばれる。
その山岡荘八は、久米正雄が書けないで困っていたとき、和田芳恵の依頼に応じて、穴埋めのための原稿を書いてくれたという。
この作品「折鶴」は、久米正雄の名前で『日の出』に発表された後、非常に高く評価され、「山岡さんは、『折鶴』を書いてから、急に作家的力量があがったことはたしかである」と、著者は振り返っている。
同時代を生きた編集者たちの姿を偲ぶ
作家の回想と同じくらいに、同時代の編集者の話がたくさん登場しているところも、本書の特徴の一つだろう。
文藝春秋の菊池寛が直木賞を創設したときの話がある。
「君、直木賞にだれか適当な人がいないかね、君」と、菊池寛さんが自動車が動きだすとすぐ、二人に早口に言った。私たちは、ほとんど、同時に「それは川口松太郎さんですよ」と答えた。(和田芳恵「ひとつの文壇史」)
このとき、一緒に同乗していたのは、講談社『講談倶楽部』の萱原宏一で、菊池寛は「そうだ、川口にしよう」と、その場で確言したという。
人気作家としては、吉川英治に関する思い出もいい。
吉川英治は興に乗ってくると、約束の枚数を越えて原稿を書き続けることが少なくなかった。
短編小説の注文なのに、中編小説としても終わりそうもない。締め切りがせまって、ぎりぎりになり、あわてた中島さんが駆けつけると、「いま、女と寝ている最中のようなものだ。途中から降りろといわれても、そう、急には降りられないよ」と答えて、吉川さんは、悠悠と名作を書きあげたそうである。(和田芳恵「ひとつの文壇史」)
<中島さん>とは、『冨士』初代編集長で、名編集者といわれた中島民千代のこと。
本書『ひとつの文壇史』は、戦前の出版史の一側面を綴った記録としても貴重なものだったと言えるだろう。
それにしても、普段、あまり大衆小説を読まないので、本書に登場する作家の名前には新鮮なものが多いが、本書で触れて、いずれ読んでみたいと思える作家も少なくなかった。
原稿料で協定を結んでいた木々高太郎と獅子文六、太宰治と若い読者の人気を二分していた高見順、中村地平との生活が破綻しかけていた真杉静枝、三上於菟吉と長谷川時雨の新居を夜な夜な訪れた近松秋江など、個性的な作家の話は強く印象に残る。
晩年の徳田秋声を支えた新潮社の働きについても、本書を読んで初めて知った。
編集部の「中の人」だったからこそ見えていた作家の姿も、きっと少なくないのだろう。
個人的自叙伝でありながら、そのまま一つの文壇史となっている点で、本作『ひとつの文壇史』は、やはり高い価値を持つ作品だと思った。
そして、昭和初期の大衆文学を、もっと読まなければならないな、とも。
書名:ひとつの文壇史
著者:和田芳恵
発行:1967/07/25
出版社:新潮社