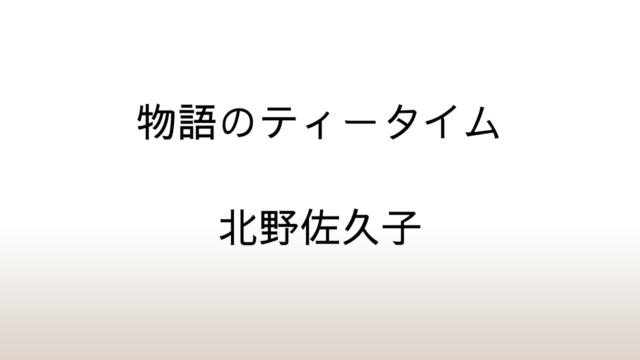今西祐行「一つの花」読了。
本作「一つの花」は、1956年(昭和31年)に泰光堂から刊行された童話集『そらのひつじかい』に収録されている短編小説である。
この年、著者は33歳だった。
童話集『そらのひつじかい』は、第六回児童文学者協会新人賞を受賞している。
国語の教科書に掲載された名作
本作「一つの花」は、初期の作品でありながら、今西祐行(いまにし すけゆき)の代表作の一つとして広く知られている。
その理由は、この短い物語が、国語の教科書に掲載されていることによるものだろう。
ちなみに、本作「一つの花」は、教育出版、光村図書、日本書籍の発行する小学四年生用の国語の教科書に掲載されていた。
「一つだけ、ちょうだい」というのは、ゆみ子のはっきり覚えた初めての言葉だった。
それは、日本がまだアメリカと戦争をしていた頃のことで、既に、国内の主要都市は、連合軍による激しい空襲を受けていた。
「町は、つぎつぎに焼かれて、灰になっていきました」とあるから、これは1945年(昭和20年)の話であることが分かる。
食べるもののない時代、ゆみ子は「一つだけ、ちょうだい」と言って、母親に食べ物をねだった。
「この子は、一生、みんなちょうだい、山ほどちょうだいといって、両手をだすことを知らずにすごすかもしれないね。……一つだけのいも、一つだけのにぎりめし、一つだけのかぼちゃの煮つけ……。みんな一つだけ。一つだけのよろこびさ。いや、よろこびなんて、一つだってもらえないかもしれないんだね。いったい、大きくなって、どんな子にそだつだろう」(今西祐行「一つの花」)
愛情とやりきれなさを込めて、父親は、ゆみ子を高い高いしてみせる。
戦争末期に子どもを育てていた父や母の、これは共通する思いだったのではないだろうか。
短い作品ながら、「いったい、大きくなって、どんな子にそだつだろう」という父の言葉は、物語の最終場面への伏線となっている。
家族の優しさのスパイラル
やがて、「あまりじょうぶでないゆみ子のおとうさん」も、戦争へ行かなければならない日がやってくる。
健康ではない人間を駆り出さなければならないくらい、日本の軍隊は切羽詰まっていたのだ(当然勝てるわけがない)。
戦地に向かう父を見送るため、ゆみ子は、母親におぶられて駅へと向かうが、父の大切な食糧(おにぎり)を、ゆみ子は何度も「一つだけちょうだい」と言って全部食べてしまう。
すっかり食べても、ゆみ子の空腹は収まらない。
この時代、子どもも大人も、人々はいつだって飢えていたのだ。
「一つだけ……。一つだけ……」と言って、ゆみ子は泣き出してしまう。
おとうさんは、プラットホームのはしっぽの、ごみすて場のようなところに、わすれさられたようにさいていた、コスモスの花を見つけたのです。あわててかえってきたおとうさんの手には、一りんのコスモスの花がありました。「ゆみ。さあ、一つだけあげよう。一つだけのお花、だいじにするんだよう……」(今西祐行「一つの花」)
父は戦場へ行き、それから十年が経過する。
大きく成長したゆみ子に父はない。
ゆみ子はおとうさんのかおをおぼえていません。自分におとうさんがあったことも、あるいは知らないのかもしれません。でも、いま、ゆみ子のとんとんぶきの小さな家は、コスモスの花でいっぱいにつつまれています。(今西祐行「一つの花」)
ゆみ子の家を包むコスモスの花が、父のくれたコスモスの花と関係があるのかどうか、それは分からない。
しかし、コスモスの花が、父の愛情を示す象徴となっていることは間違いないだろう。
ゆみ子の小さな家を包むたくさんのコスモスの花は、今は亡き父親の愛情そのものである。
「ミシンの音」は、内職をして家計を支えているゆみ子の母親を表現しているのかもしれない。
ゆみ子は、お母さんに代わって日曜日の昼食の準備をする優しい少女へと成長している。
父が「いったい、大きくなって、どんな子にそだつだろう」と考えた問いの答えが、この最終場面なのだ。
両親の愛情をたっぷりと注がれて育った女の子は、優しい少女へと成長している。
ここでは父を奪った戦争の悲惨さと同時に、家族の愛情の連鎖というものが描かれている。
むしろ、家族の優しさのスパイラルこそが、この物語の主題だったのではないだろうか。
厳しい戦争の時代でさえ、親は子どもに限りない愛情を捧げた。
その愛情を受け継ぐゆみ子もまた、自分の愛情を次の世代へと伝えていくことだろう。
作品名:一つの花
著者:今西祐行
書名:一つの花
発行:2005/10
出版社:ポプラ社