井伏鱒二「本日休診」読了。
本作「本日休診」は、1949年(昭和24年)から1950年(昭和25年)にかけて、「文藝春秋」に断続的に発表された短編連作である。
連載開始の年、著者は51歳だった。
単行本は、1950年(昭和25年)6月、文藝春秋社から刊行されている。
「本日休診」の病院を訪れる人たち
「三雲病院」は、蒲田駅前にある。
院長の<三雲伍助>は、まだ独身の若輩で、顧問をしている<三雲八春>先生の甥だった。
空襲で焼けた病院を戦後に再建したとき、八春先生は病院経営を伍助院長に任せたが、警察医をしていることなどもあって、相変わらず忙しく働いている。
開業一周年のとき、伍助院長は職員を連れて旅行に出かけた。
みんなを見送って、病院に「本日休診」の札を掛けると、留守番役の八春先生は「今日は一日中眠ってやろうか」などと考えている。
ところが、「本日休診」のはずの病院には、次から次へと訳アリの患者たちが押し寄せてきた、、、
この小説は、三雲病院を舞台に描かれる、戦後の下町物語である。
警察官と一緒にやって来た若い女性は、恋人を訪ねて大阪からやってきたところ、見知らぬ男に暴力で犯されてしまった。
八春先生は、怪我の具合や病気の感染の具合などを調べようとするが、女性は恥ずかしがって診察をさせない。
次にやって来た女性は、十六年前に病院が開院したときの一番最初の患者で、八春先生は、帝王切開でこの女の子どもを取り上げ、その上、子どもに名前まで付けてやった。
ところが、女は手術代も払わないうちに行方が分からなくなってしまった。
あのときの子どもが大きくなって、勘定を払いに行ってこいと、母親に言ったのだそうである。
蒲田駅の車庫にある電車で暮らしている男は、「なかなか子どもが生まれない」と、先生の往診を頼みにやってきた。
車庫の中にある、空襲で焼けた電車の中には、鉄道関係の人たちが生活していたのだ。
満足に代金も支払えないだろうと思われる貧しい人たちを相手に、八春先生は忙しく動き回っている。
六郷川の岸には、ところどころに砂礫運びの船がつないであって、船底の穴ぐらのようなところに人が寝起きして、そこを住宅がわりにしている家族もあった。
穴ぐらをのぞいて見ると、煎餅蒲団の端から、女の仰向いた顔と赤んぼの頭がのぞいていた。二畳間ぐらいの穴ぐらである。薄べりを敷いて、割合きれいに片づけてある。ベニヤ板で細工した嵌込戸棚もついている。夏蜜柑をそなえた小さな仏壇もある。吊ランプも見える。(井伏鱒二「本日休診」)
「本日休診」の一日は賑やかに過ぎて、そして「本日休診」の札を外した後も、八春先生は、やっぱり忙しく患者の相手をしているのだった。
焼け跡の中でしぶとく生きる日本人を描く
この小説の中では、誰もが大変な暮らしを強いられているが、陰鬱な感じはまったくない。
むしろ、からりとしていて、ユーモラスでさえある。
戦争を責めたり、境涯を嘆いたりすることもなく、ただ日常を精一杯に生きる人々の姿が、具体的に描かれているのだ。
人間観察の小説だと、僕は思った。
焼け跡のバラックや電車や船の中で暮らす人々の姿は、たくましくさえある。
井伏さんは、そこに日本人の明るい未来を見出していたのかもしれない。
細部に目を向けると、味わいのある言葉の一つ一つもいい。
どうしても注射してくれと懇願する麻薬中毒の患者に、内科担当の宇野医師は、言葉で説得する。
「では、納得が行ったね。よしんば、われわれ耄碌医者でも、場違いのことは嫌だ。人生は淋しいものだ。君、わかったね」と云うと、「わかります」と尻上がりに云う声がきこえた。(略)「ね、わかったね。ほんの小さな、毛のような細い細い銀色の針、何という悲しさ。それを何ミリか人体の皮膚に刺す。あるいは、それを思いとどまるという気持。ねえ君、あの感傷の気持、わかるだろうね」(井伏鱒二「本日休診」)
まるで、麻薬中毒だった太宰治を説得する井伏鱒二のような、言葉の臨場感がある。
台詞や文章の細かいところで楽しむことができるのも、井伏文学の醍醐味というものだろう。
ところで、この小説の主人公である<三雲八春>先生は、実在の警察医だった<南雲今朝雄>医師をモデルにしたものだそうである。
その医者は半ば狂気の坂口安吾の病気を治した人で、病気の安吾と同じ病室で一緒に暮しながら治療したそうだ。(井伏鱒二自選全集「覚え書」)
そう言えば、玉川上水で自殺した太宰の遺体を検視したのも、南雲先生だったということである。
作品名:本日休診
書名:井伏鱒二自選全集(第三巻)
著者:井伏鱒二
発行:1985/12/15
出版社:新潮社
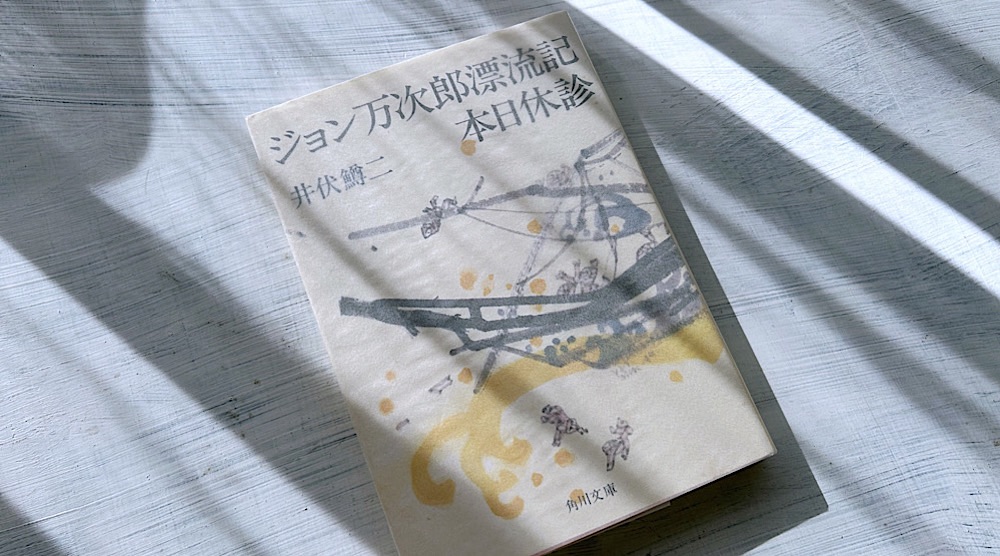
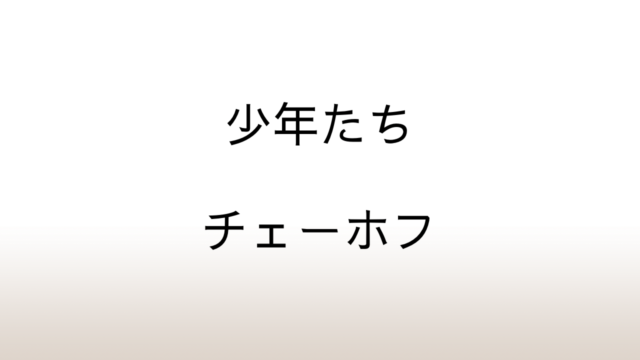




-150x150.jpg)









