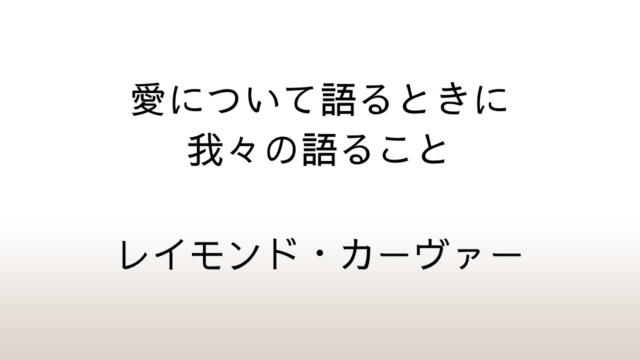川端康成「伊豆の踊子」読了。
本作「伊豆の踊子」は、1926年(大正15年)2月『文藝時代』に発表された短篇小説である。
この年、著者は26歳だった。
作品集としては、1927年(昭和2年)3月に金星堂から刊行された『伊豆の踊子』に収録されている。
14歳の少女に恋をした20歳の大学生の物語
本作「伊豆の踊子」は、14歳の少女に恋をした大学生(旧制高校生)の物語である。
孤児根性で歪んでいる自分の性格を矯正するため、伊豆地方へと旅に出た二十歳の<私>は、旅芸人の一座と道連れになる。
男は<栄吉(24)>一人で、あとは、栄吉の女房<千代子(19)>、栄吉の妹<薫(14)>、雇いの<百合子(17)>、それに千代子の母親(40代)と女ばかり。
この中で、<私(20)>は、一番年下の少女<薫(14)>に恋をしてしまう。
踊子は十七くらいに見えた。私には分らない古風の不思議な形に大きく髪を結っていた。それが卵形の凛々しい顔を非常に小さく見せながらも、美しく調和していた。(川端康成「伊豆の踊子」)
旅芸人の踊子だから、化粧で年齢をごまかしていたのかもしれない。
それでも、風呂に入ると、踊子が少女であることは一目瞭然だった。
仄暗い湯殿の奥から、突然裸の女が走り出して来たかと思うと、脱衣場の突鼻に川岸へ飛び下りそうな恰好で立ち、両手を一ぱいに伸して何か叫んでいる。手拭いもない真裸だ。それが踊子だった。(川端康成「伊豆の踊子」)
自分の前に全裸で現れた踊子を見て、<私>は「子供なんだ」と微笑ましい気持ちになるが、相手が子どもだからと言って、恋心を止めることはできない。
そもそも、<私>は、「踊子を今夜は私の部屋に泊らせるのだ」と、性欲たっぷりの視線で少女を見つめていたのだ。
実際の年齢が分かったからと言って、自分の性欲を制御できるものではなかったのだろう(なにしろ若かったから)。
ところが、栄吉の女房<千代子>のおふくろは、<私>と踊子が二人きりになることを自然体でブロックしてくる。
経験豊かな母親は、野獣のような大学生の性欲を敏感に察知していたのかもしれない。
結局、少女に指一本触れることもできなくて、お金のなくなった<私>は、失意のうちに少女と別れて東京へ帰る。
プラトニックな恋心は、あるいは、何もできなかったが故の結果論だったのかもしれない。
<私>の心を浄化した<踊子>とのプラトニック・ラブ
本作「伊豆の踊子」は、孤児根性に歪んだ大学生が、純粋な少女との出会いを通して、性格を改善するまでの過程を描いた青春小説である。
天城峠の北口の茶屋で、雨に濡れた身体を乾かすとき、<私>は「水死人のように全身蒼ぶくれの爺さん」と一緒に囲炉裏に当たる。
「到底生物とは思えない山の怪奇」は、青春の孤独を抱えた<私>自身の象徴だ。
しかし、旅芸人の一座と道連れになり、踊子の少女と仲良くなっていく中で、<私>は、自分の性格が変化していくことを感じる。
「何か御不幸でもおありになったのですか」「いいえ、今人に別れて来たんです」私は非常に素直に言った。泣いているのを見られても平気だった。私は何も考えていなかった。ただ清々しい満足の中に静かに眠っているようだった。(川端康成「伊豆の踊子」)
溢れ出る涙もまた、<私>の孤独の象徴だったのだろう。
身体の中が空っぽになるまで<私>は泣き続け、「その後には何も残らないような甘い快さ」を感じている。
踊子との(プラトニックな)心の交流が、<私>の心を浄化していったのである。
仮に、<私>と踊子の交流が、肉体的な交流にまで及んでいたとしたら、もしかすると、<私>の浄化は成功しなかったかもしれない。
私は一人で活動に行った。女弁士が豆洋燈(ランプ)で説明を読んでいた。直ぐに出て宿へ帰った。窓閾に肘を突いて、いつまでも夜の町を眺めていた。暗い町だった。遠くから絶えず微かに太鼓の音が聞えて来るような気がした。わけもなく涙がぽたぽた落ちた。(川端康成「伊豆の踊子」)
「あとがき」には「『伊豆の踊子』は私の作品としては珍ずらしく、事実を追っている」と書かれている。
少女趣味丸出しでも感傷的に描くと名作になるんだと思った。
作品名:伊豆の踊子
著者:川端康成
書名:伊豆の踊子・温泉宿
発行:2009/04/16
出版社:ワイド版 岩波文庫