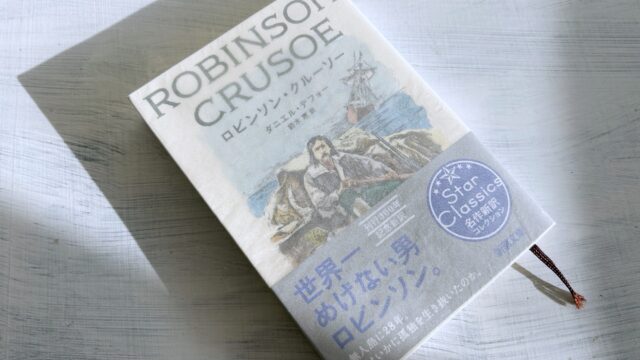庄野潤三「貝がらと海の音」読了。
本作「貝がらと海の音」は、1995年(平成7年)1月から12月まで『新潮45』に連載された長篇小説である。
この年、著者は74歳だった。
単行本は、1996年(平成8年)4月に新潮社から刊行されている。
人生の晩年を迎えた男の日常と心理
庄野潤三の晩年の作品を読んでいると、いつも思い出すことがある。
それは、『つむぎ唄』という古い長篇小説(1963年)に出てくる一節で、飛行機から下界を見下ろしている父娘が会話を交わしている場面だった。

初めて飛行機に乗った娘は、「町や村の屋根を真上から見るとこんなにいいものだとは思わなかったし、道がこんなに美しい、魅力のあるものだとは思わなかった」と言って感心する。
それを聞いた父親は、自分たちの人生も似たようなものかもしれないと考える。
われわれの毎日の暮しというものも、生活している当人に取っては、いやなことや情ないことや腹の立つことばかりで詰っているように思えるけれども、もう二度とそこで生きることが無くなって、はるか遠くから眺めるようになれば、こんな風にごく穏やかな、いい色をして見えるのかも知れないな。(庄野潤三「つむぎ唄」)
つまり、人生の機微というものを、飛行機から見下ろす街並みに託して表現したものだが、光と影が織りなす人生の綾の、どこにフォーカスするのかということは、文学にとって、いつも大きな関心事となってきた。
庄野さんも、日常生活の中に潜む不安(つまり影だ)にスポットを当てるような小説を、多く書いた作家だったが、晩年には、日常生活の中の喜び(つまり光だ)にフォーカスすることを意識するようになる。
晩年の庄野文学が、「人生の喜び」を中心として描くようになった背景は、彼の人生と深く関わっているように思われる。
『夕べの雲』以降、五人家族の日常生活をモチーフとした作品を書き続けた庄野さんは、1980年前後からは家族小説を離れ、『ガンビアの春』『早春』『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』『サヴォイ・オペラ』と、スケールの大きな作品をいくつも発表するようになる。
三人の子どもたちが、それぞれ独立をしてしまって、子どもたちの生活を中心とする家族小説は、既に成立しなくなってしまったのだろう。
ところが、1985年(昭和60年)に、大病(脳内出血)で入院した(64歳だった)ことを契機に、庄野さんの文学は、再び家族小説へと戻ってくる。
これは、闘病生活をきっかけとして、家族間の絆が深まったことと同時に、生命にかかわる病気をしたことで、残りの作家生活をどのように生きるべきかということを、深く考えた結果ではないかと思われる。
さらに、最も大きな要因となったのは「フーちゃん(文子)」という孫娘(庄野さんの次男の長女)の存在だ。
自宅の近所で生まれた初めての孫娘(1986年生まれ)は、かつて、自分の子どもたちをモチーフとして小説を書いていた頃の感覚を、庄野さんに取り戻させたのだろう。
闘病記である『世をへだてて』(1987年)に続く、『エイヴォン記』(1989年)、『鉛筆印のトレーナー』(1992年)、『さくらんぼジャム』(1994年)という、いわゆる「フーちゃん」三部作の執筆を通して、晩年の庄野文学のテーマが明確になっていく。

そして、1995年(平成7年)1月から『新潮45』に連載を開始したのが、夫婦の晩年シリーズの第一作となる『貝がらと海の音』だった。
「フーちゃん三部作」を通して、庄野さんは、人生の「光」の部分(つまり「喜び」だ)にフォーカスした作品を書くことを意識するようになる。
「嫌なことが書かれていない」と言われる夫婦の晩年シリーズには、そのような背景があるが、もちろん、作品の中で、そんな執筆の意図は書かれていないから、これはすべて一読者の推測にすぎない。
しかし、庄野潤三という作家のすべての作品を、年代順に(俯瞰的に)読み通したとき、晩年の作品群には、やはり大きな意味があるように思われる。
「夫婦の晩年シリーズ」が、1970年代に書かれた家族小説と大きく異なるところは、かつての作品群が、子どもたちにフォーカスするものが多かったのと対照的に、晩年の作品群では、庄野夫妻(もっと言えば「庄野潤三」という作家個人)にフォーカスされているということだろう。
もちろん、晩年の作品群でも子どもたちや孫たちは活躍するが、彼らは、あくまでも、庄野潤三という老人を取り巻く点景であって、テーマとして描かれているのは、人生の晩年を迎えた男の日常(と心理)である。
だから、正確に表現すると、夫婦の晩年シリーズは「家族小説」というよりも「老人小説」、あるいは「老後小説」と言った方がふさわしいが、庄野さんの老後を支えたものが、家族との交流であったことに間違いはない。
そして、家族との交流を通して得られた日々の喜びを記録したものが、『貝がらと海の音』から始まる「夫婦の晩年シリーズ」という作品群ということになるのだ。
庄野潤三という高齢作家の気持ちの揺れを描く
本作『貝がらと海の音』は、1994年(平成6年)9月から1995年(平成7年)6月までの、庄野潤三の日常生活を素材とした長編小説である。
こうした物語の舞台となっている時期は、「今年三月に私の『さくらんぼジャム』(文芸春秋)という本が出て」や「大阪帝塚山の兄は、去年の十一月、大阪の病院で亡くなった」などの記述から判断できる。
(児童文学者の庄野英二は1993年11月26日に逝去。なお、『さくらんぼジャム』の刊行は、1994年2月が正しい)。
『&Premium特別編集 あの人の読書案内。』で、山本ふみこ(随筆家)は、本作『貝がらと海の音』を紹介している。
日常には脅かされる。それを知る老夫婦の、ささやかだけれど穏やかな暮らしを静かな筆致で綴る小説。「本当のエレガンスには人の温もりと愛情が不可欠。本書にはそれがあふれています。例えば一家の長女がしたためた手紙にそれを感じます。エレガンスというとおしゃれを連想しがち。それも大事ですが、やはり中身がないと見た目のエレガンスも薄まってしまう。人の心や暮らしにも同じことが言えます」(『&Premium特別編集 あの人の読書案内。』山本ふみこ)
山本ふみこさんにとって、『貝がらと海の音』は、「私に、エレガンスを教えてくれた本」だったらしい。
作品では、冒頭からフーちゃんが登場している。
前に次男のところの小学二年になるフーちゃんと幼稚園へ行っている春夫が来たとき、とかげを欲しがったので、妻がプランターを一つ動かした。(略)フーちゃんというのは、名前が文子で、まだ私たちの家から坂を下りて行った先の大家さんの借家にいて、よくお母さんのミサヲちゃんに連れられて「山の上」(と私たちのことを呼んでいた)へ遊びに来ていた二歳のころから、私たちはこの子のことをフーちゃんと呼んでいた。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
夫婦の晩年シリーズで、フーちゃんが重要な登場人物となっているのは、もちろん、祖父である庄野潤三の強い関心を示すものだ。
晩年の庄野潤三に大きな喜びを与えてくれるものが、孫娘フーちゃんであることは、「フーちゃん三部作」を執筆する中で、既に確信となっていたはずだ。
だから、夫婦の晩年シリーズにおいても「フーちゃん」は、他の親族とは異なる、極めて重要なキャラクターとして位置付けられている。
本作『貝がらと海の音』の作品タイトルも、フーちゃんにちなむものだった。
フーちゃんが貝がらを大事そうに持って台所へ来た。お茶の用意をしている妻にフーちゃんが、「貝がらを耳に当てると、海の音が聞えるの」といった。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
フーちゃんの台詞が、そのまま作品タイトルとして引用されている。
もう一人、フーちゃんと同じように、特に重要な登場人物として描かれているのが、南足柄市に住む長女「なつ子」だった。
遠方で暮らしている長女の生活は、『インド綿の服』(1988年)でおなじみとなった「ハイケイ足柄山からこんにちは」から始まる手紙を通して、詳細に語られている。

物語としての『貝がらと海の音』を動かしていくのは、主に、「フーちゃん」と「なつ子」の二人で、その脇において、フーちゃんの両親である次男「かずや」と妻「ミサヲちゃん」、長女・なつ子一家、長男一家など、多彩な顔触れが物語に厚みを作り出していくことになる。
特に、庄野さんの「神奈川文化賞」と「秋の叙勲(勲三等瑞宝章)」の受賞のお祝いで、一族揃って箱根芦の湯まで一泊旅行に出かけたエピソードは、この年の庄野家にとって、大きな出来事となった。
広間での夕食の最後に進行係の「山の下」の長男が立って、「それでは、ここでロウ・ロウ・ロウヤ・ボートの輪唱をします」といい、はじめに私にこの歌の意味をみんなに説明してくれるようにと頼んだ。そこで私は一通り歌って聞かせてから、「漕げ漕げボート ゆるやかに川を下って」と、長男に頼まれた通り、これからみんなで歌うボートあそびの歌の歌詞を紹介した。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
庄野家の結束の固さを象徴するようなエピソードだが、「楽しい楽しい。この世は夢のようなものだ」という歌の歌詞には、『貝がらと海の音』という小説のテーマが凝縮して投影されているようにも思われる。
ちなみに、「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート」は、『つむぎ唄』(1963年)のクライマックスにも登場している。
「さあ、そろそろ輪唱だ。ロウ・ロウ・ロウヤ・ボートだ」毛利が云い出すと、食卓のまわりにいる者が四つの組に分けられた。(略)これは「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート(漕げ漕げボート)」で滑り出して、「ライフ・イズ・バット・ア・ドリーム(この世は夢に過ぎない)」という終りの句まで来ると、また始めに戻るのだが(略)(庄野潤三「つむぎ唄」)
1963年(昭和38年)に40代の父親だった主人公は、1994年(平成6年)に70代の祖父として、同じ「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート」を孫たちへと歌い継ぐ。
ここには、家族の物語を書き続けてきた庄野文学における「世代間継承」があるが、庄野さんは、様々な観点から「世代間継承」を描いた。
井伏鱒二の翻訳で知られる「ドリトル先生シリーズ」も、その一つだ。
次男のところでは、飼い犬に「ジップ」という名前をつけた。
ジップという名前は、フーちゃんの好きな『ドリトル先生物語』(次男は子供のころ、家に会ったロフティング作・井伏鱒二訳のこの物語を好んで読んでいたから、父子二代で愛好していることになる)に登場するドリトル先生の仲間の犬の名前を貰った。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
『ドリトル先生』は、当然に庄野さんも愛読していただろうから、実際には、祖父(庄野潤三)から孫(フーちゃん)まで、三代に渡って愛好された作品ということになる。
夫婦の晩年シリーズでは、こうした世代間継承を、庄野さんが意識していたことを示す場面が、随所に登場していて興味深い。
ドリトル先生の翻訳者である井伏鱒二は、庄野英二と同じく1993年(7月)に亡くなっているが、夫婦の晩年シリーズでは、庄野さんの思い出として、再三に渡って登場することになる。
大久保にある行けつけの飲み屋「くろがね」には、「大きな井伏さんのお顔のポスター」が懸っていた。
かおるさんと信子ちゃんの話を聞くと、今度、井伏さんの郷里の福山の美術館で「井伏鱒二の世界」という展覧会がある。その展覧会に所蔵の軸などを出品することになった小沼丹が、このポスターを持って来てくれたのだそうだ。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
小沼丹に関しては、随筆「消えた飛行機」の話がある。
朝食のとき、先日、朝日の朝刊に出ていた小沼丹の「消えた飛行機」という随筆のことを二人で話していたら、妻は子供のころに雑誌で読んだ「見えない飛行機」というのを思い出して、その話をする。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
小沼丹の「消えた飛行機」は、死後に刊行された随筆集『福寿草』(1998年)で読むことができる。

『エイヴォン記』以降、重要な役割を担っている近所の清水さんもいい。
「はじめて清水さんからエイヴォンを頂いてよろこんだ日のことは、私の『エイヴォン記』の中に出てくる」と、庄野さんは回想している。
「エイヴォン? エイヴォンといえばイギリスの田舎を流れている川の名前だ。ほら、『トム・ブラウンの学校時代』のなかで、トムが学校の規則を破って釣りをする川が出て来るが、あの川の名がエイヴォンだよ」(庄野潤三「貝がらと海の音」)
『トム・ブラウンの学校時代』とあるのは『トム・ブラウンの学校生活』のことだが、「エイヴォン? エイヴォンといえば~」のフレーズは、晩年の作品群で繰り返し語られる、お馴染みのエピソードとなった。

庄野文学の読者は「清水さんといえばエイヴォン、エイヴォンといえば清水さん」と、すっかり刷り込まれていくことになる。
初めてのフーちゃん物語でもあった『エイヴォン記』に対する、庄野さんの愛着を示すものだろう。
ひとつ、記しておかなければならない場面がある。
次男の一家が先に写真室に入る。はじめにフーちゃんを写す。片手に扇子、片手に赤い手さげを持ったフーちゃんが一人で壁の前に立つ。そこを覗き見た妻が、泣き出す。縁起でもないと注意してやりたいが、こちらもさっき写真屋へ入って、待合室の椅子に腰かけているフーちゃんを見たとたん、泪が出そうになった。何の泪なのだろう?(庄野潤三「貝がらと海の音」)
庄野夫妻の涙は、もちろん、孫娘の成長を祝う喜びの涙だが、フーちゃん三部作の完結編『さくらんぼジャム』の中で、フーちゃん一家が引越しをして行く場面でも、同じような表現があったことを思い出す。
私が荷物の運び出しを眺めているところへフーちゃんが来て、「さようなら」といって引返した。こちらは咄嗟のことで、何もいわずにフーちゃんのあとをついて行き、ミサヲちゃんとフーちゃんのいる前で、「遊びにお出で、泊りがけで」といった。そのあと、前田さんの車の方へ行くミサヲちゃんとフーちゃんのうしろを歩いているうちに、不意に顔がくしゃくしゃになり、泪が出そうになった。(庄野潤三「さくらんぼジャム」)
庄野潤三という高齢作家の気持ちの揺れが、孫娘フーちゃんとの交流を通して描かれている。
それが、晩年の庄野文学の、大きな特徴だったのではないだろうか。
この後、10年間続いていく「夫婦の晩年シリーズ」も、後半へ進むほど回想が中心となって、日常生活の描写が少なくなっていく。
高齢者の生活が制限されたものであることを推測させるが、『貝がらと海の音』では、庄野さんも、まだ十分に活動的だった(「お父さん、歩くのが遅くなったね」と、次男に指摘されてはいるが)。
庄野文学の「老後小説」は、いつか老後を迎えるだろう、すべての大人たちに、勇気を与えてくれる小説だ。
こういう小説は、年を取ってから(老後になってから)読むものではない。
少しでも若いうちから触れておくことが必要なのではないだろうか。
書名:貝がらと海の音
著者:庄野潤三
発行:1996/04/20
出版社:新潮社