庄野潤三「鍛冶屋の馬」読了。
「鍛冶屋の馬」は十一篇の作品から成る連作短編集である。
以下、あとがきから。
もとは草深い田舎といってもいい趣があったのではないだろうか。黍坂の、大家さんの地所続きに、はじめは三軒、あとから庭先の葡萄棚を取り払ってもう三軒、借家が建てられる。殆どが小さい子供のいる夫婦者の世帯だが、この「地域社会」の日常の交流を四季の風物とともに書きとめてみたい。ただし、直接その場に立ち合うのではなく、店子のひとりから日にちを置いて伝えて貰うことにする。噂話を聞く楽しみというものがあるとすれば、それを聞き出したい。(「あとがき」)
物語の語り手である「井村」は、結婚して家を出て、今は二人の男の子の母親となっている「和子」から、和子の周りで暮らしている若い家族の様子を聞いては、熱心に書きとめていく。
庄野文学としては、「絵合せ」や「明夫と良二」の流れに位置付けられる作品だが、かつては中心的な活躍をも見せていた和子の2人の弟(明夫・良二)も、ここでは脇役に徹していて、物語の主役は、あくまでも和子たち家族と、近所の若い主婦やその子どもたちである。
「絵合せ」の頃には、井村一家の暮らしに焦点が合っていたが、「鍛冶屋の馬」では和子の家を中心とする小さな地域社会にピントが絞られている。
「この『地域社会』の日常の交流を四季の風物とともに書きとめてみたい」と言うように、「井村」は「和子」からの情報をもとに、この小さな地域社会で起きた日常の出来事を簡潔にスケッチしていく。
もちろん、取り立ててすごいことが起こるはずもないのが、我々庶民の暮らしだ。
近所の鍛冶屋の小父さんが、稲荷ずしの作り方のコツを教えてくれたとか、家族連れしか入居を認めていない借家に入った独身のハイヤー運転手が故郷へ帰ったとか、新しく入った家の子どもは母親らしき女性を「お姉さん」と呼んでいるとか、まさしく、近所の噂話みたいなものが、次から次へと和子の言葉を通して語られていく。
和子の話を受けて、語り手の「井村」がつぶやく言葉も楽しい。
例えば、和子が鍛冶屋の亡くなった前妻は身を粉にして働いたと言うのを聞いて、「それはそうだろう、暫時(しばし)もやまずに槌うつ響、飛び散る火の花、はしる湯玉、だもの」などと、童謡を引き合いに出して、感心してみせる。
あるいは、近所の家で餅搗きをしているとき、杵が空いたと思ったら、それまで餅米を洗ったりしていたお婆さんが、餅を搗き出したというのを聞いて、「これが本当の、昔取った杵柄、だな」と言った後で、自分で「なるほどね」と感心してみせたりする。
かと思うと、和子の近所で火事があったという話を聞いた時には「運が悪ければ、こういう時に、ほかでもない自分たちの娘夫婦のいる家から煙をふき出しているということだってある」などと、しみじみと運命に思いを馳せてみたりするところも、また井村らしい(庄野さんらしい)受けとめである。
このように「鍛冶屋の馬」では、日常の暮らしの中で普通に出会うだろう「ふとした喜び」や「ふとした悲しみ」「ふとした驚き」などの、ささやかな感情のゆらめきのようなものに着目して、物語は進められていく。
庄野さんは、人生を変えるほどの「大きな喜び」や「大きな悲しみ」「大きな驚き」などよりも、普通の暮らしの中にある、ささやかな感動を愛し、慈しみ、大切に描いた作家だと思う。
「鍛冶屋の馬」は、昭和50年1月から12月まで(2月を除いて)「文学界」に発表された作品だが、仙台まで帰る列車の指定席を取るのに3日間も並んだとか、和子の主人が不意に「おれも社会的な地位が向上したから、電話をつけることにしよう」と言い出して、和子を驚かせたりだとか、いつもは練炭焜炉を玄関の外へ出して焼いている鯖を、焚火で焼いたら美味しかっただとか、昭和らしい細かいエピソードがたくさん含まれているのが楽しい。
帯には「嫁いだ家族を見まもる父親のくもりない眼。日常のささやかな歓喜を声低く、そして確かな調子で語り著者本来の『父性の文学』の、新たな到達点を示す名品」と綴られている。
昭和40年代から50年代へと移り変わる時代の庶民の暮らしをスケッチした作品として、「鍛冶屋の馬」は長く読み継がれていくべき作品だろう。
書名:鍛冶屋の馬
著者:庄野潤三
発行:1976/4/15
出版社:文藝春秋



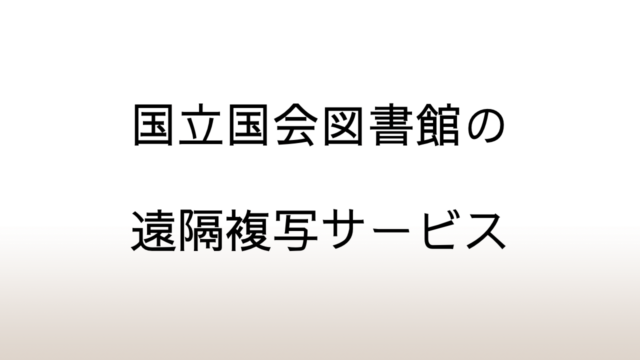


-150x150.jpg)









