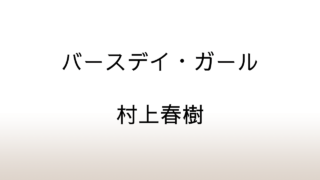村上春樹「風の歌を聴け」読了。
本作「風の歌を聴け」は、1979年(昭和54年)6月『群像』に発表された長篇小説である。
この年、著者は30歳だった。
1979年(昭和54年)、第22回群像新人文学賞受賞(ただし、応募時の作品タイトルは「Happy Birthday and White Christmas」だった)。
1979年(昭和54年)上半期、第81回芥川賞候補。
単行本は、1979年(昭和54年)7月に講談社から刊行されている。
自殺した恋人に捧げる追悼文学
トルーマン・カポーティの短編小説「最後の扉を閉めて(Shut a Final Door)」は、次のように終わる。
このままにしておいたら軍隊が部屋のドアを叩きかねない。そう思ったので彼は顔を枕に押しつけ、両手で耳をふさいだ。そして思った。何も考えまい。ただ風のことだけを考えていよう。(トルーマン・カポーティ「最後の扉を閉めて」川本三郎・訳)
この最後の一文「何も考えまい。ただ風のことだけを考えていよう(Think of nothing things, think of wind)」が、『風の歌を聴け』というタイトルに結びついた。
「何ひとつ思うな。ただ風を思え」トルーマン・カポーティの短編小説『最後のドアを閉じろ』の最後の一行、この文章に昔からなぜか強く心を惹かれた。Think of nothing things, think of wind’ 僕の最初の小説『風の歌を聴け』も、この文章を念頭にタイトルをつけた。(村上春樹『村上ラヂオ3 サラダ好きのライオン』所収「私が死んだときには」)
まるでスイッチをパチンとOFFにするように突然自殺した恋人の喪失感に苦しむ主人公は、小説を書くことによって救済の道を探ろうとするが、どうしても完成させることができない。
「完璧な文章などといったものは存在しない」からだ。
彼女の死から8年後、もうすぐ30歳になろうとする、29歳のときに、ようやく彼は、一つの小説を書き上げることができた。
その小説が、本作『風の歌を聴け』という長篇小説である。
物語は、恋人が自殺した直後の1970年の夏休みを舞台に語られていくが(恋人は1970年の春休みに首を吊って死んだ)、親友<鼠(ねずみ)>と新しいガールフレンド<小指のない女の子>の二人が、いずれも深い喪失感を抱えているのは、主人公の心理が投影されているためだろう(佐多稲子のように「主人公の分身」とまで言わないにしても)。
例えば、鼠の調子がひどく悪くなったときに「多分取り残されるような気がするんだよ」と説明する<ジェイ>の言葉は、死んだ恋人に取り残された主人公の気持ちを投影したものだし、小指のない女の子の存在は、恋人の死によって、まるで体の一部を失ってしまったかのような、主人公の深い喪失感を具象化したものと考えることができる。
主人公のこうした喪失感は、ビーチ・ボーイズやエルヴィス・プレスリー、ミッキーマウスマーチなど、「恋人の自殺」以前の時代を象徴するピースとの対比によって、より鮮明となっていくというのが、この小説の大きな構図だ。
「嘘つき!」と彼女は言った。しかし彼女は間違っている。僕はひとつしか嘘をつかなかった。(村上春樹「風の歌を聴け」)
主人公のついた、たったひとつの嘘は、最初の「ねえ、私を愛してる?」という質問に対する「もちろん」の答えだけだ。
そして、そのことが、彼女が死んでしまった後まで、彼を縛り続けることになる。
この小説について「テーマがわからない」という読後感想が散見されるのは、恋人の自殺という具体的な主題が、作品の中では巧妙にカモフラージュされているからだろう。
恋人の自殺と正面から向き合うには、29歳の主人公は若すぎたのである。
三人目の相手は大学の図書館で知り合った仏文科の女子学生だったが、彼女は翌年の春休みにテニス・コートの脇にあるみすぼらしい雑木林の中で首を吊って死んだ。彼女の死体は新学期が始まるまで誰にも気づかれず、まるまる二週間風に吹かれてぶら下がっていた。(村上春樹「風の歌を聴け」)
ちなみに、恋人の自殺というモチーフは、後年『ノルウェイの森』によって、正面から描かれている(このとき、主人公は37歳だった)。
婉曲な表現にせよ、この物語を書き上げたことによって、主人公は、青春の日のモヤモヤ感から解放されることになった。
そのことが明確に示唆されているのは、最後の場面にある「死んだ仏文科の女の子の写真は引越しに紛れて失くしてしまった」という一文だろう。
『風の歌を聴け』という小説を完成させたことによって、どうやら主人公は「自己療養へのささやかな試み」に成功したらしい。
そういう意味で、この作品は「始まりではなく終わりだった」と考えることができる。
「少なくともここに語られていることは現在の僕におけるベストだ」とあるのは、おそらく本音で、主人公は20代のすべてを注ぎ込んで、この小説を完成させたに違いない。
僕が寝た三番目の女の子について話す。死んだ人間について語ることはひどくむずかしいことだが、若くして死んだ女について語ることはもっとむずかしい。死んでしまったことによって、彼女たちは永遠に若いからだ。(村上春樹「風の歌を聴け」)
そして、この作品は、彼にとって「最初で最後となる(はずの)小説」だった。
実際には、ここからが始まりだったのだけれど。
不毛の時代を生きた若者たちの物語
僕にとって『風の歌を聴け』は、村上春樹の作品中、最も数多く繰り返し読んだ小説である。
なぜ、僕は、こんなにも何度も繰り返して『風の歌を聴け』という小説を読むのだろうか。
理由の一つは、この小説が限りなく少ない文字と簡潔な文章で構成されているということにある。
あまりに簡潔な文章であるため、時に、この作品は「ラノベみたいだ」と評されることがある。
しかし、十七文字の俳句が無限のイメージを生み出すのに似て、少ない文字数で組み立てられた簡潔な文章は、極めて具体的な情景を生み出すことに成功している。
後年、村上春樹の小説は、膨大な文字数によって構築されるようになるが、どんなに多くの文字数で構成された長篇小説も、この『風の歌を聴け』ほどには具象化されてはいない。
時に抽象画が具象画よりも写実的であるように、文字数が少ないがゆえに『風の歌を聴け』という小説は完成されているのだ。
多くの引用が、少ない言葉を支えているとも言える。
そして、僕が、この小説を繰り返し読む、もう一つの理由は、文字数が少ないがゆえの「とらえどころのなさ」が、この小説にはあるということだ。
読者の判断に委ねられる部分が大きいだけ、この作品の鑑賞は難しい。
それは、「自殺した恋人は、挫折した青春の投影ではないか?」ということだ。
例えば、ある世代にとって(もちろん団塊の世代だが)、この物語の舞台となっている1969年から1970年にかけてという時代設定は、学生運動の幻想と挫折が凝縮されているという意味において、かなり特別な意味を持っている。
だから、1969年から1970年にかけて交際した恋人が、1970年の春休みに自殺するというプロットも、何か特殊で社会的な意味を持っているのではないかと、つい考えてしまうのだ。
具体的な地名が示されていない一方で、時代設定だけがやたらに具体的なことも、時代設定に意味があることを暗示しているように見える。
恋人が自殺した半月後、主人公はミシュレの『魔女』を読んでいるが、時代の空気を読んで自ら首をくくって死んでいった「魔女たち」の姿は、学生運動に挫折した多くの若者たちのイメージに結びつく。
「彼は言う、『私の正義はあまりにあまねきため、先日捕えられた十六名はひとが手を下すのを待たず、まず自らくびれてしまったほどである』」(篠田浩一郎・訳)。私の正義はあまりにあまねきため、というところが何ともいえず良い。(村上春樹「風の歌を聴け」)
「わたしの正義はあまりにあまねきため、というところがなんともいえず良い」とあるのは、もちろん逆説的な表現であって、主人公は、そこに、時代の闘う相手が、あまりに強大であったことを認めている(これは鼠の古墳の話にも通じる部分だ)。
小説を書けないでいる鼠の「汝らは地の塩なり、塩もし効力を失わば、何をもてか之に塩すべき」という台詞は、1969年という時代の中で深く傷ついた若者たちに寄り添った憐れみのメッセージとして読むこともできる。
「それで、……何か書いてみたのかい?」「いや、一行も書いちゃいないよ。何も書けやしない」「そう?」「汝らは地の塩なり」「?」「塩もし効力を失わば、何をもてか之に塩すべき」鼠はそう言った。(村上春樹「風の歌を聴け」)
鼠の言葉は、F・スコット・フィッツジェラルド「壊れる(あるいは「崩壊」)」からの引用である。
なぜなら、鼠は、他の場面でも、フィッツジェラルドの、このエッセイの文章を引用しているからだ。
「こんなのもあった。『優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる、そういったものである』」「誰だい、それは?」「忘れたね。本当だと思う?」(村上春樹「風の歌を聴け」)
「第一級の知性の資格は、二つの対立する観念を同時に抱きつつ、その機能を十全に果たしていけることにある」は、フィッツジェラルド「壊れる」(村上春樹・訳)の冒頭に出てくる文章だ。
そして、「あなたは地の塩である。しかしもし塩がその味を失ったなら、何をもって塩とすればよいのだろう?」(マタイ伝五章十三節)も同様に、フィッツジェラルド「壊れる」(村上春樹・訳)の最後の一文である。
おそらく、鼠は、絶望の中で書かれたフィッツジェラルドの文章を、多分に意識していたに違いない。
それは、鼠自身の(同時に主人公の)絶望をも意味するものだったのだから。
主人公が抱える喪失感は、もしかすると、1960年代を生きた若者たちの、青春時代の挫折を意味しているのだろうか。
入院している少女からの手紙は、学生運動の時代に行き場を見失った若者たちのSOSのメッセージであり、主人公はラジオのディスク・ジョッキーと化して「ぼくは・君たちが・好きだ」と叫ぶ。
「でもね、いいかい、君に同情して泣いたわけじゃないんだ。僕の言いたいことはこういうことなんだ。一度しか言わないからよく聞いておくれよ。僕は・君たちが・好きだ」(村上春樹「風の歌を聴け」)
「君たち」とは、もちろん、主人公と同時代を生きた若者たちであり、その中には主人公自身も含まれているのだろう。
そうすると、全ての意味で不毛な作家だった<デレク・ハートフィールド>は、不毛な時代そのものの投影ということになる。
最後まで自分の闘う相手の姿を明確に捉えることができなかったことも、不毛な戦いを続けて死んでしまったことも。
熱狂と狂乱、疲弊と消耗という不毛な時代の象徴。
墓碑に刻まれた「昼の光に、夜の闇の深さがわかるものか」というニーチェの言葉(『ツァラトゥストラはかく語りき』からの引用)は、学生運動で行き場を失った若者たちの最後の叫びだったのかもしれない。
「夜の闇」とは、もちろん彼ら自身の(そしてデレク・ハートフィールド自身の)ことだった。
はじまりは「Don’t Think Twice, It’s All Right」
主人公(と鼠)もまた、1970年という時代に、行き場を失った若者たちの一人だ。
主人公は、デモやストライキに参加する中で、機動隊に前歯を叩き折られていたし、鼠は大学を去ってしまった。
「でもね、俺は俺なりに頑張ったよ。自分でも信じられないくらいにさ。自分と同じくらいに他人のことも考えたし、おまけにお巡りにも殴られた。だけどさ、時が来ればみんな自分の持ち場に結局は戻っていく。俺だけは戻る場所がなかったんだ」(村上春樹「風の歌を聴け」)
「俺だけは戻る場所がなかったんだ」という鼠の言葉は、どこにも行けずに自殺してしまった女の子の末路を連想させる。
この小説の深いところは、一人の女子大生の自殺という、極めて個人的な喪失感をモチーフとしながら(それさえも巧妙にカモフラージュされているが)、ある特定の時代の社会的な喪失感を象徴的に浮かび上がらせているというところにある。
主人公にとって救済の物語だった『風の歌を聴け』は、1960年代に若者だった多くの人々に捧げる青春の鎮魂歌でもあったのだ。
大森一樹監督は、映画『風の歌を聴け』の中で、ザ・ビーチボーイズの「カリフォルニア・ガールズ」をBGMに用いているが、本来、この物語を通奏低音のように流れているのは、あの時代遅れのピーター・ポール&マリーが歌う「くよくよするなよ」だった。
「もう何も考えるな、終ったことじゃないか」というボブ・ディランのメッセージは、そのまま、この小説のテーマでもあり、もしも、この小説に始まりがあるのだとしたら、それは、やはり「Don’t Think Twice, It’s All Right」だったのではないだろうか。
【村上】なぜ小説を書きはじめたかというと、なぜだかぼくもよくわからないのですが、ある日突然書きたくなったのです。いま思えば、それはやはりある種の自己療養のステップだったと思うのです。(河合隼雄・村上春樹「村上春樹、河合隼雄に会いに行く」)
確かなことは、青春の挫折を、爽やかで都会的な恋愛小説に仕立て上げている、作者の技術力だろう。
夏の香りを感じたのは久し振りだった。潮の香り、遠い汽笛、女の子の肌の手ざわり、ヘヤー・リンスのレモンの匂い、夕暮の風、淡い希望、そして夏の夢……。しかしそれはまるでずれてしまったトレーシング・ペーパーのように、何もかもが少しずつ、しかしとり返しのつかぬくらいに昔とは違っていた。(村上春樹「風の歌を聴け」)
違っていたのは、時代との戦いの前後で変わってしまった、若者たちの希望だ。
真夜中の台所で執筆された断片的な文章の組み合わせでありながら、『風の歌を聴け』は、一篇の小説として、間違いなく完成されている。
村上春樹は、この作品を書いた当時のことを、様々な場面で振り返っている。
1978年(昭和53年)4月、よく晴れた午後の神宮球場で、ヤクルト・スワローズ対広島カープの試合(セ・リーグの開幕戦だった)を観ているときに、小説を書こうとひらめいたというエピソードは、すっかりと定着した。
そのときの感覚を、僕はまだはっきり覚えています。それは空から何かがひらひらとゆっくり落ちてきて、それを両手でうまく受け止められたような気分でした。(略)それは、なんといえばいいのか、ひとつの啓示のような出来事でした。(村上春樹「職業としての小説家」)
「エピファニー(Epiphany)」という英語を、村上春樹は使っている。
そして、ジャズ喫茶の仕事が終わった後に、小説を書くという生活が始まった。
夜遅く、店の仕事を終えてから、台所のテーブルに向かって小説を書きました。その夜明けまでの数時間のほかには、自分の自由になる時間はほとんどなかったからです。そのようにしておよそ半年かけて『風の歌を聴け』という小説を書き上げました(当初は別のタイトルだったのですが)。(村上春樹「職業としての小説家」)
このとき、村上春樹は、むずかしい言葉や、凝った表現や、流麗な文体、そんなものはひとつも使わず、頭に浮かんだことを、簡単な言葉を使って、ただひたすらに書き留めたという(言うなれば「すかすか」同然のもの)。
それが結果的に、文章としてはアフォリズムというか、デタッチメントというか、それまで日本の小説で、ぼくが読んでいたものとまったく違った形のものになったということですね。それまでの日本の小説の文体では、自分が表現したいことが表現できなかったんです。(河合隼雄・村上春樹「村上春樹、河合隼雄に会いに行く」)
こうして生まれた『風の歌を聴け』は、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』や『ねじまき鳥クロニクル』とは次元の異なる完成度かもしれないが、間違いなく、この作品は「100パーセントの青春小説」だったと、僕は思う。
100年後に、村上春樹の作品がたった一つだけ残るとしたら、意外とこんな作品なのではないだろうか。
そうであってほしいのだけれど。
書名:風の歌を聴け
著者:村上春樹
発行:1982/07/15
出版社:講談社文庫



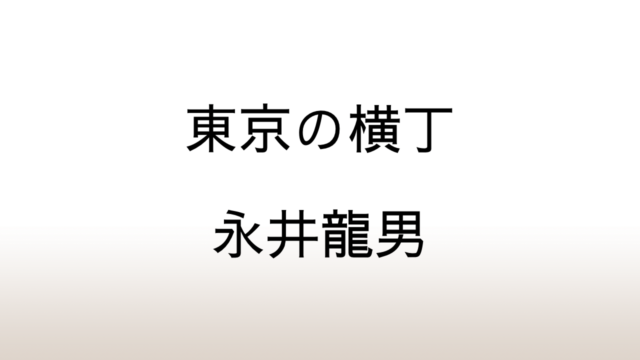



-150x150.jpg)