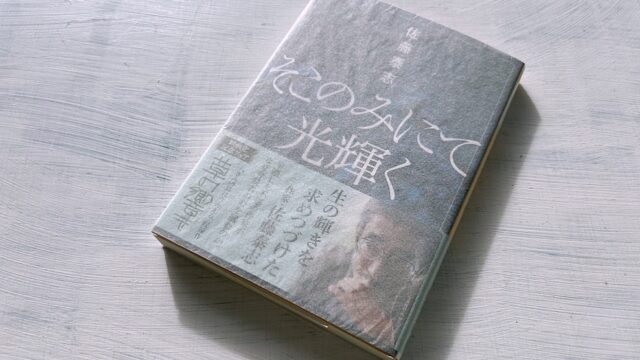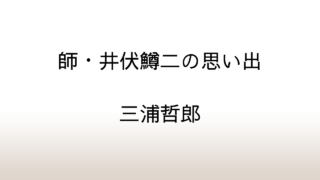船山馨「見知らぬ橋」読了。
本作「見知らぬ橋」は、1971年(昭和46年)に講談社から刊行された長編恋愛小説である。
この年、著者は57歳だった。
静謐で、美しすぎる、昭和の悲恋物語
一言で言えば『見知らぬ橋』は不倫小説である。
同時に、純愛物語でもある。
人が人を愛する感情と、真正面から向き合った恋愛小説である。
主人公の<魚住名緒子>は、京都で暮らす能面打ち師である。
27歳まで処女を通してきた名緒子は、旅先で自分を助けてくれた<並河五郎>と愛し合うようになるが、並河は妻子ある身だった。
並河は、妻の<圭子>と別れて、名緒子と結婚したいと考えているが、名緒子は並河の家庭を破壊することを決して望まない。
たった一度限りの肉体の交わりを糧として、一生、心の中だけで並河を愛し続けようと誓う。
「結婚して、夫と妻となって、ひとつの家庭をつくるという結ばれ方しか、お互いの心をつなぐ道はないのでしょうか。遠く離れて、もう二度とお目にかかることがなくても、生きているかぎり、私のなかのあなたが失われることはないのです。それでいいのではないでしょか」(船山馨「見知らぬ橋」)
夫が別の女性を愛していることを知った圭子は、泥酔して記憶を失った状態で、並河の部下の<江藤>に肉体を奪われてしまう。
絶望のあまり、自殺を図る圭子。
プレイボーイとして有名だった<葉室>は、圭子と知り合ってからは、人妻である圭子だけを一途に愛するようになる。
それぞれが自分の中に十字架を抱きつつ、互いを思いやりながら生きていく姿は、幻想的なまでに美しい。
冬の網走から始まった物語は、京都や東京などに舞台を移しながら、やがて遠いアラスカでクライマックスを迎える。
並河はそっと左手をザイルから離して、腰の登山ナイフを抜いた。それから、一瞬眼をあげた。彼は最後の挨拶を、名緒子に送りたいと思った。だが、彼の数メートル頭上には、力尽きて、まさに落ちかかろうとしている圭子の姿があった。彼は胸に噴きあげている名緒子への言葉を、辛うじて嚥み込んだ。そうして、そのかわりに、彼女への思いのすべてをもこめて、「死ぬなよ。僕のぶんも生きるんだぞ」と、落ちついた静かな声で圭子に言った。(船山馨「見知らぬ橋」)
誰も幸せになることはなく、物語は静かに幕を閉じた。
静謐で、美しすぎる、昭和の悲恋物語である。
氷と能面と愛情が極限の美を織りなしている
人を愛する美しさを描いた小説『見知らぬ橋』は、「氷」と「能面」を軸として展開していく。
並河五郎が夢中になる「氷」は、真冬のオホーツク海の流氷や、アラスカの氷河など、自然の驚異的な美しさの象徴として登場する。
一方、能面打ちの娘として生まれた名緒子は、愛する女性の面を写した女面「孫次郎」を自ら彫ることで、並河への愛を昇華しようと挑む。
歴史が培った自然の美と、人間が生み出した芸術の美が、対極の形で向き合う中で、男と女が愛し合う無垢の美しさが重ねられていくところに、この物語のポイントがあると言っていい。
氷河と能面という究極の「美」を追求しながら、最も素晴らしい「美」は人間自身の中にあった。
そこに作者の人間肯定の姿勢が現れているような印象を受けた。
タイトルの『見知らぬ橋』は、他人同士の心をつなぐ絆としての橋を意味している。
並河と自分との関係も、ほんとうは花びらの浮橋のようなものかもしれない、という気がしないではなかった。彼とのあいだに、世の男と女の結びつきを越えた、崩れることのない橋を架けようとしているつもりでいながら、それが実際は、僅かな風にも四散する水の上の花びらの橋でしかないのかもしれないのだった。現実を逃避した、観念の中の抽象の橋のようでもあった。(船山馨「見知らぬ橋」)
他人を信じられないような不安に襲われたときに、また読んでみたいと思った。
なお、本作に時折り登場する山登りのシーンは、非常に具体的で臨場感が溢れている。
昭和の「登山小説」として、注意すべき作品ではないだろうか。
書名:見知らぬ橋
著者:船山馨
発行:1974/7/30
出版社:角川文庫