庄野潤三「御代の稲妻」読了。
本書「御代の稲妻」は、庄野潤三にとって5冊目の随筆集である。
1979年(昭和54年)、講談社から刊行された。
この年、庄野さんは58歳だった。
円熟期の作家の自信と誇り
本書『御代の稲妻』には、全部で71篇の随筆が収録されている。
昭和51年から54年のはじめへかけて、ほぼ三年間に、新聞や雑誌などに発表されたものばかりだ。
「目次を作っていて、ラムやチェーホフ、伊東静雄がどこかに入っているのが分ると、たとえほんのわずかな分量のものであっても心賑やかになる。まだ文学青年ともいえない時期からの、ラムの言葉を借りれば『古なじみの顔』であるからだろう」と、庄野さんは綴っている。
実際、随筆の内容は、これまでに発表されている随筆集の流れを決してはみ出すことがない、「THE 庄野潤三」路線である。
チャールズ・ラムや福原麟太郎の話があり、チェーホフや伊東静雄の話があり、井伏鱒二や小沼丹の話がある。
いつもの庄野さんのとおりだから、読んでいて安心感がある。
この時期、庄野さんは、どのような執筆活動をしていたのだろうか。
昭和51年には、前年まで文藝春秋に連載していた『鍛冶屋の馬』を作品集として刊行している。
昭和52年は、ガンビア滞在時を回想した『シェリー酒と楓の葉』を文学界に発表し始めている。
長編小説『引潮』が新潮社から出るのも、昭和52年である。
昭和53年には、20年ぶりにオハイオ州ガンビアを訪問するほか、河出書房新社から長編小説『水の都』を刊行。
さらに、『シェリー酒と楓の葉』も書籍化され、年末には日本芸術院会員となった。
このとき、庄野さんは57歳で、円熟期の作家として、まさに充実した文学活動に取り組んでいた時期と言える。
本書『御代の稲妻』に収録されている作品は、ほんの数行の小さな作品に至るまで、実績を積んだ作家としての自信が漂っている。
それは、これ見よがしな自慢話ではなく、作家としてどうにか無事にやってこれたという安堵感のようなものだ。
例えば、「エリア随筆—本との出会い」という随筆は、こんな書き出しから始まる。
「私は生れつき、新規なことには臆病なのである」(戸川秋骨訳・岩波文庫)。これは「除夜」のはじめの方に出て来る言葉だが、ラムがこんなふうにいうと、頼もしく聞える。有力な味方を得たような心持になる。こういうことでもほかの人の口から出るとさして有難くないかも知れないが、ラムの場合はちょっと違う。(庄野潤三「エリア随筆—本との出会い」)
間もなく、日本芸術院会員に選出されようとしている大作家が、「私は生れつき、新規なことには臆病なのである」というチャールズ・ラムの言葉に共感を示しているところが、いかにも庄野さんらしい。
これは、日本経済新聞に掲載された短い随筆だが、「福原(麟太郎)さんの存在を身近に感じるようになったのも、ラムにつながる縁といえるかも知れない」と、最後は福原麟太郎に対する親愛の言葉で締めくくっている。
この頃、福原さんもまだ存命で、おそらく82歳の頃だった(約5年後に逝去)。
背伸びすることのない庄野さんの随筆は、いつ、どの作品を読んでも清々しくて気持ちが落ち着く。
これでは、まるで一服の清涼剤だ。
どの作品も短い、というところもいい。
短ければ短いほど良いような気がするくらい。
そして、イギリスのエッセイ文学を愛した人らしく、短いエッセイでも構成には気配りが感じられる。
思いついたことを思いついたままに書いているというよりは、短い中の文章の組立に、ベテランの作家らしい計算が読み取れる。
文章の組立ができていない随筆は、どんなに言っていることが立派でも感心できないものである。
書名:御代の稲妻
著者:庄野潤三
発行:1979/4/24
出版社:講談社

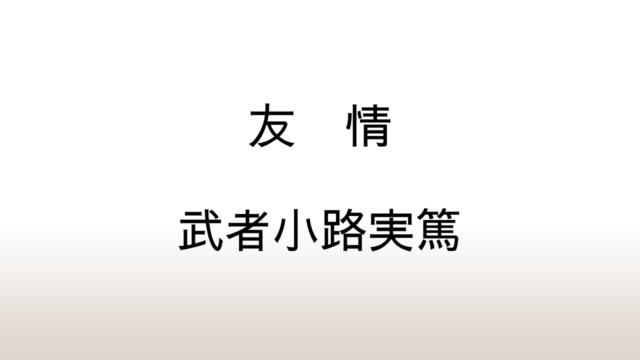




-150x150.jpg)









