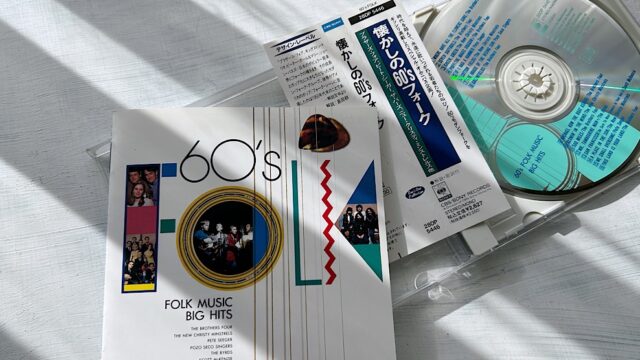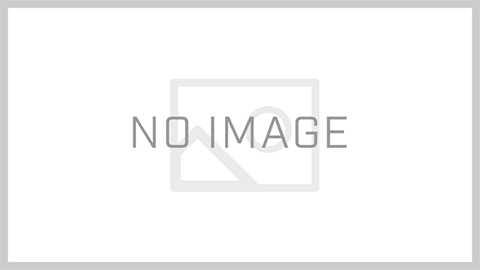F・スコット・フィッツジェラルド「マイ・ロスト・シティー」読了。
本作「マイ・ロスト・シティー」は、1932年(昭和17年)7月に書かれたエッセイである。
原題は「My Lost City」。
この年、著者は36歳だった。
作品集としては、1945年(昭和20年)に刊行された随筆集『The Crack-Up』に収録されている。
日本では、フィッツジェラルドの熱烈な愛読者である村上春樹の翻訳作品として知られている。
ニューヨークという街であがき続けた作家の苦悩
本作「マイ・ロスト・シティー」は、作家フィッツジェラルドと大都会ニューヨークとの出会いと別れについて書かれたエッセイである(心理的な面も含めて)。
私はなにもニューヨーク市の変遷について語ろうというわけではない。この都市をめぐって一人の作家の心が移りいく様を描こうとしているだけである。(F・スコット・フィッツジェラルド「マイ・ロスト・シティー」村上春樹・訳)
「一人の作家の心が移りいく様」とあるように、フィッツジェラルドは、変遷するニューヨークという街の中で、翻弄され続けた作家の一人だった。
フィッツジェラルドの栄光と破滅は、ニューヨークの栄光と破滅の変遷でもある。
つまり、このエッセイは、ニューヨークを舞台に活躍し、そして衰退していった作家フィッツジェラルドの自伝的エッセイということになる。
実際、フィッツジェラルドの作家人生は、ニューヨークの発展と大きな関わりを持っていたかのようだ。
ショウはますます大がかりになり、ビルはますます高くそびえたち、モラルはますますゆるめられ、酒はますます安価になっていた。しかしそれらは人々に真の喜びをもたらしはしなかった。若者ものたちは若くして擦り切れ、疲れ果てているようだった。(F・スコット・フィッツジェラルド「マイ・ロスト・シティー」村上春樹・訳)
一時期は「新しい世代」の象徴として華々しい活躍を見せたフィッツジェラルドだったが、彼とその妻ゼルダが重要人物だった時代は、あまりにも短かった。
「マイ・ロスト・シティー」では、ニューヨークという街であがき続けた一人の作家の激しい苦悩が、美しい文章で綴られていく。
栄華を極めた者の虚しさ
フィッツジェラルドが遺した短編小説の数は、およそ160編と言われているが、その中にはエッセイ的な風味のものも少なくない。
フィッツジェラルドは、エッセイを書くにあたっても、優れた作家の一人だったのだ。
『マイ・ロスト・シティー』あとがきの中で、訳者の村上春樹は「これまでに読んできたフィッツジェラルドの作品の中から現在翻訳が発表されていないもの、ということで五篇の短篇小説と一篇のエッセイを選んで訳した」と綴っている。
初めてのフィッツジェラルドの本の中に、わざわざエッセイを含めているくらいだから、村上さんは、よほど、この作品がお気に入りだったのだろう。
「フィッツジェラルド体験」というエッセイの中でも、村上さんは、この「マイ・ロスト・シティー」という作品について触れている。
この後の経過は自伝的エッセイ『マイ・ロスト・シティー』の中に語られている。一九二〇年の『楽園のこちら側』による華々しいデビュー、ゼルダとの結婚、ニューヨークでの奔放な生活、ヨーロッパ渡航、不況と崩壊といった一連の人生模様をニューヨークの街との関わりの中に捉えた内省的で傲るところのない見事なエッセイである。(村上春樹「フィッツジェラルド体験」)
フィッツジェラルドの「マイ・ロスト・シティー」には、成功者としての輝きがない。
むしろ、栄華を極めた者の虚しさこそが、強く描かれている。
ニューヨークは結局のところただの街でしかなかった。宇宙なんかじゃないんだ、そんな思いがあなたを愕然とさせる。あなたが想像の世界に営々と築き上げてきた光り輝く宮殿はもろくも地上に崩れ落ちる。エンパイア・ステート・ビルこそはかのアルフレッド・E・スミス市長がニューヨーク市民に贈った迂闊なプレゼントということになるだろう。(F・スコット・フィッツジェラルド「マイ・ロスト・シティー」村上春樹・訳)
日本の現代社会に置き換えてみれば、これは、バブル景気崩壊とともに不況の波の中に沈んでいった、数々の実業家たちの呻きのような文章だろう。
しかし、フィッツジェラルドは不況の波を呪ったりはしない。
遥か彼方に見える「失われた我が街」を、遠くからただ懐かしく見つめているだけだ。
作品名:マイ・ロスト・シティー
著者:F・スコット・フィッツジェラルド
書名:マイ・ロスト・シティー
訳者:村上春樹
発行:1984/06/10
出版社:中公文庫
(2026/02/28 18:29:52時点 Amazon調べ-詳細)