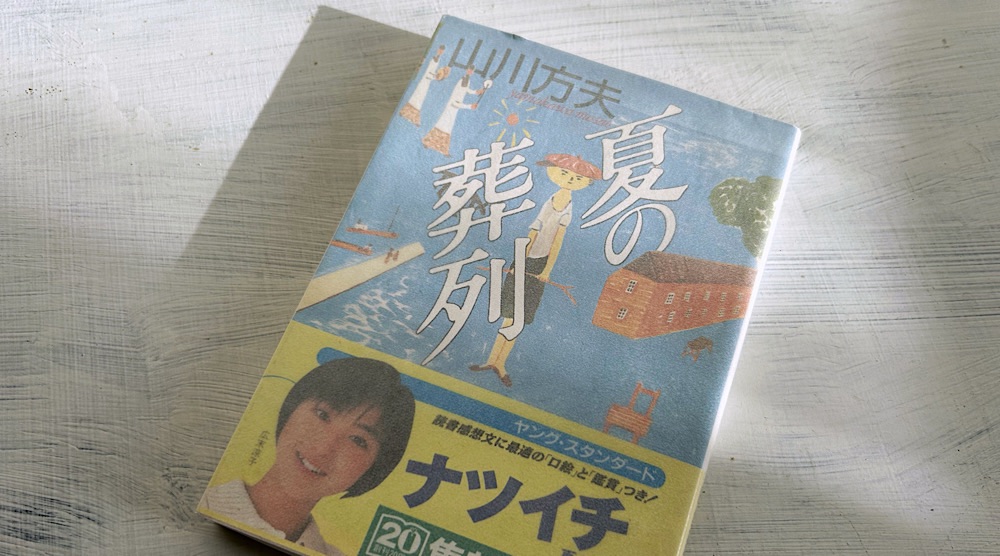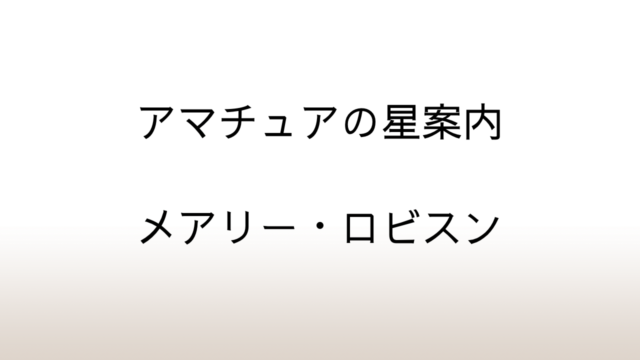山川方夫「夏の葬列」読了。
本作「夏の葬列」は、1962年(昭和37年)8月『ヒッチコック・マガジン』(第四巻第九号)に発表された短編小説である。
初出時の表題は「親しい友人たち・その7」(「親しい友人たち」のシリーズ名で発表された作品のひとつ)。
この年、著者は32歳だった(1965年、34歳で交通事故死)。
作品集としては、1963年(昭和38年)に講談社から刊行された『親しい友人たち』に収録されている。
主人公の中で戦争は今も終わっていない
本作「夏の葬列」は、<短編小説の名手>と呼ばれた山川方夫を代表する作品の一つである。
この作品が、多くの読者を得た背景として、中学校国語の教科書に掲載されたことと、戦争の悲惨さを題材とした作品であることの二点が考えられるが、小説としての本作の魅力は、短いながらも巧妙に仕組まれた、どんでん返し的なプロットにある。
海岸の小さな町の駅に、東京の若者が一人降り立つ。
そこは、戦争末期の少年時代、いわゆる<疎開児童>としての彼が、三か月ほど住んでいた街だった。
海岸の町の小学校で、東京から来た子どもは、主人公(9歳)とヒロ子さん(11歳)の二人きりで、都会の子どもたちは、年齢差や男女の別を越えて仲良くなるが、8月14日の昼近く(戦争が終わる前の日だった)、艦載機の機銃掃射を受けて、ヒロ子さんは重傷を負
ってしまう。
彼女は重傷だった。下半身を真赤に染めたヒロ子さんはもはや意識がなく、男たちが即席の担架で彼女の家へはこんだ。そして、彼は彼女のその後を聞かずにこの町を去った。あの翌日、戦争は終ったのだ。(山川方夫「夏の葬列」)
真青な波を重ねた海のような芋畑の中で、白い服を着たヒロ子さんを突き飛ばしたのは、少年時代の主人公だった。
「白い服はぜっこうの目標になるんだ!」と叫んだ誰かの声が、(それでなくとも臆病な)少年の理性を奪ってしまったのかもしれない。
あのとき、二人は、芋畑の向こうに続く小さな葬列に向かって走り始めたときだった。
そして、十数年ぶりに、海岸の街を訪れた主人公は、再び、真夏の葬列を目にする(これも、ものすごい運命のイタズラ)。
葬列は、芋畑のあいだを縫って進んでいた。それはあまりにも記憶の中のあの日の光景に似ていた。これは、ただの偶然なのだろうか。真夏の太陽がじかに首すじに照りつけ、眩暈に似たものをおぼえながら、彼は、ふと、自分には夏以外の季節がなかったような気がしていた。(山川方夫「夏の葬列」)
「自分には夏以外の季節がなかったような気がしていた」のフレーズが、主人公の中で、今も戦争が終わっていないことを示唆している(戦後、十数年も経っているというのに)。
彼は、自分がヒロ子さんを殺してしまったかもしれないという罪の意識の中で、十数年間という戦後を生きてきたのだ。
まるで、デジャヴのように、ゆっくりと通り過ぎる葬列の写真を見て、主人公は、ヒロ子さんが、これまで生きていたことを知る(――おれは、人殺しではなかったのだ)。
亡くなった女性が、ビッコでさえなかったと聞いた瞬間、主人公は、すべての罪から解放されるが(おれはまったくの無罪なのだ!)、喜びも束の間、最後のどんでん返しが、主人公を襲う。
その思いがけない結末は、彼にとって容赦のないものだった。
洟をたらした子があとをいった。「だってさ、あの小母さん、なにしろ戦争でね、一人きりの女の子がこの畑で機銃で撃たれて死んじゃってね、それからずっと気が違っちゃってたんだもんさ」(山川方夫「夏の葬列」)
少年の日の罪と後悔、一瞬の解放。そして、衝撃的なラストシーン。
まさに、ストーリーテーリングとしての文学が、この短編小説にはある(なにしろ、『ヒッチコック・マガジン』に発表された作品だった)。
罪の意識を抱いて生き続けていく庶民の姿
ここで問題となるのは、実際にヒロ子さんを殺した者は誰だったのか?ということだ。
立ちどまったまま、彼は写真をのせた柩がかるく左右に揺れ、彼女の母の葬列が丘を上って行くのを見ていた。一つの夏といっしょに、その柩の抱きしめている沈黙。彼は、いまはその二つになった沈黙、二つの死が、もはや自分のなかで永遠につづくだろうこと、永遠につづくほかはないことがわかっていた。(山川方夫「夏の葬列」)
「一つの夏」とは、昭和20年の、ヒロ子さんを突き飛ばした、あの夏であり、「二つの死」とは、機銃掃射によって殺されたヒロ子さんと、娘を殺されて狂い死にしたという母親の、二人の死である。
一つの夏の中に二つの死があり、その罪を背負って、主人公は生きていかなければならない。
とはいえ、敵機の機銃攻撃から逃げている中で、白い服を着た少女を突き飛ばした少年の恐怖(と無意識下の行動)を責めることは、少年にとって、あまりにも過酷に過ぎるような気がする。
本作「夏の葬列」の本質は、戦時中の罪の意識を抱き続けて生きる人々が、世の中に、まだ少なくなかったということである。
多くの市民が、思いがけない場面で加害者となり、罪の意識を抱いたまま、生き続けなくてはならないという事実こそ、この小説が伝えたかったメッセージだったのではないだろうか。
傍目にはどれだけ理不尽に思われるものであっても、戦争は、人々の心に傷痕を残す。
いわれのない罪の意識を抱いて生き続けていくのは、結局のところ、主人公たちのような庶民なのだ。
彼は、ふと、いまとはちがう時間、たぶん未来のなかの別な夏に、自分はまた今とおなじ風景をながめ、今とおなじ音を聞くのだろうという気がした。そして時をへだて、おれはきっと自分の中の夏のいくつかの瞬間を、一つの痛みとしてよみがえらすのだろう……。(山川方夫「夏の葬列」)
ヒロ子さんと彼女の母親の死を知った主人公は、罪の意識を抱いて生き続けていくことを決意する。
夏が来るたびに、彼は、自分の犯した罪の意識に苛まれなければならないのだ。
ヒロ子さんを殺したものは、悲惨な戦争でも敵軍の飛行機でもなく、少年時代の自分であったという自己認識だけを受け容れて。
太平洋戦争ものでは、「夏」が重要なキーワードになることが多いが、本作「夏の葬列」でも、夏という季節感が、極めて有効な演出効果を生み出している。
悲惨な戦争とか人生の皮肉とか、そういうテーマを越えて、この小説は、夏の小説として長く記憶されるべき作品かもしれない。
そもそも、山川方夫は、「夏」を得意とする作家だった。
例えば、名作ショートショート「朝のヨット」は、初夏の海に消えた少年の物語。
少女は海を見ていた。しめっぽく肌に重い早朝の潮風の中を、幾艘かのヨットが、少年のスナイプを求めてはしっていた。(山川方夫「朝のヨット」)
季節感のない病室で生きる少女の悲しみを描いた「暑くない夏」もいい。
あわてて、彼はあたりを見た。戦慄に似たものが、彼を走りすぎた。いつのまにか、まぶしかった夏の充実した日射しは消え、どこにも夏がないのだ。――彼にも、夏がないのだ。(山川方夫「暑くない夏」)
そして、避暑地の海岸へやってくる都会の連中を、地元の少年の視点から描いた「他人の夏」。
国道を真赤なスポーツ・カーが小さくなるのを、慎一はぼんやりと見ていた。女の言葉の意味が、よくわからなかった。彼はただ、小さなその町に今日も溢れている無数の都会の人びと、その人びとがそれぞれに生きている夏の一つ、そんな他人の夏の一つが、しだいに視野を遠ざかるのだけを見ていた。(山川方夫「他人の夏」)
どの物語も、夏という季節の高揚感を、物語の中へ巧みに落とし込んでいて、「夏といえば山川方夫」という印象を強く残す。
「山川方夫は、海と青空が好きな作家だった」「山川方夫は、海と青空に向かって一人で立とうとする」と述べたのは、川本三郎だった(『「それでもなお」の文学』所収)。
気軽に読めるショートショートという形態も、また、夏という季節感にマッチしていたのかもしれない(1980年代の喜多嶋隆のように、テーマまで軽くはなかったけれど)。
ショートストーリーの中に、人生の皮肉をさりげなく織り込んで、読者にメッセージを投げかける。
それが、山川方夫という作家だった。
夏と海が好きだった小説家は、湘南を走る海岸通りの横断歩道で、トラックに轢かれて急死した。
35歳の誕生日を迎える5日前のことだったという。
書名:夏の葬列
著者:山川方夫
発行:1991/5/25
出版社:集英社文庫