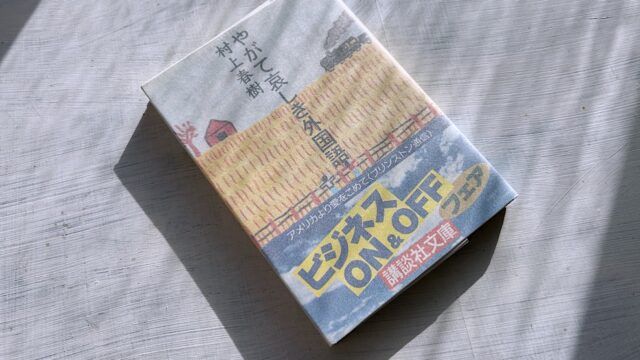庄野潤三『懐しきオハイオ』読了。
本作『懐しきオハイオ』は、1991年(平成3年)9月に文藝春秋から刊行された長篇小説である。
初出は、1989年(平成元年)3月~1991年(平成3年)4月『文学界』で、連載開始の年、著者は68歳だった。
庄野潤三の全作品の中で、最も長い作品として知られている。

ヒューマン・ドキュメントの日記文学
本作『懐しきオハイオ』は、庄野文学の中で、最長最大の長篇小説だが、読みどころのポイントは、大きく四つある。
まず、この作品は、日記形式で綴られた日記文学という形態を採っている、ということである。
1957年(昭和32年)9月から1958年(昭和33年)8月まで、庄野さんは夫人同伴で、アメリカ・オハイオ州のガンビアという小さな大学村に滞在した。
ロックフェラー財団の招待によって、ケニオン大学で一年間を過ごしたのだ。
ガンビアでの生活は、1959年(昭和34年)に『ガンビア滞在記』として発表され、各方面から高い評価を得た(福原麟太郎との交友も、ここから始まった)。
ガンビア滞在から20年後となる1977年(昭和52年)、庄野さんは、再び、ガンビアでの生活を綴った『シェリー酒と楓の葉』を『文学界』に連載する。

この『シェリー酒と楓の葉』は、1957年(昭和32年)9月から12月までの生活を回想したものだったが、その続編とも言うべき作品が、ガンビア滞在から30年を経た1989年(平成元年)になって、再び『文学界』に連載された。
それが、本作『懐しきオハイオ』である。
『シェリー酒と楓の葉』が、1957年(昭和32年)12月31日で終わっていることを受けて、『懐しきオハイオ』は、1958年(昭和33年)1月1日から始まる。
一月一日、水曜日は、雪。十二時になって起きた。頭の左側の耳の上のところが、ときどき痛む。前の晩、十二時までウイスキーを飲み、ライス氏の家へ行ってからはビールを飲んだが、そんなに飲んだわけではない。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「あや取り」)
克明な回想は、もちろん、きめ細かな日記に裏打ちされたものだろう。
作品集には収録されていないが、過去にも、ガンビア時代の日記を素材とした作品が発表されている。
一月十日。午後、ミノーとジューンが農家のパタースン夫人のところへ卵を買いに行くのに誘ってくれる。ガンビアから外へ出ると、まわりの景色がとてもいい。(庄野潤三「ガンビアの町の生活」1960年1月『市政』掲載)
同じ日のところを『懐しきオハイオ』で読んでみる。
一月十日、金曜日、晴。(略)ミノーとジューンが農家のパタースン夫人のところへ卵を買いに行くのに誘ってくれる。オーバーが要らない、暖かなお天気だ。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「パタースンさんの卵」)
ほぼ同様の記述は、日記から引用されたものと考えることができる。
つまり、本作『懐しきオハイオ』は、当時の日記を素材として使いながら、庄野さんの記憶や印象などによって補強された、日記文学だったのだ。
三月一日、土曜日。やっと今日から三月だ。嬉しい。子供たちの待っている日本へ帰国する夏が近づいて来たからだ。あと六カ月。そのうち、ガンビアのこの「白塗りバラック」で今のようにして暮すのは、三月、四月、五月とケニオンの卒業式が行われる六月はじめまでの三カ月余りだ。残りの日を大事に過さねばならない。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「モヒカン州立公園」)
ガンビアでの生活は、ほぼ、地域の人たちとの交流に費やされている。
話しているうちにミノーの目から泪が滲み出た。私は努めてなんでもないように話そうとしたが、ミノーの目の泪とその沈んだ、悩ましい表情を見ると、私の目にも泪が出て来た。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「あや取り」)
ミノーが涙を流したのは、大学側の判断により、住宅の引っ越しが行われることになったからだ。
その引っ越しは、庄野夫妻にとって不利な内容のものだったため、ミノーとしては申し訳ない気持ちになってしまったらしい。
ガンビアにやって来て、三か月が経ったばかりの頃で、既に、濃厚な人間関係ができあがっている(これは一月二日の出来事だった)。
オハイオのその田舎の小さな町では、私は遠くアメリカへ来ているということを忘れている日の方が多かった。(庄野潤三「二つの絵葉書」1955年12月『温泉』掲載)
庄野さんにとって、ガンビアでの暮らしは、あくまでも日常生活の延長線上にあったらしい。
日記を読んでいても、特殊な生活を過ごしているような緊張感は、まったくない。
サトクリッフさんの長男のジョンは、相変らず愛想がいい。妹のセーラは近所の友達の家へ遊びに行っていて、あとから帰って来た。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「玉蜀黍畑の矢じり」)
フィンランド帰りのセーラは、単行本未収録の短篇「セーラの話」の主人公だ。
当たり前だが、かつて、短篇小説として発表されたエピソードが、本作『懐しきオハイオ』では、あちこちに散りばめられている。
食堂の戸棚のところに妹が四、五人の男の学生に囲まれて花束を手に立っている写真が飾ってあった。最初家の中へ入ったとき、その写真が妻の目にとまると、スカランジェロさんは、「それは妹が今年カレッジのクイーンに選ばれたときの写真です」といった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ニューヨーク」)
スカランジェロさんのエピソードは、「イタリア風」という短篇小説になった(作品集『静物』所収)。
マーティニはミノーに作って貰った。ギルビーの壜の小さな蓋に注いで、数えながらジンを先ず入れる。そのあとで「12だから4と1の割合だとベルモットは3だ」といってベルモットを入れる。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ココーシングの水」)
ミノーのマーティニのレシピは、「四対一」という短篇小説にもなっている(単行本未収録)。
ミノーとジューンのエディノワラ夫妻は、ガンビアにおける庄野夫妻の良き隣人であり、相談相手であり、仲間であった。
帰って、家からオールド・ヒッコリーを持って来てミノーの家で飲み、夕食を御馳走になった。ポット・ローストあるいはチャック・ローストという部厚い牛肉(高くない肉だそうだ)を四時間、弱い火で煮たシチューが出た。こんなふうにあり合せの料理で一緒に食事するのを、「ポット・ラック」というのだとミノーが教えてくれる。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「雪の日」)
ミノーとジューンがいなかったら、この『懐しきオハイオ』も、さぞかし味気ないものとなっていたことだろう。
そういう意味で、重要な人物としてもう一人、ニコディム夫人がいる。
数学のニコディム教授の細君であるニコディム夫人は、自ら運転する自動車で、庄野夫妻をあちこちへと案内してくれた。
ニコディムさんが七時四十五分に迎えに来てくれた。「夏子が学級委員に任命された」というと、とても喜んで、走り出す車のなかから大きな声で、「マイ・ナツコ」といった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「春近づく」)
長女(夏子)は、新学期から小学五年生。
帰国前の挨拶をしたときの話もいい。
ほかに妻が留守宅の三人の子供、夏子、龍也、和也の写真を上げる。その写真を受取ったニコディムさんが「これがナツコ、これがタチア……」といいかけると、妻が泣き出した。「泣いてはいけない。泣いてはいけない」といいながら、ニコディムさんは妻を抱いて、頬に接吻をした。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「干草刈り」)
遠く東京にいる子どもたちまでも、ニコディム夫人にとっては、愛しい家族のような存在になっていたらしい。
この前、家から送って来た子供の写真を見せると、ニコディムさんは、夏子が優しくてスイートだといって、喜ぶ。ニコディムさんは本当に夏子が気に入っているのである。こんな子は珍しいという。そうして、「リトル夏子に手紙を書けるように日本語を勉強したい」という。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「戸外生活」)
庄野夫妻が、ガンビアでいかに充実した日々を過ごしたかが理解できるエピソードだろう。
教師陣の家族ばかりでなく、大学生と交流も多い。
ロドニイ南は、窓のそばの書き物机へ自分の皿を持って行き、身体を斜めに開いて、かがみ込んでせっせと食べ、「テリヤキ、ヴェリイ・グッド」「フライド・ライス(炒飯)、ヴェリイ・グッド」といって、満足の様子である。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「玉蜀黍畑の矢じり」)
若い学生たちとも、庄野夫妻は気軽に交際していた(ちなみに、渡米時の庄野さんは36歳だった)。
ジニイの話によると、ジニイとトムとジョーの三人がクリーヴランドまで汽車で帰り、そこからバスでマウント・バーノンへ帰って来る途中、ジョーの隣の席に一人の娘が坐った。それはジニイによると、「とてもナイスで、とても優しくて、とても知的な」女性で、ガンビアからそんなに遠くない何とかいう町の学校の先生をしている。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「パタースンさんの卵」)
海外生活における日記文学を支えていたのは、国籍や世代を超えて親しく交流した、アメリカで暮らす人々だった。
現地の人々との交流は、「ヒューマン・ドキュメント(人間記録)」でもある(これが二つ目のポイント)。
マッキーさんは話した。ずっと前、若かったころ、友達がロサンゼルスへ行くことになった。それを聞いたとき、自分の心はジャンプした。前から行きたいと思っていた。で、ロサンゼルスまで行って、そこで職を探した。当時は就職難で、職がなく、ロサンゼルスからサンフランシスコへ行った。サンフランシスコでドラッグストアに職が見つかり、約半年、働いた。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「マッキー農園」)
マッキーさんは、短篇小説「マッキー農園」の主人公だ(作品集『道』所収)。
ベンダーという背の高い、おとなしい学生とジニイと三人で話をしたが、このベンダーは非常に気持のいい学生。お父さんは死に、お母さんがいまキャンサー(癌)だという。高校を出て工場で働いていたら、奨学金が貰えたのでケニオンへ来た。学問することの喜びを知った今は、もとの職場へ戻ったら不幸に感じるだろう。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「オーロラ」)
本作『懐しきオハイオ』には、膨大な登場人物が出てくるが、どの人物も、ひとつの物語の主人公になりそうな人たちばかりだ。
カリードのお父さんとお母さんは、パレスチナで起ったユダヤとアラブとの戦争で死んだ。このとき、アメリカがユダヤを応援した。アラブはどこからの武器の援助もなしに戦って、沢山死んだ。カリードの心には父と母をこの戦争で失った悲しみがあり、それがアメリカに対する反感につながっているようだ。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「肥沃なるガンビア」)
ほんの数回しか名前の出てこないような人物にも、もちろん、それぞれの人生がある。
庄野さんは、出会った人たち一人一人の人生に、いつでも高い関心をもって接していた。
トニイ瀬戸はサファモア(二年)で、ニュージャージーから来ている。非常に親しみを示す子だ。私にどんな作家が好きかと訊く。アメリカの作家を順番に名前をあげてから、イギリスのチャールズ・ラムがいちばん好きだというと、自分もラムは好きだという。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「玉蜀黍畑の矢じり」)
『懐しきオハイオ』が、超大作となったのは、こうしたヒューマン・ドキュメントの要素が含まれているからとも言える。
ロドニイは、私が日本語を話すのを聞くと、亡くなった父を思い出す、家の中でもう誰もそんなふうに日本語を話す人がいないから、といった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「果樹園」)
庄野さんの視線は、特に、出会った人々の家族へと向きがちである。
ブラウンフィールドさんは、こんな話をした。「母はハワイで生れた二世であるが、祖母から日本の女性としての厳しい躾を受けて大きくなった。戦争が終って暫くして初めて日本へ帰った。すっかり変った日本人を見て、ハワイへ帰って来て泣いた。その悲しみは、とても大きかった」(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「水のほとり」)
一人の人間の向こう側に、多くの家族の影がある。
ジニイがニューヨークのことを話すときの顔は、うっとりしている。ニューヨークが本当に好きなのだ。亡くなった父が戦後に読んでいた、ブロードウェイを愛した作家デイモン・ラニアンのことを訊いてみると、ジニイも好きで、デイモン・ラニアンの書いたものなら殆ど読んでいるという。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ケリーズ島」)
登場人物の話が、自分の家族へとオーバーラップする傾向は、『懐しきオハイオ』では珍しくない。
テーブルにいたお父さんは、カップを持って戻って来る息子をとても嬉しそうに見て、手を差出して握手した。こういう情景を見ると、胸がいっぱいになる。八年前に亡くなった父のことを思い出さずにはいられないからだろうか。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「お別れピクニック」)
とりわけ、八年前に亡くなった父に関する記述は多い。
コンツさんが話すのを見ていると、八年前に亡くなった父のことを思い出す。頭がきれいに禿げているからだろうか。身体つきも似ている。亡くなったときの父は六十三歳だから、いまのコンツさんよりもっと年を取っていたのだが、元気のいいところが似ている。私がロックフェラー財団の研究員として、こうしてガンビアへ来ることが分れば、どんなに父は喜んだだろう。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「戸外生活」)
ちなみに、この作品を連載しているときの庄野さんは、68歳である。
物語の中で、庄野さんは、すっかりと36歳のときの自分に若返っているのだ。
大方の父親は頭が禿げている。こうしてみると、頭の禿げているのもいいものだなという気がする。本当によくやって来た、信頼すべき父親という感じがする。八年前に亡くなった私の父も、頭が禿げていたのを思い出す。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「果樹園」)
庄野さんは、二月で37歳になった。
今年の春のダンス・ウィークエンドのときであったが、ウイルソンへ行くと、主人が、「昨夜、ダンスに行ったか」と訊く。「いや、行かない。学生のなかに入ってダンスするには、年をとり過ぎた」と私がいうと、ウイルソンはむきになって、「そんなことはない。人生は四十から始まる」といい出した。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「出発」)
作家の視点は、日本とかアメリカとかいう国籍よりも、むしろ、どんな人生を歩んできたかということにフォーカスされている。
そして、こうした視点こそが、『懐しきオハイオ』を深みのある人間物語にしているのだろう。
紀行文学であり、家族小説でもある
ポイントの3つめは、本作『懐しきオハイオ』は、紀行文学としての性格を有しているということである。
ガンビア滞在中、庄野夫妻は、アメリカ各地を旅行している。
モヒカン州立公園へ行った。この登り口のところからモヒカン川を眺める景色がよかった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「モヒカン州立公園」)
短篇小説にもなったモヒカン州立公園行きは、ニコディム夫人の企画によるもので、多くのドライブ旅行は、ニコディム夫人の運転する自動車に乗ったときのものだ(短篇「モヒカン州立公園」は『屋上』所収)。
ニコディムさんが昨日、電話でコロンバスの博物館へ連れて行ってくれることになっていたが、天気が急によくなったので、予定を変更して、ガンビアから七十五マイルほど離れたオハイオ・キャバーン(洞窟)とインディアン・レークへ行くことになる。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「湖の景色」)
ニコディム夫人は、とにかくフットワークの軽い女性だった(夫のオットンは、外出があまり好きではない)。
五月十三日、火曜日。晴。朝、九時にニコディムさんの車でガンビアを出発して、エリー湖のケリーズ島へ向った。マンスフィールドから北へ行くのは、今度がはじめてである。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ケリーズ島」)
「ケリーズ島」も短篇小説として発表されている(作品集『道』所収)。
ニコディム夫人とのドライブ旅行が、庄野夫妻のガンビア生活に、豊かな変化を与えてくれたことは間違いない。
三月三十一日、月曜日。メンフィスに着いたとき、外はまだ真暗だった。バスから下りたとたんに目に入ったのは、WHITE WAITING ROOM という大きな文字であった。これには、どきんとした。日本にいるときから、南部での黒人の差別について聞かされていたが、アメリカに来て半年たつうちに、そんなことはすっかり忘れてしまっていたからだ。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「南部の旅」)
夫人と二人きり、グレイハウンド・バスで南部を旅行したときのことは、複数の短篇小説にもなっている(「南部の旅」「静かな町」「湖上の橋」の三部作)。
長篇『貝がらと海の音』(1996)では、トム・ソーヤーの歌について書かれた文章がある。
もう三十何年も前のことだが、ロックフェラー財団の給費留学生としてオハイオ州ガンビアのケニオン・カレッジに妻と二人で一年間暮した。春の休みにグレイハウンドバスで南部を旅行した。その旅の途中、ヴィックスバーグで下車して、一泊を予定しているナチェッソ行きに乗り換えるとき、足もとの崖のはるか下を流れるミシシッピーが目に入った。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
「春の休みにグレイハウンドバスで南部を旅行した」とあるのが、この「南部の旅」である。
ニューヨークに近づくと、興奮して来る。私たちの車はニュージャージーの方から入ったが、ニューヨークのそばまで来ると、それまで田舎であったのがたちまち大都会らしくなって来る。摩天楼が遠くに見えたときは、「ああ、これがニューヨークだ」といいたくなった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ニューヨーク」)
卒業式後には、学生と一緒にニューヨークを訪れ、妹(渥子)の自宅で夕食を御馳走になった(主人の八郎君が住友商事のニューヨーク支店へ転勤になったばかりだった)。
夕食は亡くなった母が家で何かあると作った、父母の郷里の徳島風の「かきまぜ」(まぜずし)とカツレツ。(ビフテキとカツレツとどちらがいいかと妹に訊かれ、これもこんなとき母がよく作ったビーフカツレツを希望した)。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ニューヨーク」)
「夫婦の晩年シリーズ」でも有名な「かきまぜ」が、ニューヨークのディナーに登場している(笑)。
雨の中をレキシントン、コンコードの古戦場へ行く。『若草物語』のオールコットの家の前を通る。この家は、中へ入って見たかった。エマソンの家がある。コンコードのあたりは市中よりずっといい。ウォールデンの池も見える。昔、学校のころ、辞書を引きながらソローの『ウォールデン』を読んだ思い出があるので、懐かしい。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ニューイングランドの旅」)
ガンビアの日常生活もいいが(それだって十分に非日常だが)、アメリカの国内旅行記もいい。
紀行文学としての『懐しきオハイオ』も、非常に充実した作品なのだ。
最後に、4つめのポイントは、本作『懐しきオハイオ』では、アメリカにいながら、日本の様子が丁寧に紹介されているということだろう。
阪田寛夫が石神井公園の留守宅へ行って録音してくれたテープは、十歳になる長女の夏子の、「お父ちゃん、お母ちゃん。明けましておめでとうございます」という挨拶で始まった。しっかりとした声であった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「雪の日」)
アメリカにいる庄野夫妻の最大の心配事は、日本に残してきた三人の子どもたちだった(夏子10歳、龍也7歳、和也2歳)。
家の二通は母からの手紙で、龍也の入学通知書が届いたのを見ると、石神井東小学校となっているので大変心配し、翌日、夏子の通学している光和小学校の校長先生に会って話したところ、区役所へ電話をかけてくれて、無事に光和小学校への入学が認められたということが書いてあった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「オーロラ」)
長男(龍也)が小学校へ入学するとき、両親はアメリカへ行っていて不在だった。
龍也がランドセルを背負って、ズック靴の上履き入れをさげている写真。帽子も服も新品のだぶだぶで、全くの新入生といった恰好。うんと照れていて、しかし、嬉しそうに写っている。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「春近づく」)
1958年(昭和33年)、庄野家最大のビッグ・イベントは、本当は龍也の小学校入学になるはずだったのだ。
家のは夏子と龍也の手紙で、二月九日の和也の誕生日に安岡の奥さんが治子ちゃんを連れて、大きなケーキの上に「和也ちゃんおめでとう」と書いたのを持って、石神井公園の家へ来てくれたときのことを書いたもの。「お父ちゃん、おたんじょう日おめでとう」と最初に夏子が書いている。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「オーロラ」)
庄野夫妻の留守中、安岡章太郎夫婦が、子どもたちの心配をしていたらしい(娘の安岡治子は、現在、東大のロシア文学者として活躍中)。
それから、悲しいのは、渡米前に仔犬で貰って来たベルがジステンパーで死んだ知らせがあったことだ。石神井公園の家で飼っていたレオが死んだあと、すぐに貰って来たベルだ。夏子を自転車のうしろに乗せて練馬の獣医の家へ出かけて行ったのは、かんかん照りの日であった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「湖の景色」)
日本の様子は、家族や友人たちが、逐一手紙で報告してくれた。
家へ帰って、いちばん先に留守宅からの七通の手紙を日附の順番に読む。NHKの「私の本棚」での『ザボンの花』の朗読がとてもよかったという。放送が始まる日、丁度学校が二時間で早く家へ帰れたので、夏子も龍也も和也もみんなラジオの前に坐り、「庄野潤三作ザボンの花」とアナウンサーがいうと、拍手をもって迎えたという。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「干草刈り」)
小沼丹からの手紙もある。
三月二日、日曜日。アメリカへ来て初めてハング・オーバーを経験する。去年、小沼丹から届いた手紙に、二人でよく飲みに行った新宿の樽平のマッチを平たくしたのが入っていて、「そちらでハング・オーバーはやりましたか?」と一行だけ書いてあった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「モヒカン州立公園」)
ハング・オーバーとは二日酔いのこと。
井伏さんは盲腸の手術を十二月三十一日になさったあと、二十四日に荻窪病院を退院、いまは傷口の手当に通っているが、これが終り次第、甲府の湯村温泉へ湯治に出かけるということで、「暫く休養して、自然に書きたくなるのを待つことにします。かなり落着いた気持です。御放念のほど願います」とある。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「花みずき」)
井伏鱒二の名前は「侘助の会」での寄せ書きなどにも見られる。
手紙は久しぶりに井伏さんから。「病気が治ったのはいいけれども、元気になり過ぎてかえって仕事が出来ないので、一計を案じ、毎週日曜日に荻窪の近所の新本さんのアトリエへデッサンに通うことにした。この間はアトリエの人たちと一緒に南伊豆へ三日間、写生旅行に行った。絵の勉強をするのは、釣りをするよりもまだ楽しい」と書いてあった。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「水のほとり」)
アメリカ生活の日記なのに、日本の話が頻繁に出てくるところが、『懐しきオハイオ』の大きな特徴ということなのだろう。
当時の井伏さんの生活については、『荻窪風土記』(1982)に詳しい。

久しぶりに夜、雨の音を聞いた。亡くなった父の夢を見た。ガンビアへ来てから、よく父や母の夢をみる。ついこの間は一昨年の四月に亡くなった母の夢を見た。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「玉蜀黍畑の矢じり」)
本作『懐しきオハイオ』においても、根底にあるのは、家族の物語である。
つまり、本作『懐しきオハイオ』は日記文学の形式を採っているが、内容的には家族小説の色彩が濃厚な長篇小説だった、ということだ。
その上、しっかりと、アメリカ旅行を綴った紀行文学としての性格も備えており、ボリュームに負けないくらいに、内容も深い。
本作『懐しきオハイオ』は、単なるアメリカ滞在記ではない、壮大な総合小説だったのである。
ドラマチックな事件はなくとも、登場人物の一人一人が背負った人生の深みが、この物語にはある。
どうして、この作品が、庄野潤三の代表作として挙げられないのだろうかと、疑問に思えるくらいだ。
『懐しきオハイオ』には、庄野潤三という作家が持つ魅力が、すべて含まれていると言ってもいい。
ドロシイの級友であった人の家も小高い丘の上にある。大きい家。まだ小学校へ行っているくらいの女の子と男の子が驢馬に乗って前の林で遊んでいた。柵があって、外へ出られないようになっている。東京の留守宅で私たちの帰国を待っている夏子や龍也らにこんな生活をさせてやることが出来たらと思った。(庄野潤三『懐しきオハイオ』より「ニューイングランドの旅」)
ある程度、庄野文学を読み進めた読者は、ぜひ、『懐しきオハイオ』にも手を伸ばしていただきたい。
その際、『ガンビア滞在記』『シェリー酒と楓の葉』の順に読むのではなく、『懐しきオハイオ』一冊だけでも、十分な満足感が得られることだろう。
『懐しきオハイオ』は、庄野潤三の代表作と言ってもいいほど、素晴らしい名作なのだから。
書名:懐しきオハイオ
著者:庄野潤三
発行:1991/09/25
出版社:文藝春秋