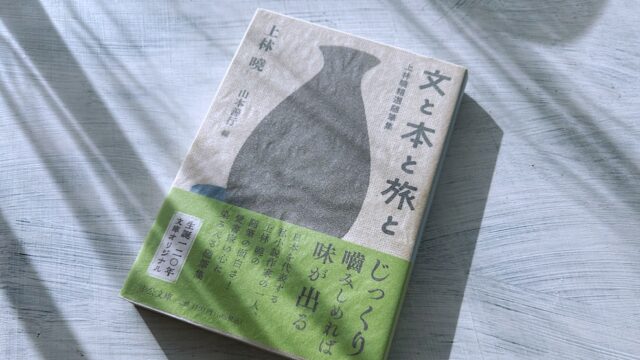『ねじまき鳥クロニクル』という物語のピースが一つに繋がるとき、我々はそこに「赤坂シナモン」という一人の少年が綴った、巨大な「年代記(クロニクル)」を目にすることになる。
なぜ、この物語は、単なる夫婦の再会ではなく「クロニクル」と呼ばれなければならなかったのだろうか。
今回は、物語の最終的な構造と、各エピソードをつなぐ「ねじまき鳥」というメタファーの真意について考察したい。
バラバラの記憶が、新京の動物園から現代の井戸の底まで一つの線で結ばれるとき、この物語が「最高傑作」と評価される真の理由が明らかになるだろう。
赤坂親子が担う「物語の継承」
物語の後半で、圧倒的な存在感を放つ赤坂ナツメグとシナモン。
彼らには、物語全体をつなぐ重要な役割が与えられていた。
赤坂シナモンの『ねじまき鳥クロニクル』
『ねじまき鳥クロニクル』は、言葉を失った少年(シナモン)が、パソコン上で綴る物語群の名称でもある。
つまり、『ねじまき鳥クロニクル』は、村上春樹の書いた小説であると同時に、「シナモンが書き直した歴史」という多重構造を持っていたわけだ。
シナモンの作りあげた物語群に「クロニクル(年代記)」というタイトルが与えられている理由は、シナモンの歴史は、シナモン一人の人生によってのみ語られるべきものではなかったからである。
シナモンは、自分という人間を語るために、祖父の生きた満州国にまで遡らなければならなかった。
おそらくシナモンは自分という人間の存在理由を真剣に探しているのだ。彼はそれを自分がまだ生まれる以前に遡って探索していたに違いない。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
シナモンの「クロニクル」は、彼一人の人生に留まらず、祖父が経験した満州国の虐殺にまで遡らなければ語り得ない、歴史としての「クロニクル」だったのである。
動物園の虐殺という原罪
シナモンの『ねじまき鳥クロニクル』で綴られる「動物園での虐殺」は、「札幌のギター弾き」のエピソードと共鳴するものだ。
銃剣を突き刺し、かき回し、突きあげ、抜いた。獣医は無感動にそれを眺めていた。彼は自分が分裂を始めているような錯覚に襲われた。自分は相手を刺すものであり、同時に相手に刺されるものだった。彼は突き出した銃剣の手ごたえと、切り刻まれる内臓の痛みを同時に感じることができた。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
激しいほどの痛みへの共感。
シナモンの物語は「Zoo」というパスワードによって管理された。
ナツメグの父(獣医)が目撃したその惨劇は、シナモンへと語り継がれ、やがて、主人公の「野球バット」へとつながっていくことになる。
メタファーとしての「ねじまき鳥」
「ねじまき鳥」は作品の通奏低音であり、最も重要な象徴でもある。
姿を見せることのない「ねじまき鳥」は、いったい何を意味していたのだろうか?
運命を司る「見えない手」
すべてのピースをつなぐ通奏低音となっているのが、作品タイトルでもある「ねじまき鳥」である。
「ねじまき鳥」の姿を見た者はいないし、その鳴き声も、誰にでも聴くことのできるものではなかった。
「ねじまき鳥」は、「運命」や「宿命」といった抽象的な言葉を具現化する象徴ととらえていい(それは「時代の流れ」という意味にもなる)。
「世の中の人々はみんなもっと立派で複雑で巨大な装置がしっかりと世界を動かしていると思っている。でもそんなことはない。本当はねじまき鳥がいろんな場所に行って、行く先々でちょっとずつ小さなねじを巻いて世界を動かしているんだよ」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
しかし、ねじまき鳥が本当に力を発揮するのは、バラバラになった複数のパズルをつなぎ合わせる効果を発揮したときだろう。
ピースをつなぐパスワード
例えば、赤坂シナモンが言葉を失った夜も「ねじまき鳥」が鳴いているし、シナモン少年と獣医だった祖父をつないでいるのも、やはり「ねじまき鳥」だった。
「ねじまき鳥」は、複数の時代と複数の人々とをつなぎ合わせるパスワードとして機能していたのだ。
獣医(シナモンの祖父)は、子どもの頃から「自分という人間は結局のところ何かの外部の力によって定められて生きているのだ」という思いを抱いて生きていた。
彼らは人形が背中のねじを巻かれてテーブルの上に置かれたみたいに選択の余地のない行為に従事し、選択の余地のない方向に進まされた。その鳥の声の聞こえる範囲にいたほとんどの人々が激しく損なわれ、失われた。多くの人々が死んでいった。彼らはそのままテーブルの縁から下にこぼれ落ちていった。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』第3部 鳥刺し男編29│シナモンのミッシング・リンク)
『ねじまき鳥クロニクル』という作品の素晴らしさは、「ねじまき鳥」というメタファーに尽きると言っていい。
「ねじまき鳥」という概念こそが、やがて「彼の最も優れた小説」という評価を受けることになる、最大のポイントだったのだ。
鳥が「ねじ」を巻くとき、人々の運命は動き出し、バラバラだったパズルがつながり始める。
あるいは、それは、異なる時代の人々と共鳴する「共通言語(パスワード)」としても機能していたのかもしれない。
夏目漱石『門』の影響
著者(村上春樹)は、『ねじまき鳥クロニクル』を執筆するにあたり、「夏目漱石『門』のイメージがあった」と発言している。
「門」を叩く男たちの物語
夏目漱石の『門』で「宗助」と「御米」は、社会から隔絶された世界で生きる夫婦として描かれている(なにしろ、世の中の常識に逆らって結婚した二人だった)。
漱石の『門』で、主人公(宗助)は禅門を叩くが、何一つ得ることができないまま、禅門から帰ってくる。
一方、『ねじまき鳥』の主人公は、井戸に潜り、壁を抜け、暗闇の世界に潜む「心の闇」を殴り殺して、現実世界へと生還する(一種の「勇者伝説」)。
「妻の心」へのコミットメント
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、妻の「心の闇」にコミットしようと努力する夫の物語だ。
少なくとも『門』よりも『ねじまき鳥クロニクル』の方が、「妻の心」にコミットしようとする姿勢が明確である。
あるいは、妻の「失踪」は、象徴としての「失踪」であったかもしれない。
自分の心の中に引きこもってしまえば、それも、ひとつの「失踪」である。
大切なことは、「心の中の見えない部分」に、どのようにしてコミットしていくかということだ。
ある意味で『ねじまき鳥』は、近代文学が描き得なかった「他者への徹底的な関わり(コミットメント)」の現代的表現だったのかもしれない。
おわりに:涸れ井戸に水が湧くとき
物語の最終場面で主人公は、涸れ井戸に水が湧いていることを確認する。
「水」が暗示しているものは、主人公の「再生」だ。
壁を抜け、暗闇の世界で謎の女(本当のクミコ)と愛し合い、野球バットで綿谷ノボルを撲殺した主人公は、物語の冒頭時よりも多くの成長を成し遂げていた。
主人公の成長を支えたものは、様々な登場人物が語った「心の闇」である。
ほとんど「トラウマ」と言っていい「心の闇」は、人々の暗闇の中にひっそりと隠されてきたものだ。
主人公は、人々の「心の闇」に触れることで「歴史の闇」に触れ、妻(クミコ)の「心の闇」へと入り込むことができたのである。
本作『ねじまき鳥クロニクル』は、「ねじまき鳥」という不可解な運命に翻弄されながらも、いかにして他者の心に触れ、再び現実へと這い上がることができるかということを、我々に問い続けているのではないだろうか。
以上で、『ねじまき鳥クロニクル』に関する考察記事は完結となるが、物語全体の俯瞰的な考察や、「なぜ本作が特別なのか」という問いの最終的な答えについては、ぜひ親記事の方で改めて確認していただきたい。
▶親記事 [村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』徹底考察|なぜ最高傑作と呼ばれるのか?
]へ戻る

書名:ねじまき鳥クロニクル
著者:村上春樹
発行:1997/10/01
出版社:新潮文庫