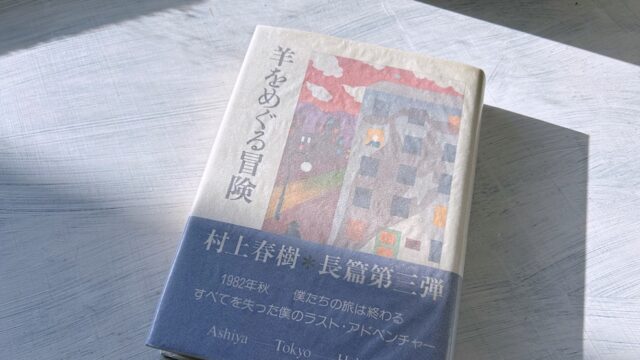村上春樹の長編『ねじまき鳥クロニクル』の読者が、必ず直面すると言っていい不思議な違和感がある。
なぜ、主人公(岡田亨)は、暗闇の底にある「井戸の底」へと降りなければならなかったのか?
そこで体験する「壁抜け」は、何を意味しているのか?
卑猥な電話をかけてくる「謎の女」の正体とは一体誰なのか?
村上春樹が仕掛けた数々のメタファー(隠喩)は、単なる記号ではなく、我々の潜在意識に潜む「欲望」や「痛み」を呼び起こすための装置として読むことができる。
加納クレタという肉体的な娼婦が象徴する「妻の化身」の役割や、河合隼雄との対話でも語られた、他者の魂に触れるための「下降」の儀式としての井戸。
物語のストーリーをたどるだけでは見過ごしてしまうだろう「性的欲望の根」と「クラゲ」が浮かぶ内面世界を、丁寧に考察してみた。
妻の化身としての女性たち:加納クレタと謎の電話
失踪した妻(クミコ)の輪郭を浮き彫りにするのは、彼女の「化身」として現れる女性たちの存在である。
加納クレタという肉体的・意識的娼婦
加納クレタは、クミコの兄(綿谷ノボル)によって「意識をこじ開けられた」存在であり、その体つきは驚くほどクミコに似ている。
それから奇妙なことが起こりました。そのぱっくりとふたつに裂けた自分の肉の中から、私がこれまでに見たことも触れたこともなかった何かが、かきわけるようにして抜け出してくるのを私は感じたのです。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
加納クレタが語る「自分の中から抜け出してくる何か」は、自覚しながらも見ないようにしていた彼女自身の「深層心理の象徴」に他ならない。
彼女の中にある「自分の中から抜け出してくる何か」は、笠原メイが語る「私の中にあったあの白いぐしゃぐしゃとした脂肪のかたまりみたいなもの」と同じものだ。
綿谷昇は、それを「欲望の根」と呼んでいる。
「動機というものはいうなれば欲望の根です。大事なのは、その根をたどることです。現実という複雑さの地面を掘るのです。それをどこまでも掘っていくのです。その根のいちばん先のところまでどこまでも掘っていくのです」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
つまり、『ねじまき鳥クロニクル』は、人の心に潜む「欲望の根」を掘るための物語だった、ということだ。
卑猥な電話の主
物語冒頭で主人公を翻弄する「謎の女」は、クミコの潜在意識下における「真の姿」の投影である(つまり「もう一人の自分」)。
僕は短く息をのみ、ゆっくりとそれを吐き出す。吐き出す息はまるで焼けた石のように固く、熱い。間違いない。あの女はクミコだったのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
日常の平穏な夫婦生活の裏側に、ポルノ・テープのような生々しい性的欲望が隠れていることを、この電話は残酷に告げている。
主人公は「加納クレタ」という妻の分身を通して、妻の潜在意識(欲望の根)にまで降りていったのだ。
メタファーとしての「井戸」と「壁抜け」
『ねじまき鳥クロニクル』において、「井戸に降りる」行為は単なる自己探求を超え、フロイト的な「イド(エス)」、あるいはユング的な「集合的無意識」への下降を意味していると読むこともできる。
「井戸」を掘るというコミットメント
心理学者・河合隼雄が説くように、他者を真に理解するためには、理性による対話ではなく、暗闇の底にある「井戸」を共有しなければならない。
主人公が空き地の涸れ井戸に潜るのは、クミコの深層意識へ物理的にアクセスするための「下降」の儀式だったのだ。
井戸の底で主人公が見たものは、妻(クミコ)が堕胎したときの記憶である。
たぶんあの時から何かが変わり始めたんだ、僕はふと思った。間違いない。あの時を境として僕のまわりで流れが確かな変化を見せ始めたのだ。今になって考えてみれば、あの堕胎手術は僕ら二人にとって、非常に重要な意味を持つ出来事だったのだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
クミコがなぜ失踪したのか?
その根源的な理由に、主人公は近づきつつあった。
「壁抜け」の心理的跳躍
潜在意識下におけるワープ現象「壁抜け」は、心の中の境界線を無効化する行為だ。
部屋の暗闇の中に廊下の光がさっと差し込むのとほとんど同時に、僕らは壁の中に滑り込んだ。(略)僕は壁を通り抜けているんだ。(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
壁の向こう側で「謎の女」と交わることで、主人公は初めて、現実世界では到達不可能だった「妻の本質」にコミットすることができる。
「井戸掘り」と「壁抜け」は、現代社会における求められるコミュニケーションを暗示していたのだ。
クラゲが象徴するもの
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』では、「カタツムリ」が自我の強固な殻を象徴していた。
同じように『ねじまき鳥クロニクル』では「クラゲ」が、意識の深層を浮遊するとらえどころのない、しかし確実な実体を持つ「不安」のメタファーとして機能している。
「だからその家の中で君はいつも孤独であり、いつも緊張していた。得体の知れない潜在的な不安の中にひっそりと暮らしていた。まるであの水族館のクラゲみたいにね」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
クラゲは「心の闇」に潜む「本当の自分」の象徴である。
我々の心の奥底にも、もしかすると「クラゲ」が漂っているのかもしれない。
笠原メイという案内人
空地の井戸へと導いてくれた笠原メイは、主人公(岡田亨)の意識下の管理人として機能している(「双子の女の子」や「羊牧場の管理人」と同じように)。
それは、現実と虚構の境界線に立つ「神話的な存在」でもあった(いずれも、村上春樹の小説では定番のキャラクターである)。
笠原メイは、「私の中にあったあの白いぐしゃぐしゃとした脂肪のかたまりみたいなもの」によって、妻(クミコ)ともつながっている。
「ねえ、ねじまき鳥さん、私には世界がみんな空っぽに見えるの。私のまわりにある何もかもがインチキみたいに見えるの。インチキじゃないのは私の中にあるそのぐしゃぐしゃだけなの」(村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』)
ねじまき鳥が鳴くとき、人間の中の「闇」が姿を現すとしたら、もしかすると、笠原メイは、目に見えない「ねじまき鳥」を具現化した存在だったのかもしれない。
メタファーの先にあるもの
村上春樹の小説には「メタファー」が多い。
その「メタファー」を読み解くことが、村上春樹の小説を読み解くということでもある。
主人公は、なぜ「井戸を掘り」「壁を抜けた」のか?
そこには、自分の心の奥底深いところまで潜って「本当の自分自身」と対話し、そのことによって初めて「他者」とつながることができるのだという、作者(村上春樹)の強いメッセージがある。
人と人とがわかり合うためには、それなりの代償が必要だということを、この物語は教えてくれるのではないだろうか。
しかし、この物語は、主人公の「個人的なトラウマ」だけに終わる物語ではない(ここがすごい)。
主人公の「心の闇」は、やがて、より根源的で巨大な「暴力の記憶」へとつながっていく。
個人の深層心理に潜む「クラゲ」のような欲望は、いかにして国家レベルの「悪」へと変貌していくのか?
次回は、物語を貫くもう一つの巨大な軸である「歴史と暴力」の断面を分析し、綿谷ノボルという宿敵が象徴する近代史の影を考察してみたい。
▶次の記事[『ねじまき鳥クロニクル』とノモンハン事件|個人の喪失と歴史の闇が交錯する理由]を読む

▶親記事「村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』徹底考察|なぜ最高傑作と呼ばれるのか?
」へ戻る

書名:ねじまき鳥クロニクル
著者:村上春樹
発行:1997/10/01
出版社:新潮文庫