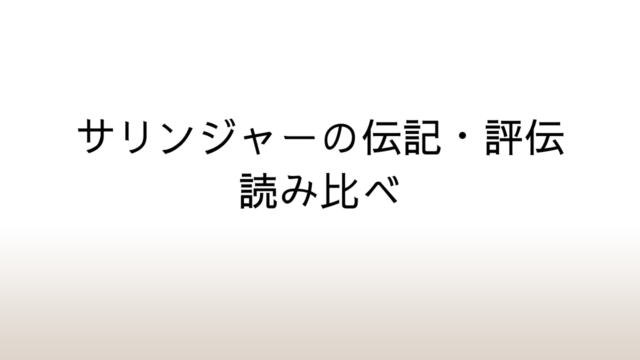庄野潤三「庭の山の木」読了。
本作「庭の山の木」は、1973年(昭和48年)5月に冬樹社から刊行された随筆集である。
この年、著者は52歳だった。
浮世ばなれした庄野ワールド
身過ぎ世過ぎの毎日には、憂鬱なことも多い。
通勤のこと、仕事のこと、家族のことなど、憂鬱の種はあちこちにある。
気持ちが滅入ったとき、僕は庄野さんの随筆集を読むことにしている。
どの本の、どのページでもいい。
庄野さんの随筆を読み始めた瞬間、生きる世界が変わったような気持ちになれる(イマジナリーな転生だ)。
本作『庭の山の木』の、例えば「好きな野菜」という随筆では、好物のふろふき大根のことを書いている。
まだ食べ出さないで、目の前の鍋に大根がいっぱい入っているのを眺めた時にも、ゆたかな気持になる。ひとりで全部食べるわけではない。ほかにも家族がいるから、そういうわけにはゆかない。(庄野潤三「好きな野菜」)
こういう文章を読んでいると、いかにも自分が急いで生きすぎているような気がして、くだらないことでくよくよしていた自分がバカバカしく思えてくる。
庭にやって来るつぐみを観察して、酒の飲み方を学んだのが「つぐみに学ぶ」だ。
つぐみは、いつも一羽で来る。これはよく飲む。ひと口飲み、またひと口飲み、またひと口飲むというふうにして、続く。急がず、慌てず、よそ見せず、いつやめても差支えないといった様子で飲む。(庄野潤三「つぐみに学ぶ──酔中酔余」)
文章のリズムが、ゆったりとしている。
めくるめく毎日を抜け出して、どこか別の世界に迷い込んだような、そんな読書を、庄野さんの本では体験することができる。
そんな別世界を、庄野さんは日常生活に普通にあるものから作り出してしまう。
庭に生えているノビルを見ているだけで、たちまち庄野ワールドが生まれる。
ノビルの生えている様子には、何か浮世ばなれのしたところがある。──漕げ漕げ ボート 流れにそいて──といった趣がある。私は、手にさわってみて、「よろしい、結構」といいたくなる。(庄野潤三「春の花・うぐいす」)
ノビルから「漕げ漕げボート」を連想し、「よろしい、結構」へつながっていく、こうした文章こそが、そもそも「浮世ばなれ」していると言いたい。
だからこそ、庄野さんの随筆は、魔法の随筆なのだ。
「郡上八幡」は、盆踊りの取材へ行ったときの紀行随筆で、この時期の庄野さんには、紀行随筆に良い作品が多い。
私たちはふだん東京にいて、朝顔のことなどすっかり忘れて生きている。それで郡上八幡の横町や裏通りのひっそり閑としたところで朝顔の花を見て、思わず立ちどまる。こんな生活があったのだなと思って、なんだか恥かしい気持がするのである。(庄野潤三「郡上八幡」)
旅行記なのに、自然と「生き方」の話になっているところが、庄野さんらしくていい。
他の作家にはない味の紀行随筆だと思う。
テレビ中継の取材に行っても、庄野さんは自分のペースを乱すことはない。
だれが悪いのでもない。そろわぬ時はとにかくそんなことになるものだ。そして、急ぐ時に限って、「片方よければ、片方まだ」という風になる。こういう時は、腹を立てても何にもならないので、ただ両方がそろうのを待つよりほかいないのである。(庄野潤三「三人のディレクター」)
鷹揚というか寛容というか、とにかく運命を受け容れる姿勢が、庄野さんの生き方だ。
「このひと月」は、文壇仲間と酒を飲んだ日々の日記を綴ったもの。
風呂から上って、飯を食べる。味噌汁を飲むと、いったんとまっていた汗が、頭の先からふき出して来る。湧き水のように出る。酒を多く飲んだあくる日は、ひとりでにこうなる。神に感謝しなくてはいけない。(庄野潤三「このひと月──酒中日記」)
飲み過ぎて調子が悪いとか、そういうことではなくて、「神に感謝しなくてはいけない」と書かれてあるところが、庄野さんらしい。
神楽坂にある紙屋から生田の山の上まで、原稿用紙の束を持って帰る話にも、そんな姿勢が感じられる。
さげているうちに少しずつ重くなるが、「これを重いと思ったら、罰が当たる」と自分に言い聞かせる。(紙屋の店員──私と原稿用紙)
こういう庄野さんの生き方は、「ゆとりときびしさ」で明確に示されている。
何かうまくゆかないことがあった場合に、もうこれでぶちこわしだと思い込まないで、一歩はなれて、違った角度から物事を眺めてみることの出来る人を、大人といってもいいだろう。(庄野潤三「ゆとりときびしさ」)
このエッセイのテーマは、「大人とはどういうことを指すのか」だった。
もうひとつ、「どんな場合にもいいわけをしない人というのが、大人であるだろう。ということは、自分のしたことに責任を持つ人である」ともある。
こうした「ゆとり」と「きびしさ」は、庄野さんの小説にも共通して見られる傾向だったような気がする。
アンコウという魚は海底で眠ったようにしていて、頭の上に小魚が来た時だけ、大きく口を開いて吸い込むそうだが、私はどちらかというとアンコウ的な作家の方が好きである。(庄野潤三「私の取材法」)
小魚を追いかけ回すような作家ではなく、アンコウのように「頭の上に小魚が来た時だけ、大きく口を開いて吸い込む」。
そんな生き方が、世の中にはあったのだ。
そして、庄野さんの人生は、アンコウ的な姿勢を生涯貫いた作家人生だった。
いくつかの随筆を読んで、気分がすっかりと切り替わったら、後は、庄野ワールドに没頭するだけだ。
ひたむきな人生肯定の文学
中村白葉の随想集『ここまで生きてきて 私の八十年』の書評にも、庄野さんらしさが溢れている。
机に向って、日記をつけているうちに薬罐の湯がたぎって来る。ここで中村さんは、砂糖入りのレモン湯をこしらえて飲む。あんまりおいしいので、時には思わず、「ああ、うまい」と声を出してしまうこともある。こういう文を読むと、身の引締まる思いがする。励まなくてはいけない。(庄野潤三「中村白葉随想集」)
自分で作った砂糖入りのレモン湯を飲んで「ああ、うまい」と声を出してしまう中村白葉の文章には、生きることに対する感謝がある。
庄野さんは、生きていることに感謝する気持ちを、非常に大切にしていた。
シェイクスピアの『夏の夜の夢』では、織物屋のボッタムが好きだった。
大工のクインさんが世話役で、配役もちゃんと決めてある。ところが、織物屋のボッタムは、どの役にも興味を持ち、自分ならこういうふうに演じてみせるのにという。このボッタムがおかしい。この元気あふれる人物に接すると、何だかこちらも生き生きして来る。シェイクスピアが身近になる。(庄野潤三「わたしと古典」)
庄野さんの随筆で欠かすことのできない存在が、福原麟太郎である。
『本棚の前の椅子』という随筆集の書評で、庄野さんは、饗庭篁村(あえばこうそん)について書かれた一篇を採りあげている。
この人の短編小説はおしまいが皆「めでたしめでたし」で終っている。それは「めでたしめでたしにならなくてはうそだ。人生の旅を楽しむ自分には、その旅が悲劇に終るなどという小説はとても書けない。めでたしめでたしでいいんだ」という考えで書かれたのであろうとある。そこまで読んだだけで私は饗庭篁村という人にひかれる。(庄野潤三「福原麟太郎『本棚の前の椅子』」)
人生とは楽しいものでなければならないという思想が、庄野さんの文学にはあった。
ひたむきな人生肯定の文学が、庄野文学だったとも言える。
ノエル・カワードを引用して、「五十六歳の彼は「そうさ、人生はいいものだよ」といっている。本当にそれはいいだろう」とあるのも、人生肯定の哲学だ(「春近し」)。
大学のダンスパーティーに参加しなかった庄野さんが「学生の間でダンスするには年を取りすぎた」と言ったとき、「そんなことをいうな。人生は五十からだ」と笑ったというアメリカ人の話もいい(「ウィルソン食料品店──写真に添えて」)。
家族生活の中でも、庄野さんは明るさを失わなかった。
子供向きに書いたのではない私の小説や随筆を、自分の子供が読むことがある。読んでいる途中でふき出してくれると、うれしい。大きな声でなくていい。ひとりでに笑ったのが分るような笑いかたなら、いい。(庄野潤三「子供の本と私」)
「生き生きした生活を捉えたい」というのが、庄野さんの文学的哲学だった。
ちょうど、このときは『明夫と良二』が、岩波書店から出たばかりで、大人と子どもとの関りも、大きな関心としてあったらしい。
ひと口に子供と大人といっても、実際の生活では分ち難く結びつき、ひとつの世界をつくり上げていることを、それでこそ哀歓は深まるのだということを、理解し、味わってもらえるものと信じている。(庄野潤三「子供の本と私」)
「変わらない景色はない」という人生観と、たちまち成長してしまう子どもたちの姿は、庄野さんの中で、何らかのつながりを持っていたのだろう。

作品との関わりで言うと、「ちいさな漁港の町」は、「蓮の花」という短篇小説になっているし(『絵合せ』所収)、ここから発展した物語は『引潮』という長篇小説にもなった。
今年の夏は、広島の親戚と一緒に山口県の白井田というところへ行った。広島から汽車で柳井まで行き、そこからバスに一時間乗ると室津に着く。渡し船で対岸の上関へわたり、今度は小型タクシーで山越えをする。そこは周囲七里の長島という島で、そのいちばん突端にちいさな漁港がある。ここへ行った。(庄野潤三「ちいさな漁港の町」)
さりげない紀行随筆だが、重要な作品である。

作家仲間では、小沼丹や吉岡達夫などの名前が見つかる。
同行は小沼丹、吉岡達夫、有木勉、新築の山小屋にわれわれを招いて、もてなしてくれたのは玉井乾介。彼だけあとに残る。酔漢四人の世話をして、さぞかしくたびれたことだろう。(庄野潤三「このひと月──酒中日記」)
これは、蔵王にある玉井乾介の別荘を訪ねたときのもので、その数日後には、井伏鱒二や三浦哲郎、横田瑞穂、新本燦(画家)と一緒に、小沼丹の家びらきの小宴に出席している。
いつものメンバーの名前が出てくると、読者としても、ほっと安心する。
文学青年の先輩というような心持ちで読みたい作家の作品として、木山捷平『昔野』、小山祐士『魚族』、中村地平『あをば若葉』などの名前が並んでいる(「熱帯柳の種子」)。
島尾敏雄と過ごした学生時代の思い出も含まれていて、若き日を回想した文芸エッセイほど楽しいものはないという感じがする。
そういう意味では、青柳瑞穂のことを回想した「青柳さんの思い出」も楽しい。
駅の近くの飲み屋で「いま、井伏(鱒二)先生と小沼(丹)先生が出て行かれたところです」と聞いて、あとを追いかけるように別の飲み屋へ行ってみる。
いい時代だったんだろうなあと、しみじみ思う(昭和47年発表の作品だった)。
『バングローバーの旅』が出たとき、安岡章太郎(『肥った女』)と二人で、出版社まで出かけて署名の作業をしたときの話も楽しい。
署名していると、途中で安岡が顔を上げて、「久保田万太郎に送ってみないか」といった。物は相談だが、というふうにいった。「ううん」私は、咄嗟のことで返事が出来なかった。「おれもまだ送ったことはないんだ」安岡はそういった。(庄野潤三「『肥った女』」)
二人とも印税をもらう前に、この出版社は潰れてしまったというから、この日のことは、なおのこと思い出深いものがあるだろう。
一冊の随筆集を読み終えると、気持ちがすっかりと晴々している。
庄野さんの随筆集は、僕にとって、心の処方箋みたいなものかもしれない。
最近の言葉で有体に言えば「元気をもらう」、そんな随筆集だった。
巻末に、庄野さんの長女・今村夏子さんの文章が収録されていることも、特筆すべきことだろう(今村夏子「父のハガキ」著者に代わって読者へ)。
書名:庭の山の木
著者:庄野潤三
発行:2020/02/10
出版社:講談社文芸文庫