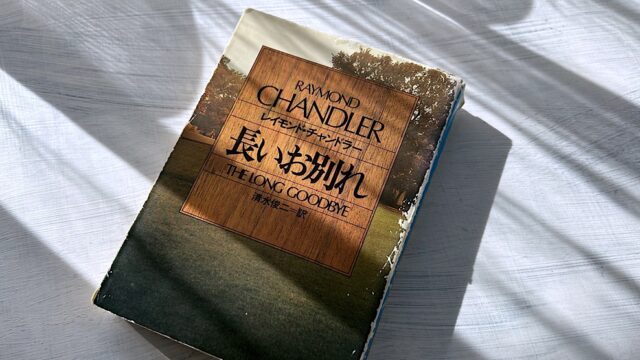横田瑞穂「山桃」読了。
本作「山桃」は、1992年(平成4年)1月、故・横田瑞穂の七回忌にあたり、遺族によって編纂された随筆集である。
著者の横田瑞穂は、1986年(昭和61年)2月19日、静岡県伊東市の自宅で逝去。
享年82歳だった。
小沼丹や庄野潤三との交流
横田瑞穂といえば、戦後期に活躍したロシア文学の翻訳家として知られている。
同時に、井伏鱒二や小沼丹との交友でも有名な人で、井伏さんや小沼さんの作品で、横田瑞穂の名前を見かけることも珍しくない。
特に、小沼丹とは、早稲田大学で同時期に教鞭を取っていたから、大学での同僚という意味でも馴染み深い存在だ。
目次を眺めて、必然的に「小沼丹君のこと」から読み始める。
「七、八年前のことだが、庄野潤三君が早稲田の文学部で一年間、非常勤講師として講義を担当していた」という文章に目がいく。
お昼の休み時間には、三人で小沼君の研究室へ集まり、一緒に食事をした。小沼君が奥さんを亡くして間もない頃で、庄野夫妻の心づかいで、庄野君がいつも三人分のお握りや巻鮨の弁当を持ってきてくれ、雑談をしながらそれをいただくのだった。(横田瑞穂「小沼君のこと」)
庄野さんの出講日は週に一回だったから、毎週一回、一緒に昼食を食べ、授業が終わった後は、新宿のビヤホールでジョッキを傾けた。
「その頃のことは庄野君の好短編『秋風と二人の男』に描かれている」という文章に続いて、「小沼君と庄野君とのまことに濃ややかな友情は、私の胸にふかく刻まれており、思い出すたびに爽やかな気持になる」とあるのがいい。
ちなみに、同じく早稲田で同僚だった上村君という数学の先生のことは、名作「懐中時計」の中に綴られている。
先日も、同僚の著書を祝う小さな会をした帰り、吉岡達夫君と三人で、いつものならわしで、荻窪の画家の新本さんの経営している喫茶店へ寄った。吉岡君が新本さんや、来合わせていた知り合いのお医者さんをつかまえ、持ち前の大声で大いに弁じたてている側で、小沼君は腰かけたまま、壁にもたれて、気持よさそうに居眠りをはじめた。(横田瑞穂「小沼君のこと」)
このエッセイは、小沼丹『汽船』の月報に寄せられたものだが、この一篇が収録されているというだけで、この著作に対する愛情が深まるような気がする。
庄野潤三は「御代田での庄野英二さん」にも登場している。
初めて庄野英二に会ったのは、庄野潤三の出版記念会のときだった。
わたしたちのテーブルには村上菊一郎君、小沼丹君がいたと思う。そこへ潤三君が英二さんを連れてやってきた。「兄です。こちらはロシア文学の横田さん」「英二です。ところで、わたしもロシア語が少々できるんです。兵隊で外地にいたとき、ロシア人のやっているレストランで覚えました。少しは話せます」(横田瑞穂「御代田の庄野英二さん」)
それから、二人は、信濃追分にある横田さんの山小屋や、御代田にある庄野英二の定宿・井幹屋で話し合うようになったらしい。
やがて、信越線の工事が進むころ、庄野英二も、御代田の井幹屋へは来なくなってしまった。
以来、英二さんと会うのはもっぱら東京であった。行きつけの新宿の酒場で、潤三君や、小沼丹君も一緒のことが多かった。(横田瑞穂「御代田の庄野英二さん」)
『庄野英二全集』の月報に寄せられた、爽やかなエッセイである。
意外なところでは、五木寛之が早稲田大学露文科での教え子だった。
或る夕方、大隈銅像前の校庭で「先生」と呼びかけられた。松延君だった。「しばらくだな」と云うと、彼は「今度、数名で『社会主義リアリズム研究会』をやることにしました。先生も出てください」と云う。血の気のない蒼黒い顔をしていた。(横田瑞穂「露文科時代の五木寛之君のこと」)
露文科で松延君(五木寛之のこと)は、一級下の岡玲子という可愛い女学生と恋愛していたらしい。
ロシア文学の専門家だが、日本の仏教への造詣が深かった。
戦災で家を焼かれ、蔵書はほとんど焼いた。家の焼けた夜、勤務先の泊まりに当っていて家にいなかったが「万一家が焼けるようなことがあったら、他に何もいらない、これだけ背負って逃げろ」と家内にいいおいて出かけたのを、家内は忠実に守ってくれて、『眼蔵』関係の何十冊だけはたすかった。(横田瑞穂「私の読書・集書」)
道元禅師の『正法眼蔵』は、生涯の精神的支柱となったようである。
ロシア文学の関係では、中村白葉の話が重要だ。
昭和二十年代の終りの二、三月頃のことだった。私はショーロホフの『静かなドン』の翻訳を仕上げるため、神田、ニコライ堂下の旅館に、いわゆる館詰めになっていたが、過労から身体をこわし、仕事ははかどらず、やりきれない日々を送っていた。(横田瑞穂「中村白葉先生のこと」)
そんなときに声をかけてくれたのが、中村白葉だったという。
熱海の双柿舎に、ロシア文学の関係者が集まって、中村白葉の喜寿のお祝いをしているとき、テレビニュースで川端康成の自殺が報道された。
皆が感想を述べあう中、中村白葉は、ただ、ふんふんと頷いていた。
帰りの列車のなかでも楽しく語り合った。先生が東横線へ乗り替えられる横浜駅が近くなった。戸塚を過ぎたあたりだったろうか、先生は私に眼を向け、ふと思い出したように「君、川端さん惜しいことをしたね」とぽつりと一言洩らされた。(横田瑞穂「中村白葉先生のこと」)
皆が、川端康成の死を話題にして論じていることを、中村白葉は、一人寂しく感じていたのかもしれない。
戦中・戦後に家族へ宛てた書簡集
本書の後半には、戦中から戦後に書かれた書簡が収録されている。
離れて暮らす家族へ宛てて書かれたもので、戦中・戦後の世相を知ることができるとともに、横田瑞穂という文学者の生き様を知る上で、非常に重要な記録となっている。
その頃父が、心血を注いで耽読していた正法眼蔵随聞記を、私にくれました。頁の角がすり切れて、赤い線がぎっちり引きこんである小さな本の扉に、「只今ばかり我が命は存ずるなり 昭和十九年四月二日夜 瑞穂」と、隅でくろぐろと書いてくれました。(山本美佐子「家族への戦中・戦後の手紙から」はじめに)
この本は、巻頭グラビアに写真が載っている。
当時、横田家の三人姉妹は、長女・美佐子が教員養成所を卒業したばかりで、次女・明子も小学六年生を終えて女学校に合格、三女・伸子が小学四年生だった。
長女・美佐子は、三女・伸子を連れて、父の実家のある九州別府へ疎開する。
昭和19年4月3日の出発だった。
家族への手紙といっても、日記と呼んでも差し支えないくらい、日常の出来事が細かく綴られている。
役所の食堂なども、この頃は全くひどくなりまるで豚に食わせるものみたようだ! と、毎日不平を言い乍らそれでもみんな、昼めしが一番楽しみだ、といっている。そうして休む人があると、その人の分を競争して、二人前喰べるのが流行っている。どうにも浅間しき世の中になりましたよ、君──。(昭和十九年九月十三日 美佐子宛)
戦況が悪くなるにつれて、食糧事情の悪化していく様子が、手紙の中からも伝わってくる。
父さんは、大戦果の話をきくと、先ず第一に、この戦果をあげるために命をすてた人たちのことを思います。単純に喜べない気持があり、昨日なども役所でみんなが大さわぎをしているのに、ひとりボンヤリ考えていました。(昭和十九年十月十七日 美佐子宛)
どんな戦果にも犠牲者があるはずで、戦果よりも、その犠牲者に思いを馳せているところが、文学者らしいということなのだろうか。
読書の真の娯しみは、このような日々の中にある。「ただ今日只今ばかりの生命なり」読書とは知識をうるとか、教養を深めるとか、娯楽、趣味などということではない。生きることだ、道元さまの言葉でいうと、行詩なのだ。(昭和二十年一月十四日 美佐子宛)
昭和も二十年代になる頃には、本を手に入れることもままならなかったらしい。
特に、文化人にとっての読書は、生きることそのものだった。
硫黄島はたいへんだ。新聞やラジオできいているだろう? あと半年何とかガン張り通せば、決して敗けやしない。その辛抱が出来るかどうか、それが日本を救うか亡ぼすかのわかれめだ。だから何としてもガン張り通さねばならない。(昭和二十年二月二十四日 正稔宛)
「あと半年何とかガン張り通せば、決して敗けやしない」という庶民の気持ちだけが、当時の日本を支えていたのではなかっただろうか。
空襲で罹災した後の生活は、困難を極める。
帰りに、うちの焼跡へ行ってみた。ちゃんと耕してお芋が植わっていた。まわりには草が生えており、ミシンの脚がそのまま残っていた。もうあんまり行くこともありますまい。(昭和二十年七月十?日 美佐子宛)
そして、やってくる敗戦という名の終戦。
武力の戦いは終ったけれど本当の戦いはこれからです。役所の方もどうなるか判りませんが、その時はまたその時です。(昭和二十年八月二十一日 富宛)
戦後の暮らしは、食糧難と住宅難という二重苦の中から始まった。
手紙の内容も、食事に関することと、家探しに関することが多くなっている。
正直なところ、これが日本の実力だったのだとも思える。ここで大いに反省して立ち直って行かなければ、日本人は、それこそ三等国民に転落してしまう。君の念願たる、科学の時代がやがてくると思う。大いに子供たちに、科学精神をふきこむことだ。(昭和二十年八月二十五日 美佐子宛)
日常生活の合理化・科学化を、父・横田瑞穂は「生活そのものの変革だ」と呼んでいる。
敗戦以来、如何に生くべきかということのみを考えつづけてきた。つまりそれまでは、いかに死ぬべきかということのみ考えていたのだったが、敗戦という事情で逆になったわけだ。しかし、詮ずるところ、いずれにしても同じだとは云えるが。(昭和二十年九月十六日 正稔宛)
昭和19年から昭和20年にかけての手紙を続けて読んでいると、この時代が、いかに激動の時代であったかということを理解できる。
この激動の時代に、横田瑞穂を支えていたものは、やはり道元禅師の教えだったらしい。
自分には厭世観などという吝みったれたものはない、が、無常感はある。これのない偉大な文学というものは考えられない。道元さまをくり返して読む。自分の生命をかけて読んだ本だ。ぬけきれないのが本当だろう。(昭和二十一年十月 美佐子宛)
この頃になっても「家のある人が羨ましい」という言葉が出てくる。
そろそろ、戦後復興が進み始めていた時期だったから、戦後の焼け跡にも格差が生じ始めていたのだろう。
焼け跡に家を建てる者と、まだ家を建てられぬままの者、そして、外地からようやく引き揚げてきた者とで、東京の街は、混沌とした時代にハマりこんでいた。
この書簡集は、そんな時代を映した、一庶民の記録である。
書名の「山桃」は、山桃に思い入れの深かった横田瑞穂の遺志を汲んだものとなっている。
晩年を過ごした伊豆の八幡野というところが別名「山桃(やんも)の里」といわれる土地だったこと、そしてこの地が終のすみかとなりましたことも、ただの偶然とは思えぬような気がいたします。(横田富「あとがき」)
未亡人と三人の遺児によって編纂された本書には、故人に対する家族の思いやりが溢れている。
幸福な人生だったのだろうと思った。
書名:山桃
著者:横田瑞穂
発行:1992/01/24
出版社:横田富(岩波ブックサービスセンター)