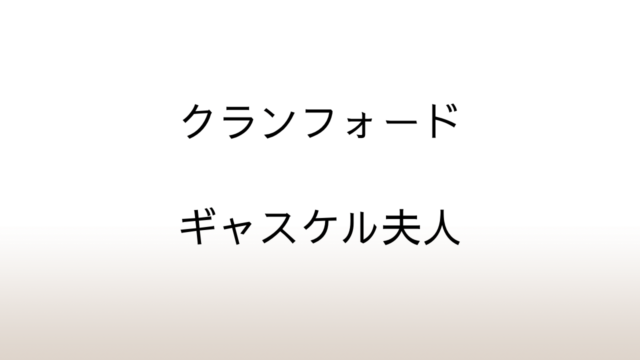ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』読了。
本作『パパ・ユーア クレイジー』は、1957年(昭和32年)に発表された長篇小説である。
この年、作者は49歳だった。
作家として生きること
本作『パパ・ユーア クレイジー』は、父親(45歳)と息子(10歳)の物語である。
巻頭に、息子(アラム・サローヤン)に宛てた文章がある(「アラム・サローヤンへ」)。
私がこの本を書く「決断」をしたのは、一九五三年、十歳のお前が私に書いてくれと頼んだからであり、また、一九一八年、私自身が十歳だった年に、私は自分の書きたいことを書くだけの文章の練習をまだ積んでいなかったからでもある。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
ここに描かれているのは、母や妹と離れ、父親と二人で暮らす10歳の少年の生活である。
私はただ、自分の十歳の頃のことを憶い出し、十歳のお前を見つめ、それらを重ね合わせ、私自身の四十五歳をそれに添えただけのことである。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
作家である父は、息子の十歳の誕生日に、小説を書く仕事を息子へと譲り渡す。
「だって、僕は何を書くの? 何について?」「お前自身についてさ、もちろん」「僕自身? 僕って何だろう?」「それは小説を書いて発見するんだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
「小説を書くこと」「作家であること」は、この物語で、ひとつの大きなテーマとなっている。
「お前と私──」僕の父はいった。「われわれは作家だ。どんな物でもわれわれにとっては、より良く、また、より多いのさ。世間の人人に較べてね。お前は作家だ。お前はいつだってお前の小説を書いているんだよ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
父は、常に作家だった。
作家にとって、小説とは「生きること」を意味している。
僕は彼に、僕もいつか物語りを書きたいといった。彼は答えた。「お前は毎日物語りを一つずつ書いているんだよ」この世のすべての人間が、毎日それぞれ一つの物語りを生きるのだ、と彼はいった。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
それは、父親の作家観でもある。
父は、観察することを大切にした。
「誰だってそういう物は見たことがあるよ」「それは見たことはあるだろう。しかし誰も見つめた人はいない。アートとはそれなのさ。ありふれた物を、それらが今まで一度も見られたことがなかったかのごとく見つめるということなのさ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
父親の視点は、作家としての視点である。
「じゃあ字引きは何のために使うの?」「楽しむために読む。字引きは素晴らしい小説なのさ。大きな本まるごとが詩の本なのさ。人生と芸術についてのエッセイなのさ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
かつて、父が暮らしていたサンフランシスコを、二人は訪れる。
父は「落ち着けなくなった」から、サンフランシスコを離れたのだと言う。
「そうさね、私が思うに、多分私はサンフランシスコに恋することから醒めてしまったんだろうよ。そして、作家にとっては、彼が恋していない都会に住むのは全然無駄なことなんだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
都会を離れて、海辺の小屋に、彼はひとり暮らしをしている。
「作家というものはこの世界に恋をしていなきゃならないんだ。さもなければ彼は書くことができないんだ」「どうして書けないの?」「それはね、善いものはすべて愛から発するからさ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
ウィリアム・サローヤンの息子(アラム・サローヤン)が、やがて、作家となるということを、現代の我々は知っている。
作家としての彼を育んだものは、父親との生活だったのかもしれない。
「僕は小説を書くよ。僕はどうやって書くか学ぶつもりだよ」「本当かね?」「神様に誓って本当だよ」「でも、どうしてなんだね?」「父さん、あなたわからないの? 僕も、あなたと同じように、作家である他ないんだよ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
息子の言葉を聴いて、父親は「人生の中の一番誇らしい瞬間」を感じる。
彼は、息子の新しい人生の始まりに立ち会ったのだ。
「もし作家がいい本を一冊、死ぬまでかかって書き上げたとしても、それでも時間がかかり過ぎたとはいえないんだ。九十歳まで生きてやっと一冊でもそうなんだ。いい本はいい本だし、人間は遅かれ早かれ誰だって死ぬ。そして、人間は死んでしまったらそれでおしまいだろ? だけど、人間は死んだあと、この世に何を残すか? いい本を一冊この世に残すというのは人間として最高のことなんだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
本作『パパ・ユーアークレイジー』は、10歳の少年の成長物語である。
父親との生活の中から、少年は自分の人生を見つけていくのだ。
人生を楽しく生きること
妻と別居生活を送る父は、決して普通の父親ではない。
「物事がうまくゆくことはあまりないんだ」彼はいった。「だからお前は、今、この瞬間から、現実が厳しい時にどうやって暮してゆくかを習い始めたほうがいい」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
彼は、自分たちの生活すべてを通して、息子に「人生」を伝えようとしていた。
「われわれは常に自分が考えているより遠くまで行けるのさ。それに、われわれは自分が考えているより遥かに少ないもので暮してゆくことができる。われわれは時時そのことを思い出す必要があるね」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
父は、常に自分の人生を歩いてきた人だった(だからこそ、彼は「クレイジー」とさえ言われた)。
「お前の人生で起きるどんな事でも、決して一つしか道がないということはないんだ。お前はうちへ帰りたくなるまで私と一緒にいられるし、お前が戻ってきたくなったら、いつだってお前は戻ってこられるんだ。一つの道しかなくて、他の道はない、なんていうことは決してないんだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
父親が伝えようとしているのは、かつて、自分が通ってきた道である。
いつか10歳だったことのある父親は、10歳の息子のことを、ちゃんと理解することができたのだ。
僕が本当になりたいのは飛行士だ。僕は最初のロケットを飛ばせて月へ行きたい。(略)彼はいった。「私はお前がやるだろうと思うよ」いつの日か僕は自分で悟るだろう。そんなことは僕にはできないのだと。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
それを「理想の親子像」と呼ぶかどうかは分からない。
「お前は知っているかね──」彼はいった。「お前と私とは──父親と息子とは──あらゆる父親と息子というものは、実はほとんど同じ男なんだ。一人は年とっていて、一人は若い。と、同時に、われわれはまた知らない者同士でもある。町で出会った者同士よりももっと他人なんだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
「息子が何を考えているか、分からない」と、世間の父親は言う。
それは、彼が、あまりにも息子の気持ちを理解することができるために、かえって息子の気持ちが理解できなくなってしまうということなのだ。
どんな父親も、完全なる客観性を持って、息子と接することはできない。
そこに、親子の難しさがある。
ハーフ・ムーン・ベイへ向かう途上のガソリン・ステイションで出会った老人にも、かつて父親があった。
老人は笑った。そしていった。「(略)儂はもうすぐ八十さ。儂にもほんの十一年前まで父親がいたもんだが──儂は本当に死んだ父親が懐かしいと思うよ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
老人にはもうすぐ60歳になる息子がいるが、大昔には彼もまた10歳の少年だったのだ。
そして、もうすぐ80歳になる老人も、父親が生きている時分には、やはり、一人の息子だったのである。
「父さん、僕、学校が嫌いだよ」「そりゃお前は嫌いだろうとも。何かをそうやってじっと憎み続けるということはお前のためにはいいことだが──でも、お前はある意味で学校を好いてもいるんだよ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
大人になれば、世の中は大きな学校みたいなものだ。
どんなに嫌いな世界であっても、人は、そこで生きていかなければならない。
父は、生きることを楽しむ人だった。
僕の父は、彼のホット・ドッグを三口で食べた。「この世界そのもの──それがホット・ドッグのうまさの中の最高の部分なのさ」彼はいった。「だから、ホット・ドッグを食べる正しい場所は町の中ということになる」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
お金の心配をする息子の不安をよそに、父はホット・ドッグを食べて、遊園地で遊ぶ。
そこは、世界中の人々が楽しく生きている場所だった。
そこにいる人人が浮き浮きしているのを見ると、僕はたまらなく楽しくなってしまう。まるで、人人は、この、楽しみが一杯の場所で、突然自分が生きており、楽しむことと、ホット・ドッグを食べる以外のことはなにもする必要がないことに気がついたかのようだった。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
肯定的にとらえることで、人生は楽しくなるということを、父は知っていた。
「人人が好き? とは何ということをいうのかね?、私がその<人人>なんだよ。もし私が人人を好きじゃないなら、私は全く生きる気がしないだろうよ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
父が伝えたかったものは、生きる姿勢だったかもしれない。
「私はイギリスの法律がどんなものか知らない。しかしわれわれのルールは、われわれの手に入るすべての愉しみを愉しもう、というルールなのさ。ただし、一人の人間も傷つけないでだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
少年は、少年なりに、人生を生きていた。
でも僕がほんとに欲しかったものを僕はみつけなかった。海賊船から来た宝物の箱だ。黄金が一杯詰まったやつだ。僕は決してそれを発見することはないだろう。どうしてかっていうと、僕は自分が絶対発見しないだろうことが判るまで齢をとってしまったからだ。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
息子が「海賊船から来た宝物の箱」を、絶対に発見することができなくなってしまった年に、父は小説を書く仕事を息子へと譲った。
「世界を理解する力」を発見したとき、世の中が変わったと、父は言う。
「私がそれを見つけたのは私が十二の時さ。でもね、私は最初から、多分、それが見つかるはずだと見当はつけていた。そして、或るものが見つかるはずだと思い続けることは、実際に見つけることとほとんど同じくらいにいいものなんだ。完全に同じくらい、とはいえないにしてもね」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
10歳の少年も、また、自分の力で人生を見つけようとしていたのだ。
「さあ、僕にはわからない。他のなんだったのか、僕がはっきり憶えてさえすりゃよかったんだけど。でも僕はね、あれは僕がいつか知るようになるいろんなこと全部だったような気がするんだ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
本作『パパ・ユーア クレイジー』に、特別のドラマはない。
別居中の父と一緒に海辺の小屋で暮らし、ドライブへ出かけ、クリスマスを家族四人で過ごす。
父親との生活そのものが、少年にとって特別なドラマだったのかもしれない。
もしかすると、多分僕が本当に望んだのは、自分が大きくなって一人立ちすることだったのだろう。しかし──それには何年もかかってしまう。人は決してアッという間に大きくなったりはしないのだ。僕は、クリスマスの次の日が変なのは、多分そのせいだと思う。(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
楽しいクリスマスを過ごした後にやってくる違和感に、少年は戸惑っていた。
「クリスマスのどこが悪いんだろうね?」「別にどこも悪くないさ。クリスマスは愉しいものだよ。すべての悲しくて愚かしいことの中では、クリスマスが一番愉しいのさ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
クリスマスの場面は、この物語で、ひとつのクライマックスとなっている。
「連中は迷える者だ。そして私も迷える者なのさ。そして、お前がまだ迷える者じゃないとしても、そして、連中の子供たちがまだ迷える者じゃないとしても、お前も遠からず迷える者になるし、それは連中の子供だって同じことなのさ」(ウィリアム・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』伊丹十三・訳)
どんな家族にも、父と子の物語がある。
大切なことは、10歳の少年と真剣に向き合うことができるかどうか、ということだ。
本作『パパ・ユーア クレイジー』は、10歳の息子と真剣に向き合った男の物語だったのかもしれない。
書名:パパ・ユーア クレイジー
著者:ウィリアム・サローヤン
訳者:伊丹十三
発行:1988/01/25
出版社:新潮文庫