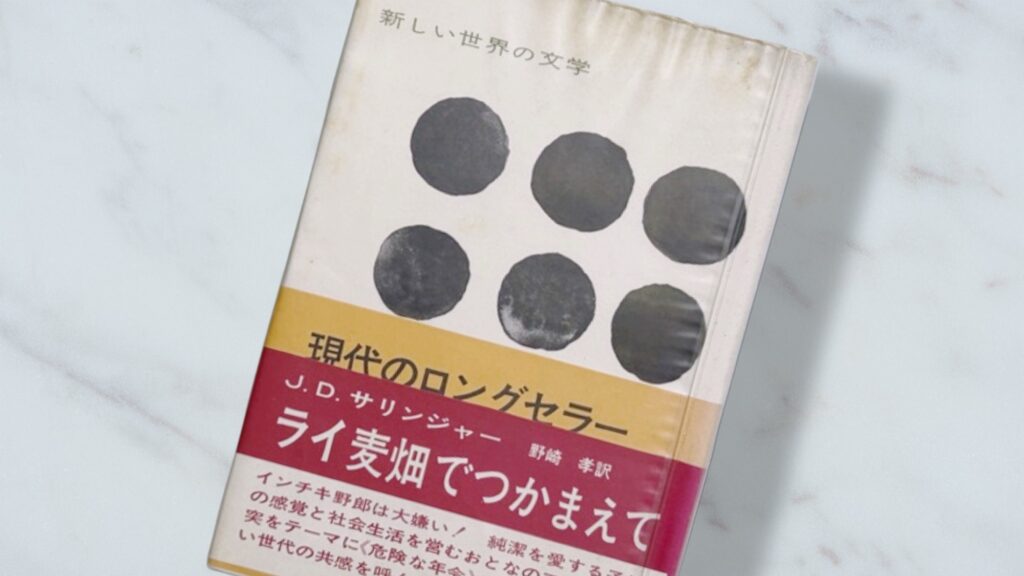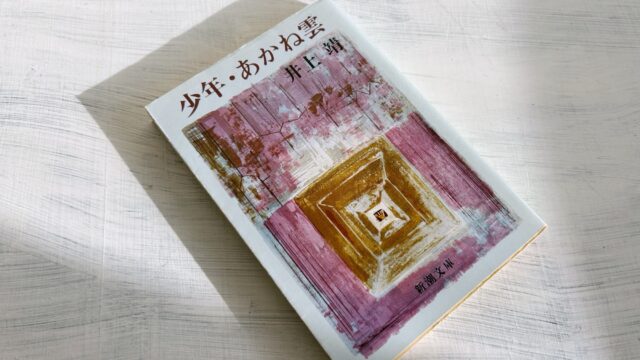J.D.サリンジャー『ライ麦畑でつかまえて』読了。
本作『ライ麦畑でつかまえて』は、1951年(昭和26年)にアメリカで出版された長編小説である。
この年、著者は32歳だった。
『ライ麦畑』が禁書になった理由
村上春樹の解説によると、本作『ライ麦畑でつかまえて』は全米で「有害図書」に指定されたという。
出版された当時この作品は、全米の保守的な教育界や、右翼勢力、教会関係などからヒステリックと言っていいほどの強い反発と弾圧を受けた。長いあいだ、その理由は主に「汚い言葉」の多用にあるとされていた。(村上春樹「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」)
現在、日本で入手できる『ライ麦畑でつかまえて』には、2種類の翻訳がある。
・野崎 孝「ライ麦畑でつかまえて」
・村上春樹「キャッチャー・イン・ザ・ライ」
「汚い言葉の多用」については、村上春樹よりも野崎孝の翻訳で顕著だ。
「そのきたねえ膝を、おれの胸からどけやがれ」僕はそう言ってやった。わめいてたと言った方がいいだろうな。ほんとに。「さあ、どかねえか、このクソッタレ」(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
いくつもの高校を追い出されてきた主人公(ホールデン・コールフィールド)は、今、ペンシー高校を退学になろうとしている。
僕がエルクトン・ヒルズをやめた最大の理由の一つは、あそこの学校がインチキ野郎だらけだったからなんだ。全くウジャウジャいやがるんだから。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
本作『ライ麦畑でつかまえて』は、クリスマス休暇を前に寮を飛び出した少年の、ニューヨーク徘徊物語である。
彼は「社会」になじむことが難しい(16歳の)少年だった(「そのときは十六だったんだけどね。今は十七さ」)。
彼の言動は、16歳の少年であるべきものを、常に逸脱していく。
いや、僕はそこのバーに一時かそこらまでねばっちゃてね、バカみたいに酔っ払っちまった。ものがちゃんと見えないくらいなんだよ。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
頻繁に登場する酒と煙草と女たち。
エドモント・ホテルでは、夜の女を金で買った(売春婦サリー)。
少年の関心は、いつでも女たちのことだったのだ。
リリアン・シモンズという女だった。以前、兄貴のD・Bがしばらくつき合ってた女なのさ。とてもでっかいオッパイをしてるんだ。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
言葉が乱暴なうえに、彼の行動は常軌を逸している。
キリスト教にさえ、彼は容赦しなかった。
「あのな。修道院に入るにはどうしたらいいんだ?」そう僕は言った。(略)「わかった、わかった、さあ、寝ろよ。とにかくおれは入りゃしない。とにかく運には恵まれねえおれのこった、入ってみたら、うまの合わねえ修道僧ばっかしだった、てなことになりかねないからな。とんまな下司(げす)野郎ばっかしでさ。あるいはただの下司野郎か」(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
いくつも高校を退学になった家出少年が、ニューヨークの街を徘徊しながら酒を飲んで酔っ払い、夜の女を金で買ったり、キリスト教批判を喚いたりする。
ある意味、この本は「有害図書」に指定されて不思議でも何でもない、非道徳的な小説だった。
今でも少なからざる場所で『キャッチャー』は学校の図書館から閉め出され、英語の授業の選択図書から外され、「有害図書」に指定されたりしている。子どもが授業の課題図書として家に持ち帰った『キャッチャー』を手に親が学校に怒鳴り込んでくるという例もいまだに跡を絶たない。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
『ライ麦畑でつかまえて』が禁じられる最大の理由は、その「反社会性」である。
健全な社会が『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を糾弾し続ける最も大きな理由は、ホールデン・コールフィールドという主人公の言葉遣いにあるのではない。その最大の理由は、ホールデン少年が、一人の個人として、学校や社会という既成のシステムに対して、はっきりと臆することなく根元的な「ノー!」の叫びを上げており、彼のそのような反抗的姿勢があらゆる時代を通して、多くの若者にとって強い説得力を持っているという事実にあるのだ。(村上春樹「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」)
エルビス・プレスリーやジェームス・ディーンが登場する前の時代(彼らは『ライ麦畑』の直後に登場する)、ホールデン・コールフィールドは「反逆のヒーロー」だった。
大人ってのは、いつだって、全く自分たちの言う通りと思うものなんだ。こっちは知ったこっちゃないやね。(略)大人ってのは、なんにも気がつかないんだからな。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
「禁書」と言えば大袈裟だが、『ライ麦畑』は青少年にとって、決して好ましいとは思われない小説だった。
そして、「健全な社会」が恐れていた大事件が、やがて訪れる。
『ライ麦畑』はなぜ怖い小説なのか
最も有名な「ライ麦畑事件」は、1980年(昭和55年)12月8日に発生した「ジョン・レノン射殺事件」である。
一九八〇年十二月に、マーク・ディヴィッド・チャップマンは『キャッチャー』をポケットに入れて、ニューヨークのダコタ・アパートメントの前で、リムジンから出てきた帰宅途中のジョン・レノンをピストルで射殺した。警官が現場に到着するまで、チャップマンは舗道の敷石に座って『キャッチャー』を読んでいた。(村上春樹「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」)
犯人(チャップマン)は「ホールデン・コールフィールド」として、欺瞞に満ちた「インチキな社会」を破壊しようとしていた。
ジョン・レノンは「インチキで不誠実な社会」の象徴として殺されたのだ。
事件の直前、チャップマンは、自分の名前を正式に「ホールデン・コールフィールド」へと変更している。
多くの若者たちが「『ライ麦畑』は自分のことを書いている」と信じていた。
誰もが「ホールデン・コールフィールド」だったのだ。
ジョン・レノン狙撃事件の直後、次に狙われたのは、アメリカ大統領(ロナルド・レーガン)だった。
ジョン・レノン狙撃事件から四ヶ月もたっていない一九八一年の三月、ジョン・ヒンクリー・ジュニアという二十五歳の情緒不安定な青年が、ワシントン特別区のヒルトン・ホテルの前で、当時大統領だったロナルド・レーガンを拳銃で狙撃した。全部で六発の弾丸が発射され、そのうちの一発が大統領報道官のジェームズ・ブレイディの頭部に当たり、彼を半身不随にした。(村上春樹「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』訳者解説」)
弾丸は、護衛警官やシークレット・サービスや、もちろん、レーガン大統領にも撃ちこまれた。
犯人(ヒンクリー)の所持品の中には、ボロボロになるまで読みこまれた『ライ麦畑でつかまえて』があったという。
『ライ麦畑でつかまえて』は(あるいは、ホールデン・コールフィールドは)、反社会的な存在として、世界中の人々に記憶された。
彼らは、常に社会を狙い続けている。
なぜなら、ホールデン・コールフィールドは「赤いハンティング帽子」を被っていたからだ(「それは赤いハンチングでね、でっかいひさしがついてやがんの」)。
「そいつは鹿射ちの帽子だ」「馬鹿をいえ」僕は帽子をぬいで眺めてみた。それから、片目をつぶったぐらいにして、狙いをつけるようなまねをしながら「こいつは人間射ちの帽子さ。おれはこいつをかぶって人間を射つんだ」と、言った。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
もちろん、小説の中のホールデン・コールフィールドは、人間を撃ち殺したりはしない。
むしろ、彼は「死」を極度に恐れる人間だったのだ。
それでも、実社会の中の「ホールデン・コールフィールドたち」は、銃を持ち、「インチキな社会」に狙いを定めた。
それは、「洗脳」と言っていいほど、大きな影響だったかもしれない。
エドワード・ノートンは、「『キャッチャー・イン・ザ・ライ』初体験は、ホールデンが自分の友達なんだと思うことじゃない。ホールデンは自分なんだって思うことなのさ。文字通りの意味でね」と語っている。(ディヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」坪野圭介/樋口武志・訳)
『ライ麦畑でつかまえて』を読んだ若者たちは、誰もが「ホールデン・コールフィールドは自分のことだ」と思いこんだ。
脚本家ロバート・タウンは、こう述べて総括した。「まるごと一世代が同じように感じたことだが、私は彼が自分について書いていると思ったのだ」(ディヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」坪野圭介/樋口武志・訳)
健全な社会が恐れていたように、『ライ麦畑』は青少年の成長に大きな影響を与えた。
「ホールデン・コールフィールドは、郊外に暮らす白人少年たちにとってのマルコムXなんだ」と、俳優ジェイク・ジレンホールは語った。(ディヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」坪野圭介/樋口武志・訳)
『ライ麦畑でつかまえて』は、なぜ、本当は「怖い小説」だと言われるのか?
その理由は「ジョン・レノン暗殺事件」や「ロナルド・レーガン狙撃事件」が教えてくれるだろう。
小説の中の「ホールデン・コールフィールド」は、実社会の中の「ホールデン・コールフィールド」を生み出していたのだ。
『ライ麦畑』はなぜ人気の小説なのか
禁書として「有害図書」に指定され、重大な凶悪事件の引き金となった『ライ麦畑』だが、その人気は(世界中で)衰えることがない。
それは、なぜか?
理由はやはり、主人公(ホールデン・コールフィールド)に対する読者の共感にある。
不良少年を主人公としながら、この物語が描いているのは、社会のどこにも居場所を見つけることのできない、少年の孤独である。
僕は返事をしなかった。何をしたかというとだな、立ち上がって、窓のとこへ行って、外を見たんだ。急に僕は、とても寂しくなっちゃった。死んじまいたいくらいだった。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
作中、ホールデン・コールフィールドは、何度も「自殺」をほのめかしている。
僕は眠くもなんともなかったけど、なんだか気分が悪かった。気が滅入ってしょうがないんだな。いっそ死んじまいたいくらいだった。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
彼は、常に「生」の「死」の境界線を生きていた。
まるで「半分は凍って半分は凍っていない」セントラル・パークの真冬の池のように。
でも、本当は自殺したい気持だったんだ。窓から飛び降りようかと思ったね。(略)僕は血まみれになった自分の身体が、物見高い馬鹿どもに見られるかと思うと、それがどうもいやだったんだ。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
「自分探しの旅」であるホールデンのニューヨーク徘徊は、あるいは「死に場所探し」の旅でもあったかもしれない。
しかし、彼は死ななかった。
読者の共感は、「疎外感」を抱えた彼がそれでも生き続けていくという、その物語性にある。
第二次大戦後、時代はいつでも「生きにくい」時代だったのだ。
死に場所を求めてさまよいながら、それでも死ぬことができない主人公(ホールデン・コールフィールド)に、読者は「本当の自分」を見出していたのだろう。
ホールデンは傷つきやすい少年である。
どうしてだかわかんないけど、泣けてきちゃったんだ。たぶん、すごく気が滅入って寂しかったからじゃないかと思うんだな。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
社会の闇に触れるたびに、彼は傷ついている。
売春婦サニー(の生き方)にさえ、彼は傷ついていた。
突然僕は泣き出しちゃった。どんなことがあっても泣くのだけはよそうと思ってたのに、泣き出しちゃったんだな。「そうだよ、君は泥棒じゃないよ」と、僕は言った。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
彼を傷つけていたのは「インチキな現代社会」である。
作者(サリンジャー)にとって、それは、第二次世界大戦後の「戦後社会」を意味していた。
サリンジャーは、なぜ、戦後社会を「インチキな社会」といって糾弾したのだろうか。
青春小説でありながら、『ライ麦畑』の中には頻繁に「戦争」の話が登場する。
ガールフレンド(サリー・ヘイズ)とのデートで、一緒に観た芝居も「戦争」の話だった。
亭主は戦争に行くが、細君にはのんだくれの弟がある。どうもおもしろくなかったな。つまり、その家族の誰かが死のうとどうしようと、僕にはどうでもよかったんだ。どうせ、みんな俳優がやってることじゃないか。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
ホールデンがこだわっているのは、「戦争」に対する世間の無関心である。
世の中にとって「戦争」は映画の中の物語であり、芝居の中の物語だった。
どこにも現実感がない「アメリカ社会の中の戦争」に、彼は傷ついていたのだ。
僕は、血を流したりなんかしてる僕に、ジェーンが煙草をくわえさせてくれる情景を思い描いたね。映画の野郎の影響さ。映画ってのはひとをだめにする。決して嘘じゃないよ。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
死にかけた兵士が「最後に煙草を一本吸わせてくれ──」と言う。
それは、映画によって歪められた戦争の「美しすぎる幻想」だ。
戦場から戻ったサリンジャーは、戦後、何度も何度も「戦争を美化するインチキな社会」を訴える作品を書き続けた。
本作『ライ麦畑でつかまえて』は、置き換えられた戦争文学である。
ホールデン・コールフィールドは戦場をさまよう兵士であり、戦場で生きる彼は常に死と向き合い続けていた。
今までいろんな学校やなんかをやめて来た僕なんだけど、みんな自分で知らないうちにやめちまったみたいな感じなんだな。そいつがいやなんだよ。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
戦場に、もちろん「さようなら」はない。
人間は、ある日、突然に死んでいくだけだ。
そうあってほしくないんだな、僕は。全体にそうであってほしくない。「幸運を祈るよ!」なんて、僕なら誰にだって言うもんか。ひどい言葉じゃないか、考えてみれば。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
「幸運を祈るよ」という言葉は、戦場で活動する兵士の命を「運」に委ねるものでしかない。
兵士たちは「幸運」と「不運」との間で、自分の生命を託していたのだ。
ホールデンが許せないのは、気軽に「幸運を祈るよ」などという言葉を使う、無神経でインチキなアメリカ社会だった。
実際、多くの仲間たちが、サリンジャーの周りで死んでいった。
そのときはひどかったな。アリーの墓石にも雨が降る。あいつの服の上の芝生にも雨が降る。そこらじゅうが雨なんだ。墓参に来てた弔問者たちは、みんな、いちもくさんに駆けだして、めいめいの車に逃げこんだんだ。それを見て僕は気が狂いそうになったね。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
戦争に無理解な人々を、彼は許せなかった。
だからこそ、彼は「赤いハンティング帽子」を被ったのだ。
「インチキで欺瞞に満ちた社会」を撃ち抜くために。
それが、彼の(生きにくい社会を生き抜くための)生き方だった。
メンタルを病んだ彼は、死んだ弟(アリー)と会話を交わすことで、精神の安定を保とうとする。
「アリー、僕の身体を消さないでくれよ。アリー、僕の身体を消さないでくれよ。アリー、僕の身体を消さないでくれよ。お願いだ、アリー」(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
もちろん、この物語は青春小説であって、戦場小説ではない。
深読みしなければ、それが「戦争文学」であるなんて誰も思わないだろう。
しかし、ホールデン・コールフィールドの疎外感は、帰還兵の疎外感が置き換えられたものだった。
『バナナフィッシュにうってつけの日』で自殺する主人公(シーモア・グラース)が抱えていた疎外感と同じものを、やはり彼(ホールデン)も抱えていたのだ。
サリンジャーには虐殺された仲間たちの記憶を呼び起こすことができないから、ホールデンがジェームズ・キャッスルのつぶれた死体を思い浮かべる。サリンジャーには彼らを悼むことができないから、ホールデンがアックリーとストラドレイターのことを懐かしく思う。(ディヴィッド・シールズ、シェーン・サレルノ「サリンジャー」坪野圭介/樋口武志・訳)
作者(サリンジャー)には、カウフェリンクを経験した後の死にたくなるような絶望を呼び起こすことができないからこそ、彼は、主人公(ホールデン・コールフィールド)に自己破壊について真剣に考えさせたのだ。
自分の体験や思いをいくつものベールで包みこんで、作者は『ライ麦畑でつかまえて』という物語に変えた。
そこに、この物語の持つ「果てしない深み」がある。
そして、読者はその深みの中に、この物語の魅力を感じ取っているのだ。
「さあ、もうよせよ」と、僕は言った。「誰も僕を殺しやしない。誰も僕を──さあ、フィービー、そんなもの、頭からとれよ。誰も僕を殺しやしないよ」(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン紛争、湾岸戦争。
第二次大戦が終わった後も、アメリカの若者たちにとって、戦争は常に現実だった。
いつか戦場に立つかもしれない彼らは、いつでもホールデン・コールフィールドになり得たのだ。
「君をおどかすつもりはないんだがね」先生はそう言った。「しかし、僕には、君が、きわめて愚劣なことのために、なんらかの形で、高貴な死に方をしようとしていることが、はっきり見えるんだよ」(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
愚劣な戦争のために、祖国を(アメリカ国民を)守るという形で、多くの若者たちが「高貴な死に方」を選んでいった。
ホールデン・コールフィールドの流す涙は、彼らのために流す涙である。
そして、敵地だけが戦場ではないということも、現代アメリカを生きる若者たちにとっての真実だった。
なぜなら、息の詰まるような現代社会そのものこそ、多くの若者たちにとっての戦場だったからである。
あいつが死んだ夜、僕はガレジに寝たんだけど、拳で窓をみんなぶっこわしてやったんだから。他にわけがあったわけじゃない。ただぶっこわしたかったからぶっこわしたのさ。(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
生きにくい世の中を生き延びるために、彼らはいつでも必死だった。
彼らが『ライ麦畑』から得たものは、生き続けていくことの意味である。
仲間たちが次々と死んでいく中で、生き続けていかなくてはならないホールデン・コールフィールドの寂しさは、もはや彼ら自身の寂しさでもあったのだ。
そこに、彼らの共感がある。
つまるところ、『ライ麦畑』という小説が、いつの時代も人気だった理由は、戦後社会の生きにくさを証明するものだったかもしれない。
「で、僕はあぶない崖のふちに立ってるんだ。僕のやる仕事はね、誰でも崖から転がり落ちそうになったら、その子をつかまえることなんだ──。(略)ライ麦畑のつかまえ役、そういったものに僕はなりたいんだよ」(J.D.サリンジャー「ライ麦畑でつかまえて」野崎孝・訳)
彼らの共感の意味を分析しようと、世界中の専門家たちが(文芸評論家や心理学者たちが)『ライ麦畑』の謎解きに挑戦した。
そして、発表から70年以上が経った今も、彼らの謎解きは続いている。
なぜなら、サリンジャーは正解を残さなかったし、答え合わせをすることは誰にも不可能だったからだ。
逆説的に言うと、正解がないからこそ、読者は自由に『ライ麦畑』を読むことができた。
その自由さこそが、『ライ麦畑をつかまえて』という小説の最大の魅力だったと言っても過言ではない。
答えが見つからない以上、そして、世の中が生きにくいものである以上、『ライ麦畑』の人気は永遠に続いていくことだろう。
野崎孝・訳と村上春樹・訳の違い
サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』には、これまでに3種類の日本語訳がある。
・橋本福男『危険な年齢』
・野崎 孝『ライ麦畑でつかまえて』
・村上春樹『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
このうちに、日本で最初の翻訳である『危険な年齢』は、古本市場でもほぼ入手困難な状況となっているが、国立国会図書館に蔵書があり、インターネットによる閲覧が可能である(これはすごく便利な機能です。要会員登録)。
一般的な読書の現実的な選択肢としては、『ライ麦畑でつかまえて』(野崎孝)か『キャッチャー・イン・ザ・ライ』(村上春樹)のいずれかということになる。
「野崎孝・訳」と「村上春樹・訳」のどちらを選ぶべきかという問題について、ここでは「両方読むこと」を推奨している。
なぜなら、どちらの作品にも、それぞれの訳でしか見えてこない物語の世界観があるからだ(不思議なことに)。
『ライ麦畑』の謎解きに挑戦したい人は、「橋本福男・訳」を含めて、3つ全部の翻訳を読む必要があるだろう。
数種類の翻訳を読み比べすることができるということは、もはや、外国文学を味わう上での醍醐味と言っていい。
さらに興味があれば、その上で英語の原文に当たってみればいいのだ。
とりあえず初めてという人は、最初に「村上春樹・訳」から入るのが無難だろう。
「野崎孝・訳」は歴史的な名訳だが、どうしても翻訳から時間が経ちすぎている。
決して古くさいと感じることはないが、「村上春樹・訳」は、あたかも村上春樹の小説のようにスマートで読みやすい。
スマートで読みやすいことが『ライ麦畑』にとってふさわしいか否かという点については、後から「野崎孝・訳」と読み比べてみれば分かる。
ただし、研究者でないかぎり、物語は物語として味わった方が、絶対に楽しい(学校の勉強じゃないんだから)。
今年のクリスマスに「村上春樹・訳」の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』を読んだら、来年のクリスマスには「野崎孝・訳」の『ライ麦畑でつかまえて』を読んでみる。
時間を置いて異なる翻訳を読み比べてみることで、読み終わった後の感想も、きっと変わってくることだろう。
なお、野崎孝・訳の『ライ麦畑でつかまえて』には、1964年版(昭和39年版)と1984年版(昭和59年版)の、二つの訳がある。
また、1984年版(昭和59年版)の白水ブックスには、かつて訳者による解説が巻末に収録されていたが、契約上の事情により現行品に解説は収録されていない(白水社のホームページで閲覧可能)。
パブロ・ピカソによるデザインの表紙カバーのイラストも、現行品からは消えた(残念)。
正解のない『ライ麦畑』は、何度読み返しても(何十回読み返しても)おもしろい小説である。
一つ一つの文章、一つ一つの会話、一つ一つの言葉に意味があることを知ってしまえば、この小説は、完全なる「底なし沼」となる。
いつの時代も、ホールデン・コールフィールドは我々であり、我々はホールデン・コールフィールドだった。
不満や不安のないパーフェクトな社会が存在しない以上、『ライ麦畑でつかまえて』は永遠の古典として読み継がれていくことだろう。
書名:ライ麦畑でつかまえて
著者:J.D.サリンジャー
訳者:野崎孝
発行:1984/05/20
出版社:白水ブックス