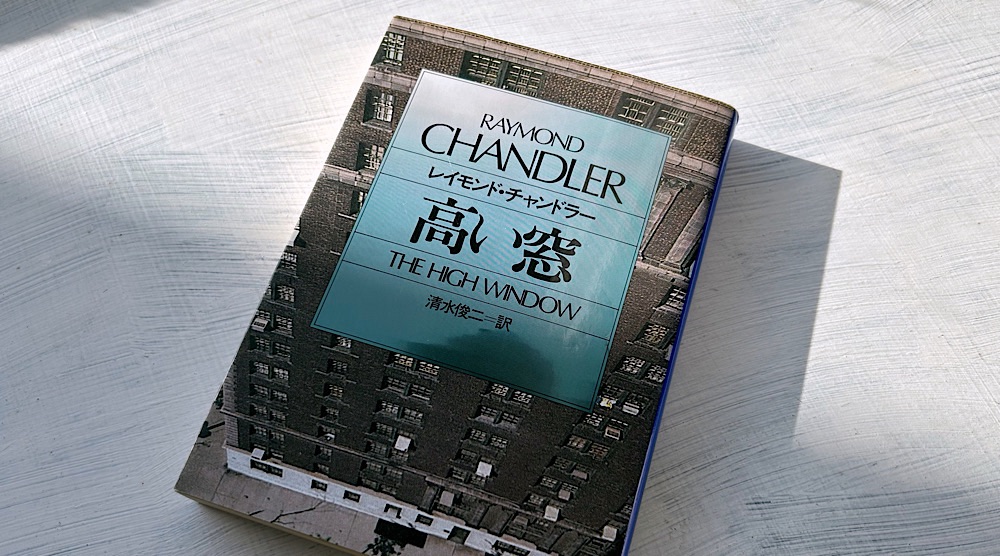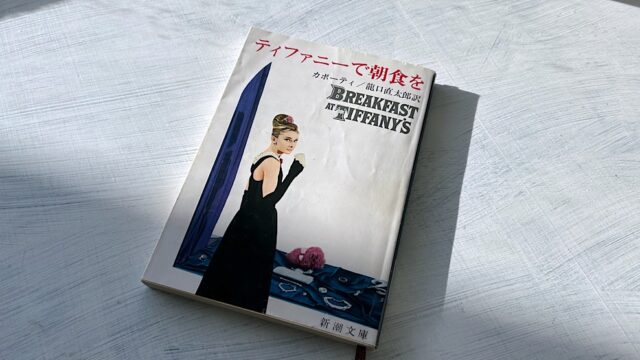レイモンド・チャンドラー「高い窓」読了。
本作「高い窓」は、1942年(昭和17年)8月にクノップ社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は54歳だった。
田中小実昌・訳のチャンドラーを読む
チャンドラーのフィリップ・マーロウ・シリーズでは3作目の長篇小説となる『高い窓』を、僕はこれまでにも何度も読んできた。
ほとんどは清水俊二の訳によるもので、時には、村上春樹の訳によるもので。
ただ、田中小実昌訳のチャンドラーを読むのは、今回が初めてだったので、そういう意味では、新鮮なマーロウ体験となったことは確かだ。
いきなり「おれは待っていた」なんていう、タフでハードボイルドなマーロウが登場して、最初は少々戸惑ったけれど、読み進めていくうちに、やんちゃなマーロウも悪くないと思えるようになった。
大切なことは細部の文章ではなく、フィリップ・マーロウという私立探偵が生きる物語の世界観にあるということが分かったからだ。
本作『高い窓』は、財産家の邸宅から盗まれた貴重な金貨の行方を探す物語だが、もちろん、消えた金貨は、物語を進行する上で重要な役割を果たすひとつの小道具であって、金貨が消えたことによって発覚する様々な人間関係が、この物語の大きなテーマとなっている。
ブリーズ警部補は、肩をつかんだ手をはずし、ドアを開けてくれ、ニヤッとわらって、おれの目をのぞきこんだ。「きみのいうキャシディ事件のためか、時々、そんな必要もないやつを、大目に見てやることがある。きたないことで大財産をつくった者から、ぼくや、そしてきみのような、ただあくせくはたらいている人間に、ほんのわずかでも、なにかもどしてもらうというわけさ」(レイモンド・チャンドラー「高い窓」田中小実昌・訳)
僕がマーロウ・シリーズの作品を読むのは、難しいトリックに挑戦したいからじゃない。
マーロウを読むとき、僕の頭の中は大抵空っぽになっていて、何も考えず、ただひたすらにマーロウの世界観に浸っている。
僕が好きなのは、フィリップ・マーロウという一人の人間の生き方であり、マーロウ・シリーズの全般に漂う、肯定的な人生観なのだと思う。
マーロウは法律の奴隷ではないから、自分の判断によって、真犯人を見逃すこともあるし、冤罪に陥れられそうな女性の痕跡を、誰にも気づかれないように消してやったりもする。
これは、誰のためでもない、マーロウの純粋な哲学なのだ。
金のためでもないし、名誉のためでもない。
男としてのプライドのためでもないし、もちろん、社会に貢献するためでもない。
おそらく、フィリップ・マーロウは、もっと大きな、目に見えない何かのために働き、人生を生きている。
読者が共感するのは、こうしたフィリップ・マーロウの、ある意味で幼稚な生き方にあるのではないだろうか。
やわらかい、しずかな夜気が、あたりをすっぽりつつみ、青白い月光は、つめたく、すんでいる。心のなかでさがしもとめ、そして実際には見つからない正義は、この月光のようなものだろうか。(レイモンド・チャンドラー「高い窓」田中小実昌・訳)
こうしたマーロウの人生哲学は、決して押しつけがましくなく、作品のところどころで、たまに姿を見せるにすぎない。
それでも違和感がないのは、マーロウの言葉や行動が、既にマーロウ哲学そのものとなっているからなのだろう。
チャンドラー生誕100年記念で刊行された『レイモンド・チャンドラー読本』には、そんなマーロウの魅力に憑りつかれた男たちの思いが、たっぷりと収録されている。
でも、僕はどちらかというと、内田裕也が創ったアルバム『さらば愛しき女よ』のように、純粋なマーロウ体験をシンプルに表現した作品の方が好きなのかもしれない。
残念ながら、内田裕也の『さらば愛しき女よ』に「高い窓」という楽曲は収録されていないけれど。
ファンタジーの世界を一人で生きるフィリップ・マーロウ
『長いお別れ』や『さらば愛しき女よ』、あるいは『大いなる眠り』などのような名作と比べると、『高い窓』は比較的地味な作品である。
村上春樹がチャンドラーを翻訳したときも、本作『高い窓』は五番目の作品だった(マーロウの長篇小説は、全部で7作ある)。
だけど、今回、改めて読み返してみると、この『高い窓』にも、記憶に残すべき文章は少なくない。
おれは手をのばし、マールのにぎりしめた両手の上にかさねた。「いいんだよ。ぼくはしってる。マーロウ探偵はなんでもしってる。ただ、ちゃんとしたくらしをする方法を知らんだけだ」(レイモンド・チャンドラー「高い窓」田中小実昌・訳)
マーロウは、決して自惚れた発言をしない。
自己認識をしっかりと持った、大人の男だからだ。
登場人物の台詞にも、人生観がある。
特に、エレベーター係の<グランディじいさん>の言葉はいい。
グランディじいさんはニヤニヤわらった。「ティーガーさんは、なにをやったんだね?」「それを、今から自宅のほうにいって、しらべてみる。しかし、きっと、もうどこかに高飛びしたあとだろう」「わしも、ティーガーさんといっしょに、いきたいよ。たとえ、サンフランシスコでとっつかまっても、この街から出て、どこかにいきたい」(レイモンド・チャンドラー「高い窓」田中小実昌・訳)
ほんのちょい役の、こんなエレベーター係のお爺さんの言葉にさえ、人生のリアリティがあり、年齢を重ねた重みがある。
それは、金持ちの住宅街<アイドル・ヴァレイ>の警備員にも感じられることだ。
「きみだって、そのうち、ここに住むようになるかもしれん」警備員は、またつばをはいた。「一年に五万ドルよこし、シフォンのパジャマを着て、ピンクの真珠のネックレースを首にかけてくれたって、こんなところに住むのはいやだ」(レイモンド・チャンドラー「高い窓」田中小実昌・訳)
どうやら、僕は、マーロウ・シリーズに登場する半端な脇役が好きらしい。
だが、こうした社会悪に対する徹底した対決姿勢は、主人公フィリップ・マーロウにこそ、もっとも強く見られるものである。
「二人とも死んでるんだ」とブリーズ警部補は答えた。「だれがだれを射とうが、かわりはないじゃないか──」「その秘書にも母親か妹、あるいは恋人がいたと考えたことはありませんか? もしかしたら、三人ともいたかもしれん。それらの人たちは、その秘書に対して、誇りと信頼、そして愛情を持ってた。その自分の愛する者が、ボスのおやじが百万長者だというだけのことで、酒乱の人殺しにされたんじゃ、たまるまいとおもう」(レイモンド・チャンドラー「高い窓」田中小実昌・訳)
彼らに共通しているのは、安っぽくて幼稚な正義感である。
そして、この安っぽくて幼稚な正義感こそが、フィリップ・マーロウの物語を根底から支えている世界観のすべてだと思う。
なぜなら、男というのは、いくつになっても、感傷的な伝説を信じたいと考えている幼稚な生き物だから。
マーロウの幼稚性は、世界中から戦争を消滅させなければならないと考える幼稚性と、あるいは同じものかもしれない。
男は夢見る男に憧れるものだ。
もっとも、マーロウの素晴らしいところは、ファンタジーの世界を一人で生き続けていることだろう。
そのファンタジーに共感してこそ、レイモンド・チャンドラーの読者になれるのだと思う。
書名:高い窓
著者:レイモンド・チャンドラー
訳者:田中小実昌
発行:1965/11/30(4版)
出版社:ハヤカワ・ポケット・ミステリー