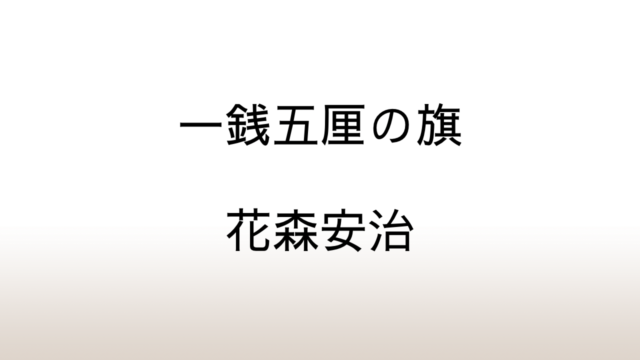井伏鱒二「さざなみ軍記」読了。
本作「さざなみ軍記」は、1930年(昭和5年)3月から1938年(昭和13年)4月にかけて、『文学』『作品』『文学界』に断続的に発表された長篇小説である(初出時の題名は「逃げて行く記録」「逃亡記」「早春日記」)。
連載開始の年、著者は32歳だった。
単行本は、1938年(昭和13年)4月に『さざなみ軍記』として河出書房から刊行されている。
平家某の一人の少年が綴った青春記
戦乱が非日常的なものだとしたなら、戦乱でしか書くことのできない人間の様子というものもあるだろう。
例えば、年老いたる功臣の宇治大納言は、逃亡の途上にある島の上で、こんな話をしている。
──私はもう暫くしか生きていない人間であるが、どうしてこんなに生きていたいのか自分でもわからない。この疑問に答える人間は一人もいないであろう。私達は何処の場所へ逃げて行くのか誰も知っていない。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
「どうしてこんなに生きていたいのか自分でもわからない」とあるのは、おそらく普遍的な人間のテーマであって、戦乱の中での逃亡という極限状態にあって、この疑問は、一際重要な意味を帯びて見える。
人間を極限状態に置いた上で、人間の様子を書いた小説というのが、つまり、この「さざなみ軍記」という作品だろう。
主人公は、平家一門に連なる「平家某の一人の少年」で、父は三位中将(平中納言三位知盛)である。
帝都を追われた少年は、海洋を西へと逃げる途上で、この日記を綴る。
帝都には安寧なく、家々では門や戸をとじて、人々は終日、供養の鐘をうちならしている。念仏をとなえる声は隣家へきこえ、隣家の人の念仏は、その隣家にきこえる。戦死者の寡婦のとなえる念仏は大声である。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
ベースになっているのは、『平家物語』と思われるが、『平家物語』を知らなくても、この小説は楽しむことができる。
『さざなみ軍記』は、歴史を描いているのではなく、歴史的な戦乱を舞台に人間を描いているからだ。
私はこの格闘のこれ以上の経過を見ていることができなかった。私は垣のかげにかくれてかたく目を閉じた。こんな残忍な出来事はあるべきことではない。私は兵変というものを嫌悪する。けれど今度の兵変は、まだ漸くその発端に達しようとしかけているにすぎないではないか。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
主人公の少年は、徹底的に人間的に描かれている。
平家の公達が「私は兵変というものを嫌悪する」と言って、目の前の戦いから目を背けているのだ。
主人公は何度も「私は脱走したい。誰よりも先に味方から逃れて行きたい」と考えるが、実際に脱走することはできない。
平家一門の公達であるという誇りだけが、少年の心を支えていたのだろう。
室の津という港町で、少年は一人の少女と恋をする。
私は彼女に、彼女の父や兄弟が留守であることをたしかめてから、竹竿でもって梨の木の枝をたたいた。梨の実は私の乗馬の首や鞍の上に落ち、かたい地面に降りそそいだ。水っぽくて固い果実が土地を打つ音をたてた。何という爽やかな音であろう。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
「水っぽくて固い果実」は、少年自身でもあり、少年に思いを寄せる少女自身でもあっただろう。
しかし、逃亡の途上にある少年には、いつまでも少女と恋を語っていることはできない。
少年を乗せた船は港を離れ、さらに西へと向かっていく。
かつて脱走したいと考え、少女と恋をした少年は、やがて、一人の侍へと成長する。
父はもはや覚悟をきめていた。私は溢れ出る涙のため口をきくことが難かしかった。本年十一歳の舎弟も十歳の舎弟も、私の涙に誘われて彼等は声をあげて泣きだした。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
時間にして、それは、わずか8ヶ月ばかりのことに過ぎないのだが、少年の日の成長には瞠目すべきものがある。
本作『さざなみ軍記』は、そんな少年の成長を描いた、ひとつの青春物語と言えるだろう。
日本人の好きな滅びの美学
庶民文学を得意とする井伏鱒二の作品だから、『さざなみ軍記』でも庶民の役割は重要だ。
とりわけ、戦乱の世を生きる庶民の姿には、歴史的にも重要な意味が隠されているように思われる。
私は彼等の慾望こそ笑止なものであることを知っている。しかし私達の階級は、彼等のそんな慾望を利用しなくては彼等を支配することができないだろう。彼等は私達の階級を支持するために、規則や制度によって傷ついて、そして彼等自ら苦しむのである。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
「彼等は私達の階級を支持するために、規則や制度によって傷ついて、そして彼等自ら苦しむのである」は、特定の時代の特別な事例を指摘したものではない。
まさに、そのような歴史は、日本の中でも繰り返されていて、井伏さんが、この作品を書いていた昭和初期という時代でさえも、それは例外ではなかった。
中務卿の舎弟が、女官某の意見として、新しい帝都の建設に向けた夢を語る場面でも、庶民の本質が綴られている。
民衆は彼等の努力によって平和や秩序を彼等のためにつくり出そうとして、彼等はわれわれに権勢を与えなくてはならない立場に彼等自ら運びこまれて行く。民衆というものはどんなに困難な状態に置かれても、われわれには不思議でならないほどの忍従と労役により、われわれに権勢を提供しないではいないものである。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
上流階級を語っているようで、実際に語られているのは、「どんなに困難な状態に置かれても、われわれには不思議でならないほどの忍従と労役により、われわれに権勢を提供しないではいない」民衆の姿だ。
権力者たちは、そんな民衆の本質を知っているからこそ、民衆を上手に掌握することができる。
そのことこそが、『さざなみ軍記』という戦争小説が発信する、重要なメッセージではなかったか。
もちろん、主人公は「私の一ばん嬉しいことは、私たち一門以外の階級のものから好意を示されることである」と考えている、純情で無垢な少年だ。
権力者と庶民とをつなぐ役割が、少年には与えられていたのかもしれない。
それにしても、平家の物語には、日本人の好きな滅びの美学がある。
それは、満開の桜の花が散っていく美しさだ。
最も気の毒なのは正三位参議の一家であった。経正、経俊、敦盛の三人の兄弟が、みな討死してしまった。敦盛は私より年が一つ上である。彼は従五位下に任ぜられると妻帯して昨年の末に一子を設けたが、その見はてぬ夢は心残りの多いことであったろうと思われる。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
熊谷直実に首を取られたとき、平敦盛は17歳とも16歳とも伝えられているから、主人公の少年もまた、15歳から16歳くらいだったのだろう。
「敦盛は私たち一門のうちで自他ともに許す美貌の公達」で「彼の顔容は匂うかと思われるほど美しかった」と、主人公は述懐している。
もちろん、『さざなみ軍記』は、井伏鱒二による完全なるフィクションだが、こういう作品を読むと、原典とも言える『平家物語』を読みたくなってしまう。
十三日には、平家の首を六条室町の源九郎の第に集めて六条河原に渡し、仲頼というもの等はこれを長刀の先に貫き赤札をつけて姓名を記し、大路をひきまわし獄門にかけた。見物の庶民はその数幾万とも知れなかったという。(井伏鱒二「さざなみ軍記」)
「首を大路に渡された人は、通盛、忠度、経俊、経正、師盛、敦盛、業盛、盛俊など十人のうちに、どういう間違いか首につけた赤札に、この私の名前が記されていたということである」とあるのは、さすがに小説の上手な人の話だと思った。
あるいは、井伏さんは、いつもこういうことを考えながら、日常の暮らしを送っていたのかもしれない。
作品名:さざなみ軍記
著者:井伏鱒二
書名:さざなみ軍記・ジョン万次郎漂流記
発行:1986/09/25
出版社:新潮文庫

(2026/03/04 03:27:45時点 楽天市場調べ-詳細)