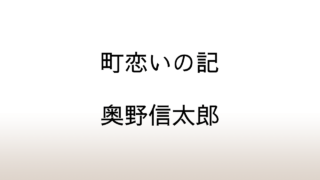大岡昇平「スコットランドの鷗」読了。
本書は小説家・大岡昇平にとって初めての随筆集である。
河上徹太郎や今日出海、小林秀雄などの飲み仲間
「非随筆家たる私の書き散らしたものの中から収録に値するものを選び出すのは大変だったと思う」とあとがきにあるように、著者は随筆の難しさというものを意識していたらしい。
構成としては、第一部に身辺雑記、第二部で文壇交友、第三部でクラシック音楽、第四部で文学批評と、大雑把に言えばそのような分類となっている。
冒頭の「雪の思い出」は、
十三年ぶりで大磯に十五センチの大雪が積もったという話から、「私の五十余年の生涯には、いろいろな雪の思い出がある」と、雪にまつわる思い出話が繰り広げられていく。
中でも興味深いのは「二月に雪が降れば、まず思い出すのは、二・二六事件の雪である」と綴られている、二・二六事件にまつわる回想だろう。
当時二十七歳で、青山五丁目付近のアパートに住んでいた著者は、正午頃に目を覚まして、町の様子がいつもとは異なっていることに違和感を覚える。
雪が降っているにしても、町はあまりに静寂で、外出してみて、初めてその原因が、都電が停まっていたためであったことを知る。
銀座の仲間の集まるおでん屋へ行くと、河上徹太郎や木村庄三郎がいて、興奮していた。「いよいよおれたちも感情教育のような時代に生きているということになった」と河上が言っていた。「感情教育」はフローベルの小説。一八四八年二月の革命を傍観者として見るインテリを主人公とした小説である。(大岡昇平「雪の思い出」)
当時の若者たちの興奮が、雪の思い出を通して綴られている。
酒を主題に書いた「酒品」には、河上徹太郎や今日出海、小林秀雄などの飲み仲間が登場するが、出会った頃、彼らはまだ酒飲みではなかったらしく、「河上は全然飲まず、今ちゃんはお猪口一杯で真赤になる方で、みんな酒の勢いでわあわあやってるとこでは、まったく気の毒だった」と回想にある。
そんな二人も訓練を重ねて一人前の酒飲みとなった。
河上はもともと無口の酒で、こっちがはっと気がついたら、向うも酔っぱらったという型だったが、近頃変り身が早くなったようだ。那須からゴルフの帰りの汽車の中へポケット入サントリイを持ち込んでいる。座席で一人ちびちびやってる恰好も、てんで落着いたものだ。東京へ着いたのが飯時なので、「徹ちゃん、すしでも食おうか」と誘うと、「なにおっ」と来た。(大岡昇平「酒品」)
この後、著者は、既に酔っぱらっている河上さんを見捨てて、「とうてい太刀打ち出来る相手ではないとあきらめて、上野駅の混雑にまぎれて、姿をくらますことにした」というところが楽しい。
「巴里の酢豆腐」には、魯山人が登場して大暴れしている。
パリのノートルダムの後の方の河岸にある「トゥール・ダルヂャン」というレストランは、鴨料理で歴史的に有名な店だが、ここで魯山人は、味を付けない鴨肉を持って来させて、わさび醤油で食べ始めた。
支配人はもちろん驚いたが、案内してくれた画家の荻須高徳さんが「東京の一流料理店主だから」と説明して、理解を得ることができたらしいが、まさにリアル海原雄山といった暴挙ぶりである。
案内役の荻須高徳さんも、さぞかし迷惑千万なことだったろう。
などというように、ひとつひとつ拾っていくと、切りがないくらいに面白いエピソードばかりが収録されている。
随筆家ではない「非随筆家」が綴る随筆だからこその醍醐味が、どうやらここにはあるらしい。
スコットランドで見つけた三好達治の詩
表題作「スコットランドの鷗」は、畏友・三好達治の作品をモチーフとした作品である。
春の岬 旅のをはりの鷗どり
浮きつつ遠くなりにけるかも
これは、三好達治の処女詩集『測量船』の開巻の詩だが、著者はスコットランドを旅しているときに、達治のこの詩を思い出していた。
それは、一九五四年六月に、ロンドン滞在中の福田恆存を訪ねて、一緒にスコットランドを廻った時のことで、二人は、レイク・ディストリクトをふり出しに、エディンバラからスターリングと道を取り、ハイランドの湖水を二十以上見て廻った。
この時、船上から波間に浮ぶ鷗を見ながら、著者は「春の岬」の意味を理解する。
スコットランド紀行と三好達治の詩が見事にマッチングして、随筆の面白さを教えてくれる作品と仕上がっている。
書名:スコットランドの鷗
著者:大岡昇平
発行:1984/11/10(新装改訂版)
出版社:三月書房