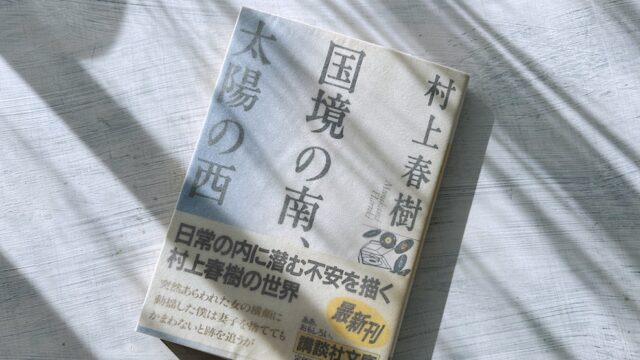島崎藤村「春」読了。
本作「春」は、1908年(明治41年)4月から8月まで『東京朝日新聞』に連載された長編小説である。
この年、著者は36歳だった。
単行本は、1909年(明治42年)10月「緑陰叢書第二篇」として自費出版されている。
島崎藤村にとっては『破戒』に続いて、これが二作目の長編小説だった。
ちなみに、島崎藤村「春」完結後に、『東京朝日新聞』に連載された新聞小説が、夏目漱石の「三四郎」である(明治41年9月1日連載開始)。
明治20年代の若者たちの青春を描いた青春小説
文芸雑誌『文学界』が創刊されたのは、1893年(明治26年)1月のこと。
この雑誌は、1898年(明治31年)1月に終了しているから、現在も続いている『文学界』とは別の雑誌である。
当時『文学界』で活動した作家として、北村透谷、島崎藤村、平田禿木、樋口一葉、上田敏、田山花袋、戸川秋骨、松岡国男(柳田国男)などがいるが、本作「春」は、『文学界』で活動していた時期の体験を素材として書かれた、島崎藤村の自伝的小説である。
主人公<岸本捨吉>(島崎藤村)を中心に、若い世代の精神的支柱であった<青木>(北村透谷)、その信奉者である<市川>(平田禿木)、<菅>(戸川秋骨)、岸本や菅とは同窓の<足立>(馬場孤蝶)たちの交流を描きながら物語は進められていく。
彼らの大きな特徴は、最年長の北村透谷(明治元年生まれ)を筆頭に、最年少の平田禿木(明治6年生まれ)まで、全員が「新時代・明治生まれ」だったということだろう。
つまり、本作『春』は、明治20年代に20代だった若者たちの青春を描いた青春小説ということになる。
それは、明治維新以来の新しい時代に生まれた、まさに「新世代の青春群像」だったのだ。
それぞれが、我が青春の主人公である彼らは、それぞれに大志を抱え、人生を苦悩していくが、とりわけ中心的なエピソードとなっているのは、主人公・岸本(島崎藤村)の失恋と、グループの実質的リーダーであった青木(北村透谷)の自殺である。
女学校で講師をしていた岸本は、教え子<勝子>(佐藤輔子)に恋をするが、勝子には既に親の決めた許嫁があった。
失意の岸本は、学校を去り、放浪の旅に出かけるが、この物語は、放浪中の岸本が、仲間たち(青木・市川・菅)と再会する場面から始まる。
みな、それぞれに恋愛を経験している仲間たちが、岸本の恋を応援するのはいいとして、親の決めた許嫁のあることは、いかに文明開化の明治時代とはいえ、それを覆すことは(特に女性にとって)容易ではなかったらしい。
「先生、いろいろ御世話様に成りました……」こう言って、勝子は紅く泣腫れた顔を上げた。彼女はまだ何か言おうとしたが、それを言うことは出来なかった。岸本は黙って、御辞儀をして、別れた。(島崎藤村「春」)
この岸本(島崎藤村)の失恋事件が、本作の全体に流れている大きなテーマである。
島崎藤村、平田禿木、戸川秋骨、馬場孤蝶、それぞれの人生
一方で、グループ中、唯一の既婚者で、幼い子どもの父親である青木(北村透谷)は、恋愛や結婚の現実を知っているが故の苦しみを抱えている。
新たな日本を築こうとする青木の志は果てしないものの、現実社会の壁は大きく、やがて疲弊した彼はメンタルを病む。
「到頭、宅も亡くなりましたよ」と操は嘆息した。疲労(つかれ)と悲哀(かなしみ)とで、彼女の顔色は蒼ざめて見えた。(島崎藤村「春」)
この物語では、青木が死に至る経過を克明に再現しており、北村透谷への追悼文学という色彩も濃い。
恋愛や家庭生活、人生の苦悩など、新たな明治時代は、若者たちが自由に生きていく上で、決して簡単な時代ではなかったらしい。
希望と挫折が折り重なっている──それが、明治20年代という時代だった。
本作『春』では、青年たち個々のエピソードも忘れがたいが、とりわけ、印象に残るのは、結束の固かった仲間たちが、やがて、それぞれの道を歩み始めていくところである。
その晩は皆な酔った。各自(めいめい)志すところは違っているにしても、猶お同じ親い記憶に繋がれていることを思い起させた。市川も菅もそこまで附合おうというので、足立や岸本の行く方へ随いて来た。(島崎藤村「春」)
各自が、それぞれの道を歩いていくところは切ないが、それは、彼らが、自分の人生を見つけた証でもある。
島崎藤村、平田禿木、戸川秋骨、馬場孤蝶。
彼らは、それぞれの道で、それぞれの人生を極めていった。
そんな彼らが集った一つの時代こそ、奇跡のようなものだったのかもしれない。
100年以上前の小説だけれど、若者たちの苦悩は(少なくとも根本的な部分において)現代とそれほど大きな違いはないらしい。
若い世代にこそおすすめしたい、明治の青春小説である。
書名:春
著者:島崎藤村
発行:2007/03/25
出版社:新潮文庫