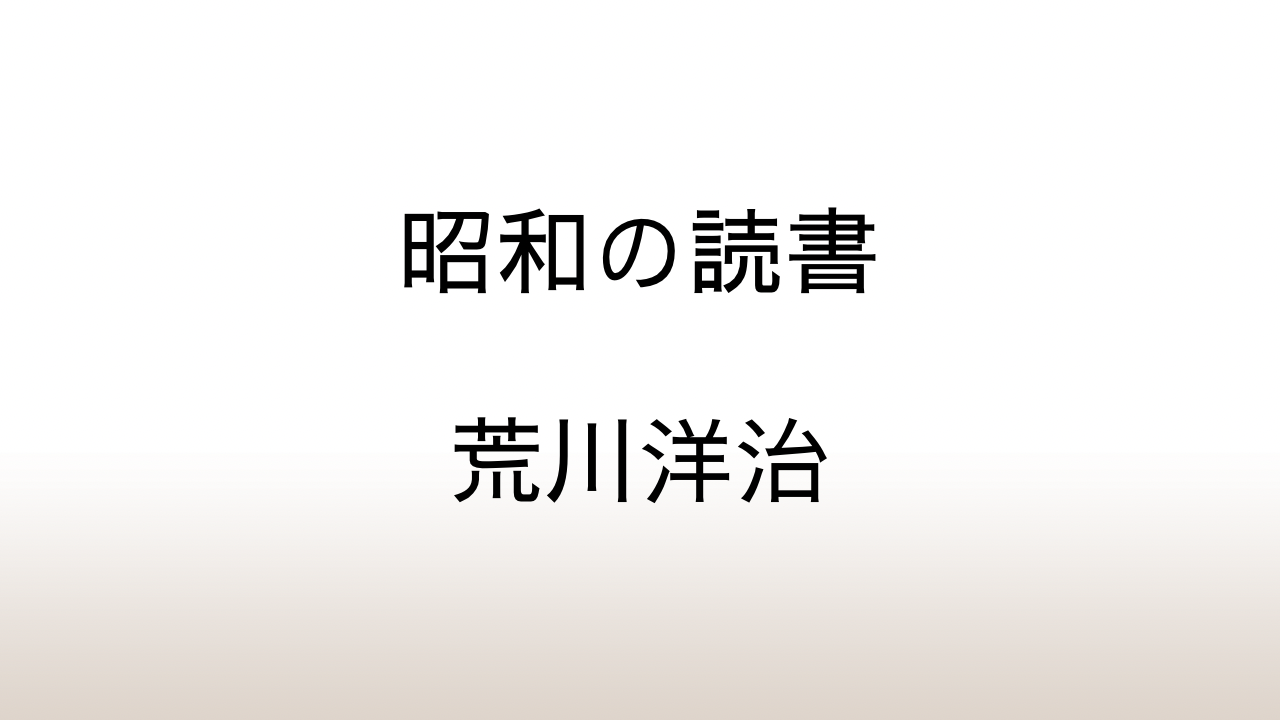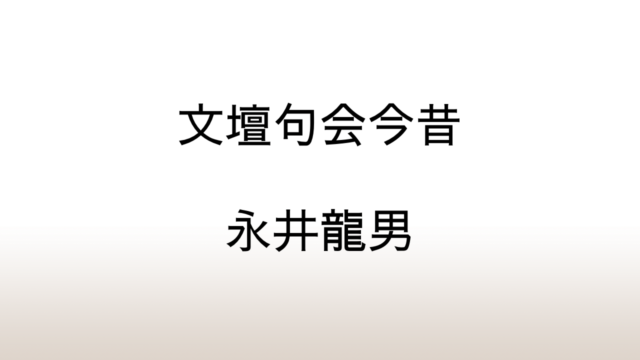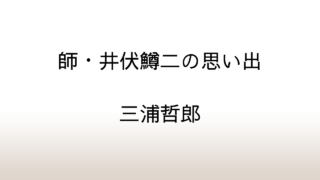荒川洋治「昭和の読書」読了。
最初に「あとがき」を読んでみる。
昭和という時代に、内容、形態の面で、いまはあまりみかけない書物が刊行された。そのなかから、文学の風土記、人国記、文学散歩の本、作家論、日本文学史、文学全集の名作集、小説の新書、詞華集などを選んだ。これらの本のすべてが、当時の読者の心をみたしたとは思えないが、心惹かれるものがある。(荒川洋治「昭和の読書」)
文学風土記や作家論、文学全集の名作集などから、昭和を生きる人々が、どのような読書と向き合っていたのかを知ることができる。
文学論のようでもあり、読書エッセイのようでもある。
昭和期に多くの出版社から刊行された文学全集の中の「名作集」に着目したエッセイがおもしろい。
基本的に、文学全集は個人集によって構成されているが、一人で一冊の場を与えられない作家の作品は「名作集」の中に収録されることが多かった。
要はアンソロジーで、CDで言えばコンピレーションアルバム(オムニバス盤)である。
こうした名作集は、著名な作家の個人集が並ぶ文学全集にあっては、しょせんオマケで、当時から注目されることは、決して多くはなかったはずだ。
しかし、今となってみると「名作集」は、現代では入手の難しい作家の作品を読むことができる、貴重な書籍となっている。
最近のアンソロジーは、どこの企画も作品が固定化しているので、若い人たちは、ごく限られた文豪の名前しか知らない。
特定の作家についての知識はあっても、同じ時代に活躍した作家とのつながりには関心がない。
「文学の全体的な光景に興味がないのだ」と、著者は指摘している。
多少は意識が多様化したとはいえ、多くの人は「売れている」という本だけに殺到する。自分の感覚で、自分の選んだものを楽しむというラインが消えているのだ。(荒川洋治「昭和の読書」)
そう言えば、ツイッターを見ていると、現代の読書は、他者との共感を得ることに重きを置いているような気がする。
昭和中期に刊行された文学全集の名作集なんて、レアな作品の塊みたいなものだから、他者との共感を得るための作品としては、決して優れているとは言えない。
しかし、現代では忘れられてしまった作品の中にこそ、現代を見つめ直すヒントがあるのではないだろうか。
著者は、個人全集の第一巻も「いつの間にか集まった」と紹介している。
鈴木三重吉、中野重治、フローベール、椎名麟三、内田百閒、葉山嘉樹、小林勝、佐多稲子、小熊秀雄、草野心平、近松秋江、本庄睦男、、、
個人全集の第一巻というのは、名刺代わりの一冊として、もしかするとお勧めなのかもしれない。
自分の好きな本だけに囲まれている生活
同じ本を何冊も買う、という話もおもしろい。
学習研究社の「芥川賞作家シリーズ」(1964-1965)なんて、いろいろな作家の巻を複数冊所有している。
「同じものを集めてどうするのかと自分でも思うが、旅行するとき、このなかの一冊をもって出ると、心が落ち着くのだ」という気持ちには、同じく文学を愛する者として共感したい。
著者が二冊持っているという『佐渡』(庄野潤三、1964)を、僕は三冊保有している。
庄野さんの本は、意外と見つからないので、見つけるたびに買う癖がついてしまった。
だから、我が家の本棚の一画には、庄野潤三の同じ本が、まるで新刊書店のように何冊も並んでいる。
こうした「花」たちにかこまれる日々はしあわせだ。必要な人が現れたときに、これまでもあげてきたので何冊あってもいいのだ。(荒川洋治「昭和の読書」)
自分の好きな本だけに囲まれている生活というのは、読書好きの人間にとって、まさしく究極の幸せではないかと思う。
書名:昭和の読書
著者:荒川洋治
発行:2011/9/19
出版社:幻戯書房