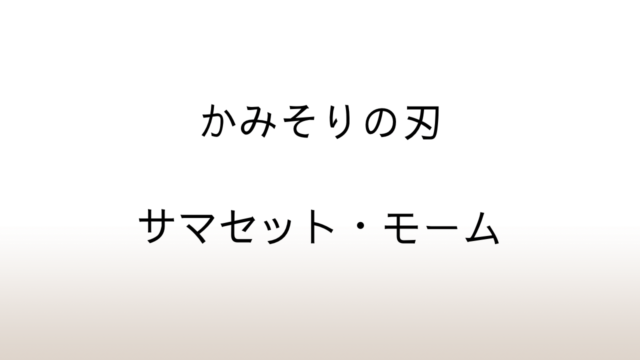アン・ビーティ「燃える家」読了。
本作「燃える家」は、1982年(昭和57年)に刊行された作品集『燃える家』に収録されている短篇小説である。
原題は「The Burning House」。
この年、著者は35歳だった。
日本では、1989年(平成元年)3月、亀井よし子の翻訳によって出版された。
インテリたちの「内面のひとりぼっち」
本作「燃える家」は、都市生活者の孤独と喪失を描いた短篇小説である。
まず、登場人物がみんなインテリ。
主人公の主婦<エイミー>は、息子の<マーク>が小学校へ入学したのを機に、美術史の修士号を取得するため、大学へ戻っている。
夫のフランクは、大学で英文学を学んだあと、経営学の大学院へ進学し、現在は、<タッカー>の経営するソーホーの画廊で、会計士として働いている。
フランクがタッカーと出会ったのは、ニューヨークの心理療法グループでだった。
<J・D>は、フランクの指導教官だったが、現在は大学を辞めてブラブラしている。
そして、夫の異父兄弟<フレディ・フォックス>は、フランクから「レディ・フォックス」と呼ばれているゲイだ。
彼らは、フェアフィールド郡(コネチカット州)にあるフランクとエイミーの家に集まって、泊まり込みの楽しいパーティーを開催中だが、彼らの心の中には、それぞれに空洞があった。
「おれは面と向かっていえないようなことをいってやるよ」とフレディ。「いかした女房とガキと犬がいるってのに、俗物のあんたは何もかもあって当然だと思ってるんだ」(アン・ビーティ「燃える家」訳・亀井よし子)
夫フランクには不倫相手がいて、おまけに妻と息子との接触を避けようとしていた。
一方で、妻エイミーにも、大学で知り合った新しい恋人<ジョニー>がいる。
パーティーの最中にもジョニーは電話をかけてきて、「きみと一緒にキーウエストに行きたい」と誘ったりなんかする。
みんな、表面上は取り繕っているけれど、実は誰もが孤独で、誰もがひとりぼっちだ。
この「内面のひとりぼっち」を描いた小説が、本作「燃える家」である。
パーティーの準備中、エイミーはキッチンでグラスを割って指を切ってしまう。
カールが重く感じる。自分の血を見たくない。汗をかいている。わたしはJ・Dのなすがままにする。彼は水道を止め、わたしの指をぎゅっと握る。二人の手首を水が伝う。(アン・ビーティ「燃える家」訳・亀井よし子)
流れるのは心の血であり、痛いのは指ではなく心の方だったろう。
プロットではなくシチュエーションのアーティスト
家庭の外に女がいる父親フランクを、息子のマークも避けている。
「あの人、困ってるのよ」とわたし。「家に帰ってきても、わたしを避けてるの。でも、マークまで避けるなんて冗談じゃないわ。あの子はまだ六つよ。なのにあの人が帰ってくると、友だちのニールに電話して、そっちへ行きたい、みたいなこというのよ。わたしと二人だけのときはそんなことしないのに」(アン・ビーティ「燃える家」訳・亀井よし子)
結局、パーティーの夜、マークはニールの家へお泊りに行くが、夜になってニールの母親・マリリンから電話がかかってくる。
マークが「家へ帰りたいと言って泣いている」というのだ。
6歳のマークもまた、自分の居場所を見失った孤独な少年だった。
自分を愛していない父親と一緒に過ごすことの不安と、自分には帰る場所がないのだという不安。
結局、パーティーに参加していない(姿が登場しない)マークこそが、この都会の一家の状況を、最も象徴する存在となっていたらしい。
「マークの誕生日が過ぎたらどうするか、決めたの?」彼は答えない。(略)「この家を選んだのはあなたよ、フランク。階下にいるのはあなたのお友だちよ。あたしはあなたの望むようにしてきたのよ」(アン・ビーティ「燃える家」訳・亀井よし子)
まるで、日常の一部を切り取っただけみたいに、この作品に特別のストーリーはない。
さりげない会話の組み合わせの中から匂ってくるような喪失感。
これが、ニューヨークの新聞コラムだと言われても、それほどは違和感を覚えなかっただろう。
繊細で透明感のある文章が、壊れやすそうな彼らの心を、丁寧になぞっていくところもいい。
「プロットではなくシチュエーションのアーティスト」というキャッチフレーズもぴったりだと思う。
作品名:燃える家
著者:アン・ビーティ
訳者:亀井よし子
書名:燃える家
発行:1989/03/25
出版社:ブロンズ新社