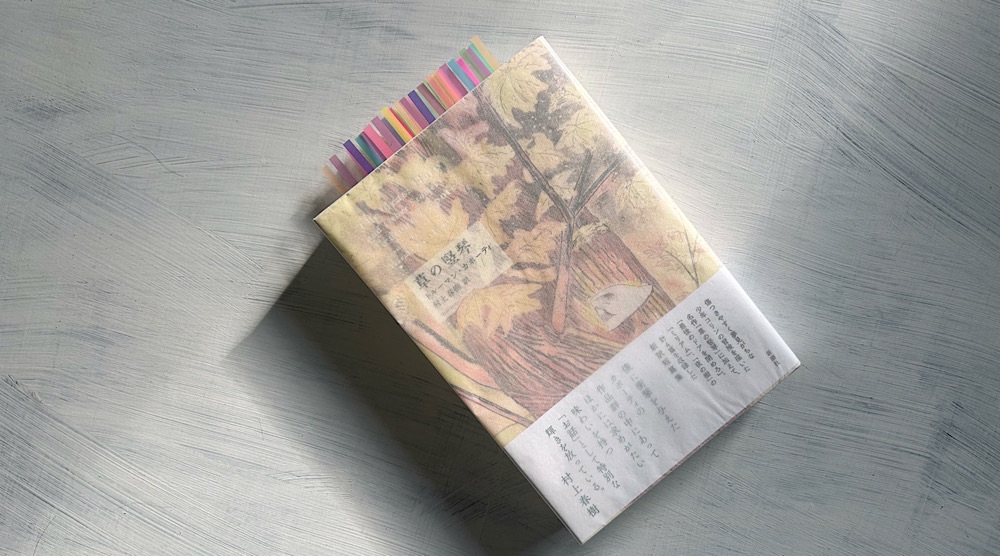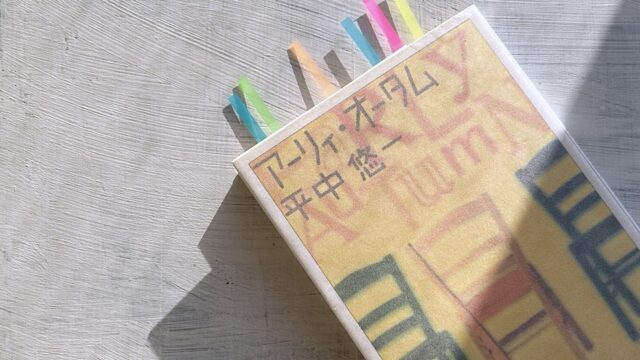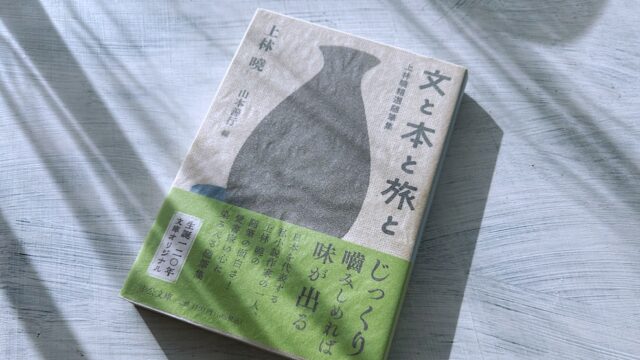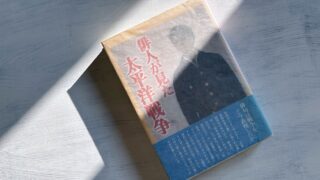トルーマン・カポーティ『草の竪琴』読了。
本作『草の竪琴』は、2025年(令和7年)6月に新潮社から刊行された作品集である。
この年、翻訳者の村上春樹は76歳だった。
著者のトルーマン・カポーティは、1984年(昭和59年)8月に59歳で他界している。
収録作品及び発表年は、次のとおり。
・草の竪琴 / 1951年(昭和26年)
・最後のドアを閉めろ / 1947年(昭和22年)
・ミリアム / 1945年(昭和20年)
・夜の樹 / 1945年(昭和20年)
少年時代のイノセント・ストーリー
村上春樹が翻訳出版したトルーマン・カポーティの本は、本作『草の竪琴』で7冊目となった。
1 おじいさんの思い出(1988年3月)
2 あるクリスマス(1989年12月)
3 クリスマスの思い出(1990年11月)
4 誕生日の子どもたち(2002年6月)
5 ティファニーで朝食を(2008年2月)
6 遠い声、遠い部屋(2023年8月)
7 草の竪琴(2025年6月 新潮社)
一連のタイトルを見て明らかなことは、トルーマン・カポーティの作品のうち、少年を主人公としたイノセントな物語と村上春樹の翻訳とは、非常に相性が良いということである。
今回の表題作「草の竪琴」は、カポーティのデビュー作「遠い声、遠い部屋」(1948)と対を成す作品と言われている。
この作品『草の竪琴』の主人公であるコリン少年は、『遠い声、遠い部屋』の主人公ジョエル少年と共通した要素を多く持ち合わせている。(略)そういう意味では『遠い声、遠い部屋』と『草の竪琴』は、同じ物語のネガとポジのような位置関係にあると評することもできよう。(村上春樹『草の竪琴』訳者あとがき)
『遠い声、遠い部屋』の村上春樹訳もハマっていたが、今回の『草の竪琴』の翻訳もいい。
作者(カポーティ)の自伝的要素が強い初期の長篇二作品を、村上春樹の訳で読むことができるというのは、かなりラッキーなことなのではないだろうか。
それほどに『遠い声』と『草の竪琴』の関係は深い。
ジョエル・ノックスがトルーマンの性格半分を表わしているとしたら、コリンは残りの半分を表わしている。『遠い声』が裏だとすると、『草の竪琴』は表の明るい側であり、コリンはトルーマン・カポーティの陽の当たる幸せな側面である。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
作者(トルーマン・カポーティ)自身、本作『草の竪琴』には強い思い入れを抱いていた。
「これはぼくにとってすごく現実的なもので、いままでに書いたどの作品よりも、またおそらくこれから書くどんな作品よりもリアルなのです。(略)だからこそ気持のうえでは辛いものがあります。いろんな思い出が甦ってくると、心がはりさけそうで、思わず泣いてしまいます」(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
本作「草の竪琴」は、両親を亡くした少年(コリン)の物語である。
父の従姉妹たち(ヴェリーナとドリー)と一緒に暮らすコリンの少年時代を物語るのは、草の竪琴だ。
ねえ、聞こえる? あれが草の竪琴なのよ。いつもお話を聞かせてくれるの──それは丘の上の人々の物語を残らず知っている。これまで生きたすべての人たちの話をね。(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
秋風に吹かれて鳴る草の葉の音は、まるで、人々の声を集めた「竪琴」のようだ。
今、草の竪琴が語るのは、妹(ヴェリーナ)への反乱を起こした姉(ドリー、60歳)やドリーの友人(キャサリン、60歳前後)と行動を共にするコリン少年(16歳)の物語である。
ぼくらは仲良しになった。ドリーとキャサリンとぼく。ぼくは十一歳だった。そしてやがて十六歳になった。何の名誉もなかったけれど、それでもそこにあったのは素晴らしい日々だった。(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
ヴェリーナとの家庭内トラブルで家を出たドリーとキャサリンとコリンは、ツリー・ハウスで暮らし始める。
この物語のポイントは、どこまでも善意の女性であるドリーが、妹ヴェリーナとの対立を経て、自分自身を取り戻す過程にあると言っていい。
「ほかに選択の余地があったかしら? それがわたしの求めていることなの。選ぶこと。別の人生を送れるんだ、そこではすべてを自分で決められるんだって知ること。それによってわたしは真実、自分と和解できるの」(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
実業家として町の実力者でもあるヴェリーナは、町の人々を動員して、暴力により事件を解決しようとするが、ドリーは、決して妥協しない。
ドリーの勇気を引きだしているのは、ドリーを愛するクール判事だ。
「我々は愛について話をしている。一枚の木の葉、ひとつかみの種子──そこから始めるんだ。愛するということがどういうことなのか、少しずつ学ぶのだ。(略)うん、それは簡単な道ではない。一生かかるかもしれない。私の場合がそうだった」(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
クール判事には、この物語を司る役割が与えられている。
「自分がどう見えるかなんて、まったく気にする必要はない。自分の本当の姿を自由に探していいのさ。誰にも我々をここから追い払うことはできないとわかってさえいればね」(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
樹上のツリー・ハウスは、彼らの「本当の姿」を象徴したものだったのだろうか。
「人はいろんなことをもっとたくさん、自分の内だけに留めておくべきなのさ。自分だけのぐっと深いところにね。そこがいちばんよい場所だよ」(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
「自分だけのぐっと深いところ」で生き続けてきた女性こそ、クール判事の愛するドリーだった。
そして、性的に奔放な女性(シスター・アイダ、42歳)や、年上の友人(ライリー)との交流が、主人公(コリン)の新しい道を開いていく。
夏、そして今ひとたびの秋、そして再び冬。それは螺旋ではない。傘の落とす影と同様、閉じ込められた円環。もし跳躍しなくてはならないとしたらそれは今だ──ぼくは思い切って切り出した。「ヴェリーナ、ぼくはここを出て行きたい」(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
少年の日のツリー・ハウスを胸に抱いて、コリンは新しい旅に出る。
つまり、本作「草の竪琴」は、少年が大人へと成長する過程を描いた物語だった、ということだ。
そしてそのときぼくは思った。ドリーがぼくに話してくれたことを、判事にも聞かせなくては。それは集め、語る草の竪琴、物語を記憶する声たちのつくる竪琴なのだ、と。ぼくらはそっと耳を澄ませた。(トルーマン・カポーティ「草の竪琴」村上春樹・訳)
少年時代の想い出が、田舎の草原を吹き抜ける風の音(草の竪琴)として描かれているところも素晴らしい。
デビュー作『遠い声、遠い部屋』のように張りつめた緊張感はなく、作品のニュアンスとしては、『あるクリスマス』や『クリスマスの思い出』に近い。
自分の内面を象徴的に描く
一方で、併録されている短篇三篇は、いずれもカポーティの名作として知られている。
「ミリアム」(1945)は、トルーマン・カポーティの、ごく初期の作品である。
その子の髪は、ミセス・ミラーがこれまで目にしたことがないくらい長く、またずいぶん風変わりだった。まるで白子のように混じりけなく銀白色なのだ。(トルーマン・カポーティ「ミリアム」村上春樹・訳)
主人公(ミセス・ミラー)と謎の少女(ミリアム)とのミステリアスな交流が、サスペンスタッチで描かれていく。
『草の竪琴』のように心温まるイノセント・ストーリーとは、正反対のムードを持っていると言ってもいい(いわゆる「夜の文体」)。
謎の少女ミリアムは、もちろん、孤独な老女ミセス・ミラーの抑圧された内面を象徴した存在だろう。
ミリアムは現実の人間なのか、あるいは超自然の存在なのか、それともミセス・ミラーの一部(それがトルーマン自身の解釈)であり、精神の分裂をきたしかけている女性が創り上げた恐るべき存在なのか。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
内面を描くということは、本書に収録された短篇三編に共通するテーマだった。
「ミリアム」に続いて発表された「夜の樹」(1945)も、女子大生(ケイ)の内面に潜む恐怖を象徴的に描いた、不可思議な物語である。
「買います」と彼女は言った。「いいわ、そのお守りを。それだけでいいのなら、買います──それだけがあなたの望みなら」(トルーマン・カポーティ「夜の樹」村上春樹・訳)
夜汽車で相席となった無気味なカップルは、主人公(ケイ)に、少女時代の様々な恐怖を掘り起こしていく。
それは、彼女の心の奥底深いところに巣くった、古いトラウマだったかもしれない。
「最後のドアを閉めろ」(1947)は、村上春樹のデビュー作『風の歌を聴け』(1979)の作品タイトルと深い関わりのある重要な作品だ。
個人的な話になるが、僕が最初に書いた小説の『風の歌を聴け』というタイトルは『最後の扉を閉めろ』の結末の文章にインスパイアされたものだ。think of nothing things,think of wind.(もうなにひとつなにも考えるまい。風を思え)。(村上春樹『草の竪琴』訳者あとがき)
本作「最後の扉を閉めろ」は、破滅しつつある自己中心的な青年(ウォルター)の孤独な内面を象徴的に描いた作品である。
まるで誰かがすぐ隣に立って、彼の耳に唇をつけているかのようだった。「冗談はごめんだ。いったい誰なんだ?」「ああ、私のことは知っているはず、ウォルター。ずっと前から知っている」(トルーマン・カポーティ「最後の扉を閉めろ」村上春樹・訳)
謎の電話は、もちろん、主人公(ウォルター)の内面の声だ。
「ミリアム」や「夜の樹」以上に、作品としての深まりがあり、物語の展開としても楽しめるストーリーとなっている。
「ミリアム」「夜の樹」「最後の扉を閉めろ」の三編を読むと、村上春樹の小説が(作品テーマという面において)トルーマン・カポーティの影響を大きく受けていることが、よく理解できる。
自分の中に隠れている「もう一人の自分」を、どのような形で象徴的に描くのか。
そういう意味で、カポーティのミステリアスな作品と、村上春樹の小説には類似性が多い。
もっとも、作品テーマが似ている故なのか、翻訳作品としては、『遠い声』や『草の竪琴』のように、少年を主人公としたイノセント・ストーリーの方がずっといい。
「冗談はやめてくれ。誰なんだ」「わたしが誰か、わかっているだろ、ウォルター。長い付き合いじゃないか」(トルーマン・カポーティ「最後の扉を閉めて」川本三郎・訳)
「わたしが誰か、わかっているだろ、ウォルター。長い付き合いじゃないか」のような芝居がかったような印象的なフレーズは、村上春樹の訳では見られない(「ああ、私のことは知っているはず、ウォルター。ずっと前から知っている」)。
村上春樹・訳は、正確性を重視するので、映画のセリフ的な(気持ちいい)翻訳は、生まれようがないのだろう。
既訳との読み比べは、翻訳小説の楽しみの一つだし、いろいろな訳を読み比べることで、作品に対する理解は間違いなく深まる。
カポーティの名作に、新しい選択肢がまたひとつ加わったことを、心から喜びたい。
もしかすると、村上春樹は、小説家として以上に翻訳家として名前を残すのではないだろうか。
書名:草の竪琴
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:村上春樹
発行:2025/06/25
出版社:新潮社