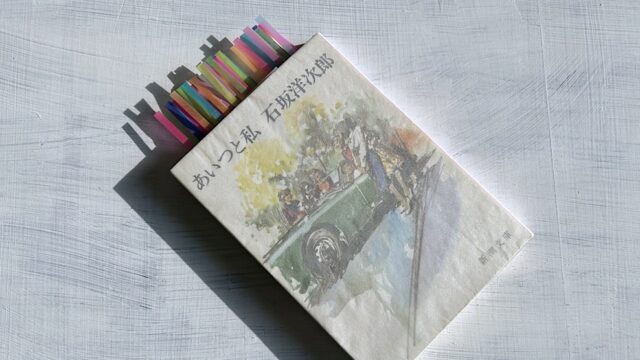エーリヒ・ケストナー「雪の中の三人男」読了。
本作「雪の中の三人男」は、1934年(昭和9年)に発表された長篇エンタメ小説である。
この年、著者は35歳だった。
冬のリゾートホテルのドタバタ物語
児童文学者として著名なケストナーには、大人向けのユーモア小説と呼ばれる作品が3つある。
それが『雪の中の男』『消え失せた密画』『一杯の珈琲から』の3編だ。
1933年(昭和8年)に誕生したヒトラー政権により、ケストナーの執筆活動は著しく制限されていた。
ドイツ国内での出版が許されなかったケストナーの発表した作品が、スイスのチューリッヒで出版された『雪の中の三人男』をはじめとする一連のユーモア小説だった。
本作『雪の中の三人男』は、冬のアルプス地方を舞台とするリゾート小説である。
ある財閥のお金持ち<トーブラー>が、偽名で応募した懸賞旅行に当選したので、<シュルツェ>という偽名のまま貧乏人を装って、10日間の招待旅行へと出かける。
「こんどは百万長者のトーブラーじゃなくって、素寒貧のシュルツェとしておれは旅行するんだ。ひとつ思いきって目さきを変えてね」彼は昂奮した。「人間てものが実際どんなもんだか、もうちっとでおれは忘れっちゃうとこだったからねえ。おれは自分のはいっているガラス室をぶち毀してみたいんだよ」(エーリヒ・ケストナー「雪の中の三人男」小松太郎・訳)
旅行には、念のため、大金持ちの<ケッセルフート>に仕立てた下男の<ヨーハン>を、こっそりと随行させるが、もちろん、ホテルにはそんなことを知らせていない。
ところが、父親の無茶を案じた娘の<ヒルデガルト>が、こっそりとホテルへ電話をかけて、大金持ちが貧乏人の振りをして旅行に行くから、なにとぞよろしくと伝えたところ、ホテルでは、同じく懸賞旅行でやって来た生粋の貧乏青年<ハーゲドルン>を例の金持ちと間違えてしまって、ここから楽しいコメディ・ドラマが始まる。
タイトルの「三人男」とあるのは、貧乏人に扮した金持ちトーブラーと、金持ちに扮した下男のヨーハン、そして本物の貧乏人ハーゲドルンの三人である。
シュルツェを本物の貧乏人だと思っているホテル側は、ホテルの雰囲気にそぐわないシュルツェを追い出そうと、様々な嫌がらせを仕掛けるが、人生勉強のつもりのシュルツェ(トーブラー)は、ホテル側の嫌がらせを楽しんでしまう。
一方、金持ちに間違えられた失業者のハーゲドルンは、仮初の貧乏人シュルツェと親友となり、偽の富豪ケッセルフートからも、トーブラーの会社への就職を世話してもらったりと、信じられないことが次々と起こる。
ハーゲドルンが言った。「ああ、うれしいなあ! 許された限度以上に、うんとぼくは幸福ですよ!」彼は不思議そうに頭を振った。「おとといは、まだベルリンにいたんだ。この何年かずっと失業してたんだ。そして二週間たったらまたベルリンへ帰るんだ、そう思うと……」「幸福であるってことは不名誉じゃないよ」と、シュルツェは言った。(エーリヒ・ケストナー「雪の中の三人男」小松太郎・訳)
極めつけは、父親の身を案じてアルプスまでやってきた娘のヒルデガルトが、やはり身元を隠したままでハーゲドルンと恋仲となり、婚約までしてしまうところだろう。
リゾートのアルプスを舞台に繰り広げられるドタバタ劇は、最後はミュンヘンに舞台を移して、最高のハッピーエンドを迎える。
児童文学じゃなくても、ケストナー文学は温かい
本作『雪の中の三人男』を読んでいて感じるのは、作者の本質的な温かさである。
児童文学ではなくても、ケストナー文学はやはり温かい。
失業青年のハーゲドルンは、いかにも母親思いだし、ハーゲドルンの母親の息子に対する愛情もいい。
このあたりは、『飛ぶ教室』や『エーミールと探偵たち』にも通じるケストナー流の家族愛といったところだろう。
金持ちと貧乏人がプロットになっているだけあって、財産に対するケストナーの哲学も、随所に織り込まれている。
「ぼくのおふくろはこう言ってるよ。財産なんてものは、とにかく、不遇な人間にたいする、神さまの贈り物にすぎない場合が多いって」「それは実に正しいねえ」と、シュルツェは断言した。「そして実に簡単だ」(エーリヒ・ケストナー「雪の中の三人男」小松太郎・訳)
そして、リゾートホテルで三人の男たちが親友になってしまう展開もいい。
ホテルには、各国から大金持ちが集まっていて、金持ちに間違えられたハーゲドルンには、富豪の女たちが次々と言い寄ってくるのだが、正直者のハーゲドルンは女性たちの誘惑にも負けず、貧民と化したトーブラーとの友情を温めている。
ハーゲドルンがトーブラーの会社に就職し、さらにはトーブラーの一人娘と結婚してしまうという展開は、正しい人間は、最後には必ず成功するというケストナーの人生哲学によるものなのではないだろうか。
「八百マークと、それにお嫁さんまでねえ!」ハーゲドルン夫人はうなずいた。「いっぺんに、ちょっと多すぎますねえ? まあ、でも子供は結局、あとで、親になるために生まれたんですからねえ」「そして、われわれがおばあさんになるためにねえ」(エーリヒ・ケストナー「雪の中の三人男」小松太郎・訳)
長篇小説の最後の一行にまで大どんでん返しが待っている仕掛けは、さすがに物語の巧者という感じがするが、なんといっても、三人の大人たちが、冬のリゾート地で子どもみたいに遊び回る様子は、理屈を抜きにして楽しい。
ストーリー展開のおもしろさから考えると、「雪の中の三人男」という分かりにくい作品タイトルはちょっと残念。
書名:雪の中の三人男
著者:エーリヒ・ケストナー
訳者:小松太郎
発行:1971/11/26
出版社:創元推理文庫