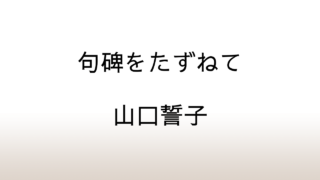吉井勇「東京・京都・大阪」読了。
本書「東京・京都・大阪」は、1954年(昭和29年)に刊行された随筆集である。
この年、著者は68歳だった。
岡野知十と久保田万太郎
タイトルが「東京・京都・大阪」で、最初の話が「柳橋界隈」から始まるから、てっきり、この本は、明治時代の風俗をテーマにしているのかと思っていたけれど、実際は、懐かしい情景を導入して、懐かしい人々を思い出す回想録となっている。
著者は『スバル』の歌人だったから、『スバル』仲間や、耽美派の活動拠点だった「パンの会」に関わった人たちの名前が多いのは当然として、意外と、役者や落語家などの名前も出てくる。
個人的には、俳人の話がおもしろかった。
例えば「半面派」は、報知新聞の経済記者から俳人となり、『半面』を主宰していた岡野知十のことが綴られている。
俳人としての交遊はかなり広く、角田竹冷、大野酒竹、尾崎紅葉、巌谷小波、鵜澤四丁、森無黄などという人達と秋声会を起し「秋の声」「卯杖」などという雑誌を出していたが、その後自分で「半面」という雑誌を発刊して、当時としては新味のある、独自の流派を作っていた。(吉井勇「東京・京都・大阪」)
代表句として「ゆく春に印籠一つ残りけり」「飲み習う薄手の猪口や秋袷」などの作品があった。
「私達の俳句の師匠は」とあるから、吉井勇も俳句を作っていたらしい。
「鵙の贄」は、大正六、七年頃に活動していた句楽会の話。
この句楽会は、小山内薫、久保田万太郎、長田幹彦、岡村柿紅、田村西男、川尻清潭、落合浪雄、中村秋湖などという主として芝居に関係のある文士や俳優が集まって、俳句を楽しむ会だったという。
「ゆく雁や屑屋くづ八菊四郎(傘雨)」「襟巻やまた旅に出る講釈師(勇)」などの句が紹介されていて、特に「ゆく雁や屑屋くづ八菊四郎」がいいと思ったら、傘雨は久保田万太郎の当時の俳号だった。
増田龍雨と磯田多佳女
興味深いのは、市井の俳人・増田龍雨を回想した「増田龍雨」である。
吉井勇は、この龍雨を絶賛していて、龍雨の作品を、もっと読みたいという気持ちにさせてくれる。
龍雨君はその後住み馴れた深川を去り、浅草田町の孔雀長屋のような家に住んでいたが、そこで久保田万太郎君と知るようになり、それから年来志していた俳諧の大道を歩むようになった。久保田君はその頃俳号を傘雨と云っていたが、当時の龍雨君の觸目即吟として、次のような句を作っている。「夜寒さの膳拵えや盆二つ」「茶焙じを掛けたる壁や冬隣」「長き夜の二つの時計鳴りにけり」(吉井勇「東京・京都・大阪」)
龍雨は、傘雨の作品を読んで、俳句を作る態度はこうなくてはならぬと考え、「わたしの俳句の先生は実に傘雨氏である」と言っていたそうである。
ちなみに、「龍雨君唯一の遺文集と云ってもいい」という『龍雨俳話』には、吉井勇の「序歌」が収録されているらしい。
『龍雨俳話』はまだ未読なので、いずれ読んでみたい(安藤鶴夫の作品も登場していた)。
俳人の話にもう一つ「磯田多佳女」がある。
磯田多佳女は京都の女性で、谷崎潤一郎に『磯田多佳女のこと』という著作があるほか、『新小説』明治43年7月号でも、「代表的婦人」の一人として、その略歴と談話筆記が載せられているというから、才媛としての令名は、かなり広く聞こえていたのだろう。
さて又多佳女の身の上に戻るが、その姉は祇園の万亭の前の女将のさだ女であって、そういった関係から、多佳女自身もまた煙華の巷にその身を置くようになったが、何しろ趣味が広いので、文人墨客に知己が多く、夏目漱石も大正四年頃入洛して木屋町の大嘉に泊った時、「木屋町に宿をとりて川向のお多佳さんに」という前書をした、「春の川を隔てて男をんな哉」という句を贈っている。(吉井勇「東京・京都・大阪」)
多佳女と気の合った漱石は、京都滞在中は度々彼女と会って、いろいろと語り合ったらしい。
本書には、こうやって拾い上げていくと、きりのないくらい興味深い話がたくさん紹介されている。
著者曰く「市井の懺悔録」である。
書名:東京・京都・大阪 よき日古き日
著者:吉井勇
発行:1956/12/5
出版社:中央公論社