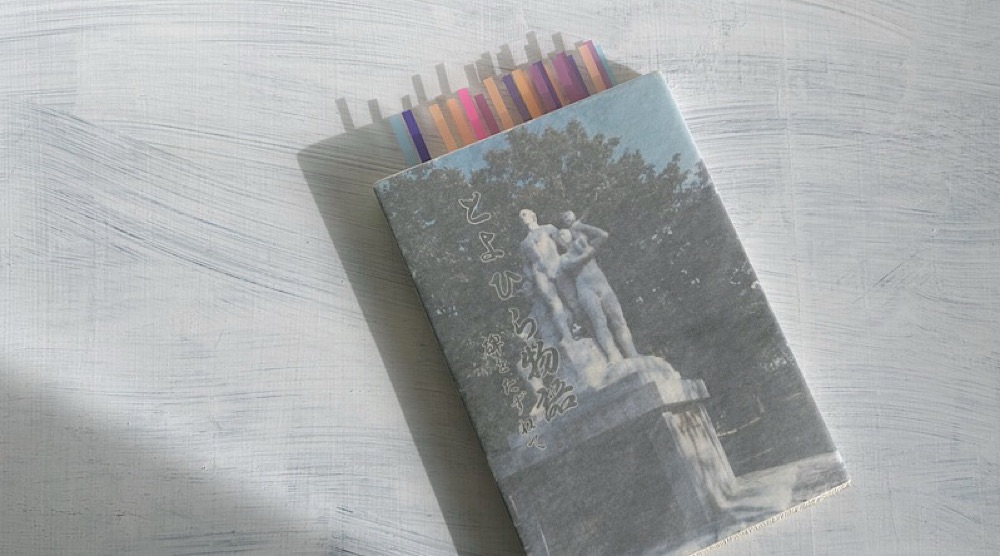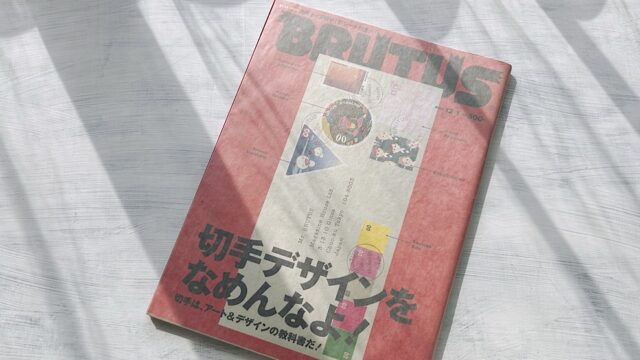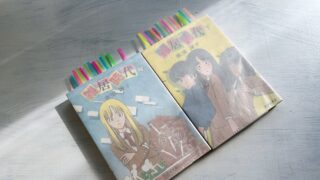豊平区役所『とよひら物語──碑をたずねて』読了。
本作『とよひら物語──碑をたずねて』は、1980年(昭和55年)3月に発行された歴史ガイドである。
厳島神社に残る「福住開基百年記念碑」
1980年(昭和55年)の豊平区は、現在の豊平区とは大きく違うところがあった。
現在の「清田区」が、まだ豊平区に含められていたのである。
豊平区から清田区が分区されるのは、1997年(平成9年)のことで、1980年(昭和55年)当時の豊平区は、まだ広大な地域を所管していた。
本書『とよひら物語──碑をたずねて』は、だから、現在の清田区までを含んだ豊平区の歴史ガイドということになる。
歴史探訪の最も簡単な方法が、記念碑を訪ね歩く方法である。
本書では、豊平区内に設置されている記念碑をきっかけとして、豊平区の歴史を紹介している。
豊平区の歴史は、豊平川の渡し守として知られる「志村鉄一」から始まる。
この渡船場の渡し守を命じられ、和人として最初の定住者となったのが、信州生まれの浪人・志村鉄一だった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
1857年(安政4年)、剣客・志村鉄一は、豊平川東岸に渡し守として定住し、後に「札幌の開祖」と呼ばれた。
しかし、1869年(明治2年)11月に札幌本府の経営が始まると、志村鉄一は職を解雇され、住居まで追い払われてしまうことになる。
晩年の志村鉄一は、定山坊のところに寄寓した後、豊平川の東岸に草小屋を建てて暮らしていたらしい。
鉄一が世を去ってから、すでに百年の歳月が流れ、六十数回の架け替えを経て、永久橋となった豊平橋とその周辺は、遠く過ぎ去った明治を偲ぶ何ものも残さないまでに、その姿を変えてしまった。(略)豊平川の渡し守・志村鉄一が存在したことを示すものは、わずかに中ノ目家所蔵の「廃家復籍願」と、豊平橋に近い橋台小公園に移設された記念碑のみなのである。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
歴史ガイドというよりは、物語風に綴られた文章が印象に残る。
札幌開祖の晩年は、あまりに不遇なものだったらしい。
それだけに、鉄一があまりに痛々しいということから、地元の「志村鉄一顕彰保存会」では、鉄一の業績を掘り起こし、晩年の不遇をいたんで、毎年八月十六日、多数の参列者を迎えてしめやかに供養を営んでいる。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
志村鉄一を偲ぶ記念碑は、豊平橋上流の橋台小公園にある。
和人最初の定住者であり、豊平川の渡し守として交通の要衝を守った志村鉄一の記念碑。昭和四十二年、橋台小公園に移設した。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
月寒に残るのは「月寒開基百年之碑」だ。
この碑は、月寒開基百年にあたる昭和四十五年九月、明治初期の月寒を開拓した先駆者の労苦を偲び、その偉業をたたえて地元の有志によって建立されたもの。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
月寒に入植した人たちは、南部藩士が主体の募集移民だった。
ナラやカバ、イタヤ、ニレなどの大木が立ち並ぶ土地の開拓は、悲惨を極めたという。
この不慣れな仕事で怪我をしても、医者がいないので自分で治療しなければならず、指が落ちそうな大怪我をした人が、木綿針に糸を通して自分で縫い、しかも慌てて縫ったので指がねじれてついたなどという話も残っている。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
開拓が軌道に乗り始め、農業人口が次第に増加していったのは、明治18年~19年頃のことだった。
四十四戸が月寒の草分けとして入植してから、既に百十年の歳月が流れたが、その名をとどめているのは、吉田善治、似鳥仁太郎、長岡重治、岡田駒吉、岩瀬末治などの子孫にあたる人たちだけとなった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
地下鉄東豊線の駅がある福住にも開基百年の記念碑がある。
市道福住中央線の、やや国道36号線寄りの一角に位置する厳島神社内境内の一隅に、福住開拓記念館と並ぶ碑のあることを知る人は意外に少ないようである。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
福住の開拓は1871年(明治4年)、月寒に入植した44戸のうち6世帯が割り当てを受けて入植したのが始まりである。
道路沿いに六軒の家が建っていたところから、後には「六軒村」と呼ばれていたが、この地名は昭和二十四、五年ころまで、札幌市内でも通用するくらい親しまれていた。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
福住地区が農村としての形態を整えたのは、41戸が入植した1889年(明治22年)から1897年(明治30年)の間と言われ、大正年間には、さらに55戸が入植している。
このような農村一色の福住地区も、戦後は次第に農村脱皮の様相を呈しはじめ、昭和二十二年には待望の電灯がつき、同二十四年には、上水道利用組合を設立して水道を敷設した。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
札幌近郊の農村地区では、電灯の普及も、戦後まで待たなければならなかったらしい。
現在のような住宅地となったのは、昭和30年代以降である。
昭和三十二年には塚本果樹園の廃園を皮切りに宅地化がはじまり、同年(昭和三十二年)羊ヶ丘住宅地が、三十六年にはアカシヤ団地が造成された。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
福住開基百年の記念碑は、福住厳島神社の入り口に設置されている。
開基百年にあたる四十六年には、三十六戸の農家によって設立された、財団法人「三六会」が、旧公会堂跡に新会館を建て、さらに神社境内に開拓記念館を設置し、記念碑の建立をみたが、その当時で、福住に五十年以上在住する戸数は、わずか二十三戸にすぎなかった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
開基百年は、地区住民にとって大きな意味を持つもので、厚別(あしりべつ)神社境内にも、清田地区の開基百年を記念する碑が設置されている。
平岡の国道36号線から左側の坂道を、百メートルほど登った厚別神社境内の一隅に、花崗岩に黒の大理石で、開拓の「拓」を表した記念碑がある。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
平岸や月寒と異なり、集団入植のない清田地区では、先の入植者を頼る形の個別入植が中心で、明治20年代に入っても、戸数はわずか12~13戸だったという。
清田・真栄・北野の稲作、平岡・里塚・有明の畑作が定着して、村としての機能が発揮できるようになったのは、1901年(明治34年)頃のことだった。
西岡八幡宮に残る「西岡開拓記念碑」
西岡八幡宮に設置されているのは、西岡地区の開拓記念碑である。
この碑は、明治二十二年、この地に開拓の鍬を入れてから、十七年の歳月を経て、ようやく自立営農の見通しがついた部落民一同が、部落の安全と豊作を祈願して、明治三十九年一月に建立したもの。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
当時、西岡地区一帯は「月寒村焼山」と呼ばれる原始林地帯で、1888年(明治21年)の入植者52人は、けものみちを頼りに道を切り拓いていった。
明治二十年代に入植した人たちは、月寒の境界から今の西岡小学校までの、以前は西岡一区と呼ばれた一帯に、土地を求めて切り開いたが、同三十年には、その奥地の国有林が払い下げられ、ここに三十戸が入植して、西岡の開拓は本格化していった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
稲作に成功して、米が食べられるようになったのは、1921年(大正10年)頃だった。
西岡八幡宮には記念碑が整備されていて、開拓記念碑の隣には「西岡開基七十年記念碑」が建っている。
この碑は、明治二十二年から、営々七十年にわたる開拓の苦闘と、その上に築かれた西岡の繁栄を記念して、当時の農事実行組合に加入していた人たちによって、昭和三十三年十一月十日に建てられたもの。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
風水害や凶作と戦いながら少しずつ農地を広げる開拓者にとって、一年一年を生き延びるということが、既に困難な目的とも言えた。
やがて時代は昭和となり、人々の懸命な努力によって、営農安定の見通しがついてきたので、部落の人たちは、今までの苦難の道をふりかえり、前途への希望を新たにして、昭和三年、開拓四十年の祝いを盛大に行った。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
冷害や風水害による凶作と昭和大恐慌は、西岡地区の人々も大きな打撃を与え、この時期に離農していく人々も少なくなかったらしい。
やがて、戦後となる頃、西岡地区も大きな転換期を迎える。
文化的に恵まれなかった西岡地区も、昭和八年からの根気強い運動が実って、昭和二十年、終戦を契機に電灯がつきはじめ、昭和三十五年までに、西岡地区の全戸に電灯がついた。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
西岡地区の宅地化は、昭和40年代から本格化していった。
昭和四十一年には札幌大学が生まれ、四十四年には西岡小学校が鉄筋三階建てで現在地に移転改築され、四十七年の冬季オリンピックを契機に道路整備が進み、四十八年にCIタウンが完成し、それ以後の人口は増加の一途をたどり、大きく住宅街が広がってきている。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
終戦時には電気も通じていなかった農村が、現在は、大規模な住宅街へと変貌している。
西岡二区の油沢地区も、かつてデントコーン畑だったCIタウンも、既に往時を偲ぶことは不可能だ。
有明地区の開拓記念碑は、公有地神社に設置されている。
国道36号線の交差点から、道道真駒内御料地札幌線を約六キロメートルほど行くと公有地神社があり、その境内の樹林のなかに、軟石で作られた開拓記念碑が建っている。この碑は、有明開拓の基盤が形造られてきた明治四十一年の九月に、当時の青年会と部落民一同の協力により建てられたもの。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
有明地区は、もともと「篠路屯田兵村」の公有地であったことから「有」の字を生かし、明朗闊達の「明」を添えて、1944年(昭和19年)の字名改正時に「有明」と改称された。
つまり、有明地区のルーツは篠路村だったということになる。
この地区も集団入植ではなかったため、個別入植した人々は、孤高の開拓を強いられたらしい。
奥地の三滝の沢の開拓は、明治四十一年、持田謹也が山田尋源を監督として、大正五年までに三十戸の小作人を入植させたが、その後、離農者が続出して荒れ地になってしまい、以後だれも住みつく人がいなかった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
山間部ゆえに日照時間が短く、温度の低い沢水を使うことから冷害にも泣かされた有明地区では、木を切り払うたびに洪水被害も大きく、営農が困難だった。
大正期から昭和初期にかけての有明地区の暮らしは、冷水害や不況との戦いだったと言っていい。
終戦後、外地からの引揚者三十五戸が入植し、再起をかけて明治時代さながらの開墾に汗しているさなかに、アメリカ軍の演習地として接収され、やむなく全戸が転出していった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
有明部落に電灯が灯ったのは、終戦後の1949年(昭和24年)、年の暮れのことだった。
有明の人たちにとって、その明かりは、単なる電灯の明かりではなかった。それはまさに、明治以来からの苦闘の末にようやく、人々の心にともった「有明のともしび」であった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
戦後、農村としての有明は、少しずつ姿を変えていった。
有明はいま、ひたひたと押し寄せる都市化の波を間近にみながら、わずかにその田園的な情緒を保っているが、戸数は五十四戸を数えるのみとなった。そして、農業を継ぐ若者もいない現実のなかで、古老もまた、一人ふたりと世を去り、昔を語る人は数少なくなってしまった。(豊平区役所「とよひら物語──碑をたずねて」)
札幌の歴史を遡ると、必ず、開拓者たちの歴史へとたどり着く。
それは、札幌近郊の農村地帯で特に顕著で、平岸村・月寒村・豊平村の合併によって誕生した「豊平村」の農村部に残る記念碑が、開拓の歴史を如実に物語っている。
記念碑を建立したのは、開拓者たちの末裔であり、だからこそ、各集落に今も残る記念碑には、移住者たちの血と汗と涙が染みついていると言っていい。
歴史を祝う開拓記念碑は、生き延びることができたことを祝う記念碑でもあったのだ。
本書『とよひら物語──碑をたずねて』(1980)の発行から、既に40年以上が経過し、開拓地・札幌の変貌は著しい。
しかし、まるで都会のような顔をしているこの街の歴史が、移住者たちによって切り拓かれた慎ましい農村から始まっていることを忘れてはならないだろう。
札幌の歴史は、すでに一世紀を経ましたが、今日に至るまでの先人たちの、厳しい自然に立ち向かった不屈の開拓者精神と新参労苦を考えるとき、私は、感謝の気持ちと同時に、心からの敬意を表するものであります。(札幌市長・板垣武四「とよひら物語──碑をたずねて」発刊に寄せて)
札幌開基から150年を経て、「開拓者精神」という言葉も、すっかりと力を失ってしまったらしい。
現在の札幌は、外国人観光客の誘致(インバウンド)に振り回される、不安定な観光都市でしかない。
時代は変わっても、各地に残る開拓記念碑から札幌の歴史は始まっているということを忘れないようにしたいものだ。
書名:とよひら物語──碑をたずねて
編集:札幌市豊平区役所総務部総務課
発行:1980/03