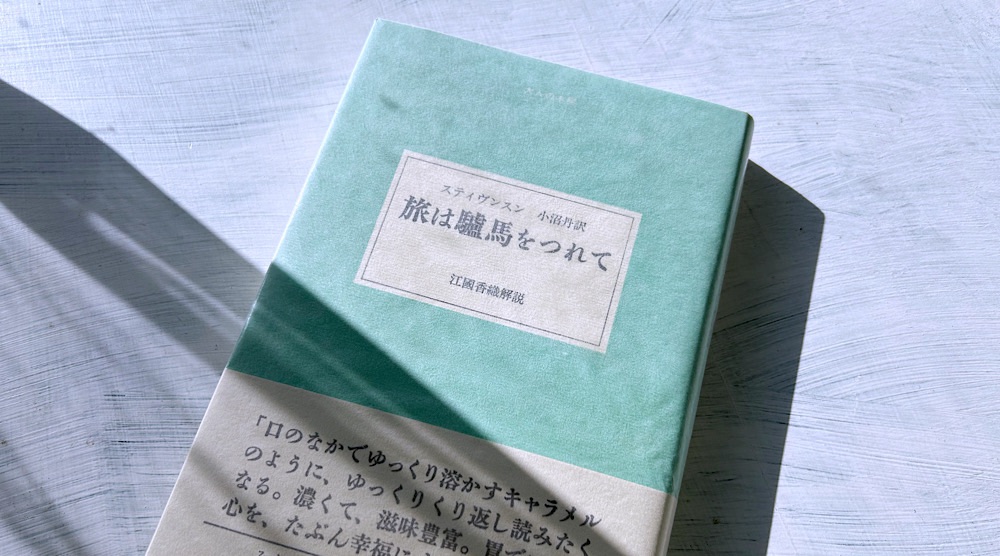ロバート・ルイス・スティーヴンソン「旅は驢馬をつれて」読了。
本作「旅は驢馬をつれて」は、1879年(明治12年)にイギリスで刊行された紀行文である。
この年、著者は29歳だった。
日本では、小沼丹の翻訳で、1950年(昭和25年)に家城書房から刊行された。
なお、岩波文庫に吉田健一の訳がある。
ちなみに、本作「旅は驢馬をつれて」は、小沼丹の盟友・庄野潤三も大好きだったと綴っている。
フランス中部を十二日間かけて徒歩旅行した際の記録
本作「旅は驢馬をつれて」は、フランスのセヴェンヌ地方を十二日間かけて踏破した徒歩旅行の記録である。
この旅行は、現在でいうバック・パッキングの旅だったが、著者のスティーヴンソンは、荷物を運搬させるにあたり一匹の驢馬を購入した。
だから、旅の記録は、著者が小さな牝驢馬を購入するくだりから始まっている。
作中、著者は旅の動機について、こんなことを綴っている。
私はどこか行くところがあって旅するのではない。ただ、行くために旅する。旅するために旅するのである。(スティヴンスン「旅は驢馬をつれて」小沼丹・訳)
もっとも、実用的ではないこの徒歩旅行は、当時のフランスの人々からは、あまり理解されなかったらしい。
スティーヴンソンは、各地で思いがけない経験をすることになる。
道を訊ねて冷たくあしらわれることも少なくなかった。
ところでこの二人の娘っ子であるが、彼らは小生意気な、狡猾な跳ねっかえりで悪戯しか考えぬ一対であった。一人は私に対って舌を突き出し、もう一人は、牛のお尻について行けといった。それから二人ともクスクス笑うと互いに肘で突き合った。(スティヴンスン「旅は驢馬をつれて」小沼丹・訳)
この旅行記の見どころのひとつが、こうした地元の人々と著者との交流のありようである。
キリスト教に関する記述が多いのは、宗教が地域の文化と密接に関連していたためだろう。
地域の人々を理解するためには、宗教の話題を持ち出すことが手っ取り早かったのである。
徒歩旅行(バック・パッキング)の楽しさ
この旅行記のもう一つの見どころは、徒歩旅行、いわゆるバック・パッキングの楽しさである。
十日間の旅のうち、著者は野営の夜をいくつか過ごしているが、こうしたビバーク(野宿)は、著者にとって貴重な経験となった。
何人といえども、フランス人がいみじくも申しているように「美しき星の下に」眠ったことのない者には、星は判らない。星の名前や距離や等級なぞすっかり御存知だとしたところで、人間に関係のある唯ひとつのもの、つまり星が人の心に及ぼす静かな喜ばしい影響についてはとんと無知かもしれないのである。(スティヴンスン「旅は驢馬をつれて」小沼丹・訳)
このとき、著者の荷物はスリーピング・バッグ(寝袋)のみで、荷物を減らすためにテントは持参しなかった。
映画『スタンド・バイ・ミー』で少年たちが星の下で眠ったように、スティーヴンソンもまた、大地の上に直接置いたスリーピング・バッグの中に入って眠ったのである。
ちなみに、この野営は、野営のもっとも基本的なものだが、夜露の多い日本では難しいのが残念。
そして、本紀行文の最後の見どころとして出てくるのが、荷物を運ぶために購入した牝驢馬<モデスチン>との心の交流だろう。
この小さな牝驢馬は歩くにも遅く、荷物運搬の役割をまともに果たすことができなかったため、著者は余計なハンディを背負いこんでしまったとしか考えていない。
一方のモデスチンも、スティーヴンソンの指示に従おうとはせず、ムチでひどく叩かれながら旅を続ける。
この旅人と驢馬との関係が、旅の終わりに向かって、どのように変化していくのかということは、読者の大きな関心事となるだろう。
なぜなら、彼女は私に何やら一種の愛情を抱いていたからである。ところでその愛情を、私はほどなく裏切らねばならなかったのだが。(スティヴンスン「旅は驢馬をつれて」小沼丹・訳)
最後に、この紀行文の序文は素晴らしかった。
「親愛なるシドニー・コルヴィン」と題された序文に、次のような一節がある。
ところで僕たちはすべてジョン・バンヤンいうところの、この世の荒野の旅人です。すべてのものが、驢馬をつれた旅人であります。この旅で僕たちが見出す最上のものは、誠実な友人です。その友人を沢山見出したものが、幸運な旅行者なのであります。(スティヴンスン「旅は驢馬をつれて」小沼丹・訳)
旅は、人生を豊かにしてくれる。
まして、徒歩旅行の旅ならなおさらだ。
久しぶりに、バック・パッキングの旅行へ出かけたいと思った。
一人用の小さなテントとスリーピング・バッグを背負って。
作品名:旅は驢馬をつれて
著者:ロバート・ルイス・スティーヴンソン
訳者:小沼丹
書名:旅は驢馬をつれて
発行:2004/12/08
出版社:みすず書房(大人の本棚)