杉山春/アルク出版編集部「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち―90年代への予感」読了。
本作「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」は、1989年(平成元年)11月にアルクから刊行されたインタビュー集である。
アルクの広報誌『CAT』掲載のオリジナルインタビューを再編集したもの。
帯の推薦文を高橋源一郎が寄せている。
日本の雑誌のためのオリジナルインタビュー
本作「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」には、全部で10人の作家が登場する。
日本の雑誌(しかも会報誌)のためのオリジナルインタビュー。
インタビューに対する作家の姿勢に個性が現れていて、アメリカ文学に精通していなくても楽しめる。
むしろ、この10人の中から読んだことのない作家を見つけて、新しい読書の入口を開いてみる、という手もある。
作品の根幹に関わるインタビューも多く、著者本人の解説を聞いてから作品を読むという楽しみ方も可能。
作家の人間性として一番好感を持てたのは、短篇集『ファミリーダンシング』で注目を集めた若手作家デイヴィッド・レーヴィット。
彼は、ゲイを公言する作家で、「ニュー・ロスト・ジェネレーション」(あらかじめ失われた世代)というエッセイでも有名。
彼のインタビューに対する姿勢は、極めて誠実で、いかにも繊細な若者という印象を与えている。
「文学において、主題はもっとも取るに足らないものだという確信を強めています。重要なのは、言葉であり、文章です。僕は、自分の書く文章をもっともっと個性的なものにしようと、つまり、もっと自分のパーソナリティーを与えようとしています」(デイヴィッド・レーヴィット「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・山川美千枝)
ニューヨークが嫌いだと言う、彼の腺病質な言葉は、あまり作家っぽくない。
シャツをインしたセーターの上にウールジャケットを羽織っている写真も、昔の大学教授みたいでいい。
インタビューというか、インタビュアーとの議論みたいになっているのが、『ガープの世界』のジョン・アーヴィング。
インタビュアーのツッコミに、ひとつひとつ丁寧に反論する姿は、作家というよりも批評家のようでさえある。
「僕はこの世界を書いているのであって、SFや刺激的なノンフィクションを書いているわけではない。僕は社会小説家なんだ。政治小説といわずに社会小説というのは、政治そのものをテーマにしているのでなければ、政治小説ではないと考える人がいるからだ」(ジョン・アーヴィング「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・相原真理子)
本書の中で、最も読み応えがあって面白いのが、ジョン・アーヴィングだった。
言葉が多いから、必然的に注釈も多く、アーヴィング文学を理解する上で、非常に参考になるインタビューだと思う。
『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』のジェイ・マキナニーは、言葉は雄弁だけれど、内容は薄っぺらい印象を受けた。
「日本人はアメリカ文化を──特にポップ・カルチャーを──何か大げさに考えている。つまり、理想化している。一方、京都の外国人たちはそれと同じことを日本に対してやっている」(ジェイ・マキナニー「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・斎藤英治)
マキナニーには、日本での滞在経験を織り込んだ『ランサム』という作品があるので、日本への印象などについて語っている部分が多い。
文学作品を理解する上で、著者の話は参考になる
インタビューに対して、あまりまともに対応していないと思われたのが、『ニューヨークの奴隷たち』のタマ・ジャノウィッツ。
もともと言葉が少ない人なのか、インタビュアーが困惑している感じすら受ける。
「私が作り出した登場人物はすべて私の分身です。小説を書くのは演技することに似ていて、それぞれの登場人物を書いているときには、私はそれになりきっている。五十五歳の男であれ、二十歳の若者であれ。私の世代の女であれ。すべて、私の分身だわ」(タマ・ジャノウィッツ「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・山川美千枝)
本書を読んで愉快じゃなかったのは、タマ・ジャノウィッツくらい。
多くのインタビューは、真面目で心地良い。
例えば、『エンペラー・オブ・ジ・エア』のイーサン・ケイニンは、まさしく好青年という印象の作家。
「僕は現在を描くことには興味がありません。僕にとって、フィクションというのは、記憶とかノスタルジアに結びついていて、現在形の世界には存在しない。現在形を使って書くのは好きじゃないんです」(イーサン・ケイニン「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・山川美千枝)
自分たちのライフスタイルを描く若手作家が多い中で、彼の主張には好感が持てる。
『レス・ザン・ゼロ』のブレット・イーストン・エリスは、インタビューに対する警戒心が見て取れる。
作品に対する余計な先入観を与えたくない、というのが、彼のやり方らしい(ジョン・アーヴィングとは正反対だ)。
「僕は作家になろうと思っていたから、さまざまな場面でつかず離れずなりゆきを観察したんです。物書きは、人生に起こるいろんなシーンを、本の筋書きの場面展開を見るように観察しているものです」(ブレット・イーストン・エリス「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・片岡みい子)
彼は、作家としては多分、真面目すぎる人なんだろう。
『ウィンターズ・テイル』のマーク・ヘルプリンは、川端康成の『雪国』に影響を受けたという。
「でも、私は日本の文学なら、昔からかなり読んできた。そして、ずっと北国や北海道に憧れてきた。たぶん、それは私が山や雪が好きなせいもあるだろうけれど、でもそれ以上に幼い少年の頃に読んだ『雪国』のせいだろう。あの小説はずっと私の心を魅了してきた」(マーク・ヘルプリン「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・斎藤英治)
マーク・ヘルプリンのインタビューは、なんというか、小説家らしいインタビューという印象。
未読の作品で「読んでみたい」と思ったのは、ウィリアム・ケネディの『オー、オールバニー』。
「オールバニーの町の歴史を印象主義的に書いたもの」と、本人が言っている。
ただし、2023年現在で未訳らしいから、もう邦訳の可能性はないかもしれない(笑)
「私はまだ終わっていないことについては書きたくない。まず結果が見たいんです。それを見て自分なりに理解できれば、それを書こうという気持ちになります。たとえば、自分のことを書こうとすると、すぐに嫌気がさしてくるんですよ」(ウィリアム・ケネディ「INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち」訳・相原真理子)
ミニマリズムの短篇小説ばかり読んでいると、読み応えのある長編小説も読みたくなる。
文学というのは作品がすべてだとは思うけれど、作家の話を聴いてみるということも、やはり大切なことだと思う。
もちろん、作品の解釈については、作家本人の意図と違うところがあっていい。
批評家の見解に縛られる必要がないのと同じように、読者は文学作品を自分の自由な解釈で読めばいいのだ。
ただし、文学作品を理解する上で、著者の話が参考になることは確か。
自分の解釈と異なるところがあれば、それは、著者の意図がうまく伝わらなかった作品、というだけにすぎないから、恐れることはない。
小説を読む息抜きにインタビューのようなものを読んでみるのも、悪くないと思った。
書名:INTERVIEW 素顔のアメリカ作家たち―90年代への予感
編者:杉山春/アルク出版編集部
発行:1989/11/7
出版社:アルク
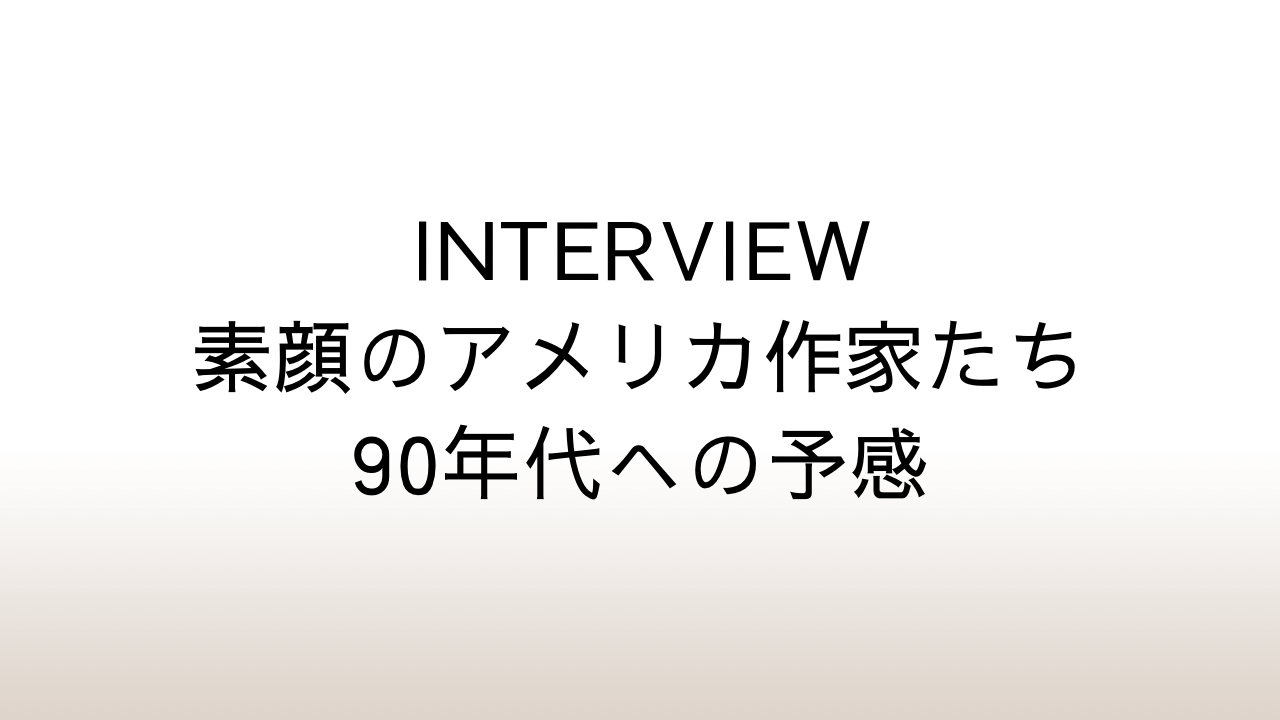


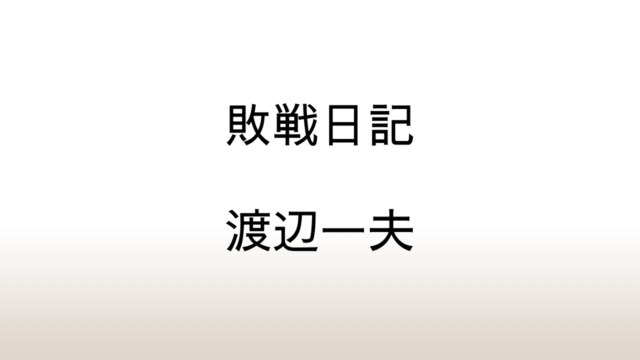
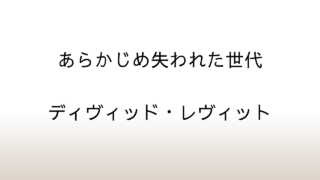

-150x150.jpg)









