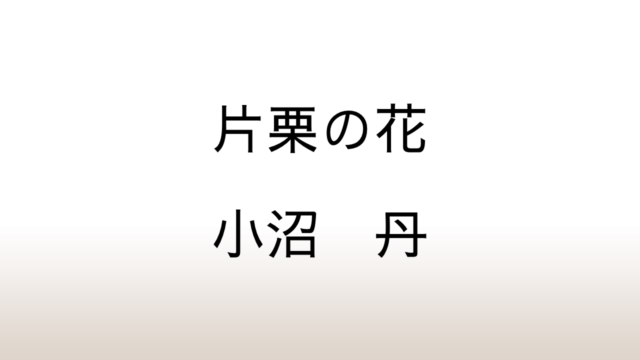エーリヒ・ケストナー「わたしが子どもだったころ」読了。
本作「わたしが子どもだったころ」は、1957年(昭和32年)に刊行された自伝的小説である。
このとき、著者は58歳だった。
著者のケストナーは、本作をきっかけとして、1960年(昭和35年)に国際アンデルセン賞を受賞した。
日本では、岩波書店「ケストナー少年文学全集」の一環として、高橋健二の訳で、1962年(昭和37年)に刊行されている。
ちなみに、翻訳者は、このとき60歳だった。
ケストナーの少年時代の思い出を綴る
本作「わたしが子どもだったころ」は、著者ケストナーの自伝的少年文学である。
ケストナーは1899年(明治32年)生まれだから、およそ1900年前後の話が中心なのかと思ったら、ケストナー少年が誕生するまで、物語は意外と長かった。
1899年生まれの作家としては、アーネスト・ヘミングウェイや川端康成がいる。
つまり、「わたしが子どもだったころ」は、ケストナーの誕生から始まるのではなく、ケストナーが生まれるずっと前、ケストナーの父や、ケストナーの祖父や、そういった人々の話から始まっているのである。
全246ページの中で、エーリヒ・ケストナーが登場するのは70ページ目のことである。
ケストナーの祖先の話は、それはそれで(非常に)面白いのだが、ケストナーの自伝の一部としては長すぎるような気がする。
しかし、読み進めていく中で、ある文章に出会ったとき、僕はケストナーの狙いが理解できたような気がした。
子どものころ体験したいろいろなことが、多くの年月ののち、初めて意味を持ってくる。後になってわたしたちの出くわす多くのことは、幼年時代の思い出をともなわなかったら、ほとんど不可解におわるだろう。わたしたちの歳月は、両手を組み合わせた時の指のように、からみ合っている。すべてのものがすべてのものと関連している。(エーリヒ・ケストナー「わたしが子どもだったころ」)
つまり、ケストナーにとって両親や祖父母の昔を語ることは、少年時代のケストナーを語る上で、どうしても必要なことだったのだ。
ケストナーの自伝の中では、過去と未来とが互いに絡み合っているから、時間軸が前へ行ったり後ろへ行ったりする。
およそ、人の思い出話というのは、それほどまとまったりしていないものらしい。
大切なことは、本書において記憶と思い出とは、はっきりと区別されて書かれているということである。
思い出は、引き出しや家具や頭の中にはいってはいないで、わたしたちのただ中に宿っている。たいていはまどろんでいるが、生きて呼吸していて、ときどき目を開く。思い出はいたるところに宿っており、生きており、呼吸しており、まどろんでいる。手の平に、足の裏に、鼻の中に、心の中に、ズボンのおしりに。(エーリヒ・ケストナー「わたしが子どもだったころ」)
本書は、ケストナーの少年時代の思い出を綴った作品なのだ。
互いに愛し合っていた少年と母親
少年ケストナーの思い出は、多くが母親イーダ・ケストナーの思い出でもあった。
物語の隅々にまで、母親に対するケストナーの愛情が散りばめられている。
彼女の賭け札はわたしだった。だからわたしは勝たねばならなかった。だからわたしは母を失望させてはならなかった。だからわたしは一ばん優秀な生徒、一ばんけなげなむすこにならねばならなかった。母がその大きな賭けに負けるということは、わたしには耐えがたいことだったのだろう。(エーリヒ・ケストナー「わたしが子どもだったころ」)
そして、ケストナーは「わたしは母をひじょうに愛していた」と綴っている。
ケストナーは、母と二人で徒歩旅行に出かけ、自転車旅行にも出かけた。
教師を目指していたケストナーが、教師の道をあきらめて大学で研究したいと申し出たとき、彼の母は微笑しながらうなずいた。
二人の母子は互いに信頼し合い、愛し合っていたのだ。
『わたしが子どもだったころ』を読みながら、これはまるでケストナーの作り出す物語みたいだと思った。
健全な少年が、愛する母親を失望させまいとして努力する物語。
ケストナーの作る物語は、あるいは、ケストナー自身の物語でもあったのかもしれない。
やがて、楽しかったケストナーの少年時代は、1914年(大正3年)の夏休みに終わりを告げた。
ケストナーの子ども時代は、世界大戦の始まりとともに終わったのだ。
書名:わたしが子どもだったころ(ケストナー少年文学全集7)
著者:エーリヒ・ケストナー
訳者:高橋健二
発行:1962/8/18
出版社:岩波書店