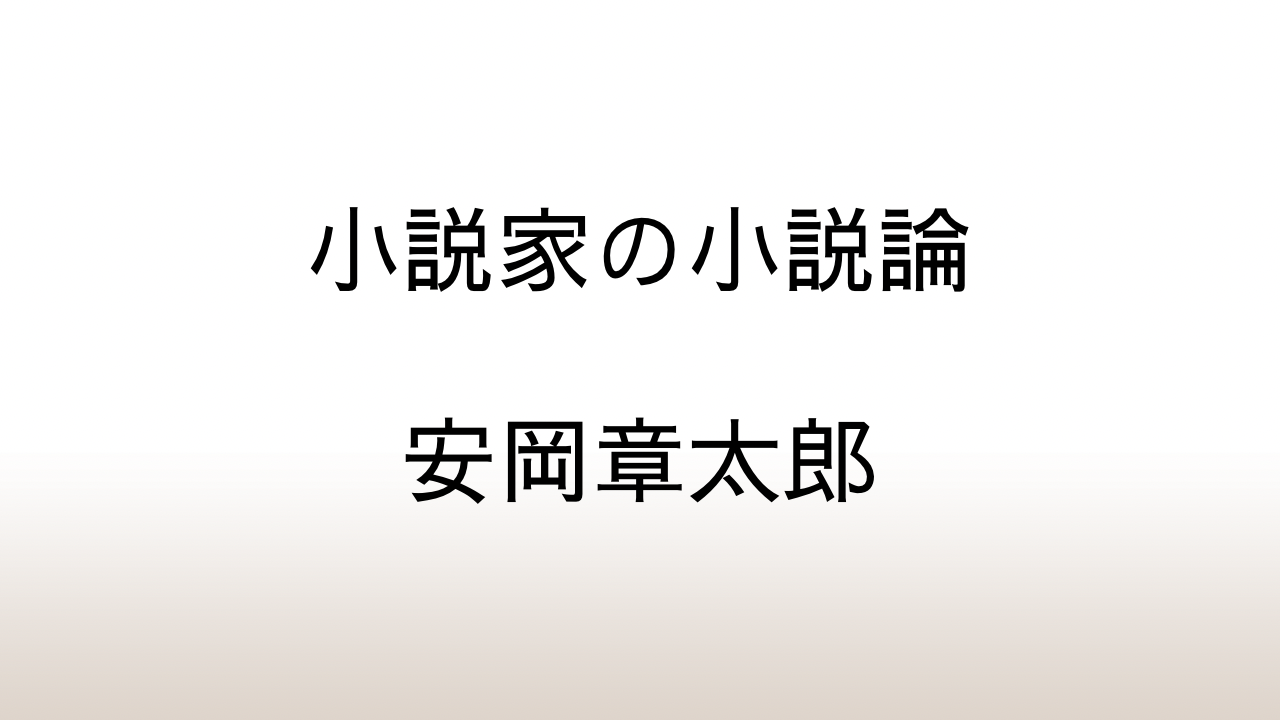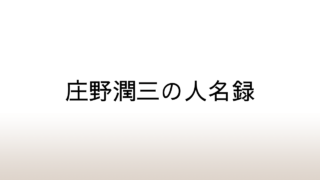安岡章太郎「小説家の小説論」読了。
庄野潤三の顔は熊の子のようにまるく、頭髪は黒くて剛く縮れており、笑うと、浅黒い頬の筋肉がまるく盛り上ってキレイに並んだ真白い歯がのぞく。自分ではその風貌をオーソン・ウェルズやウィリヤム・ホールデンになぞらえたがっているが、客観的に見ればカナカかポナペの島からたッたいま泳ぎついた人のようである。(安岡章太郎「小説家の小説論」)
『小説家の小説論』の中の「庄野潤三」の章は、そんな書き出して始まっている。
著者(安岡章太郎)は「小説を書く男というと、どこか体が悪かったり、暗い過去をもっていたり、何かの傷あとを持っていたり、要するにどこかしらに弱さを引きずっているように想像される。ところが、庄野潤三にはそういった感じはまるでない。心も体も健康そのもので、ふとい頸が真直ぐ前を向いており、もり上った背中や腕のあたりに、充満したエネルギイを感じさせる。・・・こういう男を見ると僕らは何となく悪口を言って、やっつけてやりたい誘惑を感じるものだ」と綴りながら、「あんな奴が、一体どうして小説なんか書く必要があるのだろう?」と疑問符を付けて見せる。
もちろん、庄野潤三の盟友である著者は庄野文学を理解しているはずで、「庄野潤三について一つだけハッキリと言えることがある。それは彼が孤独な魂の持主だということだ」という指摘は、庄野さんの作品を超えて、庄野潤三という小説家の本質に迫る指摘ではないだろうか。
庄野さんは「愛撫」や「喪服」を書いてから二年ほど沈黙した後、昭和28年になって「喪服」「恋文」「噴水」「会話」などを発表しているが、この当時、庄野さんは「小説に対する考え方が大ぶ変ってきたようだ」と語ったそうである。
この点について、著者は「それまでの奔放に、流れるままにまかせてあった(生きようとする力)を、もう一度別の眼で見直そうとしたのであろうか」と指摘している。
その頃の庄野さんは、周囲の者に執筆の苦痛を訴えるようなところもあったらしく、「恋文」が芥川賞候補となってジャーナリズムの注目を集め始めたことや、会社の転勤で東京へ移住してきたことなどが影響していたのかもしれないが、「このごろは小説をかくのが、まるで中学時代に苦手の数学の宿題をやらされたときみたいな気持だ」などとも言っていたという。
もっとも、作品の本数は以前に比べてずっと多くなっていて、「十月の葉」「黒い牧師」「結婚」などの作品は、「『愛撫』のころにくらべて、形式がととのい、意図が明確に感じられるだけに、一方ではそれだけ(生きようとする力)のある盲目的な強さが弱まっているようでもある」と、著者は綴っている。
名作「プールサイド小景」が生まれるのは、この直後のことで、作品のモチーフについて事前に庄野さんから聞いていた著者も、「熊の掌のように柔らかい筆致で、どこまでもマンベンなくなでまわすようだった彼の文章が、ここでは急所だけをあやまたずに狙う鋭い爪に代わっている」「これまでのシツコイ反復のうちに滲み出していた(生きようとする力)が、この作品では、途切れがちな段落や、章と章との余白の中に最も力強く現れているのだ」と、最大限の賛辞を惜しみなく送った。
最後に、この庄野潤三論の終わりの部分を引用しておこう。
この一作で庄野は彼の一頂点をきわめた感がある。この一点にたどりつくまでに彼の選んだコースは、誰にでも泳げそうで、それでいて泳ぎにくい水路だった。自分の肌にあった水質のコースを嗅ぎ分けながら、せい一ぱいの馬力で、今後はどのような島々を征服して行くことであろうか。(安岡章太郎「小説家の小説論」)
書名:小説家の小説論
著者:安岡章太郎
発行:1970/10/30
出版社:河出書房新社
村上春樹の文学世界をより深く知るために
もっと村上春樹の世界を知りたいという方に、次の記事もおすすめ。
村上春樹作品の読み方完全ガイド
村上春樹の読み方を解説した完全ガイド。村上春樹のプロフィールからオシャレな楽しみ方まで。本サイトの村上春樹はここから始まります。

村上春樹のおすすめ作品10選+α
どの作品から読み始めるべきか迷っている方に。全作品から厳選したおすすめ10作品+αを解説しています。

庄野潤三の文学世界をより深く知るために
庄野潤三の世界を、もっと深く知りたいという方に、おすすめの記事をご紹介します。
庄野潤三 完全ガイド│プロフィールから詳細な年譜まで
庄野潤三について詳しく解説しています。プロフィールや代表作のほか、全著作リストや詳細な年譜、各作品の詳細考察まで、このページを読むことですべてが分かります!

庄野潤三作品一覧|年代順で読む全長編と短編集
庄野潤三の全著作を年代順でまとめてみました。あなたの読みたい作品は、この中に必ずあるはずです。