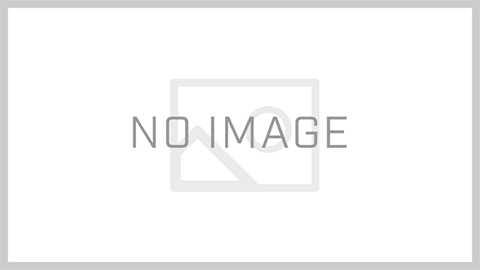井伏鱒二『遙拝隊長・本日休診』読了。
本作『遙拝隊長・本日休診』は、1955年(昭和30年)6月に新潮文庫から刊行された作品集である(新潮文庫オリジナル)。
この年、著者は57歳だった。
収録作品及び初出は、次のとおり。
「遙拝隊長」
・1950年(昭和25年)2月『展望』
「本日休診」
・1949年(昭和24年)8月~1950年(昭和25年)6月『別冊文芸春秋』(計4回掲載)
いずれも、終戦直後に発表された作品である。
軍国主義の亡霊として生き続ける狂人
本作『遙拝隊長・本日休診』は、新潮文庫オリジナルの作品集である。
巻末の「解説」を、阿佐ヶ谷会で仲間だった上林暁が書いている。
文庫版は、この「解説」が楽しみ。
井伏氏は、戦争末期から戦争直後にかけて、郷里に疎開していた。その関係で、材を自分の村に取ったとおぼしい、『当村大字霞ヶ森』物とも言うべき一連の作品がある。現に『当村大字霞ヶ森』と題した作品もあるし、その他には『追剥の話』『丑寅爺さん』などの作品が「霞ヶ森」の出来事となっている。(上林暁『遙拝隊長・本日休診』解説)
本作「遙拝隊長」にも『当村大字霞ヶ森』シリーズの趣きがあるが、これは、疎開先で得た話ではなかったらしい。
この作品の題材は、井伏氏の村の出来事ではないそうである。或る雑誌社の婦人記者から、これに類したちょっとした話を聞いて、それをもとにして組み立てたものであると、いつか井伏氏が語ったことがあった。(上林暁『遙拝隊長・本日休診』解説)
本作「遙拝隊長」のキモは(ポイントは)、戦争中と戦後とのコントラストだろう。
岡崎悠一(三十二歳)は気が狂っている。普段は割合おとなしくしているが、それでも、いまだに戦争が続いていると錯覚して、自分は以前の通り軍人だと勘違いしている。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
主人公(岡崎悠一)は、戦争中の世界から舞い戻ってきた「軍国主義の亡霊」である。
お袋が煙草を買って来てやると、恩師の煙草だと云って、感極まったような風で東の方に向って遥拝の礼をすることがある。道を歩きながら、突如として「歩調をとれえ」と、気合を込めた号令をかけることがある。──これはみんな、誰も戦争中には、軍人がするのを見慣れているので珍しくないが、今日では、ただふざけているように見えるだけである。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
戦争中には当たり前だった光景が、戦後には狂人の振舞いとなっている。
狂人(岡崎悠一)の言動は滑稽なものでしかないが、「滑稽でしかない」というところに、戦争という歴史の本質が表われている。
平時でなければ見えないものこそ、戦争の「滑稽」な素顔だったのだ。
「反抗するか、ばか野郎。愚図々々いうと、ぶった斬るぞォ」(井伏鱒二「遙拝隊長」)
数年前までは当たり前だったものが、戦後には異文化でしかない。
しかも、庶民は戦争にアレルギーを抱えているから、当然、主人公に対しても強いアレルギー反応を示す。
「ぶった斬るとは、何ごとじゃ。まるで、軍国主義の亡霊じゃ、骸骨じゃ。おい棟次郎さん、放して下され。おい放せ、村松棟次郎さん。この危急存亡のとき、わしの自由を村松棟次郎さんは、奪うのか」(井伏鱒二「遙拝隊長」)
主人公(岡崎悠一)のモデルになっているのは、長篇『徴用中のこと』に登場する「輸送指揮官」だったかもしれない。
「髭」は「気をつけ」の号令をかけて、いきなり大きな喚き声で云った。「儂は、お前たちの指揮官である。今からお前たちの生命は、儂が預かった。ぐづぐづ云う者は、ぶった斬るぞ」(井伏鱒二「徴用中のこと」)
最初の集合で「ぶった斬るぞ」と脅されたとき、海音寺潮五郎は「ぶった斬って見ろ」とやり返した、という話が、『徴用中のこと』にある。

そもそも「遥拝」が好きだったというところが、主人公と輸送指揮官との共通点だった。
元来、遥拝隊長は遥拝をすることが好きであった。輸送船のなかでも、ラジオで何か朗報なるものが伝わると、部下を甲板に整列させて東方を遥拝させ、万歳を三唱させた。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
似たような話が『徴用中のこと』にも出てくる。
この人は輸送船に乗ってからは、ラジオで日本軍の捷報ニュースがあるたびに、私たちを甲板に集合させて東方を遥拝させた。同じ船に乗っていたビルマ組徴員の輸送指揮官が「髭」に、「東方遥拝も、ほどほどにせんか」と云った。(井伏鱒二「徴用中のこと」)
作者(井伏鱒二)は、この「輸送指揮官」のことが、よほど好きではなかったらしい。
戦後になってから小説の中に「軍国主義の亡霊」として、この上官を登場させた。
いわば、作者にとって、この輸送指揮官は「軍国主義の象徴」として記憶されていたのだろう。
「いや、ぶった斬るとは、何ごとじゃね。軍国主義の、化物が云うことじゃ。あの一言で、わしは腹わたが煮えくりかえる」「まあ、そう云うな。戦争中だと思ったら、お互に我慢できんこともなかろう。戦争中には、散々に聞かされた言葉じゃ。お互いに、よく聞かされて来た間柄じゃないですか」(井伏鱒二「遙拝隊長」)
実際、狂人になる前、戦地での主人公は正常の軍人だった。
遙拝隊長は輸送船のなかで、部下に遥拝させること以上に、兵隊に訓示をするのが好きらしかった。訓示をしたいばっかりに遥拝させるのだ、と悪口を云う兵もいた。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
「遙拝隊長」は、遥拝が好きすぎる故に、軍隊で付けられたニックネームである。
主人公は「遙拝隊長」のあだ名を名誉に思って、さらに遥拝に励んだ。
現代から思えば滑稽でしかないのだが、コメディがコメディにならないというところに、戦争の諧謔性がある。
相棒がそう云って、「あれを見い。マレー人が、わしゃ羨ましい。国家がないばっかりに、戦争なんか他所ごとじゃ。のうのうとして、ムクゲの木を刈っとる」と、云った。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
物語から浮かんでくるのは、戦争の犠牲者として生きる庶民の姿だ。
それは、もちろん、戦地へ赴いた作者自身の本心でもあったことだろう。
「なんちゅう贅沢なことじゃ。あの原っぱの池を見ろ。惜しげもなく、爆弾を落としとる」と云う者があった。すると、友村という上等兵が「贅沢なものじゃのう、戦争ちゅうものは。まるで贅沢じゃ。そもそもが、戦争ちゅうものは費用のかかるものじゃ」と云った。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
このひと言を聞きつけた遙拝隊長が、友村を放置しておくはずがない(なにしろ、遙拝隊長は軍国主義の亡霊なのだ)。
厳しく咎めている際中の不慮の事故が原因で、友村は死に(行方不明だった)、主人公は狂人となった。
戦争は贅沢だと云ったばっかりに、死ぬ直前に平手打ちを喰らわされて、故障車から転落する巻添まで喰らった。おまけに、頭をコンクリートに打ちつけて、名前も知らぬ濁り川に沈められ、散々な仕打ちを受けている。まるで、戦争というものを、瞬時の間に縮尺して見せてくれたようなものである。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
「戦争というものを、瞬時の間に縮尺して見せてくれたようなもの」とは、つまり、戦争とは無意味なものである、ということだ。
軍国主義の亡霊として生き続ける狂人をユーモラスに描きながら、この小説は、無意味な戦争の虚しさを伝えている。
もちろん、主人公(岡崎悠一)も、戦争の被害者ではあった。
「君に悠一ッつぁんのうちの、コンクリートの門柱を見せてやりたいな。あれを見なくっちゃあ、悠一ッつぁんの正体は、掴めない。門柱のてっぺんに、色硝子のかけらを植えつけているんだ。それは悠一ッつぁんのお袋の考案だそうだ」(井伏鱒二「遙拝隊長」)
主人公(岡崎悠一)の母親の存在は、この物語に一層の深みを生み出している。
主人公の父親は、主人公が幼いころ、過労と貧困による栄養不足が祟って病死したため、主人公はシングルマザーである母親によって育てられた。
ひどい苦労をしながらも、母親は主人公を立派に育て上げた。
それから二三日して、村長は小学校長といっしょに悠一のうちを訪れて、お袋の前で、悠一を幼年学校入学応募生の有資格者として推薦すると云った。理由は、悠一が学童として優秀であり、悠一のお袋が人格者であり、模範的な一家である故だというのであった。(井伏鱒二「遙拝隊長」)
主人公を「軍国主義の亡霊」へと育てあげたものは、日本社会そのものである。
ワンオペで育てあげた息子が、狂人となって戦地から帰還した。
そこに、この物語の悲しさがある。
そして、その母親の生き方もまた、やはり「戦争中という時代」が生みだしたものであったに違いない。
校長は、主人公宅にある車井戸が鳴らす釣瓶縄を手繰る音まで褒めた。
「あの音は、遠くからきいておると、まるきり鶴の鳴声に、そっくり生き写しですなあ。鶴、九皐に鳴きて、声、天に聞こゆ、云々……。これは、目出度いことの意味ですからなあ」(井伏鱒二「遙拝隊長」)
主人公の母親にとって、コンクリートの門柱と釣瓶縄を手繰る音は「成功の証」だったかもしれないが、息子が狂人となった今、「コンクリートの門柱」は一家の墓標であり、「釣瓶縄を手繰る音」は家庭に響く鎮魂の鐘の音でしかない。
どこにも幸福になった者がいないところに、この物語の恐ろしさがある。
そして、それこそがつまり、戦争というものの恐ろしさだった。
本作「遙拝隊長」は、戦争の悲劇を描いた物語である。
戦争の悲劇を描いているのにベタベタしていない。
この作品は、戦争と戦争思想の愚劣さを痛烈に発き、嘲笑したものであることに間違いない。一方では、この哀れな戦争犠牲者に対するヒューマニティの熾烈さも見逃してはならない。(略)愚劣さを嘲笑すればするほど、ヒューマニティが掻き立てられるといったあんばいである。(上林暁『遙拝隊長・本日休診』解説)
上林暁は「解説」の中で「読者は泣き笑いを催すにちがいない」と指摘している。
泣かずにはいられない「笑い」こそが、この物語の真に意味しているところだったのではないだろうか。
荒廃した庶民の戦後生活
一方の「本日休診」は、戦後の世相を反映した風俗小説である。
空襲で病院を焼かれた主人公(三雲八春)は、甥っ子(三雲伍助)と一緒に新しい病院(三雲病院)を始めた。
医者の視線から見た戦後の東京(蒲田駅前)が、この物語では克明に描かれている。
開業一周年の記念日には、「本日休診」の札をかけ、八春先生が留守番で、ほかのものはみんな遊山に出ることにした。(井伏鱒二「本日休診」)
病院の案内札をタイトルにしているところは、戦後の住宅難の時代を背景に、アパートの住人たちの生活を描いた『貸間あり』(1948)にも似ている。
ただの病院物語ではなくて、ちょっとひねりを加えて「本日休診」の病院が舞台となっているところに、巧みなプロットが感じられる。
それは、とにかく荒廃した時代だった。
「本日休診」の札を掛けた病院を最初に訪ねてきたのは、若い女性(悠子)を連れた警察官(松木ポリス)である。
娘は腕時計を強奪されようとしていることに気がついて、咄嗟に自分でそれを取りはずし、その場に放り出して逃げようとした。暴漢はその時計をひったくって、ポケットに入れ、「声をたてると、承知しないぞ。逃げようたって、もう無駄じゃないか。ちょっと、つきあえよ」と云った。(井伏鱒二「本日休診」)
婦女暴行の被害者が泣いているところへ現れたのは、かつて「旧・三雲産婦人科医院」を開業してときに、一番最初に診た患者(湯川美千代)である。
「先生、ほんとに申しわけ御座いません。もう十六年たちました。あのとき、そのままにいたしましたもの、持って参りましたのですが、あのときの勘定書通りに持って参りました。お恥ずかしくって……」(井伏鱒二「本日休診」)
美千代が長男(春三)を出産したとき、帝王切開の手術をしながら治療費を請求しなかったのは、湯川夫妻が大変貧しかったためである。
なにしろ、貧しい人たちの多い時代だった。
蒲田駅の車庫の電車の中にも、人の暮らしがあった。
車庫のなかの電車住宅は、たぶん不潔だろうと思って消毒液も多量に用意した。車庫が空襲のとき火をかぶって、使いものにならない車輌が何台もできたので、そのなかに鉄道関係の人たちの家族が住んでいる。(井伏鱒二「本日休診」)
八春先生も、また、空襲の罹災者だった。
戦災ですっかり焼かれてから、自分でも引込思案にすぎはしないかと思うほど消極的になって来た。焼け出されたとき、医者に入用な品として手もとに残ったのは、たった一つ上着のポケットに入れておいた聴診器だけであった。(井伏鱒二「本日休診」)
旧・蒲田区は、1945年(昭和20年)4月15日の大空襲により、全住宅の約68%にあたる4万戸以上が消失したという。
八春先生の「三雲医院」も、その中に含まれていたのだろう。
戦後復興の際に、旧・蒲田区は、旧・大森区と再編して、現在の大田区となった(大森と蒲田)。
戦後の小説とは言いながら、描かれているのは、戦争の犠牲者たる庶民の暮らしである。
川岸につないだ船の中で生活している者もいた。
「六郷川の、船です。砂礫船で御座います。──産婦が、ときどき脳貧血のような症状を現わします」六郷川の岸には、ところどころに砂礫運びの船がつないである。船底の穴ぐらのようなところに人が寝起きして、そこを住宅代わりにしているものがある。(井伏鱒二「本日休診」)
砂礫船の生活をスケッチしたものは、貴重な記録だったかもしれない。
穴ぐらをのぞいて見ると、煎餅蒲団の端から、女の仰向いた顔と赤んぼの頭がのぞいていた。二畳間ぐらいの穴ぐらである。薄べりを敷いて、割合きれいに片づけてある。ベニヤ板で細工した嵌込戸棚もついている。夏蜜柑をそなえた小さな仏壇もある。吊ランプも見える。(井伏鱒二「本日休診」)
医者を主人公としていながら、本作品は、決して本格的な医学小説というわけではない。
この物語において、主人公(八春先生)は、焼け跡の街の案内人である。
貧しい人々の暮らしを紹介するために、八春先生は街のあちこちを往診して回るのだ。
16年ぶりに手術台を支払いにやってきた湯川一家の住宅は、若布(わかめ)を染める工場の右手にある棟割長屋だった。
湯川家の隣人宅で難産があったときも、八春先生が往診した。
先ず一ぷくすることにしたが、部屋が狭苦しくって煙草をすうことも出来そうにない。茣敷きの上に、バケツ、茶碗、お櫃、摺鉢、鍋、釜など、いっぱいに並べてある。戸のない三尺の押入れと、竈を置いた三尺幅の土間が隣あって、板壁に取りつけた棚に、これだけは金ぴかの厨子が置いてある。(井伏鱒二「本日休診」)
彼らだけが特別に貧しいというわけではなかった。
戦後、多くの人たちが(罹災して)同じように貧しかったのだ。
炭団屋の竹さんの家は、炭団を売る店ではなく、焼跡の開墾畑のはずれにあるバラック建の家であった。やはり春三たちの長屋の造りにそっくりで、地面と殆どすれすれになるように床を低く張って掘立式に出来ている。(井伏鱒二「本日休診」)
貧しい人々の暮らしを、庶民の目線から描いているという意味では、山本周五郎の作品に通じるものがあるかもしれない。
井伏文学の特徴は、いつでもユーモアを忘れなかったということである。
弁当は幕の内で、おかずは先生も大好物のラッキョウと油揚の焼いたのであった。幕の内には、過不足なく程よい加減に黒胡麻が振りかけてあった。(井伏鱒二「本日休診」)
貧しい暮らしの中では、人心も荒廃していく。
看護婦たちも、この患者には手を焼いていた。隣のベッドのお町さんを見廻りに行くと、横合から看護婦に卑猥な言葉を浴びせかける。「色情狂みたいです」と滝さんが云っていた。(井伏鱒二「本日休診」)
貧しい暮らしと同じくらい、荒んだ人々は、この物語の大きなテーマとなっている。
警察は、荒んだ人々の案内人としての役割を果たしている。
黒瀬君という看手が監房から連れ出してきた女性も、かつて、八春先生が診たことのある女だった。
「あのとき、先生は、お伽噺の青い鳥の話をして、あたしに嘘泣きさせました。でも、嘘です。青い鳥なんて、嘘っぱちさ」
この女性は、下腹が痛いと言って、八春先生に自分の裸を見せたのである。
「痛いですかね」と声を落してきくと、「先生、痛いんです」と声を落して答えた。女は、八春先生がまだ云わないのに、幅のせまい差込帯をぐるぐる解きはじめた。着物の前がはだかると、経済学全集の広告の幟で再生した湯巻が見えた。(井伏鱒二「本日休診」)
「経済学全集の広告の幟で再生した湯巻が見えた」とあるあたり、細かなモチーフにも戦後が描かれている。
刺青を消し取る手術を求めて来院する若者も少なくなかった。
「手術して下さい。休暇になっても、僕は刺青があると郷里に帰れません。父に叱られます。父は厳格なのです」と泣顔で云った。案の定、年増の女に威かされ、仕方なしに刺青したのだと云っていた。(井伏鱒二「本日休診」)
気の弱い色男には、どこか太宰治の面影がある。
太宰治は、1948年(昭和23年)に亡くなっているが、意外と、こんなところにも顔を出していたのかもしれない(ちょっとしたモデルとして)。
当時は刺青を入れるのが流行していたらしい。
最近、場所がらのせいか、若い男が刺青を抜いてくれと云って来るようになったので、ごく簡単な刺青なら剥ぎとる手術を施している。なかには若い女も、刺青を取ってくれと云って来ることがある。(井伏鱒二「本日休診」)
男の場合は「桃」や「錨」、「女の名前や頭文字」などを上膊部に刺青しているし、女の場合は、二の腕や「下着で隠れる部分の勝手な個所」に「小さな動物とか昆虫」や「頭文字や人の名前」などを入れている。
女の二の腕に刺青しているのは、決まったように頭文字かイニシャルだった。
新しい時代を描いているという意味で、この作品は、敗戦直後のトレンド小説と言ってもいい。
「先生、手術して頂けますかしら」「しかし、このエス・エム氏が御承知の上なんでしょうか」「あら、エス・エム氏だなんて、いやですわ」(井伏鱒二「本日休診」)
入院用ベッドの布団とシーツを盗んで夜逃げする悪党もいれば、入院費を心配するがあまり無理に退院して死んでしまう困窮者もいる。
1949年(昭和24年)から1950年(昭和25年)にかけて、それは、まだまだ復興途上の時代だった。
新しい時代を歩み始めている庶民の生活が、この物語には描かれている。
それは、令和へと続く現代日本の原点でもあった。
新潮文庫『遙拝隊長・本日休診』の文庫帯には「「サヨナラだけが人生だ──」井伏鱒二の世界」との文章がある(平成5年7月30日、44刷)。
井伏鱒二が亡くなったのは、1993年(平成5年)7月10日だから、この文庫は、井伏鱒二の没後直後に出版されたものだろう。
書名:遙拝隊長・本日休診
著者:井伏鱒二
発行:1955/06/05
出版社:新潮文庫

(2026/03/01 20:10:09時点 楽天市場調べ-詳細)