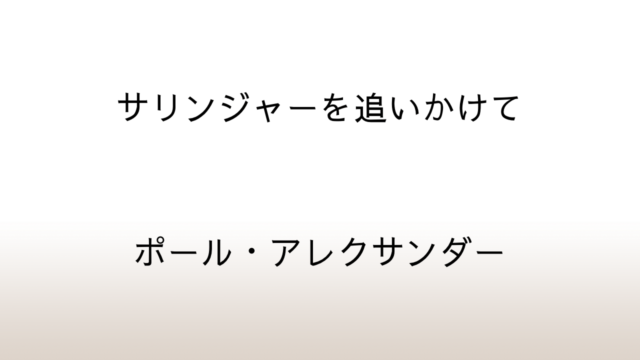ウィーダ「フランダースの犬」読了。
本作「フランダースの犬」は、1872年に発表された児童文学である。
この年、著者は33歳だった。
1975年(昭和50年)、『世界名作劇場』でテレビアニメ化された。
ひとつの墓に葬られたネロとパトラッシュ
本作『フランダースの犬』は、画家を夢見る貧しい少年(ネロ)が、年老いた愛犬(パトラッシュ)とともに、失意のもとに死んでゆく悲劇の物語である。
テレビアニメ『フランダースの犬』最終回のラストシーンは、つとに有名で、教会で憧れのルーベンスの作品を観たネロが、「パトラッシュ… 疲れたろ…。僕も疲れたんだ。なんだかとても眠いんだ…」と言いながら死んでゆくシーンは、多くの視聴者に強烈な印象を与えた。
この場面は、原作小説の中にも、ちゃんと書かれている(セリフはちょっと異なっているが)。
少年は低い叫びと共に身をおこし、パトラシエをひしと抱きしめてささやいた。「ふたりでよこになっていっしょに死のう。人はぼくたちに用がないんだ。ふたりっきりなんだ」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
冷たい村人たちの仕打ちに絶望したネロは、画家への夢も断たれて(コンクールに落選)、アロアと再会することもできず、激しい飢えと寒さを抱え、クリスマス・イブの教会にたどり着く。
少年と犬はルーベンスの絵の下に身動きもせずに横たわり、寒さで感覚も麻痺し、気持のよい眠りに落ちかかっていた。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
ネロとパトラシエが、ルーベンスの絵を観たのは、このときだ。
とつぜん闇の中をつよい白い光が広い通路からさしこんだ。(略)一瞬「十字架にかけられるキリスト」と「十字架からおろされるキリスト」は、くっきりとうかび出た。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
「とうとう、見たんだ!」「おお、神様、もうじゅうぶんでございます!」と、ネロは叫ぶ。
そして、この喜びが、ネロに最後の安堵感を与えたのかもしれない。
少年の腕はふたたび犬の胴体をしっかりと抱きしめた。「ぼくたちはあのイエスさまのお顔を──あの世で見られるだろう。そしてイエスさまはぼくたちを離れ離れにはなさるまいよ」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
翌日(クリスマス当日)、アントワープの人々は、大伽藍の聖壇所の近くで、死んでいる少年と犬を見つけた。
コゼツ(アロアの父親で、裕福な粉屋の主人)は「わしはあの子にむごい仕打ちをした。それを今埋合わせをしようと思ったのに──わしの財産の半分だってやったし──わしの息子にしてやるんだったのに」と泣きじゃくり、世界的に有名な画家は「昨日、当然賞に入るべきであり、入る価値のあった者をさがしにきたのだが」「まれにみる未来有望の天才少年です」と、少年の若すぎる死を悼んだ。
とりわけ、大きなショックを受けたのは、ネロの恋人(アロア)だった。
「ああ、ネロ、いらっしゃいな! あんたにきてもらう用意がすっかりできているのよ。小さいキリストさまは手にいっぱい贈物を持っているし、笛吹きのおじいさんはあたしたちに笛を吹いてくれてよ。二人でクリスマスの週間じゅうずっと、炉ばたで栗を焼いていいって、母さんが言ってるのよ。──『神顕節(エピファニー)』までずっとよ! それからパトラシエもそりゃあしあわせになるのよ! おお、ネロ、起きていらっしゃいな」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
もちろん、人々が、どれだけ悔いたところで、少年と犬が甦ることはない(「口もとには微笑さえたたえて、大ルーベンスの光明を仰いでいる青ざめた若い顔は、人々一同に「もう間に合わない」と答えていた」)。
こうして、ふたりは(少年と犬は)ひとつの墓に葬られる(ここがすごい)。
生涯ふたりはいっしょにすごし、死んだ後もはなれなかった。なぜなら少年の腕があまりにしっかりと犬を抱いているので、腕力をふるわずには引離せないことがわかったうえに、後悔し恥じいった村人たちが、特別の許可を得てこの二者を一つの墓におさめて相並んで眠るようにしたからである──永久に!(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
少年にとって、パトラシエは唯一の希望であり、パトラシエにとって、ネロは唯一の生きがいだった。
貧しい孤児と哀れな労役犬の友情が、この物語の大きな骨組みを形成している。
救いは、ネロが、最後まで誠実な少年のままで死んでいったことだろう。
「パトラシエが今夜この大金をみつけたんです」とネロは口早に説明した。「コゼツの旦那にそう言ってください。この犬も年をとっているのですから、旦那もこれをここに置いて食べものをやるのを、いやとは言いなさりますまい」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
コゼツの財布(紙幣で二千フラン入っていた)は、少年にとって最後の踏み絵だった。
財布を届けたネロは、パトラシエを置き去りにして、アントワープの教会へ向かう。
それが、壮絶なクリスマス・イブの夜の出来事だった。
フランダース地方の複雑な歴史
本作『フランダースの犬』の舞台は、ベルギーの大都市(アントワープ)のほど近くにある、小さな農村である。
彼らの住居は小さな小屋でアントワープから三マイルのところにあるフランダースの一小村のはずれにあった。(略)村には普通の家も農家もとりまぜて二十軒ほどしかなかった。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
そこは、決して美しい村ではなかった。
フランダースは風光明媚の土地ではなく、ルーベンスの住んでいた町の周辺はとりわけ美しくなかった。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
ルーベンスは、17世紀前半にアントワープで活躍した画家で、宗教画で特に評価が高い。
ルーベンスなしでは、アントワープはどうであろうか? 波止場で取引をする商人のほかは、だれ一人見むきもしないきたない、陰気なごみごみした市場にすぎないのだ。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
画才に恵まれた貧しい少年が、ルーベンスに憧れたのは、風土的にも当然のことだったのかもしれない(つまり、ルーベンスは地元の英雄だったのだ)。
両親のいないネロにとって、ダースじいさんが、唯一の身寄りだった。
小屋はひどく年をとった貧しいジェハン・ダースじいさんのものであった。老人は壮年時代には兵士だったので、さながら牡牛が畔を踏みつぶすようにこの国をじゅうりんした戦争のことを、よくおぼえていた。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
「この国をじゅうりんした戦争」とあるのは、ナポレオン戦争のことで、「アントウェルペン包囲戦」において、アントワープの街は、壊滅的な被害を受けていた(「アントウェルペン」は「アントワープ」のこと)。
一方で、ネロの恋人(アロア)にも、フランダース地方の持つ悲劇的な歴史が描かれている。
アロアはかわいらしい、まだ幼い子供で、やわらかなまるいばら色の顔を引きたてているのは黒い瞳であった。オランダ、ベルギー地方がスペインの支配下にあったころ、多くのフランダースの人々の顔に残されたのがこの黒い瞳で、アルバ公爵の治世を語るよすがともなっているが、それと同時に、スペイン美術もこの国のいたるところに、壮麗な城や、いかめしい広場、金めっきの玄関、彫刻をほどこした横木などに跡をとどめている──すなわち、装飾には歴史を、石には詩をのこしていったのである。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
フランダース地方のこうした背景は、『フランダースの犬』という小さな物語に、歴史的な奥行きを与えている。
スペイン統治、ナポレオン戦争、フランドル派の活躍といった時間の流れの中に、貧しい少年ネロが位置付けられていると読むことができる(「フランダース」は「フランドル」のこと)。
二十軒ばかりしかない小さな村で、貧しい少年が孤立したのは、粉屋の旦那(コゼツ)の怒りを買ったからだ。
「あの男の子をあまりアロアに近づけてはいけない。このさき厄介なことがもちあがらないともかぎらないからな。あの子はもう十五になっているし、うちの子は十二だ。それにあの男の子は器量も姿もいいからな」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
コゼツがネロを忌み嫌ったのは、ネロが貧しいうえに、画家などという夢を見ていたためである。
「あの若いのは乞食も当然だ。おまけにこんな画描きなどという妄想を持っているんだから、乞食よりも始末がわるい。今後はうちの子といっしょにさせないように気をつけるのだぞ」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
村一番の裕福な百姓だったとは言え、コゼツもまた、芸術に価値を見出すことのできない、無教養な男だった。
村人たちは、コゼツの怒りに触れないよう、ネロを遠ざけるようになる。
ダース老人が死んで、ネロがまるきりの孤児になった後で、村人たちのよそよそしい態度は、よりいっそう顕著なものとなった。
ネロとパトラシエはまったくふたりきりになってしまった。キリスト降誕祭一週間前のある夜、死がおとずれて、貧困と苦労のほかは知らずじまいであったダース老人を永久にこの世から連れ去ったのである。(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
そして、その一週間後に、孤児となったネロも(パトラシエと一緒に)この世を去った。
小さな村社会が、とりわけ貧しい少年たちを葬ったのである(「あれは乞食だ。あんな子供をうちのアロアのそばに近寄らせるものか」)。
少年を支えていたのは、将来への夢だった。
「それでもぼく、やっぱり偉くなるよ」ネロはささやいた。「偉くなるか、さもなければ、死ぬかなのだ、アロア」「あんたはあたしを愛しちゃいないんだわ」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
画家への夢が断たれたとき(コンクールに落選したとき)、ネロの希望は、すべて失われた。
少年はよろめきながら立ちあがり、犬をかきいだいた。「いっさい終わってしまったんだ、パトラシエ。いっさいが終わったのだ」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
貧しい少年にとって、15年間の生涯は、試練の連続だったと言える。
2歳で母親を失い、牛乳の配達で祖父の貧困家庭を支え、ルーベンスだけに希望を見出した。
「いつかこれとはちがったことになるよ、アロア。君のお父さんが持っているあの小さな松の板を、いつか同じ目方だけの銀ほどの値打ちにしてみせる。そのときになったらお父さんはぼくを閉め出しはなさるまい。ただ、ぼくを愛しておくれ、アロア。いつまでもぼくを愛しておくれ、そうしたらぼくはきっと偉くなってみせるから」(ウィーダ「フランダースの犬」村岡花子・訳)
「小さな松の板」は、ネロの描いたアロアの肖像画である。
しかし、明日への希望も虚しく、ネロの夢がかなうことはなかった。
貧しい少年にとって、挫折は、そのまま死を意味していたから、これ以上、先の夢を描くことは困難だったのだろう。
貧しい少年の夢と挫折が、この物語では描かれている。
ただし、少年は孤独ではなかった。
あるいは、「孤独ではなかった」というところにこそ、この物語の希望はあるのかもしれない。
書名:フランダースの犬
著者:ウィーダ
訳者:村岡花子
発行:1954/04/15
出版社:新潮文庫