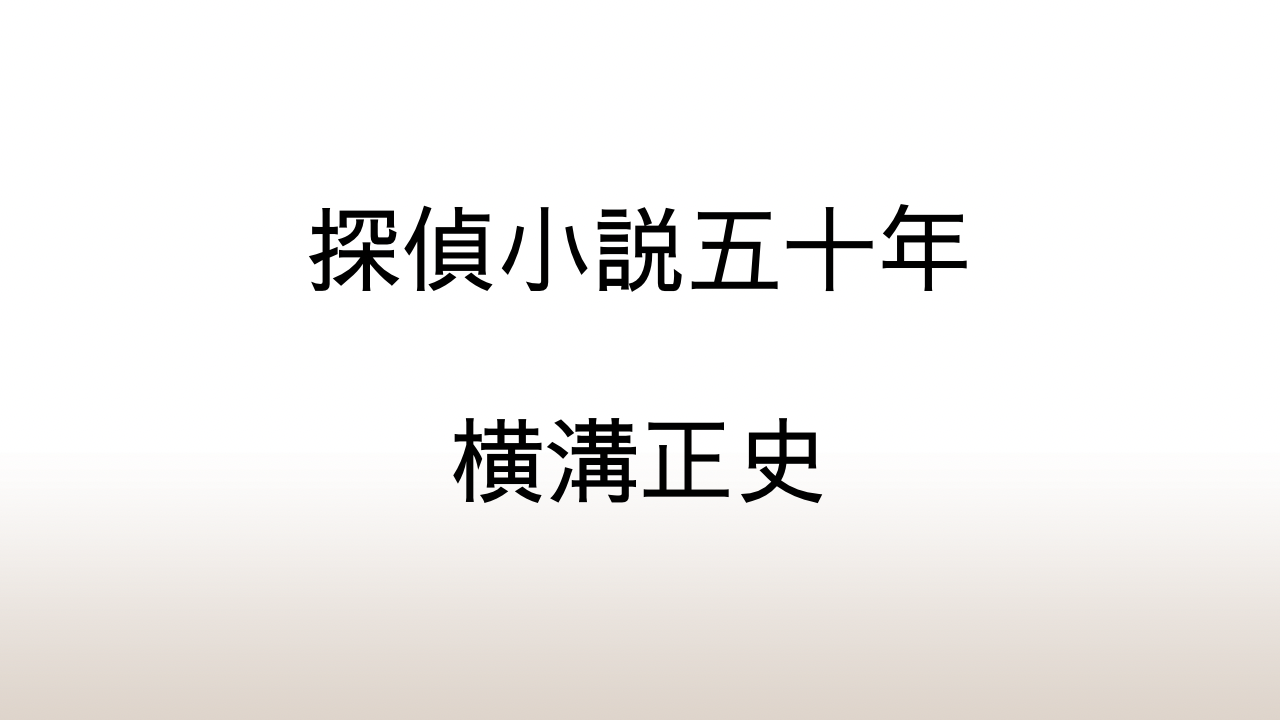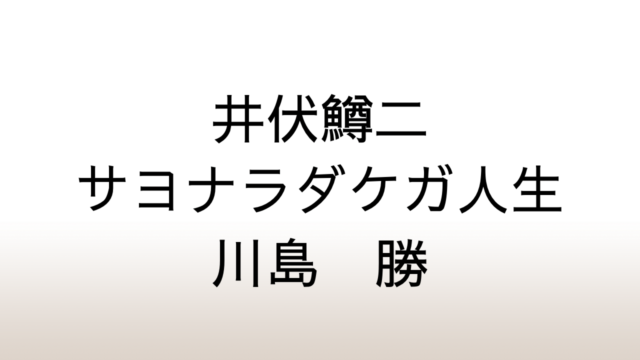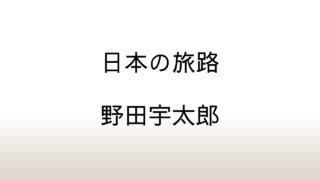横溝正史「探偵小説五十年」読了。
本書「探偵小説五十年」は、1972年(昭和47年)に刊行されたエッセイ集である。
この年、著者は70歳だった。
デビュー作と雑誌記者時代
本書「探偵小説五十年」は、雑誌や新聞などに発表した短文を収録したエッセイ集で、断片的な作品が多いが、『横溝正史全集月報』に連載された「途切れ途切れの記」や、『定本人形佐七捕物帳全集月報』に連載された「続・途切れ途切れの記」などは、ある程度まとまった自伝的エッセイとなっていて読み応えがある。
「序にかえて」では、古希を迎えた著者の率直な気持ちが綴られている。
だれの人生でもそうであろうが、私の五十年も山あり谷ありだが、その間、私はそのときそのときの流れに身をまかせて、アップアップしながら、この年まで生きてきたに過ぎないように思われてならない。ときたま情熱を燃えあがらせることはあっても、それは線香花火のようにすぐ燃えつきて、あとは惰性でことを処してきたことが、今になってみると残念でならない。(横溝正史「探偵小説五十年」)
その五十年は、「途切れ途切れの記」でおおよそを辿ることができる。
就職先の第一銀行を辞めて、家業の薬局を継ぐために大阪薬学専門学校へ通っているときに書いた「恐ろしきエイプリル・フール」が『新青年』の懸賞小説に当選したのが、作家としてのデビュー作となった。
江戸川乱歩の誘いで上京後に、出版社の博文館に入社、『新青年』『文芸倶楽部』『探偵小説』で雑誌記者として過ごすが、特に『新青年』で編集長を務めた頃が充実の時代だったらしい。
いまにして思えば、温ちゃんの死は同時に私の青春の日の終焉を意味していた。昭和七年私も博文館を退いた。そして翌八年大喀血をやってのけた私は、それ以来いまにいたるまで、いたって非社交的で閉鎖的な生活を送っている。私が七十年になんなんとする生涯のうちで、いくらかでも社交的な生活をもった唯一の時期は、『新青年』時代だったように思う。(横溝正史「惜春賦──渡辺温君の想い出──」)
博文館退社後、文筆業に専念するが、間もなく病気療養のため、信州上諏訪へ移転(肺結核だった)、回復後に東京へ戻ったものの、太平洋戦争の激化を受け、やがて、岡山県吉備郡字桜への疎開を余儀なくされる。
もっとも、この岡山時代は、横溝正史にとって『新青年』時代と並ぶ充実期だったという。
横溝正史ブームの到来まで
戦時中に温めていた構想は、戦後間もなく(1946)『宝石』に「本陣殺人事件」として連載されるが、我々が知っている探偵小説の横溝正史は、ここからがスタートだった。
「本陣殺人事件」に続いて、『宝石』に「獄門島」が連載された(1947-1948)。
イムポシブル・クライムと意外な犯人、しかも一貫した論理性があって、その間に妖しき情報が揺曳している。そういう小説が書きたいのだけれど、そして果してそれが出来るかどうか十分の自信はないのだけれど、しかも作家たるもの、自分の才能の許す範囲で大きな野心を持ち、そして試みるべきではあるまいか。題して「獄門島」金田一耕助君の冒険第二話である。(横溝正史「獄門島──作者の言葉──」)
「獄門島」の着想は、戦争中に疎開していた岡山県の、瀬戸内海にある島から得たらしいが、乗物恐怖症だった横溝正史は、実際に離島を訪ねたことはなかったという。
やがて、名探偵・金田一耕助シリーズは不朽の名作としての地位を獲得することになるが、横溝正史が再ブレイクするのは、『八つ墓村』(1949)が角川文庫に入った1971年(昭和46年)以降のことである。
渥美清が金田一耕助を演じた松竹映画で「祟りじゃ〜っ!」が流行語になるのは1977年(昭和52年)。石坂浩二の金田一耕助は、1976年(昭和51年)の『犬神家の一族』が最初だった。
横溝正史といえば角川文庫のイメージが強いけれど、角川文庫の頃は、もうリバイバルだったんだなあ。
ちなみに、書名の『探偵小説五十年』は、江戸川乱歩『探偵小説四十年』へのオマージュで、乱歩の『探偵小説四十年』は、本作『探偵小説五十年』でも繰り返し引用されている。
書名:探偵小説五十年
著者:横溝正史
発行:1972/09/15
出版社:講談社