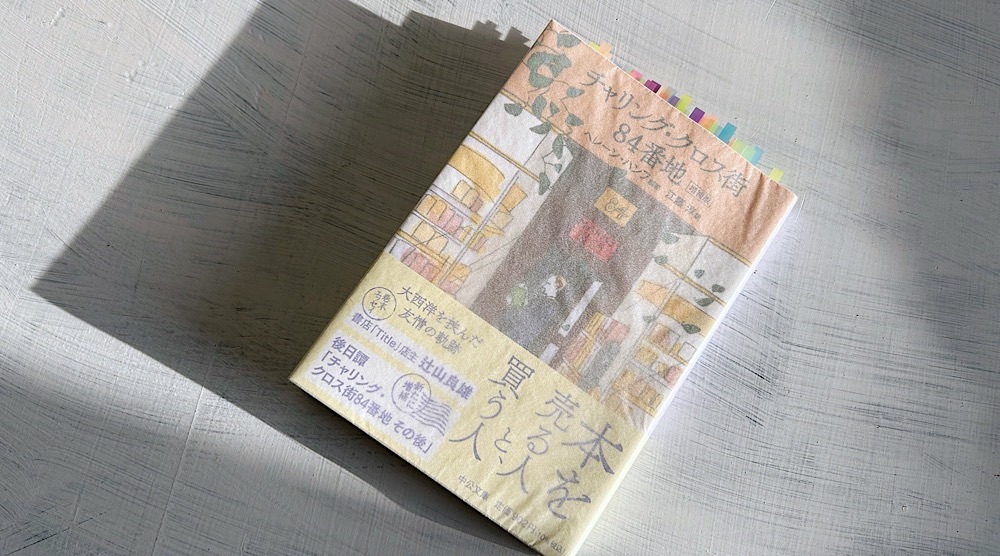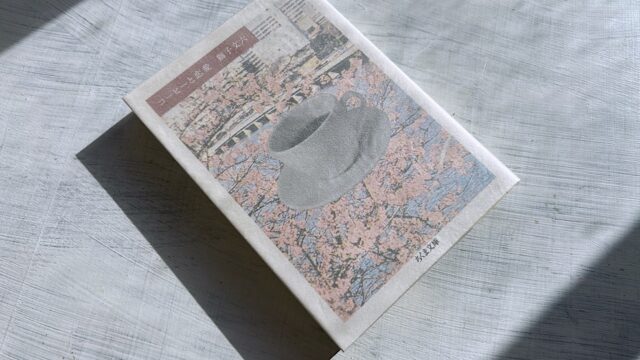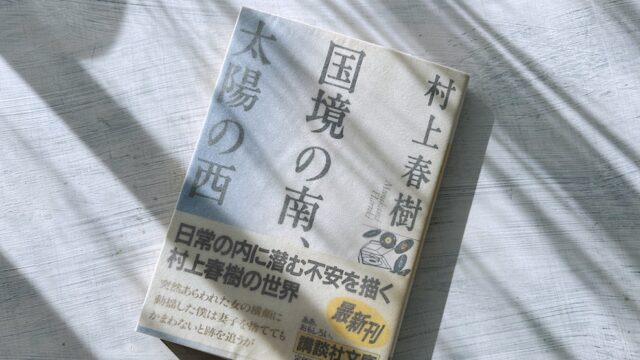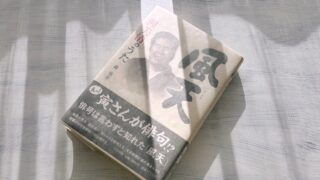ヘレーン・ハンフ『チャリング・クロス街84番地 本を愛する人のための本』読了。
本作『チャリング・クロス街84番地 本を愛する人のための本』は、1970年(昭和45年)に刊行された書簡集である。
原題は「84 Charing Cross Road」。
この年、著者は54歳だった。
日本では、1980年(昭和55年)4月、江藤淳の訳によって講談社から刊行された。
中公文庫(2021年増補版)には、ヘレーン・ハンフ「『チャリング・クロス街84番地』その後」が増補されている。
イギリス文学への良き案内書
本作『チャリング・クロス街84番地』は、イギリス文学を好きな人にはたまらない内容の書簡集である。
アメリカの女性(ヘレーン・ハンフ、33歳)が、絶版本を専門に扱うイギリスの古本屋(マークス社)へ手紙を送る。
今すぐにもほしい書籍のリストを同封いたします。このリストに載っておりますもののうち、どの本でも結構ですから、よごれていない古書の在庫がございましたら、お送りくださいませんでしょうか。ただし、一冊につき五ドルを越えないものにしてください。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
マークス社は、リストにしたがって商品をアメリカへ送る。
当方といたしましては、ご要望の書籍の三分の二はどうにかそろえました。ハズリットの随想三編は、ナンサッチ・プレス版『ハズリット随想選』にはいっておりますし、スチーブンソンは『懇談録』に収められております。ともにきれいな本を、送り状同封のうえ、書籍小包にてご送付申しあげます。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
ウィリアム・ハズリットは、『円卓』『卓上談』『直言集』などの随想集を残したイギリスの批評家で、1800年代前半に活躍した。
ロバート・ルイス・スチーブンソンは、『宝島』や『ジキル博士とハイド氏』で知られるイギリスの小説家だが、作者(ヘレーン・ハンフ)は、スチーブンソンの小説ではなく随想を求めている。
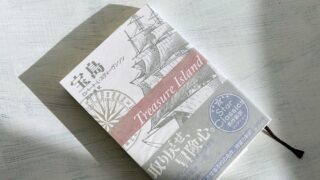
やがて、テレビドラマの脚本家となる作者も、どうやら、作り物の小説は好きではないらしい(「わたしのほうときたら、九五丁目に足止めを食ったまま、『エラリー・クィーンの冒険』なんていうテレビ・ドラマの脚本を書かされているんですものね」)。
『サー・ロジャー・ド・カバリーの記録』のことでございますが、当方にたまたま一八世紀の随筆集一巻の在庫がございまして、これには「カバリーの記録」が精選されて収められておりますし、チェスターフィールドやゴールドスミスの随筆も載っております。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
『サー・ロジャー・ド・カバリーの記録』は、ジョーゼフ・アジソンとサー・リチャード・スチールの二人が創案した架空の人物による随筆。
18世紀イギリスの政治家チェスターフィールド(フィリップ・ドーマー・スタンホープ)には、『むすこへの手紙』という書簡集がある。
イギリスの小説家オリバー・ゴールドスミスの『ウェークフィールドの牧師』は、井伏鱒二や太宰治など、日本の小説家にも愛読された。
とことん、作り物ではない文章を愛する作者の読書傾向は、十代の頃に培われたものだ。
ただ、本に関しては妙な好みがあるだけなのです。一七歳のころ図書館で夢中になって読んだ、Qの名で知られるケンブリッジ大学の教授、クイラー=クーチのせいで、こうなっちゃったのよ。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
「Q」の筆名で知られたイギリスの批評家サー・アーサー・クイラー=クーチは、本書で重要な役割を果たしている。
クイラー=クーチの名作選集『巡礼の道』、書籍小包にてご送付申しあげました。不足額は一ドル八五セントですので、お送りくださいました二ドルで十分足りることになります。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
『オックスフォード名詩選』(1900)は、クイラー=クーチの編んだ名詩選集だし(「『オックスフォード名詩選』もいっしょに送ってくださいね」「『Q名詩選』頂戴したいと思います」)、『巡礼の道』(1906)も、クイラー=クーチによる名文・名詩の選集だった。
これから送っていただきたい本のリストの中に、ウォルトンの『伝記集』を加えてくださっても結構。読んでない本は買わないというわたしの主義に反するし、着てもみないで洋服を買うようなものですけれど、ウォルトンの『伝記集』はここの図書館には置いてないのですもの。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
「読んでない本は買わないというわたしの主義」というところがいい。
「ウォルトンの『伝記集』」は、『釣魚大全』の著者アイザック・ウォルトンによる伝記集のことで、ジョン・ダンの伝記なども含まれていたらしい。
ああ、びっくりした。ウォルトンの『伝記集』、ほんとにありがとうございました。一八〇四年出版の本が一〇〇年以上たった今でも、こんな完璧な状態を保っているなんてとても信じられないわ。小口を裁ってないギザギザべりの、こんなに美しいしなやかな紙! 一八四一年に自分の名前をこの本に書き込んだウィリアム・T・ゴードンなる男性をつくづくかわいそうに思います。こんなよい本を不注意にも、ただ同然でおたくに売り払うなんて、なんという下劣な子孫を持ったことでしょうね。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
この書簡集には、作者(ヘレーン・ハンフ)のイギリス文学と古書に対する深い愛が満ち溢れている(「『ピープスの日記』、在庫があります? 冬の夜長に読みたいのです」)。
最近さる個人の蔵書をひとまとめに購入いたしましたところ、ウォルトンの『釣魚大全』のはなはだきれいな本が一冊はいっておりましたので、来週お送りできることをお知らせ申しあげます。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
手許に届いた『釣魚大全』を見て、作者は「さし絵の木版画だけでも、本のお値段の一〇倍も値打ちがあるわ」と感動する。
『愛書家のための名文選集』が包装紙の中から現れいでました。総金箔押しの浮出し模様のある革表紙、小口は金縁、手っ取り早く言ってしまえば、ニューマンの初版本を含めて、私の持っているものの中でいちばん美しい本です。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
美しい出版物に対する畏敬の念が、そこにはある。
やがて、電子書籍の時代が到来すると知ったら、彼女はどれほど絶望するだろうか。
そして、彼女の絶望は、現代を生きる愛書家たちの絶望でもある。
彼女の手紙は「1949年(昭和24年)10月5日」に始まり、「1969年(昭和44年)4月10日」に終わる。
それは、愛書家が、まだ愛書家らしく生きることのできる時代だったのだ。
彼女の読書は、やがて、小説にも広がっていく。
ついに、(小説ぎらいの)わたしとしたことが、ジェーン・オースティンに取りかかり、『自負と偏見』にぼおっとなっていることをお知りになったら、快哉を叫ばれることでしょう。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
小説とはいえ、ジェーン・オースティンは、やはり、作り物ではない世界を描いた。
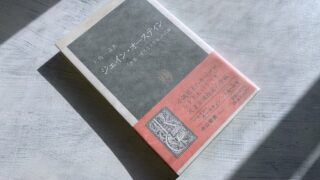
『ジェイン・オースティン』の著者(大島一彦)は、井伏鱒二や小沼丹、庄野潤三らの名前を引用して、ジェイン・オースティンの文学を考察している。
ロブのさし絵のある非常にきれいな版の『トリストラム・シャンディ』をやっとのことで見つけましたよ。お値段は二ドル七五セントくらいです。それに、一九〇三年オックスフォード刊のベンジャミン・ジョーエット訳によるプラトンの『ソクラテス的対話四編』も一冊手にはいりました。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
イギリスの小説家ローレンス・スターンの『トリストラム・シャンディ』(1759-1767)は、夏目漱石『吾輩は猫である』に影響を与えた作品として知られている(そもそも、『トリストラム・シャンディ』を日本へ紹介したのも夏目漱石だった)。
ブライアンさんが、ケネス・グレアムの『楽しい川べ』を教えてくださいましたので、ぜひ手に入れたいと思います──シェパードのさし絵のある版にしてください。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
ケネス・グレアム『楽しい川べ』は、石井桃子の訳で岩波少年文庫に入っている。
さし絵のアーネスト・シェパードは、A・A・ミルン『クマのプーさん』などの挿絵でも有名な、イギリスの漫画家だった。
ところで、見返しにさし絵入りマクドナルド古典文学双書の別の本のリストが載っていて、その中に『エリア随筆』がはいっています。この本、マクドナルド版でほしいわ──でなければ、きれいな版ならどの版でも結構です。もちろん、もしお値段が手ごろならよ。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
『トリストラム・シャンディ』に挿入されていた出版リストを見て、作者は、チャールズ・ラムの『エリア随筆』をオーダーする。
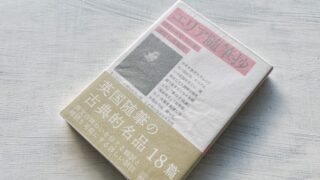
古い本の巻末にある出版リストから欲しい本を見つける方法は、古本好きあるあるだろう。
マクドナルド版古典双書は確かにときどき数冊入荷することがありますが、現在は在庫ゼロです。ラムの『エリア随筆』は以前数冊あったのですが、休日にお客さんが殺到して品切れになってしまいました。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
この手紙の日付は「1958年(昭和33年)3月11日」。
当時は、ラムの『エリア随筆』に対する需要も、まだ、あったらしい。
庄野潤三『陽気なクラウン・オフィス・ロウ』(1984)には、既にチャールズ・ラムが現代的な作家ではないことが記されている。
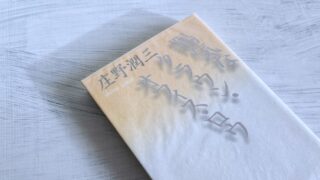
チャールズ・ラムについては、福原麟太郎『チャールズ・ラム伝』に詳しい。
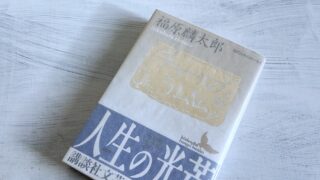
福原麟太郎つながりということでは、サミエル・ジョンソンがいる。
ジョンソンのシェークスピア論ですが、ウォルター・ローリーの序文のあるオックスフォード刊の在庫がたまたまありましたので、本日書籍小包でお送りします。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
「ジョンソンのシェークスピア論」のことは、福原麟太郎『ヂョンソン大博士』(1969)に書かれている。

福原麟太郎も、また、作者(ヘレーン・ハンフ)と同じように、英文学を愛する愛書家だった。
『カンタベリー物語』の現代語訳版のようなものありますか? 気がひけることながら、私はチョーサーを一度も読んだことがないのです。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
イギリス文学に対する、あくなき探究。
『カンタベリー物語』につきましては、最高の学者でも現代英語になおすことは敬遠していたように思われますが、一九三四年にロングスマズ社から出た版が一つだけあります。これは『カンタベリー物語』だけを現代語訳したもので、訳者はヒル、これならまちがいないと思います。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
本書を読んでいるだけで、イギリス文学に対する興味関心が、強く惹起されてしまいそうだ(「ド・トックビルの『アメリカ紀行』、在庫あります?」「E・M・デラフィールドの『田園夫人の日記』がようやく手にはいりました」)。
つまり、本作『チャリング・クロス街84番地』は、イギリス文学への良き案内書としての役割を果たしているのだ(「バージニア・ウルフの『一般読者』二巻がいずれお手もとに届くと知ったら、きっとびっくりなさることでしょう」)。
時代を超えた読書家同士の心の交流
作品タイトル「チャリング・クロス街84番地」は、イギリスの古書店「マークス社」の住所のこと。
作者(ヘレーン・ハンフ)は、アメリカのニューヨーク(東九五丁目一四番地)から、「チャリング・クロス街84番地」と、手紙のやり取りを繰り返す。
愛書家の彼女は、決して、裕福なお金持ちではなかった。
交流当初の手紙には「みかん箱を積み重ねて作った私の本箱」という表現もある。
当時、彼女はまだ「台本のチェック係」にすぎなかったのだ(「今のわたしは週給四〇ドルのしがない台本チェック係なのよ!」)。
セーターもスラックスも虫食いだらけ。そのうえ、私の住んでいるアパートは、茶色っぽい砂岩づくりの五階建てで、日中は暖房なんてぜんぜんありませんの。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
彼女の書斎は「建物の正面の茶色の砂岩が崩れ落ちている、ひと間きりしかないあばら屋にある、中古のベッド兼ソファー」だ。
貧しい暮らしは、もちろん、ナチス・ドイツの空襲を受けたイギリスで、より深刻だった。
ところで、そのブライアンさんのお話ですと、お国では食糧が配給制で、肉は一週間に一世帯当り六〇グラム、卵は一カ月に一人当て一個なのだそうですね。ほんとうに、びっくりしました。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
連合国の勝利者とはいえ、アメリカとイギリスでは、戦後の生活に大きな差があったらしい。
私たち一同、お肉を見て目がクラクラしてしまいました。卵や缶詰もこのうえなくうれしいものです。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
ロンドン市民の苦境を知った作者は、マークス社宛てに食品を贈り始める。
もはや、古本屋と顧客との関係を越えた市民同士の交流が、そこには生まれていたのだ。
アメリカって国、イギリスが飢えているのにそれを放っておいて、日本とドイツの再建に何百万ドルもつぎ込んだりして、ほんとうに不誠実な国ですね。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
イギリス文学を愛する作者だから、イギリス国民に対する共感は、とても強いものだったのだろう。
20年という歳月の中で、彼らはたくさんの手紙を交わし合い、互いに年を取っていく。
そして、いつか訪れてみたいと憧れ続けていたマークス社(ロンドン)を、作者が訪れる日は、ついにやって来なかった。
何年か前、私の知り合いのある男性が、イギリス旅行をする人は、見ようという目的のものが必ず見られる、って言ったのを覚えています。で、私ならイギリス文学のイギリスが見たいわって言ったら、彼、うなずいて、あるともって言ってたわ。あるかもしれないし、ないかもわからない。今私がすわっている敷物のまわりをながめると、一つだけ確実なことが言えます。イギリス文学はここにあるのです。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
作者(ヘレーン・ハンフ)が、やがて、イギリスを訪れたことは、中公文庫増補版に収録された「『チャリング・クロス街84番地』その後」で知ることができる。
しかし、「『チャリング・クロス街84番地』その後」は、あくまでも後日譚であり、実際にはイギリスを訪れることができなかったというところに、この物語の意味がある(「イギリス文学はここにあるのです」)。
そして、古本に対する作者の熱い情熱。
私が古本の中でも特に好きなのは、前に持っていた方がいちばん愛読なさったページのところが自然にパラッと開くような本なのです。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
時代を超えた読書家同士の心の交流が、古書にはある。
私は見返しに献辞が書かれていたり、余白に書き込みがあるの大好き。だれかほかの人がはぐったページをめくったり、ずっと昔に亡くなった方に注意を促されてそのくだりを読んだりしていると、愛書家同士の心の交流が感じられて、とても楽しいのです。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
いわゆる「蔵書家」とは異なる「愛書家」の姿が、ここにはある。
本の中じゅうあちこちに鉛筆で薄くしるしをつけて、だれか後世の愛書家のために、いちばんよく書けているくだりを教えてあげることにしましょう。(ヘレーン・ハンフ「チャリング・クロス街84番地」江藤淳・訳)
あるいは、古書店との交流を編纂したこの書簡集そのものが、世界中の愛書家との心の交流を意味するものだったのかもしれない。
書名:チャリング・クロス街84番地(増補版)
著者:ヘレーン・ハンフ
訳者:江藤淳
発行:2021/04/24
出版社:中公文庫