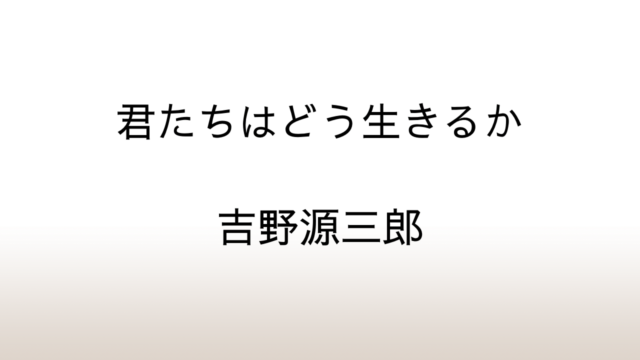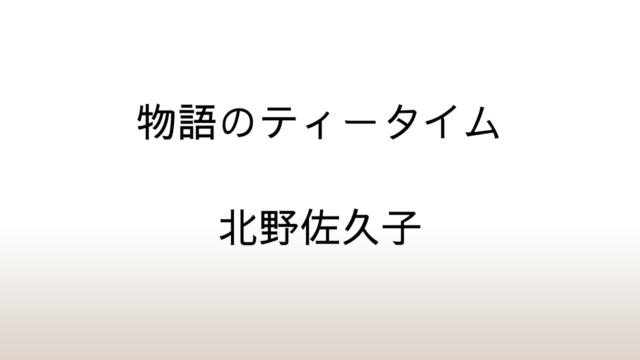小沼丹『藁屋根』は、1975年(昭和50年)10月に河出書房新社から刊行された短篇小説集である。
この年、著者は57歳だった。
収録作品及び初出は、次のとおり。
「藁屋根」
1972年(昭和47年)1月『文藝』
「眼鏡」
1970年(昭和45年)9月『文藝』
「竹の会」
1972年(昭和47年)6月『群像』
「沈丁花」
1975年(昭和50年)3月『文藝』
「キュウタイ」
1973年(昭和48年)6月『婦人之友』
「ザンクト・アントン」
1973年(昭和48年)7月『早稲田文学』
「湖畔の町」
1973年(昭和48年)1月『群像』
「ラグビイの先生」
1974年(昭和49年)10月『群像』
海外紀行と「大寺さん」もの
本作『藁屋根』には、計8篇の短篇小説が収録されている。
1972年(昭和47年)4月から10月まで、著者はイギリス(ロンドン)に滞在しており、ロンドン滞在の記録は『椋鳥日記』(1974)として発表されているが、本書収録の「キュウタイ」「ザンクト・アントン」「湖畔の町」「ラグビイの先生」の4作品は、イギリス滞在時の体験を素材としていることから、『椋鳥日記』のスピン・オフ的な作品と言うことができる。
また、「藁屋根」「眼鏡」「沈丁花」の3作品は、著者を投影した主人公(大寺さん)が登場する、いわゆる「大寺さんもの」シリーズの作品となっている。
残る「竹の会」は、恩師・谷崎精二の思い出を描いた作品である。
藁屋根 │ 盛者必衰の理
1972年(昭和47年)1月『文藝』初出の「藁屋根」は、大寺さんものとして第八作目の作品。
年譜の1943年(昭和18年)3月のところに「勤務校の学園長の長女丸山和子と結婚、後の作品「藁屋根」の舞台になる武蔵野市関前の大きな藁屋根の家に住む」とある(25歳だった)。
1945年(昭和20年)に疎開するまで、この藁屋根の家では、約2年間暮らした。
元は「銀行」だったという藁屋根の家の旧オーナーの没落を描いた作品だが、新婚当時の思い出を随所に挿入しながら、亡くなった先妻への温もりある愛情に満ちた物語となっ
ている。
「一朝眼醒むれば有名であった詩人の文句」とあるのは、19世紀イギリスの詩人バイロンの「ある朝目覚めてみると有名人になっていた」のこと。
寒い風の吹く夕方、大寺さんは単調な路を歩いていた。空も寒そうな浅葱色で、西の方に僅かばかり赤い色が残っている。向うから畑仕事を終えたらしい農夫がリヤカアを牽いてやって来て、擦違うとき、「――今晩は。寒いねえ……」と云った。(小沼丹「藁屋根」)
浮き沈みの激しい人の世のはかなさを描いている。
なお、終戦直後の暮らしについては、<吉野君>を主人公とする長篇小説『更紗の絵』に詳しい。

眼鏡 │ 新宿「蘭」のマダムの思い出
1970年(昭和45年)9月『文藝』初出の「眼鏡」は、大寺さんものとして第六作目の作品。
タイトルの眼鏡が進行係を務めながら、新宿「蘭」のマダムの思い出を綴っていく。
「大寺さんはその何年か前に病気になって、一年ばかり臥たことがある」とあるのは、年譜の1950年(昭和25年)「胸部疾患を得て、この前後より約一年間療養生活に入る」のこと。
「或るとき、或る所で大寺さんは凌霄花の花を見た」とあるのは、井伏鱒二や吉岡達夫と一緒に、波高島(はだかじま)の宿屋に泊まったときのことで(1952年7月)、短篇小説「凌霄花」に詳しい(『山鳩』所収)。
「埼玉の安行に行ったとき凌霄花の三尺ばかりの苗を何本か買って来て」というエピソードも、同じく「凌霄花」で描かれている(村上菊一郎や室淳介が一緒だった)。
「大寺さんの先生の所で、庭に土竜が出て困っていたことがあった」とあるのは、井伏鱒二のこと。
暗い店で小さな歌声を聴いていると、何だかいろいろ忘れていることがぐるぐると動き出すようであった。マダムは遠い所を見ているような顔で歌っていたが、その唄と共にマダムに何が甦ったのだろう?(小沼丹「眼鏡」)
「ロング・ロング・アゴオ」が、自殺したマダムへのレクイエムとして、素晴らしい役割を果たしている。
竹の会 │ 谷崎精二の思い出
1972年(昭和47年)6月『群像』初出の「竹の会」は、早稲田大学の英文学者・谷崎精二の思い出を綴った物語。
谷崎潤一郎の実弟・谷崎精二は、エドガー・アラン・ポーの翻訳者として有名(『ポオ小説全集(全六巻)』がある)。
谷崎潤一郎と谷崎精二との関係については、二人の末弟(谷崎終平)の『懐かしき人々─兄潤一郎とその周辺』に詳しい。

早稲田大学で谷崎精二の教え子だった小沼丹は、谷崎精二の推薦により、早稲田大学に就職している。
本作「竹の会」は、1971年(昭和46年)12月に谷崎精二が亡くなったことを受けて、追悼の物語として執筆された。
「竹の会」とは、終戦後に『早稲田文学』が廃刊になったとき、井伏鱒二の提案により開催された、谷崎精二を励ます会の名称である(青野季吉、保高徳蔵、浅見淵、逸見広、小田嶽夫、木山捷平、村上菊一郎、吉岡達夫、上林暁、新庄嘉章、結城信一、江戸川乱歩、火野葦平、横田瑞穂、岩淵鉄太郎、三浦哲郎などが参加していた)。
短い路に姿を見せては直ぐに消えてしまう通行人が、此方のそのときの気分に似つかわしい感じがしたのはどう云う訳かと思う。あんまり見ていると、谷崎さんがステッキを振って出て来そうだから戻ってきたら、着いた電車から降りて来た友人が、いや、どうも、と谷崎さんのような口を利いた。(小沼丹「竹の会」)
難しい性格の人だったから、随分迷惑も被ったらしいが、30年間の交流を、思慕の情を込めて追想している。
「竹の会」については、小沼丹と一緒に幹事を担当していた村上菊一郎にも、同様のエッセイがある。

「お墓の字を書く会」のことは、随筆「お墓の字」でも描かれている(『小さな手袋』所収)。

井伏鱒二が揮毫した谷崎精二の墓は、東京巣鴨にある慈眼寺の墓地に建立されている。

沈丁花 │ テニス仲間ケネディ君と、春子の肺炎
1975年(昭和50年)3月『文藝』初出の「沈丁花」は、大寺さんもの第九作目の作品である。
冒頭に「昔、大寺さんは郊外の大きな藁屋根の家に住んでいたことがあるが」とあり、本作「沈丁花」が、「藁屋根」の続編に位置するものであることが分かる。
「工員寮を改造した学校のなかに住んだ」とは、年譜の1946年(昭和21年)4月のところ「盈進学園に復帰。旧中島飛行機工場の工員寮を改造した校舎の元舎監の部屋に約二年間住む」とあるもの。
「ちっぽけな女の子」「春子」として登場しているのは、2歳の長女「諄子」だろう(次女「李花子」は、昭和21年6月誕生)。
テニス仲間ケネディ君の思い出と、春子の肺炎が、中心的なエピソードとなっている。
大寺さんのストオヴのある部屋の窓の外に、沈丁花が三、四株植えてあった。工員寮だった頃誰か植えたものらしいが、それが枯れずに残っていて、蕾を附けたから大寺さんは珍しいものを見る気がする。(小沼丹「沈丁花」)
沈丁花の匂いは、主人公にとって終戦直後の匂いでもあったのだ。
キュウタイ │ オーストリア旅行の思い出1
1973年(昭和48年)6月『婦人之友』初出の「キュウタイ」は、友人の吉岡達夫や「浩三」と一緒に、オーストリア・チロル地方のキュウタイを訪ねたときのことを題材とした紀行小説である。
「浩三」は「ドイツ語の先生」らしいから、早稲田大学のドイツ文学者(中村浩三)と思われる。
ヴェランダに出たら、夥しい星が散らかっているから吃驚した。ちょっと手で掻き寄せて掬ってみたい。文字どおり満点の星で、見ていると、ときどき長く尾を曳いて星が流れる。星空はこれ迄何遍も仰いだが、こんなに沢山星が出ていて綺麗な空は見たことが無い。(小沼丹「キュウタイ」)
年譜には、1972年(昭和47年)4月として「早稲田大学の在外研究員としてイギリスに渡り、約半年間、次女李花子とともにロンドンに滞在し、エディンバラ・ミュンヘン・チロル・パリなどを訪ねる」とある。
吉岡達夫と海外旅行をした思い出は、晩年の「トルストイとプリン」でも語られているものだ(『埴輪の馬』所収)。

ザンクト・アントン │ オーストリア旅行の思い出2
1973年(昭和48年)7月『早稲田文学』初出の「ザンクト・アントン」は、上記「キュウタイ」の続篇となる紀行小説である。
ただし、ドイツ語の先生(浩三)はミュンヘンへ帰ってしまったから、インスブルックからは、主人公(小沼丹)と吉岡達夫の二人旅である(二人ともドイツ語を話すことができない)。
ビイルを何杯か飲んでステエキを食ったら、それでも好い気分になって暫く吉岡と話をした。それから夜風に吹かれて宿に戻って、コニャックを飲んだ。森閑と静まり返って、何の物音もしない。(小沼丹「ザンクト・アントン」)
遠い異国の地を旅するときの、寂しくて不安な気持ち(つまり旅愁)が、よく伝わってくる。
なお、「ザンクト・アントン」とは、オーストリア・チロル地方の「サンクト・アントン・アム・アールベルク」のこと(「アルペンスキー発祥の地」として有名)。
短篇小説「胡桃」に登場する胡桃割は、ここザンクト・アントンで購入したものだった(『木菟燈籠』所収)。

湖畔の町 │ オーストリア旅行の思い出3
1973年(昭和48年)1月『群像』初出の「湖畔の町」は、上記「ザンクト・アントン」の続篇となる紀行小説である。
タイトルの「湖畔の町」とは、スイスのチューリッヒのこと。
「キュウタイ」「ザンクト・アントン」「湖畔の町」の3作品は、吉岡達夫とのヨーロッパ旅行三部作ということになる。
長い橋の途中で吉岡が写真を撮っているから辺りを眺めていると、先方から歩いて来た三十前后の女が通り過ぎて二、三米行ったと思ったらくるりと振向いて立停った。片手を腰に当がって此方を見る。ファッション・ショウの女性そっくりの恰好をしたから、何だか可笑しい。(小沼丹「湖畔の町」)
長篇紀行『椋鳥日記』にも言えることだが、小沼丹の旅行記は、淡々としているようで、しみじみと味わい深い名紀行文だ。
随筆も含めると、海外紀行は他にもあるので、一冊にまとめて読んでみたい。
どこかの出版社で企画してくれないものか。
ラグビイの先生 │ パブリック・スクールの思い出
1974年(昭和49年)10月『群像』初出「ラグビイの先生」は、湖水地方を自動車で旅行したときの思い出を綴った紀行小説である。
「ラグビイ」というのは、イングランドで最高峰のパブリック・スクール(名門私立学校)「ラグビー・スクール」のことで、トマス・ヒューズの長篇小説『トム・ブラウンの学校生活』のモデルにもなっている。

『トム・ブラウンの学校生活』は、庄野潤三『エイヴォン記』でも詳しく触れられている。

多分廊下を歩いてきたときだと思うが、「──あたし達のこと、秋山さんはあの先生に何て話したのかしら?」と娘が低声で冬木君に云うと、冬木君は、「──日本の学校の先生だとでも話したんですよ、だから、そう云うことにして、先生らしい顔をしていましょう」と、これも低声で答えていた。(小沼丹「ラグビイの先生」)
「秋山君」は「当方と同じ学校に勤めている」、つまり早稲田大学の教員だが、「冬木君」は「秋山君の知合で、日本の或る大会社の社員」であり、「会社から派遣されて、倫敦の大学で勉強している」ところだった。
湖水地方を回ってロンドンへ帰る途中、ドライブ旅行の進行係「秋山君」の提案で、一行はラグビイという町へ立ち寄る(主人公の娘のほかに、冬木君も一緒だった)。
トーマス・アーノルドの肖像画があったりと、イギリス文学の好きな人には興味深いエピソードが並んでいるのではないだろうか。
イギリス滞在時のその他エピソードについては、長篇紀行『椋鳥日記』に詳しい。

まとめ │ 円熟期の小沼文学に溢れる「寂しさ」
本書『藁屋根』では、大寺さんもの3作品と、海外紀行4作品、そして、井伏鱒二が実名で登場する「竹の会」の、計8作品を楽しむことができる。
テーマは、それぞれ異なるが、その作品にも、小沼文学にしかない寂しさがある。
この寂しさは、小沼文学に唯一無二のものであって、ここに小沼文学の神髄がある。
大寺さんものの「藁屋根」と「沈丁花」は続きものとして読むことも可能で、戦中戦後の武蔵野物語となっている。
もうひとつの大寺さんものである「眼鏡」は、亡くなった人へ捧げる追悼小説であり、まさに、小沼文学の王道とも言えるテーマを扱った作品だ。
谷崎精二の追悼小説である「竹の会」は、大寺さんものではないが、井伏鱒二や青野季吉、木山捷平など、多くの作家が実名で登場することで、生き生きとした文壇小説となっている。
年齢的には五十代半ば、円熟期に入った小沼文学を心ゆくまで楽しみたい。
作品名:沈丁花
著者:小沼丹
書名:藁屋根
発行:2017/12/08
出版社:講談社文芸文庫