小沼丹「小さな手袋」読了。
本作「小さな手袋」は、1976年(昭和51年)4月に小澤書店から刊行された随筆集である。
この年、著者は58歳だった。
庄野潤三と井伏鱒二
庄野潤三の随筆集『野菜讃歌』で、小沼丹の『小さな手袋』が紹介されている。
なお、この『清水町先生』を読んで、もっとほかに小沼丹の作品を読みたくなる人がきっといるに違いない。そういう方には、随筆集の『小さな手袋』と短篇集の『懐中時計』がどちらも講談社文芸文庫に入っているから、一読をお勧めしておきたい。(庄野潤三「師弟の間柄」)
もともとは、ちくま文庫版『清水町先生』の解説として書かれたものだが、『清水町先生』の次の一冊として『小さな手袋』をお勧めしているあたり、庄野さんらしいなと思う。
本作『小さな手袋』は、小沼丹最初の随筆集である。
いろいろな雑誌や新聞などに発表された短文を集めたものだから、幅広い時代のものを読むことができる。
全72篇で、一篇一篇が短いことも、庄野さんが気に入っている理由の一つかもしれない(庄野さんは、短ければ短いほど好きだと言っているので)。
その庄野さんが登場するものは二つあって、ひとつは「庄野のこと」という、そのものずばりの題名。
この一月、学校に出た日、教室から研究室に戻って来たら扉に小さな紙片が鋲で留めてある。穴八幡迄家内と参詣に来た序に寄ってみたが、授業中らしいので帰ると云う意味のことが書いてあって庄野の名前があった。(小沼丹「庄野のこと」)
「この一月」とあるのは、1974年(昭和49年)1月のことで、この随筆では、小沼さんと庄野さんとの親しい交際が、かなり丁寧に紹介されている。
もうひとつは「テレビについて」で、天狗太郎からテレビを購入した話を聞いて、自分も買ってしまうという話だ。
さらに、「──テレビは面白いですよ、横田さんも一つどうですか?」と、横田瑞穂にも勧めると、酔った勢いで、横田さんも買ってしまう。
それから、更に暫くして、或るとき庄野潤三と酒を飲んでいたら、庄野が云った。「──君は前に、テレビの店を横田さんに紹介した話をして、そのとき、僕にもどうかと云ったね?」「──そうだったかな?」「──それで、あれから慎重にうちじゅうで相談した結果、買うことにしたんだが……」(小沼丹「テレビについて」)
時代は1960年(昭和35年)、日本中にテレビが普及していった頃で、当時は白黒テレビが、まだ一般的だった。
ちなみに、横田瑞穂は「チェホフの葬式」にも登場しているが、チェーホフの話は「チェホフの本」でも語られていて、冒頭に登場する『露西亜三人衆』(新潮社の世界文学全集)は、庄野さんも『野菜讃歌』の中で触れている。

偶然かもしれないが、一定の年齢層の人たちには、影響のあった本なのかもしれない(訳は秋庭俊彦)。
庄野さん以上に登場するのが、師匠格の井伏鱒二だ。
将棋仲間でもあった井伏さんとの対局について、小沼さんは何度も随筆として発表している。
その裡に、「──原稿なんて、どうだっていいんだ」井伏さんは乱暴なことを云い出した。僕が盤の上に顔を出して考えていたら、井伏さんは、君、暗いよ、だから僕が負けるんだ、と云われた。(小沼丹「井伏さんと将棋」)
将棋に夢中になる井伏鱒二の姿をスケッチした作品として、「井伏さんと将棋」は、非常に有名な随筆となった。
荻窪で飲んでいる場面では、井伏さんの名前が出てくるのではないかと期待してしまう。
昔、最初にこの露地へ入ったのは、井伏さんのお供をして来たのである。そのころ、井伏さんは、後家横丁へ行こう、と云ってよくこの露地に来られた。後家横丁と命名したのは、井伏さんではないかと思う。(小沼丹「後家横丁」)
暗い狭い露地に入っていって「何だか十年二十年昔に逆戻りした気分になった」とあるのが、いかにも小沼さんらしい。
谷崎精二の墓石を揮毫する話を書いた「お墓の字」は名作。
今度墓を造りたいが、その墓の字は井伏鱒二氏に書いて貰いたい、君から宜しく頼んで欲しい。或る日、谷崎先生が僕を摑まえてそう云われた。縁起でも無い話だと思って変な顔をしたらしい。(小沼丹「お墓の字」)
嫌がる井伏さんも、最後には根負けして、お墓の字を揮毫することになる。
おかげで、僕たちは、谷崎精二のお墓参りをするたびに、井伏さんの字と会うことができる。

井伏さんの『仕事部屋』という作品集の初校原稿を製本した、世の中に一冊しかない珍本の話は「珍本」に書かれている。
井伏さんの「仕事部屋」と云う作品集は硲伊之助氏の装幀で、昭和六年に春陽堂から出版された。その本は持っているが、それとは別にもう一冊「仕事部屋」と云う本があって、これは日本に一冊しかない。(小沼丹「珍本」)
実は、伊馬春部が持っていたものを、酔った勢いで持ち帰ってしまったものらしいが、小沼さんとしては、まったく記憶がないという。
「誰がやったと言いました?」「とんでもない人だ」「ちょっと貸して呉れとあんたが強引に持去ったのだ」と、伊馬春部が怒る場面がいい。
昔、井伏さんからもらったむべのことを綴った「むべ」も楽しい。
いつだったか、井伏さんにお会いしたら、「──君、むべの葉は何枚になったかね?」と訊かれた。大いに面喰って考えてみたが判らない。井伏さんは嘆かわしそうな顔をして、僕は憮然とした。(小沼丹「むべ」)
井伏鱒二とか庄野潤三とか吉岡達夫とか横田瑞穂とか伊馬春部とか、仲間が登場する話は、大抵おもしろい。
仲間うちの飲みネタが作品になってしまうんだから、本当にすごい人たちだったのだろう。
懐かしい登場人物たち
小沼さんが太宰治と知己の仲になったのも、井伏さんの紹介だった。
いつだったか、井伏鱒二氏のお宅に伺ったとき、井伏さんはロシアの雑誌か何かを見せて下さった。記憶がはっきりしないので間違っているかもしれないが、多分プウシキン特集号みたいなものだったのではないかと思う。(小沼丹「母なるロシア」)
プーシキンが、自作の詩を朗詠している姿を見て、井伏さんは「──颯爽たるもんだね」と言った。
この後、太宰治の回想になって、「太宰治の初期の作品にはプウシキンの──と云うよりは「オネエギン」の影響が多分に見られるが、太宰さんは井伏さんに奨められてプウシキンを読み出したのである」と、小沼さんは綴っている。
太宰治最初の短篇集『晩年』は、「オネエギン」の影響が濃い作品集だ。

「片片草」という随筆では、太宰治の「新ハムレット」を読んで、シェイクスピアの「ハムレット」を読み直したという話も出てくる。
小沼さんにとって太宰治は、あくまで同時代作家の一人だったのだろう。
井伏さんのお供をして、伊豆の谷津へ旅行する話もいい。
翌日、修善寺へ出るので、湯ケ野でバスを乗り換えた。后に残る井伏さんは、湯ケ野迄送って来られた。引返すバスの方が早く出るので井伏さんは先に戻られたが、そのとき、狭い坂路を指して、「──この下の宿で太宰が原稿を書いたんだ」と云われた。(小沼丹「夾竹桃」)
太宰が湯ケ野で書いた作品は「東京八景」だったことを、小沼さんは帰ったあとで知る。
ここに登場する「夾竹桃の咲く宿」の話は、別に短篇小説の中でも挿入されていて、小沼さんの随筆には、小説の素材となっているエピソードも少なくないようだ。
「枇杷」は<竹林亭主人>こと、友人・玉井乾介のことを綴った作品。
「──いい墓を見せてやる」と云って、竹林亭お気に入りの墓の前へ連れて行って呉れたのを想い出す。「何とか子ちゃんのお墓」と書いてあったことしか記憶に無いが、多分小さな女の子の墓だったのだろうと思う。(小沼丹「枇杷」)
玉井乾介の案内で、早朝の雑司ヶ谷霊園を散策する話は、小説でも書かれている。
玉井乾介は「竜胆」にも登場していて、1971年(昭和46年)11月に「蔵王山麓の玉井の別荘へ遊びに行った」話が綴られている。
別荘に着いたら白石の料理屋からちゃんと料理が届いていて、即席ラアメンは影も形も見えない。ストオヴの暖い部屋で酒を飲み御馳走を食っていると、みんな昔の学生時代に戻るようで好い機嫌であった。(小沼丹「竜胆」)
石川隆士との交流を描いた「長距離電話」は、最後にオチがある楽しい随筆だ。
名古屋の新聞社が出たので、石川を呼んで貰うことにして此方の名前を告げて待っていると、「──やあ、もしもし、石川だ。暫くだなあ、元気かい?」と、石川が出てきた。何だか、いいことでもあったのか陽気な声で、知らぬ者がその声を聞いたら、かつて学生のころ世紀の憂鬱を独りで背負っているみたいな顔をしていた人間とはとても信じられないだろう。(小沼丹「長距離電話」)
実は「石川違い」なのだが、そのことに気づかない二人は、頓珍漢な会話を続ける。
わざわざ、新宿の樽平から、酔っぱらって長距離電話をかけるという始まりからして、期待されてくれるというものだ。
「或る友人」は、学生時代の仲間、小笠原貴雄への追悼記である。
学生時代の親しい友人に矢島と云う男がいて、その友人に小笠原と云う男がいた。矢島と小笠原は同人雑誌の仲間で、その雑誌を矢島から貰って初めて小笠原の名前を知ったのだろうと思う。(小沼丹「或る友人」)
「全然知らない裡に、知人がいつの間にかこの世から消えていた、と云うのは何とも妙に淋しい気のするもので、野村さんの文章を読んでから暫くぽかんとしていた」という最後の一文が小沼さんらしい。
友人の話は、まだある。
室君はフランス語の先生で、郊外の雑木林のなかに住んでいる。雑木林は庭であって、家を建てるとき、昔の儘の雑木林を切らずに残したのである。(略)一度は室君が散歩に出ようとしたら、若い女が用を足していて、これには室君も唖然としたらしい。(小沼丹「トト」)
身近な友人・知人の話を書くだけで、一篇の作品が生み出されていく。
そして、小沼さんの作品では、小説でも随筆でも、こうした身近な人が登場するものに、おもしろいものが多い。
それは、やはり、人間に対する(あるいは人生に対する)愛情のようなものが感じられるからではないだろうか。
小鳥の声を聴きに来て呉れと云うので、暮の一日、中君の所へ行った。中君は小鳥に熱中していて、三十羽近い小鳥を飼っている。それも洋鳥はいけない、和鳥に限ると云う。(小沼丹「鶯」)
植物や小鳥などをモチーフとする作品が多いことも、小沼さんの特徴の一つかもしれない。
「月桂樹」に登場しているのは、木山捷平。
まだ木山(捷平)さんが存命のころ、或る会で同席したら、君の所に月桂樹があるそうだが、それは雄か雌か? と木山さんに訊かれて面喰った。それ迄月桂樹に雌雄の別があるとは知らなかった。調べてみるといい、と木山さんは云ったが忘れている裡に木山さんは逝くなった。(小沼丹「月桂樹」)
「雨の降る日、傘を差してお葬式に行ったら、月桂樹の香が漾って来て木山さんの言葉を想い出した」とあるのは、植物を通して人間を語る、小沼文学の好例だろう。
名前は登場しないが、将棋好きの荻窪の寿司屋も出てくる。
或る晩、荻窪の寿司屋へ寄ったら、台の隅に将棋の雑誌が載せてあった。相変らずだな、と思って、「──少しは強くなったのかい?」と訊くと、主人が、「──いいえ、さっぱりです」と云った。(小沼丹「雨の夜」)
小沼さんの読者には懐かしい登場人物が、あちらこちらに顔を出す。
これも、小沼丹の随筆を読む楽しみの一つと言っていいのではないだろうか。
60歳目前で初めて出した随筆集
「障子に映る影」も、短篇小説になったエピソードだ。
まだ学生のころだが、矢張り障子に映る樹立の影をぼんやり見ていたことがある。しかし、このときは炬燵に当っていたのではない。伯母の一周忌か何かで寺の広い本堂に坐っていた。(小沼丹「障子に映る影」)
舞台となっているのは、品川の海晏寺というお寺で、「障子に映る樹立の影を見ていると、古い記憶が思い掛けなく顔を出すことがある。それは障子に映って消える小鳥の影のように、心の窓を掠めて消えて行く」という、小沼丹らしい文章で締めくくられている。
「大寺さんもの」を書き始めた頃のことについては「十年前」という随筆に詳しい。
一体どこで大寺さんを見附けたのか、どこから大寺さんが出て来たのか、いまではさっぱり判らない。日記に書いてあるといいが、備忘録も同然の日記だから、そんな面倒臭いことは一切書いていない。(小沼丹「十年前」)
この「十年前」は、小沼文学の転換点を示唆するものとして、重要な随筆となった。
「歌の本」は、中学生のときに先生だったヘルムさんの思い出を綴ったもの。
ヘルムさんがよく提案したのは、「漕げ、漕げ、ボオトを」と云うのであった。一組ずつ抜けて行って、最後の組の歌声が消えて行くと、ヘルムさんは如何にも満足そうに点頭いたりした。その歌詞は「流れを愉しく愉しくボオトを漕いで下りなさい、どうせ人の世は夢だもの」と云うのである。(小沼丹「歌の本」)
「漕げ、漕げ、ボート」の輪唱は、酔った庄野さんが宴席で好んだ余興でもあった。
随筆集の後半には、ロンドン滞在時の話が、まとまって収録されていて、『椋鳥日記』のスピンオフとして楽しめる。
スタツフオオドは「釣魚大全」の著者アイザツク・ウオルトンの生地である。だからと云う訳でも無いが、ウオルトンに敬意を表したつもりでスウプの他に魚料理を注文したらなかなか旨い。(小沼丹「ウオルトンの町」)
スコットランドへ旅行したときの話は、『椋鳥日記』には出ていないので、一連の随筆は貴重だ。

捨てるところがないという言葉があるけれど、小沼丹の『小さな手袋』は、本当に捨てるところがない随筆集である。
60歳を目前にして、初めて出した随筆集なんだから、相当に濃密なのも納得だろう。
上の娘の二人の子どもを綴った「コタロオとコジロオ」、散歩途中にある保谷の小学校が移転新築した「リトル・リイグ」、ギャルスケ夫人の『クランフォオド』を二冊持っているという「古い本」なども、特に好きな作品。
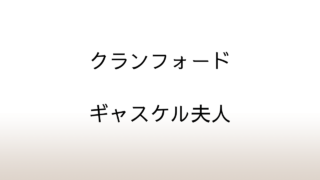
幸せな気持ちになれるという意味で、すごい随筆集だと思う。
書名:小さな手袋
著者:小沼丹
発行:1994/07/10
出版社:講談社文芸文庫



















