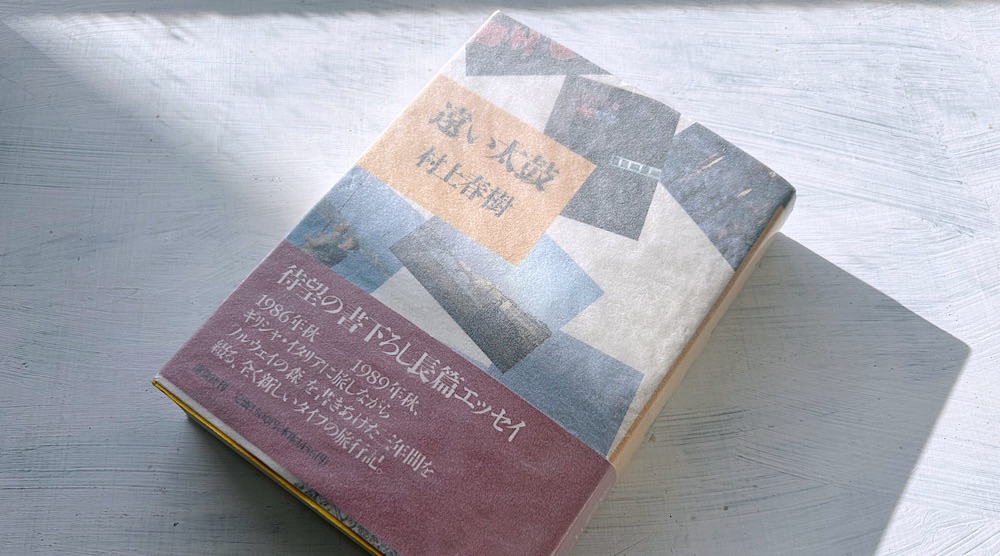村上春樹「遠い太鼓」読了。
本作「遠い太鼓」は、1990年(平成2年)6月に講談社から刊行された旅行記である。
この年、著者は41歳だった。
『ノルウェイの森』ができるまで
1986年(昭和63年)10月から1989年(平成元年)秋まで、村上春樹はヨーロッパで暮らしている。
理由は、日本にいては、おちおちと小説も書いていられない、と思ったからだ。
当時の村上春樹が置かれている状況を理解しないと、ここは理解しにくい部分かもしれない。
1985年(昭和60年)に『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』という長篇小説を発表した後、村上さんは、そろそろ次の長篇小説を書き始めるべき時期に来ていた。
喫茶店(ピーターキャット)を辞めて専業作家となり、『羊をめぐる冒険』を発表したのが、1982年(昭和57年)である。
『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』の青春三部作を乗り越える形で、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』を発表した村上さんは、作家として、さらなる次のステップへ踏み出そうとしていた。
当時(1985年)、村上さんは36歳で、40歳という人生の節目が迫りつつあった。
それは予感のようなものであった。でも三十も半ばを過ぎるころから、その予感は僕の体の中でどんどん膨らんでいった。だからこそ僕はそうなる前に、──僕の中で精神的な組み換えが行われてしまう前に──、何かきっちりとした仕事をして残しておきたかったのだ。もうおそらくこの先、こういう種類の小説は書かないだろう(書けないだろう)というようなものを書いておきたかったのだ。(村上春樹「遠い太鼓」)
「もうおそらくこの先、こういう種類の小説は書かないだろう(書けないだろう)というようなもの」は、結果的に『ノルウェイの森』(1987)という作品となって発表される。
さらに、1988年(昭和63年)、村上さんは、三部作の延長線とも言うべき『ダンス・ダンス・ダンス』を発表して、「初期の村上春樹」に決着をつけた。
この年、村上さんは39歳で、思惑どおり、40歳になる前に、大きな節目となる仕事を完成させたのだ。
その三年間に僕は二冊の長編小説を書いた。ひとつは『ノルウェイの森』であり、もうひとつは『ダンス・ダンス・ダンス』である。それから『TVピープル』という短編集も書き上げた。その他にも何冊かの翻訳の仕事をした。でもこの二冊の長編小説は、僕にとって三年間の海外生活におけるいちばん大事な仕事だった。(村上春樹「遠い太鼓」)
つまり、本作『遠い太鼓』は、作家・村上春樹が、どのような環境下で『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』を書いたかということのドキュメンタリーである。
読者によっては、こうした生活環境そのものを作品に投影して、深読み解釈をすることができるかもしれない。
日本を出発した頃、村上さんは神経症的に疲れていたらしい。
そんなこんなで、僕はすごく歳を取ってしまったような気がする。昨日は女房の誕生日だった。彼女の誕生日に我々は日本を出てきたのだ。時差の関係で、彼女はとても長い誕生日をもつことができた。とてもとても長い三十八回目の誕生日。僕が初めて彼女に会ったのは、僕らが二人ともまだ十八のときだった。(村上春樹「遠い太鼓」)
1986年(平成元年)10月4日、最初に彼らがたどり着いたのが、イタリアのローマだった。
僕は四十になる前に二冊の小説を書きたいと思っている。いや、思っているというよりは、書く必要があるのだ。それはとてもはっきりしている。でも僕はそれに手をつけることができないでいる。何を書けばいいのか、どう書けばいいのか、それもだいたいわかっている。でも書き出すことができないのだ、不幸なことに。(村上春樹「遠い太鼓」)
「蜂のジョルジュ」と「蜂のカルロ」が、頭の中でぶんぶんと飛び回る中(やはり病的だ)、村上夫妻はギリシア(アテネ)へ向かった。
ここからが、本当の旅行記の始まりである。
それは、頭の中に2匹の蜂を抱えた作家が復活するまでの再生物語でもある。
「蜂のジョルジュ」と「蜂のカルロ」は、構想段階から前へ進むことのできない2冊の小説のメタファーだったのかもしれない。
「だから君が問題にしているのは原則なんだろう? つまり──」「私が問題にしているのは」と彼女は僕の先取り的発言を払いのけるようにして言う。「そういうあなたの不注意なところなのよね。金曜日にちゃんと両替をすませておかなくちゃいけないというのは原則でしょう? そういうのをあなたはすぐに忘れちゃうじゃない。どうして普通の大人の男のひとみたいに、そういうことをきちんきちんと処理できないの?」(村上春樹「遠い太鼓」)
トラベラーズ・チェックを現金化するのを忘れていたことで、村上さんは、陽子夫人から厳しい攻撃を受ける。
この夫婦のやりとりは、本作『遠い太鼓』の中でも、ちょっとした見もののひとつで、まるで、村上春樹の小説を読んでいるかのような味わいがある。
ギリシャ語をうまく話せないということについても、陽子夫人の指摘は厳しかった。
「でもね、あなたずうっとギリシャ語の勉強をしていて何を覚えたのよ、いったい?」と女房があきれて言う。僕はギリシャに住みたくて、一年間週一回、明治学院大学のギリシャ語講座に通ったのだ。(村上春樹「遠い太鼓」)
陽子夫人が言っているのは、温水ヒーターのお湯や、まな板や漂白剤など、実生活上で必要となる、プラクティカルなギリシャ語のことだ(「じゃあ、それはもういいからゴミ捨てのことだけ訊いてよ。何曜日にゴミをどこに出せばいいか。それ、すごく大事なことなんだから」)。
オーストリアでアルプス越えをしている途中で自動車(ランチア)が故障したときも、陽子夫人は怒った。
「だからイタリア車なんて買わないほうがいいって言ったでしょう。どうせこんなことになると思ってたんだ。日本車かドイツ車を買えばよかったのよ。そうすればこんな馬鹿な目にあわなくて済んだのよ」(村上春樹「遠い太鼓」)
ちなみに、このときの海外滞在では、村上夫人(村上陽子)が写真を撮影していて、後に『風のなりゆき』(1991)という写真集を出版している。
ミコノス島のつつき鳥はほんとうに変なやつだ。ただつつくだけで飛びもしない。いつ会ってもひとりだし、友達だっていないみたいだ。つぎの年にひょっとしたらまだいるかなと思って来てみたら、同じのがちゃんといた。(村上陽子「風のなりゆき」)
まるで『ねじまき鳥クロニクル』(1994)みたいだけれど、この本の中に「村上春樹」は登場しない(ただ、陽子夫人の「名もなき夫」が登場するだけだ)。
村上春樹『遠い太鼓』とセットで楽しみたい作品だ。

ギリシャで、村上さんは(後に『ノルウェイの森』となる)長編小説を書き始める。
今回の旅行中に仕上げる予定でいるのは翻訳二冊ぶんと、旅行のスケッチ(今書いているような文章)と、それから新しい長編小説。だから決して暇ではない。自前の原稿をしばらく書いてそれに飽きると翻訳に移る。翻訳作業に飽きると今度はまた自前の原稿を書く。雨の日の露天風呂と同じである。(村上春樹「遠い太鼓」)
ギリシャ(スペッツェス島)では、ひどい嵐に遭って部屋に閉じ込められ、町中の石塀が崩壊するのを見た。
なにしろ、ギリシャには、嵐で壊れない石塀を作ろうとする習慣がないらしい。
「何年後かに大雨が降ったら」と僕は言う。「あれ、また崩れるね」「崩れたら、あれまた作るね」と女房が言う。そう、彼らはそれをもう何千年も繰り返してきたのだ。僕はやはりギリシャ人にはなれそうもない。(村上春樹「遠い太鼓」)
翻訳をひとつ仕上げたときはミコノスにいた。
僕はここでC・D・B・ブライアンの『グレート・デスリフ』という小説の翻訳を仕上げた。けっこう長い小説だったのだけれど、面白い話だったし、とにかくこれを早く仕上げて自分の小説にかかろうと思って、こつこつと毎日翻訳を進めていた。この頃はまだワードプロセッサーを使っていなかったから、大学ノートに万年筆でぎっしりと字を書いていた。(村上春樹「遠い太鼓」)
村上春樹・訳の『偉大なるデスリフ』は、1987年(昭和62年)11月に新潮社から刊行された。
当時の僕は、都会派の小説みたいなものに、けっこう強く心を惹かれていたと思う。(村上春樹「村上春樹翻訳ほとんど全仕事」)
『偉大なるデスリフ』を翻訳している間、『ノルウェイの森』は村上さんの脳内で待機していたわけで、「その頃にはその小説が書きたくて、僕のからだはどうしようもなくむずむずしていた」「からだが言葉を求めてからからに乾いていた」とある。
この小説はのちに『ノルウェイの森』になるわけだが、このときにはまだタイトルもついていない。四百字詰めで三百枚か三百五十枚くらいのさらっとした小説にしようというくらいの軽い気持ちで書き始めたのだが、百枚くらい書いたところで「こりゃ駄目だ、とても三百、四百じゃ終わらない」とわかった。以来翌年(一九八七年)の四月まで、シシリー、ローマと移動しながら小説漬けの生活にのめり込んでいくことになる。(村上春樹「遠い太鼓」)
ミコノスで村上夫妻は、一か月半を過ごした。
そして荷物をまとめながらふと思う。この一か月半という歳月は俺にとっていったい何だったんだろう、と。この季節外れのエーゲ海の島で、俺はいったい何をやっていたんだろう。しばらくのあいだ、それについて何も思い出せない。本当に思い出せないのだ。(村上春樹「遠い太鼓」)
神経症的な村上春樹が、ここにも顔を覗かせている。
僕は旅行のスケッチのような文章を幾つか書いた。翻訳も仕上げた。長編小説の最初の何章かを書いた。悪くはない成果だと思う。でもそれにもかかわらず、ある意味では僕は失われてしまっている。(村上春樹「遠い太鼓」)
つまり、『ノルウェイの森』を書く作業というのは、それほどに苦しい作業だったのだろう。
そう、僕の小説には暗い雨の匂いと、激しい夜中の風の音がしみついてしまっている。ロシア戦線ほどじゃないにせよ、それはそれなりにちょっとした戦闘だったのだ。ねえ君、それは違うんだよ。君が掘り返しているのは僕の死体じゃない。僕と似てはいるけれど、それは僕じゃない。君は僕のことを少し誤解しているんだ。(村上春樹「遠い太鼓」)
一時期、『ノルウェイの森』には、『雨の中の庭』という仮タイトルが付けられていたという。
『ノルウェイ』の主人公(ワタナベ君)に、自分自身を投影する作業は、作家としてもしんどいものだったのかもしれない。
『ノルウェイの森』は、シシリーに生活の舞台を移して書き続けられる。
そんな街に一ヵ月住んだ。そしてそのあいだずっと『ノルウェイの森』を書いていた。その小説のだいたい六合めくらいまではここで書いた。(略)毎日小説を書き続けるのは辛かった。ときどき自分の骨を削り、筋肉を食いつぶしているような気さえした。(村上春樹「遠い太鼓」)
「それでも書かないでいるのはもっと辛かった」と、村上さんは続けている。
『ノルウェイの森』の世界は、もちろん、楽しい世界ではない。
それは、損なわれてボロボロになる男の子の物語なのだ。

『ノルウェイの森』が完成したのは、イタリア(ローマ)だった(「ヴィラ・トレコリ」という名前のホテルに宿泊していた)。
小説の第一稿は三月七日に完成した。(略)講談社の出版部の木下陽子さんに電話をかけて、小説がいちおう完成したことを連絡すると、四月の初めにボローニャで絵本の見本市があって、講談社の国際室の人が行くので、そこで原稿を直接手渡してもらえるとありがたいのだがということであった。なかなか面白い小説になったと思うよ、と僕が言うと、「えー、九百枚もあるの? 本当に面白いんですか?」と疑わしそうに言う。(村上春樹「遠い太鼓」)
10月はじめに日本を脱出してから、約5か月で、一本の長編小説を書き上げたことになる。
ノートやレターペーパーに書いた原稿をボールペンで書き直し(第二稿は三月二十六日に完成)、さらに細かい修正を施して、『ノルウェイの森』というタイトルを付けたのは、ボローニャのブックフェアへ行く二日前のことだった。
あるいはこれは文学史に残るような立派な作品にはならないかもしれない、でも少なくともそれは僕自身なのだ。もっと極端に言えば、その小説を完成させなければ、僕の人生は正確にはもう僕の人生ではないのだ──(村上春樹「遠い太鼓」)
『ノルウェイの森』の原稿を渡したあとの旅行記は、一転して(まるで憑き物が落ちたかのように)からっと爽やかなものになる。
作家にとって、小説というのは、本当にカタルシスのようなものなのかもしれない。
『ダンス・ダンス・ダンス』と「村上春樹現象」
1987年(昭和62年)の4月をギリシャ(パトラス)で過ごした村上夫妻は、再び、ミコノスへと舞い戻る。
でも参ったことには、僕らが着いた翌日からミコノスはすっかり冬に逆戻りしてしまったのである。僕はしっかりと泳ぐつもりで水着の用意をしてきたのだが、風が強くて寒くて、とても泳ぐどころではない。(略)しかたないので部屋で本を読んだり、スコット・フィッツジェラルドの『リッチ・ボーイ』を翻訳したりしていた。(村上春樹「遠い太鼓」)
村上春樹・訳の『リッチ・ボーイ』は、1988年(昭和63年)4月にTBSブリタニカから刊行された『ザ・スコット・フィッツジェラルド・ブック』に収録されている。
クレタ島の小さなホテル(グリーン・ホテル)の食堂には、世界中のバックパッカーたちが読み捨てた本が置かれていた。
それから新潮社から送ってきた新潮文庫の新刊『象工場のハッピーエンド』安西水丸・村上春樹著、もここに置いていく。これだけいろんな本があるんだから、日本語の本が一冊くらいあってもいいだろう。クレタ島の山あいの小さな村の小さなホテルの食堂の終末的にひっそりとした汚い本棚にも。(村上春樹「遠い太鼓」)
1987年(昭和62年)の初夏、村上さんは久しぶりに日本へ一時帰国している。
一九八七年の初夏にほぼ一年ぶりに日本に戻った。『ノルウェイの森』のゲラに手を入れるためだ。猜疑心の強い講談社の木下陽子さん(本人はそんなことないと主張するけれども)も「うん、とても面白かった」と言ってくれた。(村上春樹「遠い太鼓」)
ポール・セロー『ワールズ・エンド』と、ブライアン『偉大なるデスリフ』の翻訳ゲラをチェックしたのも、このときで、1987年(昭和62年)の後半には、『ノルウェイの森』と合わせて、3冊の本が出版された。
再び、日本を脱出してヘルシンキに入ったのは、1987年(昭和62年)9月はじめのことである(一時帰国の時期が意外と長い)。
寒いフィンランドをあっという間に通り過ぎて、ローマへ戻った村上さんは、『ダンス・ダンス・ダンス』の執筆作業に取りかかる。
僕はここにいる間にいくつか翻訳の仕事をしたし、『ダンス・ダンス・ダンス』という長編小説を書き上げることもできた。仕事の面では順調に捗ったと思う。四十歳を前にして、まずまず満足できる仕事ができたと思う。(村上春樹「遠い太鼓」)
ただし、実際に小説を書き始めるのは、もう少し先の話だ。
でも悪い気はしない。前には港がある。後ろには山がある。ホテルの部屋に帰れば、ワインとパバドプロスのクラッカーがある。そして僕には今のところ考えなくてはならないことが殆ど何もないのだ。マラソンは走り終えたし、航空券は払い戻してもらった。小説はもう書いてしまったし、次の小説までにはまだ少し間がある。(村上春樹「遠い太鼓」)
アテネ・マラソンを走り終えた後の解放感が、そこにはある。
レスボス島で過ごす時間もいい。
誰かが僕らの絵を描いてくれないかな、と思う。故郷から遠く離れた三十八歳の作家とその妻。テーブルの上のビール。そこそこの人生。そしてときには午後の日だまり。(村上春樹「遠い太鼓」)
印象的なのは、ホテルの奥さんとの会話だ。
「お子さんはいらっしゃらないの?」とふと思いついたように彼女は尋ねる。いない、と僕らは答える。彼女は僕らの様子を見て、それからにっこりと笑う。「でもまだお若いですものね」(村上春樹「遠い太鼓」)
いろいろな意味において、四十歳というのは、人生の大きな節目だったのだろう。
『ダンス・ダンス・ダンス』を書き始めたとき、季節は冬になっていた。
年も押し迫った十二月十七日から『ダンス・ダンス・ダンス』という長編小説を書き始める。(略)『ノルウェイの森』とは違って、『ダンス・ダンス・ダンス』の場合は書き始める前にまずタイトルが決まった。(村上春樹「遠い太鼓」)
「ダンス・ダンス・ダンス」の出典は、ザ・デルズという黒人バンドの古い曲である(ビーチボーイズではない)。
この小説は始めから終わりまでだいたいすんなりと気持ち良く書けたと思う。(略)隅から隅まで僕自身のスタイルの文章だし、登場してくる人物も『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』と共通している。だから久し振りに自分の庭に戻ってきたみたいで、すごく楽しかった。(村上春樹「遠い太鼓」)
番外編だった『ノルウェイの森』と違って、『ダンス・ダンス・ダンス』は、伸び伸びと楽しく執筆している光景が目に浮かんでくるような小説だ。

ただし、小説の執筆環境として、冬のローマは、少々寒すぎたらしい。
僕はあまりに寒いのでオーバーコートを着て机に向かい、ぱたぱたとワードプロセッサーのキーを叩きつづけた。シシリーで『ノルウェイの森』を書いたときとは正反対である。(略)今回は寒くて、ワードプロセッサーのキイを打ちそこねるくらいである。(村上春樹「遠い太鼓」)
熱帯への希望が『ダンス・ダンス・ダンス』という小説の中にハワイが登場する原因となったらしい(確かに、主人公とユキのハワイ行きは唐突感があった。雪の北海道から春の東京、そして、常夏のハワイ)。
三年間にわたるヨーロッパ滞在の中でも、この冬が最悪の時期だった。この年の冬に起こった良い事は、小説が完成したことだけだった。だから僕は『ダンス・ダンス・ダンス』という小説のことを思うたびに、ローマのあのマローネさんの寒い家のことを思い出す。そして、そうだそうだ家の中でオーバーコートを着てこの小説を書いたんだなあと思う。(村上春樹「遠い太鼓」)
『ダンス・ダンス・ダンス』を書き上げたのは、ロンドンのワールズ・エンドにある部屋だった(ポール・セロー『ワールズ・エンド』の舞台)。
僕はこの部屋で『ダンス・ダンス・ダンス』という長編小説を書きあげた。ラジオ・カセットで音楽を聞き、窓の外のアビーロードを眺めながら、来る日も来る日もワープロのキイをぱたぱたと叩きつづけた。(村上春樹「遠い太鼓」)
そして、無事に『ダンス・ダンス・ダンス』を完成させたあとに、あの空白の1988年(昭和63年)がやってくる。
四月に僕は日本に戻り、既に印刷所から届けられていた『ダンス・ダンス・ダンス』のゲラをチェックした。それからTBSブリタニカから『スコット・フィッツジェラルド・ブック』というフィッツジェラルドについての文書と翻訳を集めた本を出し、運転免許を取った。(村上春樹「遠い太鼓」)
『ダンス・ダンス・ダンス』を書きあげた後の虚脱感は、日本に戻った後に「混乱した無力感」へと移行していく。
ふりかえってみると、この年は我々二人にとってはそれほど良い年ではなかったように思う。日本に戻ると、『ノルウェイの森』は大ベストセラーになっていた。ずっと外国にいてよく事情がわからなかったせいもあるのだけれど、久しぶりに日本に戻って自分が有名人になっていることを知って、僕はなんだか愕然としてしまった。(村上春樹「遠い太鼓」)
1988年(昭和63年)の秋には、『ダンス・ダンス・ダンス』もベストセラーとなる。
いわゆる「村上春樹現象」が、日本中を席巻していた。
すごく不思議なのだけれど、小説が十万部売れているときには、僕はとても多くの人に愛され、好まれ、支持されているよう感じていた。でも『ノルウェイの森』を百何十万部も売ったことで、僕は自分がひどく孤独になったように感じた。(村上春樹「遠い太鼓」)
本人不在の中で、バブル時代の日本では「村上春樹」をめぐる狂騒曲が巻き起こっていたのだ。

再び、病的な何かを抱えた作家は、1988年(昭和63年)8月、奥さんを日本に残して、再び、単身でローマ入りする(夫人とは10月にローマで合流した)。
でも僕が回復したのは、小説を書くひとりの人間として本当にきちんと回復できたのは、おそらくティム・オブライエンの『ニュークリア・エイジ』という小説の翻訳を終えてからである。(略)この『ニュークリア・エイジ』の翻訳作業は僕にとって精神的リハビリ以外の何ものでもなかった。(村上春樹「遠い太鼓」)
村上春樹・訳の『ニュークリア・エイジ』は、1989年(平成元年)10月に文藝春秋から刊行された(「残念ながらこのティム・オブライエンの小説は思ったほど売れなかった」)。
1989年(平成元年)は、40歳を迎えた村上春樹にとって、回復の一年となる。
損なわれては回復し、ということを、作家の村上春樹は繰り返していたのだ(まるで小説の主人公の「僕」のように)。
失われた自分を取り戻すうえで、ローマ生活は正解だったのかもしれない。
夫婦を縛り付ける何ものも、その街にはなかったから。
やがてそんな夏も終わり、人々がぽつぽつと街に帰ってきた。車も増え始め、またたく間に道路は車でいっぱいになった。(略)またいつものローマが戻ってきたのだ。僕は窓からそんな街の風景を眺めながら何本か短編小説を書いた。やっと小説を書こうという気になってきたのだ。短編を一気に書き終えると、いくつか翻訳をした。そうこうするうちに、僕らがローマを引き払う日が近づいてきた。いよいよ日本に戻るのだ。(村上春樹「遠い太鼓」)
1986年(昭和63年)の秋から始まったヨーロッパ生活は、1989年(平成元年)の秋に終わりを告げる。
37歳だった村上さんは、40歳になっていた。
本作『遠い太鼓』は、ヨーロッパ滞在の紀行文だけれど、本当は、ヨーロッパで暮らしている村上春樹という一人の作家の内面を綴った物語だったのではないだろうか。
「蜂のジョルジュ」と「蜂のカルロ」は、無事に村上さんの頭の中から旅立っていった(『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』という二つの小説に姿を変えて)。
この本は、ただの旅行記として読むべきではないと、僕は思う(単行本の帯にも「全く新しいタイプの旅行記」と書かれていた)。
『遠い太鼓』は、村上さんの心の中を旅する旅行記だったのだ。
『ノルウェイの森』と『ダンス・ダンス・ダンス』、そして、80年代の村上春樹現象。
そのとき、村上春樹という作家の中で、いったい何が起こっていたのか?
村上春樹という作家の変容を理解するうえで、一つの手がかりが、このエッセイ集の中にはある。
それは、80年代を生きた小説家自身の、損傷と回復の物語だったのかもしれないのだ。
書名:遠い太鼓
著者:村上春樹
発行:1990/06/25
出版社:講談社