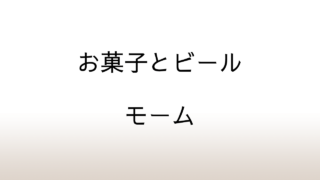ジャック・ロンドン「どん底の人びと」読了。
1902年(明治35年)の夏、アメリカの作家・ジャック・ロンドンは、イギリスのロンドン(イースト・エンド)にある貧民窟に潜入し、このルポタージュを書き上げた。
当時のジャック・ロンドンは、『荒野の呼び声』などの短篇小説で国民的な名声の高い小説家となったばかりで、ロンドンのスラム街探訪は、アメリカの出版社の支援を受けての海外取材だった。
1902年のイギリスは、エドワード七世の戴冠式で賑わっていたが、ジャックはあえてスラム街の中に身を投じて、そこで暮らす人々を客観的に描いている。
ロンドンに到着したジャックは、すぐに拠点となる下宿を探し、古着を手に入れて、浮浪者へと身を化す。
アメリカ人のジャックは、牛運び船でイギリスに渡ってきた船乗りとして、イースト・エンドで暮らし始めるが、スラム街の生活は想像を絶するほどに悲惨を極めており、時にジャックは潜入取材を中断して、貧民窟から脱出しなければならないほどだった。
浮浪者に身をやつしたジャックは、本物の浮浪者たちと行動を共にしながら、スラム街の実情を詳細に記録していく。
路上では真昼間から酔っぱらいの女性同士が殴り合いの喧嘩で騒ぎ、公園には行き場のない浮浪者たちが芝生で寝転んでいる。
当時のロンドンでは、浮浪者の存在を認めていないため、夜間に路上や公園で寝ることは禁止されていた。
浮浪者の人々は、長い夜を歩きながら過ごし、夜が明けた後になって公園で休むことが許されるのだという。
「あそこにいる女たちは三ペンス、いや二ペンス、あるいは古パン一個ででも体を売るんだ」と、地元の浮浪者が笑って教えてくれた。
屋根のない夜は想像以上に厳しく、ジャックも救貧院を訪れるが、あまりにも多くの浮浪者が集まってくるため、救貧院に宿泊することができる浮浪者も限られている。
ひとつの救貧院で断られた浮浪者は、さらに別の救貧院を訪ね歩き、運が悪ければ夜通し歩き続けるしかない。
ようやく救貧院に泊まることができても、食事はスキリー(オートミールを熱湯で溶いた流動食)で、まともな人間なら飲み込むことさえ難しいから、初めての利用者は大抵半分以上を食べることはできない。
若くて外国人だからという理由で、偽物の浮浪者となったジャックに、スラム街で暮らす貧民は優しくて親切だったが、救貧院や俘虜収容所で働く職員や路上を見回る警察官、喫茶店の店員たちからは、同じ人間とは思われない侮蔑的な扱いを受けた。
あくまでもジャーナリストの視点を失わずに「取材」に徹したジャック・ロンドンは、イギリスの首都ロンドンのひとつの地域で起きている現実を、冷静に、客観的に、社会科学者の目を持って考察している。
貧民窟で暮らす人々に対する哀れみや同情は含まれているにしても、感情に流され過ぎることはないし、感傷的な表現は抑制されている(アメリカ人らしい比喩は散見されるにしても)。
イースト・エンド滞在中に書いたジャックの手紙には「イースト・エンドという人間の地獄にいてすっかり気が滅入っています。目撃した身の毛のよだつような事柄は、この目で見たのでなければ、真実に存在するとは到底信じられません」とあり、実地体験型だったジャックの取材は、やがて、新聞雑誌などに掲載された報告書や統計などの研究へとシフトしていった。
貧民窟で生きる者の生活の断片をジャックは体験できたかもしれないが、そこで生き続けることの本当の苦しみにまでたどり着くことはできたのだろうか。
書名:どん底の人びと
著者:ジャック・ロンドン
発行:1995/10/16
出版社:岩波文庫