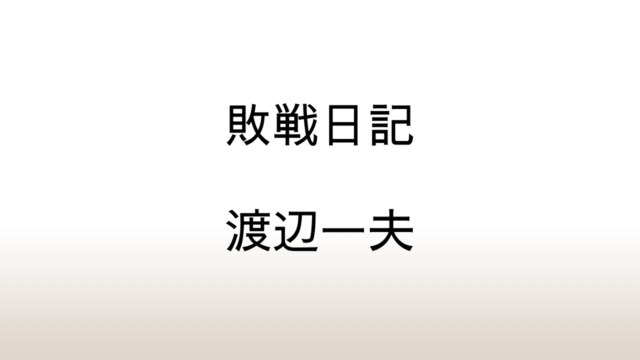戸板康二「女優のいる食卓」読了。
本書は、演劇評論家・戸板康二の随筆集で、1963年(昭和38年)から1965年(昭和40年)までにかけて発表された作品が収録されている。
1960年代前半のソヴィエト旅行
第一部が海外紀行、第二部が風物詩、第三部が身辺雑記と、大雑把に分けると、そのような構成になっている。
表題作「女優のいる食卓」は、俳優と一緒にソ連東欧西欧を周遊する「日本演劇視察図」に参加した際の紀行文で、東山千栄子や杉村春子、岸輝子、村瀬幸子、長岡輝子、波野久里子などの女優の名前が登場する。
「女優は老いも若きも、いかにも舞台に立つ人らしく、自分を着かざることに陶酔している。男子たちとくらべれば当然、荷物の数が多かったが、みんな食卓に着て出る服装の、ちょっとしたアクセサリひとつにも、とりどりの好みが見られて、それを眺めるだけでも、うれしかった」とあるのは、華やかな女優と一緒に食卓を囲むことの楽しさを率直に表したものだろう。
何と言っても、1960年代前半のソヴィエト旅行の話だから、異国情緒の趣が深い。
モスクワでは、アルメニヤ産のコニャックが今でも時々おもい出すように、おいしかったが、ホテルでは、もっぱらシャンパンを抜いた。いよいよ、ロシヤを離れる前夜も、岡田嘉子さんが来て、シャンパンをご馳走になった。今は演出家の岡田さんだが、あい変らず若く、みずみずしい表情を保っている。黒いドレスの岡田さんが一人加わって、女優の食卓はさらに華やかになった。(戸板康二「女優のいる食卓」)
こうした海外紀行を読むだけでも、本書を開く価値があると思う。
第二部は東京の風物詩を季節順に綴ったもので、著者の思い出と現代とが巧みに交錯する。
著者は1915年(大正4年)生まれなので、紹介されているエピソードは大正から昭和初期にかけてのものが多い。
例えば「雪」という作品では、昭和十一年の二・二六事件の日には慶応本科の一年生で、万葉集の試験を受けていたという思い出が紹介されている。
さらに、この年は、その月に初めごろに、もっとすさまじい大雪があって、全市が停電となり、電車も停まってしまったという。
雪をモチーフにして描く画家として小絲源太郎が有名だが、「二十世紀の東京では、近代的な建築を雪と結びつけて見るのが、むしろ名所らしいともいえる」と、著者は締めくくっている。
「五月」という作品では、高浜虚子の「三越の屋根より見たり労働祭」という俳句を紹介したり、「お会式」では、谷崎潤一郎の「母を恋ふる記」を引用してみたり、「文化の日前後」では、永井荷風の文化勲章受章に触れてみたりと、文学的な挿話を交えながら、東京の風物詩がリズミカルに綴られてゆく。
十二月二十四日がクリスマス・イブで、銀座通りはむやみに人が出る。この二・三年イブは家にいることにしているが、それはある年の混雑に懲りたからである。イブは、バー・キャバレーがシャンペンもしくはそれに似たびんを抜いたり、へんな帽子をお客にかぶせたりして、ある時期までは終夜営業で、朝がえりの客のオーバーのポケットから、テープのきれっぱしがぶら下がっている天下泰平の風景も見られた。そういうイブのセットになっているサービスは、土産にくれる洋菓子のように、無味乾燥で、とてもいただけない。(「戸板康二「クリスマス」)
随所に昭和の風景が描かれていて、こんな随筆を読んでいるだけで、何だかホッとして、疲れた心が癒されていくような気がする。
「下人の行方は、誰も知らない」
第三部に収録されている「ラスト・シーン」は、「小説ならば、むろん、最後の行が、鍵である」と、芸術作品におけるラスト・シーンの重要性を説いた作品だが、ここでは、芥川龍之介の「羅生門」が紹介されている。
「下人の行方は、誰も知らない」は「羅生門」の終わりの一行だが、芥川の処女出版『羅生門』(阿蘭陀書房)に収録されている「羅生門」の終わりは、「下人は、既に、雨を冒して、京都の町へ強盗を働きに急いでいた」となっていた。
「下人」の行方が分かっていては、文学作品として詰らないのであって、「下人の行方は、誰も知らない」で終わっているからこそ、「羅生門」の文学的価値があると、著者は主張している。
もちろん、芥川龍之介も同じことを考えて、書き改めたものだろうけれど、文学作品の最後の一行の重さというものを教えられたという意味では、非常に楽しい随筆であった。
書名:女優のいる食卓
筆者:戸板康二
発行:1984/8/15
出版社:三月書房「ルビー選書」