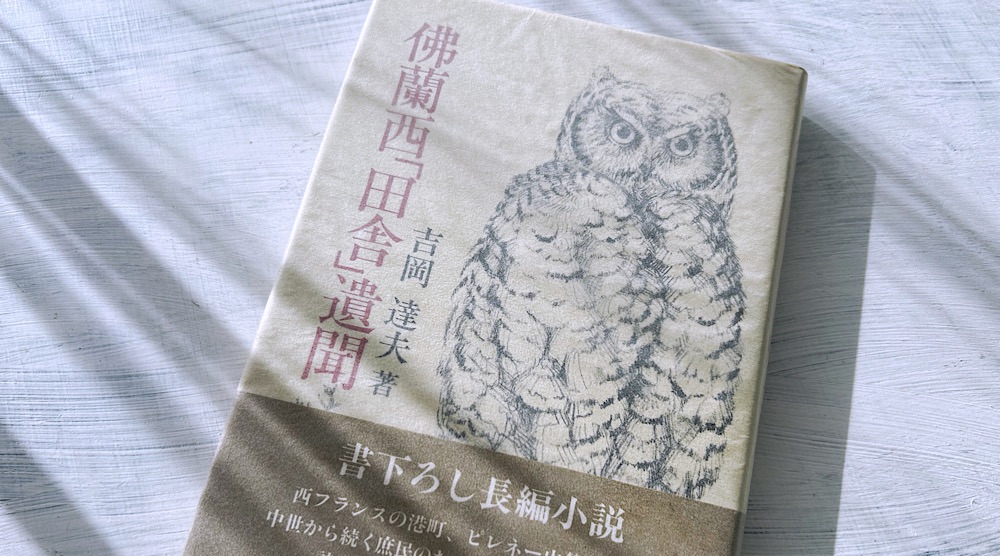吉岡達夫「仏蘭西「田舎」遺聞」読了。
本作「仏蘭西「田舎」遺聞」は、1981年(昭和56年)4月に評伝者から刊行された長篇小説である。
この年、著者は64歳だった。
バイヨンヌからサン・ジャン・ド・リューズまで
庄野潤三『せきれい』で、小沼丹の訃報を庄野さんに知らせてくれたのは、吉岡達夫だったことが書かれている。
夕方、吉岡達夫から電話かかり、「小沼が昨日のお昼、十二時半に病院で肺炎で亡くなった。家族だけで葬儀をすませて、小沼はもうお骨になって家に帰った。さっき、奥さんから電話があった」という。(庄野潤三「せきれい」)
吉岡達夫は、早稲田大学で小沼丹や武田繁太郎らとともに、文芸誌『文学行動』を拠点に活動していた作家である。
2004年(平成16年)に未知谷から『小沼丹全集』が刊行されたときには、庄野潤三や三浦哲郎とともに、吉岡達夫の名前も監修者として並んだ。
小沼丹の作品にも、ちょいちょい登場している(「鶺鴒」では、井伏鱒二らと一緒に埼玉県弘光寺を訪ねた)。
小沼丹とは「二十四年に武蔵野市の住人になって以来、家が呼べば答えるほどの近くだったので、長いつき合いであった」らしい(『小沼丹全集』監修の辞)。
本作『仏蘭西「田舎」遺聞』は、1981年(昭和56年)に刊行された、吉岡達夫の長篇小説である。
もっとも、単行本の帯には「書下ろし長篇小説」とあるが、むしろ、優れた紀行エッセイとして評価したい内容の作品だった。
8月下旬、物語の語り手<私>(著者だろう)は、中世の外科医<シォーリアク>の足跡を求めて、ピレネー山麓のバスク地方を訪ねる。
シォーリアクは、1348年にヨーロッパで黒死病(ペスト)が大流行したとき、治療に当たった外科医の一人である。
一三四八年に黒死病(ペスト)がヨーロッパに流行したとき、アビニヨンにも大勢の患者が発生した。町のほとんどの医者たちがアビニヨンを逃れて安全な土地に避難したが、シォーリアクは町にとどまって患者の手当てをした。手当てをした患者の一人に、イタリアの詩人、ペトラルカの愛人ラウラがいた。(吉岡達夫「仏蘭西「田舎」遺聞」)
中世ヨーロッパの医者の話だから、理解が難しいのではないかと思ったけれど、専門的なことはほとんどなかった。
シォーリアクは旅先案内人であって、要は、バスク地方の歴史紀行ということなのだろう。
HOTEL・REGINO<女王>は四階建の二つ星の小さなホテルで、玄関口の石の鴨居に1782と年号が刻んであった。二百年も昔に建てたホテルは、玄関を入るとうす暗い長い廊下がつづき、廊下の突き当りが二十坪ほどのロビーで、四階まで吹き抜けになっている。(吉岡達夫「仏蘭西「田舎」遺聞」)
物語は、著者がバイヨンヌの町へ向かうところから始まり、ウスタリッチを経由して、<小さな港町>サン・ジャン・ド・リューズで「聖バルテルミー祭」を見学するところでクライマックスを迎える。
巻末に「塔のある町」「巡礼の町」「城のある町」の三作品が「小さな町・三景」として併録されていて、これも南ヨーロッパを旅したときのことを綴った、読み応えのある紀行文だった。
中世ヨーロッパから現代バスク地方まで
ピレネー山麓のバスク地方は、フランスとスペインの国境にある地域の名称で、ビスケー湾に面した小さな港町バイヨンヌは、フランス・バスク、つまり、西フランスの国境の町ということになる。
バスク地方の紀行文を読むのは、もしかすると、これが初めてかもしれない。
サント・マリ寺院の回廊の壁には、黒死病(ペスト)の記念碑がはめ込まれている。
中庭の回廊の記念碑はペストで死んだ七三二人のバイヨンヌ市民の供養のモニュメントで、大理石のパネルには一三五一年十月と刻んであった。黒死病がヨーロッパ全土に蔓延したのは一三四八年の春から翌年の秋にかけてのことであったから、このモニュメントはペストが終熄して二年後、日本流では三周忌に造られたことになる。(吉岡達夫「仏蘭西「田舎」遺聞」)
新型コロナが終息したばかりの時代に、これを読むと、ペストの大流行は、決して歴史の中の都市伝説ではないことが分かる。
このとき死んだ一人の若い美女と詩人、そして外科医の三角関係が、このバスク紀行を瑞々しい物語にしていると言えるかもしれない。
中世を生きた人々の伝説を辿ってゆく中で、著者は、多くの地元の人たちとすれ違っていく。
停留所の標識棒に、「ニーヴ橋」と書いてある。その前で、手押車に大きな蔓籠をのせた麦わら帽子をかぶった娘が運転手に声高に話しかけている。バスク語で話しているらしく、何を言っているのか私には判らないが、運転手は乗車口まで出て行って、娘から蔓籠を受け取ると、重そうに郵便袋のそばにおいた。(吉岡達夫「仏蘭西「田舎」遺聞」)
実は、バスク地方の人々の何気ないスケッチこそが、本作『仏蘭西「田舎」遺聞』の、最大の味わいなのではないだろうか。
そういう意味で、この物語は、やはり、優れた紀行エッセイだと思う。
そして、西フランスのスケッチは、単なる素描に留まらない膨らみを文章に湛えている。
バスは土手にそった道を西に向って走り、土手の向うに低い屋根の農家が見える。この土地では住居も什器も、そして、生活の仕きたりも昔のままで、私たちニッポン人がすでに失ってしまったものを、いまだに大事にし、粉ひき亭も、ブイヨットのおかみさんも、この土地に誇りをもちながら精一杯に生きているようであった。(吉岡達夫「仏蘭西「田舎」遺聞」)
この本を読んで、西フランスへ行ってみたいと思わなかったら、それは嘘だろう。
本作『仏蘭西「田舎」遺聞』は、中世ヨーロッパと現代バスク地方のいずれにも、大きな関心を向けさせてくれる、素晴らしい紀行エッセイなのだ。
書名:仏蘭西「田舎」遺聞
著者:吉岡達夫
発行:1981/04/25
出版社:評伝者