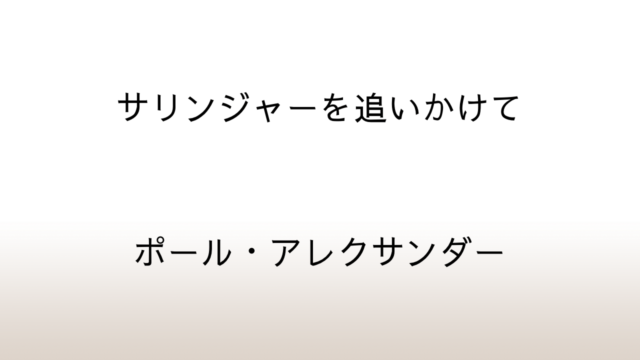「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』読了。
本作『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』は、2006年にユビキタ・スタジオから刊行された対談集である。
この年、村上陽子は58歳だった。
素顔の村上春樹
「覆面雑談」の「あのひと(Yさん)」とあるのは、村上春樹の妻(村上陽子)である。
「覆面雑談」とは言いながら、自分の素性を完全に隠そうという意図は感じられない。
対談の中では「部数の出る、海外への翻訳も多い小説家の妻」として紹介されている。
夫なんか見てるとほんとに忙しいと思う。朝起きるとすぐ仕事するでしょ。書く量が多い方じゃないから、みんなそう感じないかもしれないけど、仕事が丁寧だし、やっぱり時間がかかると思う。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
「日本語」についての対談とは言いながら、内容的には夫婦生活に関するものが圧倒的に多い。
つまり、この本は、村上陽子による村上春樹夫妻に関する対談なのだ。
うちの夫はほら、関西の人だから、何か見つけて間食をするときに、「あ、虫養いだ」なんて言って食べてる。(略)夫はそう言えばね、その昔、隠元豆を丼一杯茹でてね、「虫養いをする」と言って食べてた。それから、カリフラワーも、山ほど。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
関西では「間食すること」を、普通に「虫養い」と言うらしい(「関西では普通の言葉みたいよ」)。
OL。だからならなかったじゃない。そういうことは最初から考えなかった。お店を始めたのは、さっき言ったように、団塊の世代だから、「自由」というものを一番目に持ってきたのね。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
早稲田大学在学中に学生結婚をした村上夫妻は、国分寺駅南口でジャズ喫茶『ピーター・キャット』を始める。
経営者という職業は、決して楽な商売ではなかったらしい。
まんじりともしないことは、けっこうあった。「明日までにあのお金を」というのは、けっこうずっとあったし、ほんと最近だよね。余裕が出てきたのは。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
村上春樹のエッセイでお馴染みのエピソードも、ちょくちょく登場している。
お金がないときに、道でお金拾ったことはあるけれど。×万円。明日振り込まなきゃならない×万円で、どうしようと思って下見たら×万円落ちてた。でもそういうのってわりとあるんですよね。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
夫(村上春樹)が専業作家になった後は、共同経営者として夫のサポート役を務めた。
夫の仕事上、アメリカでも出版社の社長の家でパーティーする、とかありますよね。そこに来るのはいろんな作家とかで、ほとんどはその日だけで、あとで会う機会があるわけではない。そこで何か、その場限りで話す、そういうのがわりに好き。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
村上春樹が創作に専念する上で、陽子夫人の果たす役割は大きかった。
夫の小説に対する理解は、もちろん深い。
夫の場合は、外から肥やしを持ってくるんじゃなくて自分の内側を開拓しているようなものですから、方向性が違うんですね。どちらかって言うと、領域を広げるというよりは、求心的。自分の脳みそを発掘していけば、古代の記憶だってどこかに埋まってるわけですよね、細胞の中に。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
『ノルウェイの森』をはじめ、村上春樹の小説には性的な描写が多かった。
性的な描写についても、夫婦間で会話をしている。
夫の小説は、セックスがいろんな形で出てくるでしょ? それで私聞いたことがあるのよ。なんでそんなに出すのか、って。そうしたら、「わかんない」って言うの。「考えたこともないんだよ。とにかく出てくるんだ」って。それで、そのときに思ったのかな。セックスってなにかの鍵なんですよね。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
人間の深いところと関係しているセックスは、「なにかの鍵」だったのだ。
その「何かとは何か?」を探求していくのが、村上春樹の小説だったのかもしれない。
自分を見ると、他人は見えるの。ある時そう思った。自分の井戸を掘っていって、水脈に当たると、他人の井戸とも繋がる、という、あの話。自分を深く掘らなければ、決して他者とも通じない。ほんとうの意味では。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
『ねじまき鳥クロニクル』では、井戸の底へ降りることによって主人公は、行方不明となった妻の心と繋がっていく。
こういう会話を読むと、村上陽子さんは(ある意味において)村上春樹の創作活動においても共同経営者だったように思われてくる。
陽子夫人と議論していく中で、作家・村上春樹が気づくものも多かったのではないだろうか。
近所の人とも親戚とも親とも、うまく行ってなかった。(略)親戚にも、冠婚葬祭には一切行かない、と言ってある。あるとき、お葬式で、これってすっごいばかばかしいと思って、行けなくなったの。死んだあとでいろいろ言うの聞いてると、じゃ、なんで生きてるうちにしてあげなかったのよ、とか思って。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
『ダンス・ダンス・ダンス』に、母(アメ)の恋人(ディック・ノース)が交通事故で急死する場面がある。
霊感少女(ユキ)が「生きてるうちにもっと優しくすべきだった」と後悔したとき、主人公は13歳の少女に対して本気で怒った。
そんなエピソードを思い出す会話だ。
『ノルウェイの森』のガールフレンド(小林緑)には、女子大生時代の高橋陽子の面影が投影されている。
私は、アメリカが帝国主義だと言われても、歴史の授業で習ってきた帝国主義と、いろいろ違う点がある気がした。でも先輩たちは、それを説明してくれずに、前提なしで「アメ帝」と言う。私が歴史上の帝国主義との違いを聞くと、馬鹿にしたような顔をされる。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
小林緑と同じように、高橋陽子も東京の(「お嬢様学校」と呼ばれる)女子校の出身だった(「私は四ツ谷の高校だったから」「女子校だし、男の先生は少ないんだけど」「高校までは周りにお金持ちが多かったから大変だった」)。
もちろん、高橋陽子は小林緑ではない。
夫に、君のことを小説にしたら一ページで終わっちゃう。何でも直ぐに決めるから、と言われる。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
身の回りの素材を、作品の中に投入していく。
村上春樹にとっては、それが、小説家としての在り方だったのだろう。
「夫(村上春樹)は死ぬまで現役」だと、妻は言う。
リタイア、うちはないですよね、夫はね。死ぬまで現役。うちの場合リタイアっていうのはたぶん、人を使わなくていいくらいに仕事が縮小していった時かな。そんなに遠くないと思うけど。だって、若い人あんまり夫の本を読まないと思うよ。もう。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
この対談集の発行後、村上春樹は『1Q84』(2009)や『街とその不確かな壁』(2023)など、代表作にもなり得る長篇小説を発表している。
村上春樹のリタイアは、まだまだ先のことになるのだろう。
村上春樹に子どもがいない理由
村上春樹夫妻に子どもがいないことを不思議に思う読者は多いらしい。
デビュー当時から、子どものことは話題になった。
村上春樹には、なぜ、子どもがいないのか?
私は「子ども的なもの」に興味がないのよね。たとえば、「子猫=可愛い」とは思わない。齢取った猫の方が、個別性があって味がある。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
もちろん、「子ども」と「猫」とは異なるはずだ。
私が子どもの頃夢だったのは、孤児院をつくること。それは、別に子ども好きだったからではなく、単純なことで、親がいない子が差別されるんだったら、じゃあ全部の子を養子に取っちゃえばいいんじゃないか、って。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
「子どものいない人にはわからないだろうけど」などと主張する人とは相容れなかった。
そういう人は、何か自慢したい気持ちがあれば、そこに子どもをひっぱって来る。そういうものを必ずもっているから、何かしら、「あなたにはわからない」と、自分を特権化するのよ。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
そもそも、親子の繋がりには懐疑的だった。
だって、つながりようがないじゃない。自分っていうのは、全く自分だけだと思っているから。死後に、誰にも憶えていてもらわなくても構わない。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
「子どもがいないこと」をネガティブには捉えない村上陽子の生き方が伝わってくる。
それは、価値観の共有を大切にする生き方にもつながっている。
親戚で、付き合わなくなっていく人を、懐かしいとあまり思わない。「血は水よりも濃い」の反対で、血が薄いの。価値観も違っているしね。べつに会いたい人いないな。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
夫・村上春樹を誰よりも知るのは、妻・村上陽子だった。
なにか嫌なこととか辛いことがあったときには、「それには意味がある」と考える方ですね。うちの夫は、自分たちの起こったことの「意味」についてなんて全く考えない人なので、その補償的な意味もあるかな。役割として。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
のんびりとした夫と、ちゃきちゃきとした妻という夫婦関係が、そこからは浮かんでくる。
とにかくあの人は、そこにある、それを、ある意味で受け入れる、ということかな。あまり、ものごとにコメントしないのよね、だいたいが。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
夫にやきもきさせられることは多い。
約束忘れるし、時間忘れるし。もの忘れるし。「これとこれをしなきゃいけないんだから出かけるわよ。用意して!」とか、いつもやってる。やきもきします。「鍵持った?」とか。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
スピード感というか、生きるリズムが、夫婦の間では異なっている。
きょとん……とするのは向こう(夫)ですね。ほんと、「お前とぼけてるんじゃないだろうな」と言いたくなるくらい。話してても、すぐどっか行っちゃうのね、頭が。私が文句言ってる最中でもそうなって、「聞いてなかったんでしょ!?」「きょとん」となる。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
そんな夫との夫婦の絆は強かった。
「結婚は早い方でしたよね?」という質問に、Yさん(村上陽子)は「直観で決まった」と答えている。
うん。直観で決まった。それで、経済的にどうこうということは全く考えないで、わりとすぐした。当然、家族の賛成は得ていない。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
もちろん、それは「盲目的な愛」ではない。
だから、私はとてもクール、というか、ものすごく愛してても、絶対に、批判は持ってる、というと変だけど……盲目的になれない。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
スタイルの異なる二人の夫婦生活だったから、危機は何度もあった。
彼はけっこう好き勝手に育ってきたようだから、はじめはびっくりしたみたい。共同生活のルールに。だから、「いつでも最後通牒」よ。だって私「退がらない」から。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
夫婦の愛情は、相手と闘う中で深めてきたらしい(さすがに「団塊の世代」だ)。
愛情は手塩に掛けて育てたわけじゃないよ。闘って来たんです。相手と闘うことによって、愛を深めてきた。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
もしも、夫が先に死んだら「一緒に死にます」と言う。
一緒に死にます。って言うか、気持ち的にそうかな。生きていたとしても、心は死んでいる。それに、実際そんなに長く生きないんじゃないかな、私も。そうなったら。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
対談全体を通して、村上陽子という一人の人間の生き方が理解できる、濃密な内容の発言が、あちこちにある。
それは、夫・村上春樹(の作品)を知る、ひとつの切り口にもなるかもしれない。
村上陽子は、かつて『風のなりゆき』(1991)という写真集を出版したことがある。

夫と一緒に旅行する中で撮影した写真をまとめたものだったが、主体的な表現活動は続かなかった。
なぜ何かしないのか、とよく言われるけれど、自分の人生を全うする以上の自己表現はない。(「あのひと」+ユビキタ・スタジオ『覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語』)
あるいは、村上春樹の小説そのものが、村上陽子にとっての表現活動でもあったのではないだろうか。
この対談集を読み終えたとき、なんとなく、そんな気がした。
書名:覆面雑談 あのひとと語った素敵な日本語
著者:「あのひと」+ユビキタ・スタジオ
発行:2006/01/15
出版社:ユビキタ・スタジオ