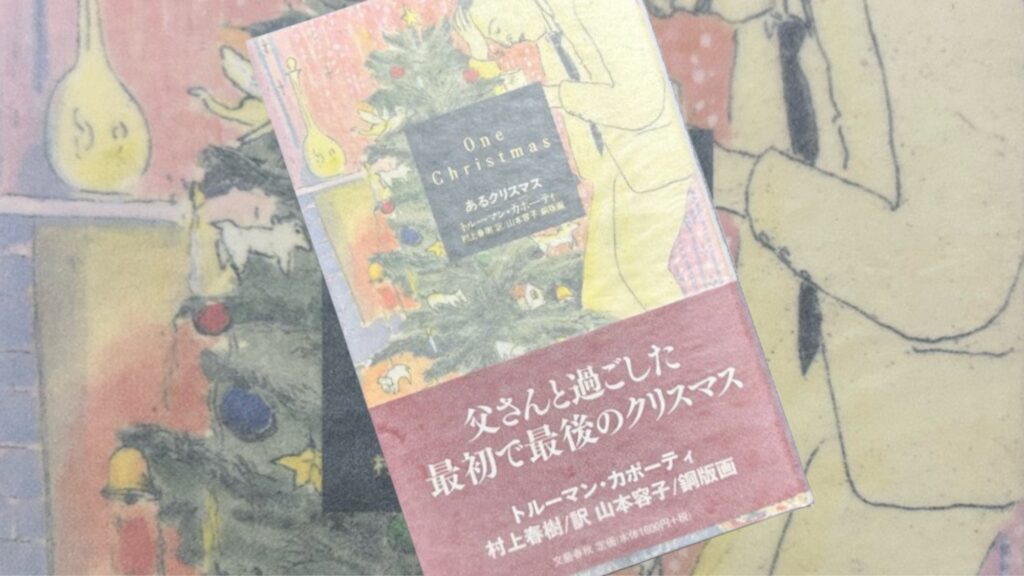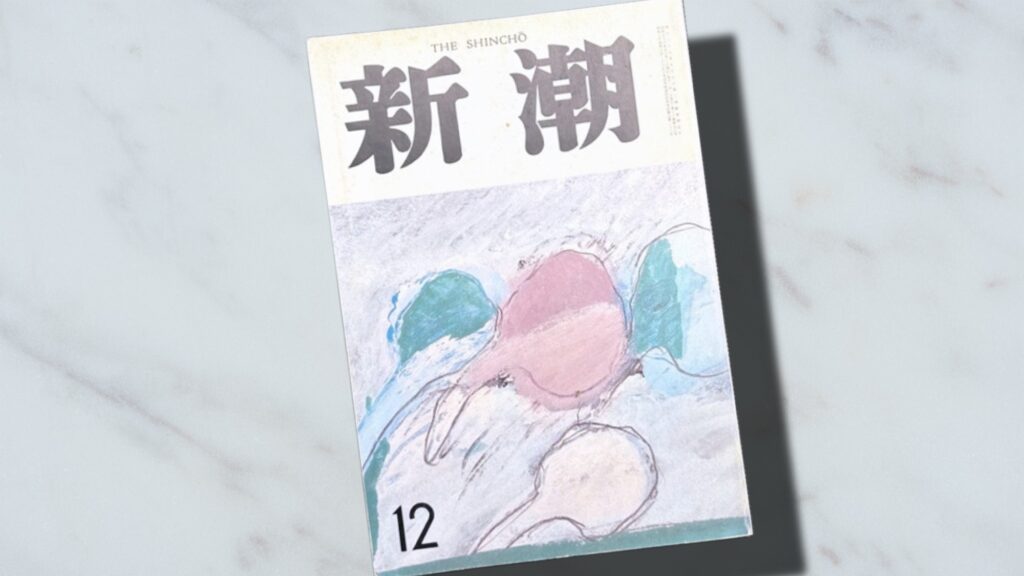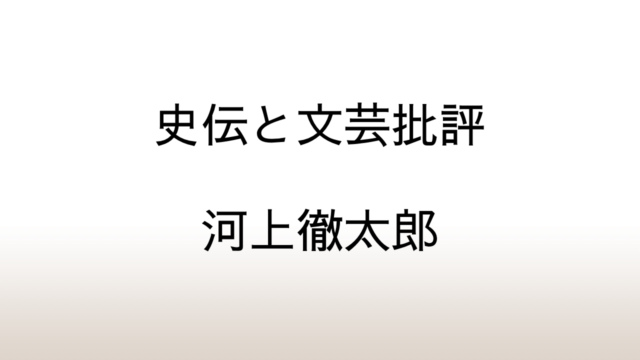トルーマン・カポーティ「クリスマス三部作」読了。
カポーティのクリスマス三部作とは、『クリスマスの思い出』『あるクリスマス』『おじいさんの思い出』の3つの短編小説のこと。
村上春樹・訳、山本容子・銅版画により、それぞれ単行本化されている。
少年の日の美しいクリスマスの思い出
「クリスマス三部作」という言葉を使っていたのは、銅版画家(山本容子)だ。
この展覧会は、1988年に再びカポーティ作品をテーマに作品をつくるきっかけになった。 それは現在も刷数を重ねている「おじいさんの思い出」「あるクリスマス」「クリスマスの思い出」(文藝春秋)の本の仕事だった。 村上春樹さんが訳したこの本は、カポーティの少年時代がテーマになっている。クリスマス三部作だ。(山本容子美術館「映画 トルーマン・カポーティ 真実のテープ」)
いわゆる「カポーティのイノセント・ストーリー」シリーズの作品群である。
原題と発表年は、次のとおりとなる。
クリスマスの思い出
・A Christmas Memory(1956)
あるクリスマス
・One Christmas(1982)
おじいさんの思い出
・I Remember Grandpa(未発表)
トルーマン・カポーティは、1958年(昭和33年)に代表作とも言える『ティファニーで朝食を』を出版しているが、短篇「クリスマスの思い出」は、「ティファニー」とほぼ同時期に書かれた作品だった。
日本語訳としては、新潮文庫版『ティファニーで朝食を』(龍口直太郎・訳、1968)に収録されているので、「ティファニー」とともによく知られるカポーティ作品である。
その後、1990年(平成2年)になって、村上春樹・訳、山本容子・銅版画の単行本『クリスマスの思い出』が出版されて、この作品の人気は決定的なものとなった。
村上春樹の解説にあるとおり、この作品に描かれているのは「完璧なイノセンスの姿」である。
「ねえ、ごらんよ!」と彼女は叫ぶ。瞳はシェリー酒色で、見るからに内気そうである。「フルーツケーキの季節が来たよ!」(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
そのとき、作者であるトルーマン少年は7歳で、最愛の親友(スック)は60歳を超えるお婆さんだった。
両親から離されて、アラバマ州モンローヴィルの親戚宅に預けられたトルーマン少年にとって、スックは確かに「親友」だったに違いない。
(スックは)三人のなかでは精神的にも気持の上でも一番若かった。太り気味で白髪を短く刈りこみ、とても子供っぽかったせいで、多くの人から知的障害があると思われていた。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
まるで幼い少女のようなスックは、主人公(バディ少年)と一緒にクリスマスのためのフルーツケーキを作る。
彼らにとって、それが「冬の始まり」の楽しみだったから。
十一月のある朝がやってくる。すると我が友は高らかにこう告げる。「フルーツケーキの季節が来たよ! 私たちの荷車を持ってきておくれよ。私の帽子も捜しておくれ」と。(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
物語は、少年の日の美しい思い出に満たされている。
少年バディと、老女スックと、そして愛犬クイーニーとで築かれた、純粋無垢な遠い思い出の日々に。
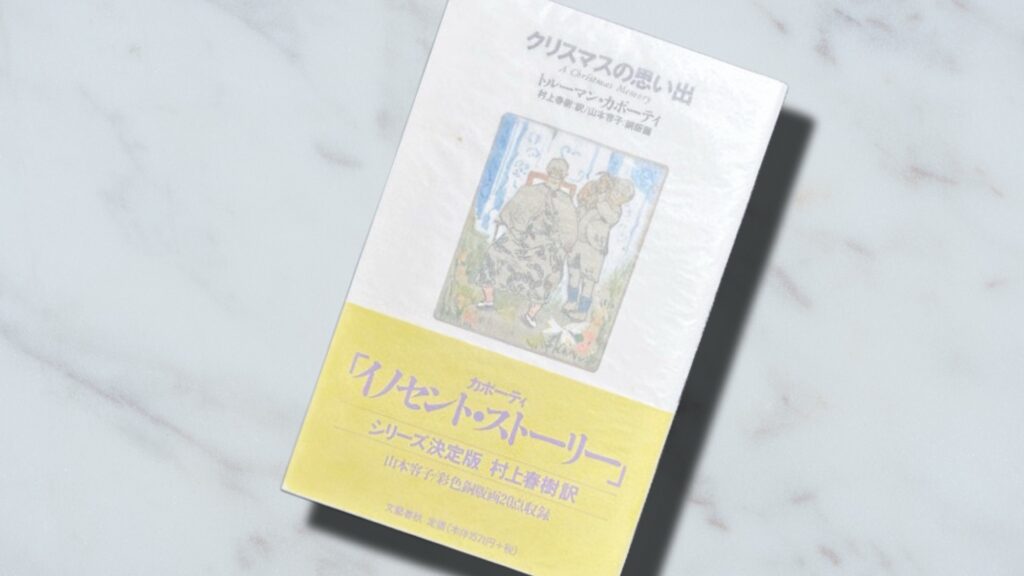
美しい思い出は、カポーティの繊細な文章によって克明に再現されていく。
「ツリーは子供の背丈の倍はなくちゃいけないよ」と我が友は思慮深げに言う。「そうでなくちゃ、子供はてっぺんの星を取っちゃうからね」(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
まるで子供のようにはしゃいで(ケーキづくりで残ったウイスキーを飲んだ)スックは、二人の姉から叱られる。
「泣かないで」と僕は頼む。僕は彼女の足の指をいじり、両脚をこちょこちょとくすぐる。「もう大人なんだからさ、泣いちゃいけないよ」「私が泣くのは大人になりすぎたからだよ」と彼女はしゃくりあげながら言う。「年とってもちっともまともになれないからだよ」(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
少女のように繊細すぎるからこそ、スックは傷つきやすかった。
クリスマス・ツリーの準備を整えた彼らは、次に、クリスマス・プレゼントを用意する。
もちろん、彼らにお金はない。
「欲しいものがあるのにそれが手に入らないというのはまったく辛いことだよ。でもそれ以上に私が頭にくるのはね、誰かにあげたいと思っているものをあげられないことだよ」(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
慎ましい暮らしの中で、彼らはクリスマスを楽しんでいた。
つまり、彼らは(バディとスックとクイーニーは)「幸せ」だったのだ。
「お前の手も以前はもっとずっと小さかったような気がするねえ。お前が大きくなっていくのは、あまり嬉しくないね。お前が大きくなっても、私たちはずっと友達でいられるだろうかねえ」(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
いつまでも少女のままで生きるスックと違い、バディは少しずつ成長していた。
やがて、彼はスックのもとを離れ、寄宿学校へと入れられる。
そして、十一月のある朝が訪れる。木の葉も落ち、鳥も消えてしまった、冬の訪れを知らせる朝だ。それなのに彼女は身を起こして「ねえ、ごらんよ、フルーツケーキの季節が来たよ!」と叫ぶことはできない。(トルーマン・カポーティ「クリスマスの思い出」村上春樹・訳)
最愛の親友(スック)と過ごした最後の「クリスマスの思い出」を、大人になったバディは(つまりトルーマンは)懐かしく思い出している。
この美しい小篇は評価も高く、朗読会でも人気の作品となった。
1966年(昭和41年)に『冷血』が出版されたとき、『クリスマスの思い出』も箱入りの特装版で出版された。
「まじめな作家は金儲けをすべきではないとされているが、そんなことはくそくらえだ。ぼくの次の本は『クリスマスの思い出』というタイトルだ。四十五ページの長さで、値段は五ドル。その金額だけの値打ちは充分にある。手始めに、みなさんどうですか」(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
確かに、それだけの価値がある短篇小説だった。
書名:クリスマスの思い出
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:村上春樹・訳、山本容子・銅版画
発行:1990/11/25
出版社:文藝春秋
野崎孝・訳の「あるクリスマス」
「あるクリスマス」は、未完となった長篇『叶えられた祈り』を除くと、トルーマン・カポーティ最後の作品である(初出は『レディース・ホーム・ジャーナル』1982年12月号)。
既に全盛期を過ぎたカポーティにとっては、この小品さえも大変な仕事だったらしい。
彼にとってはせいぜいいらざるお節介をやくことくらいで、どうにか書き上げたごくごく短い作品『あるクリスマス』や回想風のコラムですら、彼自身の動かしがたい疲労を反映して、気息奄々といった感じだった。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
日本では、1989年(平成元年)に出版された村上春樹の訳で知られているが、日本で最初の翻訳は、1983年(昭和58年)12月『新潮』に発表された、野崎孝・訳の「あるクリスマス」である。
トルーマン・カポーティの最新作である。作品と仕立て方としては遠く「クリスマスの思い出」(1958)や「感謝祭の来客」(1967)の系譜につらなる。ということは、これもまた自らの伝記的事実を骨格にした短篇小説であり、幼児の追憶という結構をそなえた詩的な散文小品であるということだ。(野崎孝「あるクリスマス」訳者付記)
「クリスマスの思い出」の完全なイノセント・ストーリーとは違って、本作「あるクリスマス」は、父親とクリスマスを過ごす少年の孤独が描かれている。
主人公(バディ)は6歳で、両親と離れて親戚の家で暮している(つまり『クリスマスの思い出』の前年のクリスマスだ)。
サンタクロースのことを僕に教えてくれたのはスックだった。たっぷりとした顎鬚、赤い衣裳、プレゼントを満載したじゃらじゃらと音のする橇。僕は彼女のその言葉を信じた。(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」村上春樹・訳)
まるで少女のように純粋な老女(スック)と離れてバディは、そのクリスマスを(ニュー・オーリンズにいる)父親の家で過ごすことになった。
僕は泣いた。ニューオーリンズになんか行きたくなかった。僕は森と畑と河に囲まれたこの小さな、辺鄙なアラバマの町を、生まれてこのかた一度も離れたことがなかったのだ。(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」村上春樹・訳)
少年時代のトルーマンは、ネル・ハーパー・リーの『アラバマ物語』に登場している。

トルーマン少年にとって、ネルは(スックを除くと)最高の親友だったらしい。
本作「あるクリスマス」では、地元(アラバマ)を離れてクリスマスを過ごす少年の孤独が描かれている。
両親は既に離婚しており、母親はニューヨークで暮らしていた。
「なあ、本当の気持ちを教えてくれ。ニュー・オーリンズに来てお父さんと一緒に暮らしたくないかい?」「それは無理だよ」「無理ってのはどういうことだい?」「だってスックと別れたくない。クイーニーとも別れたくない。僕らはラット・テリア飼ってるんだよ」(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」村上春樹・訳)
「クリスマスの思い出」の美しい物語とは異なり、「あるクリスマス」からは、(ほぼ交流のない)父親と過ごさざるを得ない少年の緊張感が伝わってくる。
それは、両親のもとを離れ、親戚の家に預けられて暮らしている、幼い少年の孤独だ。
当然、父親への愛情なんかあるはずはない(ほとんど一緒に生活したことなんかなかった)。
主人公(バディ)が愛していたのはスックだった。
「サンタクロースは実在しない」という現実を知らされたときも、スックに対する信頼は揺るがなかった。
スックは本当のことを知っていたのだろうか? そして僕に嘘をついていたのだろうか? いや、スックは僕に嘘なんかつきはしない。彼女はそう信じていたのだ。(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」村上春樹・訳)
バディが愛していたのは、スックが持つ無垢な心だった。
純真無垢のスックを愛するほどに、バディの心は父親から遠く離れていく。
息子と通じ合うことのできない父親の描写は、野崎孝の翻訳がいい。
「パパの言うことをよく聞くんだ、バディ。いいか、神さまなんてものはおりはせん! サンタクロースなんてものはどこにもいやしないんだ」(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」野崎孝・訳)
バディが孤独であったように、父もまた孤独だったのかもしれない。
「キスしておくれ。お願いだ。お願いだからパパにキスしておくれ。きみのパパに愛してると言っておくれ」しかし、わたしは口がきけなかった。(略)「言っておくれ。『ぼく、パパを愛してる』と。言っておくれよ。バディ。お願いだ。言っておくれ」(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」野崎孝・訳)
多くの年上の愛人に支えられて生きる父の裕福な生活は、もしかすると決して幸福ではなかったのかもしれない。
村上春樹の解説によると、カポーティにこの作品を書かせた背景には、懐かしき父の記憶があった。
この『あるクリスマス』は一九八二年に発表された作品である。まとまった作品としてはカポーティの最後の作品である。カポーティはその前年に父を亡くしている。彼にとっては父の死はショックであったし、その哀しみが彼をもうひとつのクリスマス・ストーリーへと向かわせたのである。(村上春樹「『あるクリスマス』のためのノート」)
父への思慕は、同時に、スックへの思慕でもある。
ニュー・オーリンズから戻ったバディにスックは言った。
「もちろん、サンタクロースはいるのよ。でもひとりきりじゃとても仕事が片づかないから、主は私たちみんなにちょっとずつ仕事をおわけになってらっしゃるのよ。だからみんながサンタクロースになっているの。私もそうだし、あなただってそうなのよ」(トルーマン・カポーティ「あるクリスマス」村上春樹・訳)
亡くなった父の金庫には、バディ少年がアラバマから投函した父宛てのハガキが残されていたという。
書名:あるクリスマス
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:村上春樹・訳、山本容子・銅版画
発行:1989/12/15
出版社:文藝春秋
クリスマス・プレゼントにおすすめのカポーティ
『おじいさんの思い出』は、クリスマス・ストーリーではない。
それは、幼少期を過ごした家を出て、祖父母と別れたときの思い出を描いた、少年時代の回想譚である。
「なあ、ボビー」とある金曜日の夜に彼は言った。「わしにはひとつ秘密があってな、いつかお前にそれを教えたいんだよ」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
「おじいさんの秘密」は、この短篇小説の大きな柱となっている。
村上春樹の解説によると、本作『おじいさんの思い出』は、カポーティの死後に発見された未発表作品である。
「おじいさんの思い出」はトルーマン・カポーティがその小説家としてのキャリアの最も初期の段階に書いた作品であり、四〇年間未発表のまま埋もれていた。(村上春樹「『おじいさんの思い出』のためのノート」)
トルーマン・カポーティが59歳で亡くなったのは、1984年(昭和59年)8月25日のことである。
1988年(昭和63年)2月『Switch』(Vol.6 No.1)が「美しき子供 トルーマン・カポーティ」を特集したとき、村上春樹の訳による「おじいさんの思い出」が掲載された。
カポーティがこの短篇を書き上げたのは「遠い声、遠い部屋」を書き進めていた夏で、彼はその原稿を伯母(母の妹)のマリー・ルドシーに渡し、「これ、あげるよ。これ、伯母さんのために書いたんだ。伯母さん、バドのこと好きだったろう」と言った。(村上春樹「『おじいさんの思い出』のためのノート」)
トルーマン少年の同居者には、スックを含めた三人姉妹のほかに、世間と没交渉の孤独な兄(バッド)がいた。
口論好きで難しい妹たちに囲まれているのと、喘息で半病人であることもあって、がりがりにやせたのっぽのバッドは自分一人で閉じこもっていた。(ジェラルド・クラーク「カポーティ」中野圭二・訳)
母(リリー・メイ)は、妹(マリー)と一緒に、ニューヨークで暮らしていたらしい(息子トルーマンをアラバマへ預けたままで)。
だから、少年時代のトルーマンにとっては、年老いた三人姉妹と年老いた男性が、いわゆる家族だった。
本作『おじいさんの思い出』は、孤独な老人(バド)の思い出を綴った作品である。
「お前がいなくなると淋しいよ。お前は新しく知りあった人達と一緒にやっていくんだろうが、わしのことを覚えていてくれよな。そしてわしの秘密のこともな。いつかここに帰ってきて、その秘密を二人で分けあおうな」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
彼の両親は、新しい人生を始めようとしていた。
そして、父親は、息子(バディ)にも新しい人生を与えようとしていた。
「俺はこれまでずっとなんだかよくわからんものに縛りつけられて生きてきた。そして相も変わらん貧乏暮らしだ。今、ボビーがそれと同じ道を辿ろうとしている。いいか、俺の目が黒くて働けるうちは、あの子に俺の人生よりましな人生を与えるために何でもしてやる」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
大人たちに振り回されながら生きる少年の混乱が、そこでは描かれている。
彼は都会で暮らす両親よりも、むしろ、田舎暮らしの孤独な老人たちを愛していたのだ。
僕は心の中でおじいさんに懇願した。秘密を持ちだして、僕らが出て行かなくていいようにしておくれよ、と。でも僕はもう幻想に耽ったりはしなかった。(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
孤独なおじいさんは、バディがいつか離れていくだろうことを、もちろん知っていたに違いない。
しかし、彼は、そこを離れることはできなかった。
彼の人生は、そこから離れることのできない人生だったのだ。
「秘密のことを忘れるんじゃないぞ」おじいさんの目がきらりと光って、涙が一筋頬をつたった。「さようなら、ボビー」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
子どもたちが家を出ていった、その翌日に、おばあさんが死んだ。
「どうしたら良いのか、私にはわからない」と、おじいさんは手紙に書いていた。
「まわりの人たちはみんな赤の他人だ。お医者がおばあさんを埋めてしまって、私は一人ぼっちだ。おばあさんと一緒に死んでしまえばよかったと思うこともある」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
やがて、おじいさんが亡くなったという知らせが届いたとき、主人公(バディ)は、「おじいさんの秘密」の意味を知る。
僕にはやっとわかった。そういうのは全部、おじいさんの「秘密」の一部だったのだ。いかに生き、いかに他人とうまくやり、人生を楽しむかという。それは他人に愛され、他人と愛し合うことに関わっているのだ。(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
少年時代の自伝的作品という意味で、『おじいさんの思い出』は『クリスマスの思い出』や『あるクリスマス』と同じ系統の作品と言っていい。
一方で、『クリスマスの思い出』『あるクリスマス』『感謝祭の客』と並ぶ、いわゆる「ホリデー・ギフト・ブック」とは、やはり毛色が違うような気がする。
僕は泣き始めたが、頭にふとこんな言葉が浮かんできた。「これは遺産なのだ。これは僕の過去なのだ。これは僕の人生の一部なのだ」(トルーマン・カポーティ「おじいさんの思い出」村上春樹・訳)
それは、おじいさんとの心の交流を描いた、少年時代の「秘密」の物語だったのだ。
それにしても、カポーティの少年シリーズは、やはりすごい。
子どもの作文と言ってもいいような「少年時代の思い出」が、極めて高いレベルで文学作品として昇華されている。
ひとつひとつの文章表現が巧みで光っていることは当たり前で、全体構成のバランスにも非の打ちどころがない。
そして、目立ったドラマはないのに、完璧なストーリーがある。
カポーティにしか書けないだろうという、オリジナルの世界観がある。
原動力となっているのは、孤独な少年が抱く「家族愛」への憧れだったかもしれない。
長篇小説では『冷血』くらいしか代表作と呼ばれなかったカポーティだが、短篇小説には、実に優れた作品が多かった。
クリスマスは、カポーティを読むのにぴったりの季節である。
なぜなら、雪の降るこの季節は、誰もが少年時代の記憶を懐かしく思い出す季節だからだ。
山本容子の銅版画がゴージャスな単行本は、クリスマス・プレゼントにもおすすめ。
書名:おじいさんの思い出
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:村上春樹・訳、山本容子・銅版画
発行:1988/3/11
出版社:文藝春秋