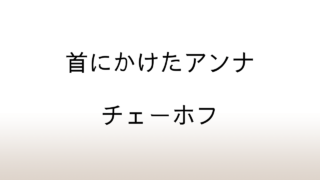山本周五郎「季節のない街」読了。
本作「季節のない街」は、1962年(昭和37年)4月から10月まで『朝日新聞(夕刊)』に連載された長篇小説である。
この年、著者は59歳だった。
単行本は、1962年(昭和37年)12月に文藝春秋新社から刊行された。
1970年(昭和45年)の黒澤明監督映画『どですかでん』原作。
2023年(令和5年)、宮藤官九郎脚本によりテレビドラマ化された(主演は池松壮亮)。
貧民街に生きる人々にスポットを当てた人間物語
本作「季節のない街」は、貧民街に生きる人々にスポットを当てた人間物語である。
全15篇の連作短編集とも言うべき構成は、一つ一つの物語で異なる人物を主人公に仕立てながら、全体として、この名もなき貧民街を浮かび上がらせる工夫となっている。
例えば、本作を代表する作品とも言える「プールのない家」は、犬小屋のような小さな小屋で暮らす父子家庭を描いた物語で、仕事をすることもなく、理想の家を建てることばかり<子供>に向かって話し続けている<父親>が主人公だ。
一家は、子供が<柳横丁>からもらってくる余り物で凌いでいたが、鮨屋からもらったしめ鯖を生のまま食べたため、二人ともお腹を壊してしまう。
自分は回復するものの、子供は死んでしまったので、父親は子供の遺体を墓地の横の空き地に埋める。
「大丈夫、きっと作るよ、きみがねだったのは、プールを作ることだけだったからな、──きみはもっと、欲しいものをなんでもねだればよかったのにさ」雨のしずくがたれるので、彼はまた顔を手で撫で、眼のまわりをこすった。(山本周五郎「季節のない街」)
夢見がちで生活能力のない父親が語る<家物語>は、現実逃避にすぎない。
現代で言えば児童虐待(ネグレクト)だが、子供はそんな父親の夢物語にも従順に従い、死ぬ直前まで父親を愛し続ける。
父親は、子供が危篤の状態にあるときも、あるいは死んでしまってからも、現実を受け入れることができずに、相変わらず家の話ばかり続けている。
まるで何かの象徴のようにも思えるが、貧民街を舞台にしたとき、これは象徴としての物語ではなく、「どこかにあったかもしれない」事実としての文学となる。
一番好きだったのは、15歳の少女<かつ子>を主人公にした「がんもどき」。
実母から離されて伯父夫妻に育てられたかつ子は、実母<かなえ>から「踏んつぶしたがんもどき」とからかわれるくらい器量が悪い。
いつしかかつ子は、街の人たちからも「がんもどき」と呼ばれるようになった。
──わるぎはないんだ、と人は云うだろうがね、とたんば老人は評した。わるぎどころか、みんなは憎んでいるんだな、どんなにはたらいても酬われない自分たちの境遇を、あの子がかたちにしてみせているように感じるからね。(山本周五郎「季節のない街」)
そのかつ子が、実の父親代わりだった伯父からレイプされて妊娠してしまい、何を思ったか、酒屋の小僧を出刃包丁で刺し殺そうとしたのだという。
この話なども、実際にあった事件を題材にしているかのようにリアルで悲しい。
『季節のない街』は『青べか物語』の続編的な作品
本作『季節のない街』の全15篇に出てくる登場人物は、実に多彩で個性的だ。
15篇の短編作品で、それぞれ異なる住民を主人公に据えながら、全体として<街>という一つの空間を描き出している。
作品タイトルは「季節のない街」だが、この街からは、季節ばかりか、時間の流れそのものが失われていたのかもしれない。
なぜなら、人々は、明日のことを考える余裕もなく、今この瞬間を生きるだけで精いっぱいのように見えるからだ。
著者の「あとがき」によると、「季節のない街」にはモデルがあったらしい。
私は『季節のない街』の中でこれらの人たちと再対面したわけである。登場する人物、出来事、情景など、すべて私の目で見、耳で聞き、実際に接触したものばかりであって、『青べか物語』と同様、素材ノートの総ざらえといってもいいくらいである。(山本周五郎「季節のない街」あとがき)
浦安をモデルにした『青べか物語』は、1961年(昭和36年)1月刊行で、本作『季節のない街』は、翌年の1962年(昭和37年)4月から新聞連載が始まっている。
著者の中でも、『季節のない街』は『青べか物語』の続編的な作品というイメージはあったらしい。
貧しい漁師町を描いた『青べか物語』に対し、『季節のない街』は都市部の貧民街を描いた物語ということができるのかもしれない。
『季節のない街』のおもしろさは、それが、日本中のどこにでもあった街かもしれないという、普遍的なおもろしさだ。
さらに、街という生活環境は、かなり改善されたかもしれないけれど、そこで生きる人間たちの悲喜劇は、時代を超えて普遍的でもある。
同居する養子に性行為を強要する「がんもどき」なんて、少女の性被害がモチーフになっているし、貯金に精を出して質素な生活を突き詰めるあまり命まで落としてしまう「倹約について」も何かしら教訓的な物語である。
つまり、『季節のない街』は、時代や地域を越えて、どこにでもある<街>だということだ。
それゆえ「ここには時限もなく地理的限定もない」ということを記しておきたい。それは年代も場所も一定ではないのである。ではなぜこの「街」という設定をしたかというと、年代も場所も違い、社会状態も違う条件でありながら、ここに登場する人たちや、その人たちの経験する悲喜劇に、きわめて普遍的な相似性があるからであった。(山本周五郎「季節のない街」あとがき)
明治から昭和にかけて、貧民街に取材したルポルタージュは、たくさんあるけれど、本作『季節のない街』は、そんなルポルタージュよりもずっとリアルで現実的な作品である。
児童虐待や性被害など、日本が乗り越えなければならなかった課題が、そこにはある。
そして、それは、これからの日本が乗り越えていかなければならない課題でもあるのだ。
古くて新しい小説。
それが、本作『季節のない街』という作品なのかもしれない。
巻末にある開高健の解説もよかった。
書名:季節のない街
著者:山本周五郎
発行:2019/7/1(新版)
出版社:新潮文庫