小沼丹「黒と白の猫」読了。
本作「黒と白の猫」は、「世界」1964年(昭和39年)5月号に発表された短編小説である。
作品集では『懐中時計』(1969)に収録された。
面白い話を作ることに興味を失った
「黒と白の猫」は、作家・小沼丹が、その小説スタイルを大きく転換させた最初の作品として知られている。
どちらかと言えば、それまでの小沼丹は、代表作『黒いハンカチ』に見られるように、ちょっとユーモアのあるミステリー小説の書き手として人気があった。
ところが、1953年(昭和38年)4月に愛妻を病気で亡くした後、小沼さんは、自身の体験を小説として描くようになる。
小説は昔から書いているが、昔は面白い話を作ることに興味があった。それがどう云うものか話を作ることに興味を失って、変な云い方だが、作らないことに興味を持つようになった。自分を取巻く身近な何でもない生活に、眼を向けるようになった。(小沼丹「『懐中時計』のこと」)
最愛を妻を失った悲しみを書くために、小沼さんは、相当の苦心を強いられたらしい。
悲しいことを、ただ「悲しい」と書いてしまっては、それは文学ではなく、一介の感情の吐露に過ぎない。
突然女房の死に出会って、気持の整理をつけるためにそれを小説に書こうと思った。それが「黒と白の猫」だが、無論、こんな場合には話を作る興味も何もありはしない。当時の手帖を見ると、「いろんな感情が底に沈殿した後の上澄みのような所が書きたい。或は、肉の失せた白骨の上を乾いた風がさらさら吹過ぎるようなものを書きたい」と書いてある。(小沼丹「『懐中時計』のこと」)
「いろいろな感情が沈殿した後の上澄み」をすくい取るまでには、およそ一年間の時間を要した。
いろんな感情が底に沈殿した後の上澄み
主人公<大寺さん>の自宅に、近所の飼い猫が勝手に訪問するようになる。
職場の同僚の米村さんに、この話をすると、米村さんは大層喜んだ。
米村さんには病気の妻があって、その妻が、大寺さんの猫の話を楽しんでいるらしい。
やがて、米村さんの妻が病死したとき、米村さんは、大寺さんの猫の話を聞いて大いに笑った。
大寺さんは、米村さんをもっと慰めてあげようと思い、酒を飲みながら将棋を指す約束をする。
ところが、約束が果たされることはなかった。
約束をしたその二日後に、大寺さんの妻が急死してしまったからである。
「全く、妙なことになっちゃった」大寺さんは細君の死の前后の話を簡単にした。もう何人もの人に話したから、云うことは殆ど決っているのである。「兎も角、死ぬにしてもちゃんと順序を踏んで死んで呉れりゃいいんだけれど、突然で、事務引継も何もありゃしない。うちのなかのことが、さっぱり判らない」(小沼丹「黒と白の猫」)
それから、しばらく、大寺さんは、例の猫の姿を見かけることがなかった。
「あの猫、死んだんじゃないかしら?」
娘たちとそんな話をしていたとき、ひょこっと、その猫が現れる。
大寺さんも、その猫は死んだとばかり思っていたから、そいつが昔通り澄しているのを見て、呆れぬわけにはいかなかった——。
物語は、そんな猫の消息を明らかにしたところで終わる。
最初から最後まで猫が主役で、妻の死はまるで脇役、「刺身のツマ」のような扱いである。
しかし、小沼さんは、猫を主役にして、妻の死をあえて脇に添えることで、「いろんな感情が底に沈殿した後の上澄みのような所」を書くことに成功したのだ。
辛いでも悲しいでもない「全く、妙なことになっちゃった」という大寺さんの言葉にも、「いろんな感情が底に沈殿した後の上澄み」のような響きがある。
「黒と白の猫」は、小沼さんの転換地点を示す最初の作品であるとともに、短篇小説の名作として、後世に長く読み継がれていくべき作品だと思う。
作品名:黒と白の猫
書名:懐中時計
著者:小沼丹
発行:1991/9/10
出版社:講談社文芸文庫
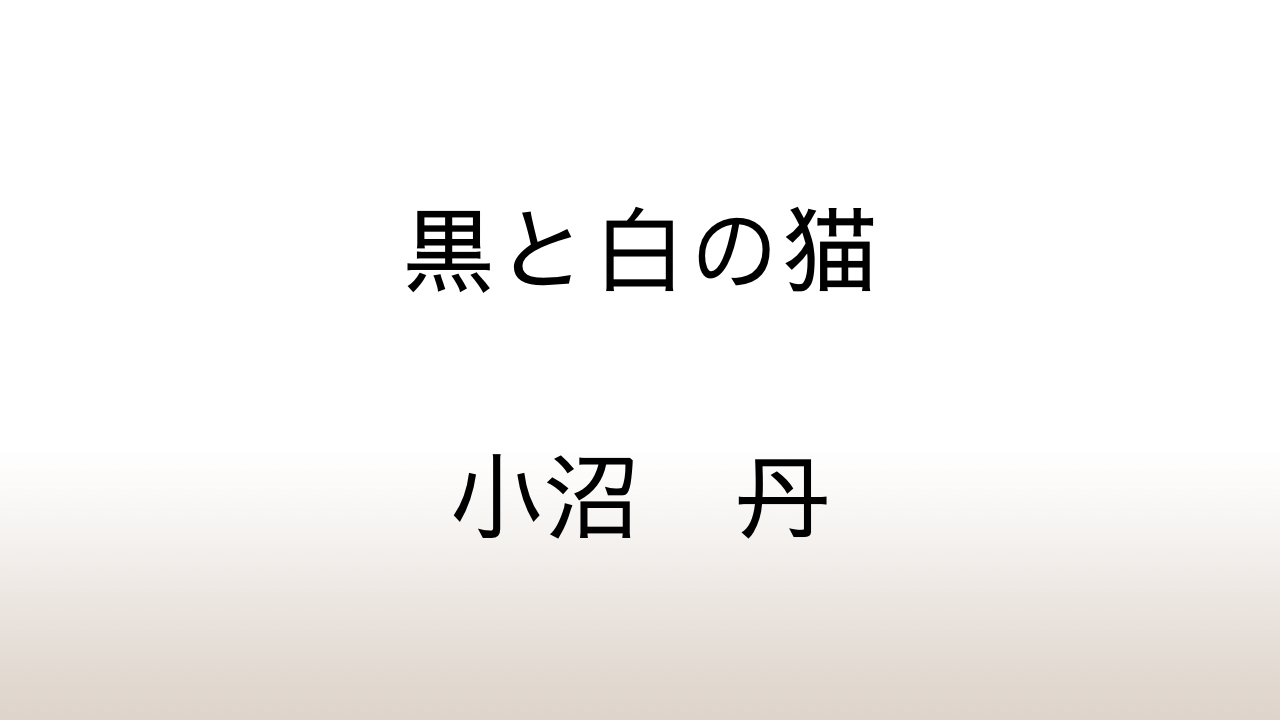


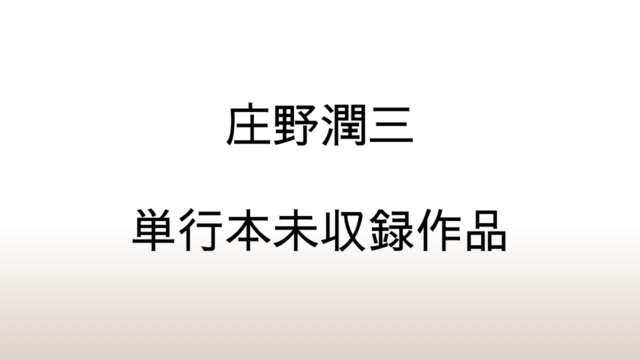

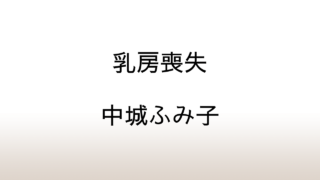
-150x150.jpg)









