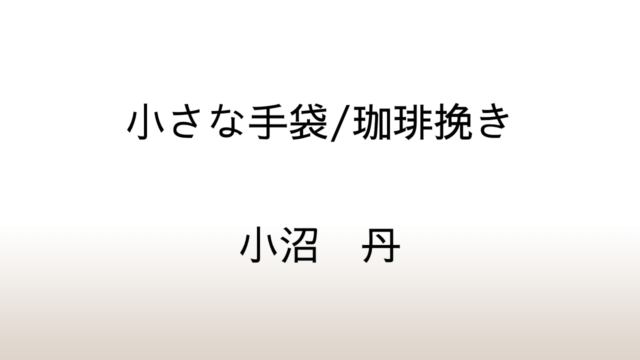宇佐美りんの『推し、燃ゆ』は、居場所を見つけることの難しさを描いた物語である。
人は、なぜ「居場所」を必要とするのか?
「居場所」のない人間は、どこへ行けばいいのか?
そして、そもそも「推し」とは何か?
「推し活」の物語は、現代社会を生きる我々の戸惑いを可視化している。
居場所を見つけることの難しさ
主人公の女子高生(山下あかり)には居場所がない。
16歳の彼女にとって、家庭は居場所ではなかった。
姉が、自分が言われたように小さく息を呑む。どうでもよいことばかりしゃべりながら、姉はずっと母の動向をうかがっている。いつもそうだった。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
単身赴任の父親は不在で、高い理想を持つ母は「当たり前のこと」ができない主人公を受け容れられないでいる(「仕方ないよ」「あかりは何も、できないんだから」)。
学校は、もとより居場所ではなかった。
担任は「勉強がつらい?」と訊いた。「まあ、できないし」「どうしてできないと思う」喉が押しつぶされるような気がした。どうしてできないなんて、あたしのほうが聞きたい。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
原級留置が決まったとき、高校を退学した。
アルバイト先も、彼女の居場所ではなかった。
「やっときたよ」と勝さんが唇をねじまげるように言い、その顔のまま「ちゃんとやんなよ、お金もらってんでしょ」と言った。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
わかりあうことのできない社会生活。
家庭にも学校にも居場所のない彼女が見つけた居場所が「推し」だった。
「推し」の中に自分の居場所を見つけたことで、主人公は初めて自分自身と向き合うことができる。
彼女にとって「推し」は、彼女自身を支える存在であり、唯一の精神的支柱である(「どこにいようと、推しに囲まれていないと不安だった」)。
少なくとも「推し」が(家族や学校のように)彼女を否定することはない。
生きづらさの向かった先が「推し」だった。
ピーターパンは劇中何度も、大人になんかなりたくない、と言う。(略)大人になんかなりたくないよ。ネバーランドに行こうよ。鼻の先に熱が集まった。あたしのための言葉だと思った。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
「推し」を推しているかぎり、彼女は彼女であり続けることができる。
その意味で「推し」は彼女自身であり、彼女のアイデンティティでもあったかもしれない(山下あかりにとって「推し」は山下あかりを投影した存在だったから)。
「推し」が存在することによってのみ、彼女は自分自身の存在意義を確認することができた。
あたしには、みんなが難なくこなせる何気ない生活もままならなくて、その皺寄せにぐちゃぐちゃ苦しんでばかりいる。だけど推しを推すことがあたしの生活の中心で、絶対で、それだけは何をおいても明確だった。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
その意味で、「推し」が炎上したとき、本当に揺らいでいるのは「彼女自身」だったと言える。
「推し」は、彼女のためにも、常に「推し」であり続けなければならない(「推しを推さないあたしはあたしじゃなかった」)。
「推し」とともに崩壊していくのは「彼女自身」である。
「推し」が「ファン」を殴ったように、彼女は「綿棒」を投げつける。
「推しの苛立ち」は「彼女自身の苛立ち」であり、「推しの崩壊」は「彼女自身の崩壊」を意味している。
推しを推すことはあたしの業であるはずだった。一生涯かけて推したかった。それでもあたしは、死んでからのあたしは、あたし自身の骨を自分でひろうことはできないのだ。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
彼女が拾う綿棒は「推しの骨」であり、「彼女自身の骨」でもある。
「推し」という幻影の中に定められた彼女の居場所は、「推し」の喪失とともに消失する。
つまり、この物語は「居場所を喪失することの苦しさ」を描いた物語だったのだ。
「推し」が「推し」であること
しかし、本当の問題は「推し」の側にあったのかもしれない。
「推し」はなぜファンを殴ったのか?
ファンを殴る行為は、「推し」にとって自己破壊でさえある。
もしかすると、それは「推し」が「推し」である現状に満足していない可能性を示唆しているのではないだろうか?
なぜなら、「推し」は「推し」で、彼自分の居場所探しをしていたからだ。
「そのときおれは悟ったよ。あ、作りわらいって誰もわかんないんだなあって、おれが思ってることなんて、ちっとも伝わんねえみたいな」(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
孤独な主人公が支えを求めた「推し」は、実は彼自身が孤独な存在である。
そう考えたとき、この物語は「現代社会の壮大なメタファー」であることに気付く。
現代社会において、人は誰もが孤独であり、常に何か自分の支えとなるものを探し続けている。
時に、それは恋愛であり、部活動であり、受験勉強であり、宗教活動だったりした。
主人公にとって、それが「推し活」だったとすれば、この物語は決して「特別な女の子」のための「特別な物語」ではない。
なぜ推しが人を殴ったのか、大切なものを自分の手で壊そうとしたのか、真相はわからない。(略)でももっとずっと深いところで、そのこととあたしが繋がっている気もする。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
この物語は「推し活」を中心とする「オタク文化」や「SNS文化」の文脈で語られることが多い(あたりまえだが)。
「発達障害の生きにくさ」を描いた小説として読むこともできる。
さらに、母と娘の関係を中心に「女性としての生きにくさ」という視点から考察する、ひとつのジェンダー論として展開することも可能だろう。
しかし、過剰な装飾を除いたときに現れるものは、多くの現代人が抱える「居場所探しの難しさ」である。
学生は「家庭」や「学校(部活動)」や「アルバイト」に居場所を求め、大人は「結婚」や「仕事」に居場所を求める。
しかし、もしも、その「居場所」が失われたとき、我々はどのように生きていけばいいのだろうか。
主人公が見つけた居場所である「推し」でさえ、それは決して永遠の居場所ではなかった。
最終場面に近く、彼女は「推し」が自分と同じ存在であったことに気付く。
何もわかっていない。推しが苦しんでいるのはこのつらさなのかもしれないと思った。誰にもわかってもらえない。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
「人が互いに理解しあうことは難しい」という、悲しけれどあたりまえの事実に彼女は傷つく。
両親が主人公を理解できてないように、主人公もまた「推し」を理解できていなかったのだ。
ある場面で「支える側だった人間」が、別の場面では「救いを求める側」になるという循環構造の中で、我々は生きている。
「気持ち悪い」「共感できない」といった読後感は、もしかすると、我々自身の内面に潜む「不安」から生じているものではなかっただろうか。
それは、我々も「いつかは居場所を失うかもしれない」という不安であり、そのとき、我々は「どこへ行けばいいのか」という不安でもある。
直視できない「不安」を、この物語は掘り下げている。
作者の本当に伝えたかったメッセージは、あるいは、そこに含まれていたのかもしれない。
「推しの喪失」がもたらしたもの
冒頭に登場する「推しの炎上」がもたらしたものは、最終場面で描かれる「主人公自身の居場所の喪失」である。
主人公にとって「推しの炎上」は、スキャンダルなどという言葉では言い表すことのできない「深い孤独」を意味している。
「推しの炎上」により主人公の「居場所」は不安定となり、その意味を誰よりも理解しているのが、主人公の山下あかりだった。
しかし、学校を退学となり、アルバイト先でも失職し、家族を離れて一人暮らしをする中で、主人公の居場所は「推し」しか残されていない。
そこから明らかにされるのは、「人は居場所なくして生きていくことはできない」ということだ。
東横キッズが東横に集まるのは、そこが彼らの「居場所」だからである。
同じものを抱える誰かの人影が、彼の小さな体を介して立ちのぼる。あたしは彼と繋がり、彼の向こうにいる、少なくない数の人間と繋がっていた。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
家庭にも学校にも「居場所」を見つけられない彼らは、路上に自分たちの「居場所」を探り当てた。
「居場所」は、彼らの生命線である。
「推しの喪失」により「居場所」を失った主人公は、一人で立つこともできず四つん這いになる。
這いつくばりながら、これがあたしの生きる姿勢だと思う。二足歩行は向いてなかったみたいだし、当分はこれで生きようと思った。体は重かった。綿棒をひろった。(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
大切なことは「物語はこれで終わり」というわけではない、ということだ。
おそらく、彼女は、自分の「新しい居場所」を探し続けなければならない。
家庭でも学校でもアルバイトでもなく、そして「推し」ではない、新しい何かを。
我々にとって「生きること」とは、常に「居場所」を探し続けることである。
問題は、そんな「不安定な居場所」に頼らなければならないほど、彼女には「居場所」がなかった、という現実だ。
普通に生活することさえ困難な「難しさ」を抱えて、それでも彼女は生きていかなければならない。
それは「居場所探し」に振り回される我々自身の姿にも繋がっていく。
現代社会を生き抜く上で「居場所探し」は重要な問題である。
そこ(居場所は)、我々の存在を「無条件に」受け容れてくれるものでなければならない。
彼女にとって、それが「推し」だった。
「推し」の存在は、居場所のない孤独な主人公の存在を浮き彫りにさせる。
そして、その主人公は、もしかすると我々だったかもしれないのだ。
現代は「居場所探し」の難しい時代である。
傍目からは安楽の居場所に見える空間さえ、当事者には苦痛でしかない場合がある(物語の中の「推し」に象徴されているように)。
「でも、近くにいる人がわかってくれるわけでもないんだよ。誰と話してても、あ、今こいつ何もわかってねえのに頷いたなって」(宇佐美りん「推し、燃ゆ」)
家庭や学校が居場所だった時代は、とうに過ぎ去っているのかもしれない。
それでも、人はみな「居場所」なしには生きていくことができない。
なぜなら、本質的に人は「弱い生き物」であるからだ。
弱い生き物だからこそ、人は誰かにすがり、自分の居場所を確保しようとする(意識的であろうと、無意識のうちにであろうと)。
『推し、燃ゆ』は、「居場所」を失った女子高生の物語だった。
そこには、不安定な居場所に生命を委ねて生きる「人間の弱さ」が描かれている。
生き延びるために、主人公は「推し」を選んだ。
それもまた、現代人に与えられた選択肢のひとつである。
そういう意味で『推し、燃ゆ』は、新しい時代の姿を具体的に描き出していたと言えるだろう。
そして「推し」の先へ
推しが「燃えた」ときに「崩れた」ものは、主人公(山下あかり)自身である。
彼女にとって「推し」は彼女自身の投影であり、「推し」なくして彼女は生きていくことができなかった。
それは、悲しいかな、何かにすがって生きる我々自身の姿でもある。
ただ、ひとつ言えることは「生き延びるために居場所を見つける」という生き方を、我々は否定する必要はない、ということだ。
主人公が、自分の「居場所探し」を素直に受け容れることができたのは、彼女自身が「自分の難しさ」としっかり向き合うことができたからである。
もしかすると、本当に難しいのは「自分の難しさ」と向き合うことのできない、我々の方だったのではないだろうか。
不意に「居場所」を失ったときに初めて気付く「自分の難しさ」が、我々の中にもあるとしたら、この物語は、やはり不気味だっただろう。
なぜなら、「見えていないもの」を見せられる物語ほど、恐ろしいものはないのだから。
書名:推し、燃ゆ
著者:宇佐美りん
発行:2020/09/30
出版社:河出書房新社