浅見淵「新編・燈火頬杖」読了。
本書は、文芸評論家・浅見淵の精選随筆集である。
「新編」とあるのは、昭和45年刊行の『燈火頬杖』とは、収録作品を大きく見直しているためである。
昭和の私小説作家たち
浅見淵は、昭和前期に活躍した文芸評論家で、戦後は長く早稲田大学に勤めた。
本書『燈火頬杖』は「浅見淵随筆集」と銘打たれているが、評論家である浅見淵の随筆は、限りなく文芸評論に近いものが多いと感じた。
例えば「夏日抄」は、瀧井孝作と鮎釣りへ行く話だが、釣り紀行の中にも「「小説というものは、何か他に気を取られていてはよいものが書けるものではない。小説だけに打ち込まなくちゃあ」といわれ、僕はドキリとした」など、文学に関する話は尽きない。
「井伏鱒二会見記」は、早稲田大学の旧友・井伏鱒二との交友録である。
井伏君が早稲田時代の恩師として敬愛しているのは、吉田弦二郎と辰野隆氏とである話などをした最後に、芸術院授与式のエピソードが出てくる。
井伏君の用件というのは、芸術院授与式に代理人として出頭してくれという頼みなのである。「君は最近結婚式を挙げたから、モオニングを持っているだろう? ぼくは無いんだ。それに、神経痛で要害山温泉に出掛けるので、出られそうもないのだ。頼む」(浅見淵「井伏鱒二会見記」)
井伏鱒二は昔からハニカミ屋で、「本日休診」の読売賞受賞祝賀会では、会場の廊下まで引下がって挨拶をしていた昔話なども紹介されている。
「外村繁論」は、タイトルのとおり文芸評論である。
戦後、外村は、尾崎一雄、上林暁、川崎長太郎と共に、私小説の代表作家のように見なされている。そして、亡妻物、再婚物を書きつづけて来ているが、それらの私小説で取扱っているのは、性欲の摩訶不思議、つまり男女関係の純粋な愛情といったものも性欲を通過しないことには成立しない哀しさ、また愛情の追想といったものにも必ず性欲が付きまとっている人間生活のいやらしさ、しかも、性欲と一体不離の愛情なくしては暮らせぬ凡人の恥かしさ、こういった種類のものだ。それと共に、自分じしんの内部にも、家系に流れている淫蕩な血を反撥しながらも、なおかつ、その芽がひそんでいることをハッキリ意識し、これに由来する無常感を吐露している。(浅見淵「井伏鱒二会見記」)
外村繁の流れで「上林暁と酒」を読んでいくのも楽しい。
上林君が一ばん元気だったのは、敗戦の明くる年の昭和二十一年から二十六年にかけての五年間ではなかったか。二十一年には長いあいだ病気だった夫人が亡くなり、当時ぼくは千葉県御宿住まいだったので、だいぶ日かずが経ってから弔問したことを覚えている。が、そのころから、遅筆家の上林君が毎月のように続々と作品を発表しだし、一方、阿佐ヶ谷界隈の酒場や屋台などに、上林君自筆の俳句の短冊がひんぴんと見られるようになった。(浅見淵「上林暁と酒」)
檀一雄と川崎長太郎と梅崎春生
戦後に登場する私小説作家・梅崎春生の話も興味深い。
その頃、浅見淵は、飢えの公園裏の谷中坂町に住んでいて、家主は徳田秋声夫人の墓のある禅寺だった。
同盟通信の仕事をして湯島の方に住んでいた川崎長太郎は、秋声夫人の月命日には必ず墓参りにやってきて、その帰りに浅見淵の家にも顔を出したという。
あるとき、そこに檀一雄が現れ、「最近、静かで落着いた酒場を発見しました。これから行きましょう。川崎サンもいいでしょう」と言いながら、強引に二人を引っ張っていった。
なるほど、静かで落着いてはいたが、その代り、如何にも寂びれていて落莫としていた。客も偶にしか入って来ず、その客も大抵珈琲一杯ぐらいで出て行った。しかし、女子大出で、以前ドイツ人の細君だったという中年のマダムは、僕たちを酷く歓待した。(浅見淵「梅崎春生君のこと」)
これが「シオン」という店で、そのときの珈琲の客の一人が梅崎春生だったそうである。
昭和の文人の随筆には、様々な著名作家の日常が描かれていて、実に楽しい。
最近、僕は文学作品そのものよりも、作家の生活の様子の方がおもしろいと思うようになってしまった。
書名:新編・燈火頬杖
著者:浅見淵
編者:藤田三男
発行:2008/12/24
出版社:ウェッジ文庫
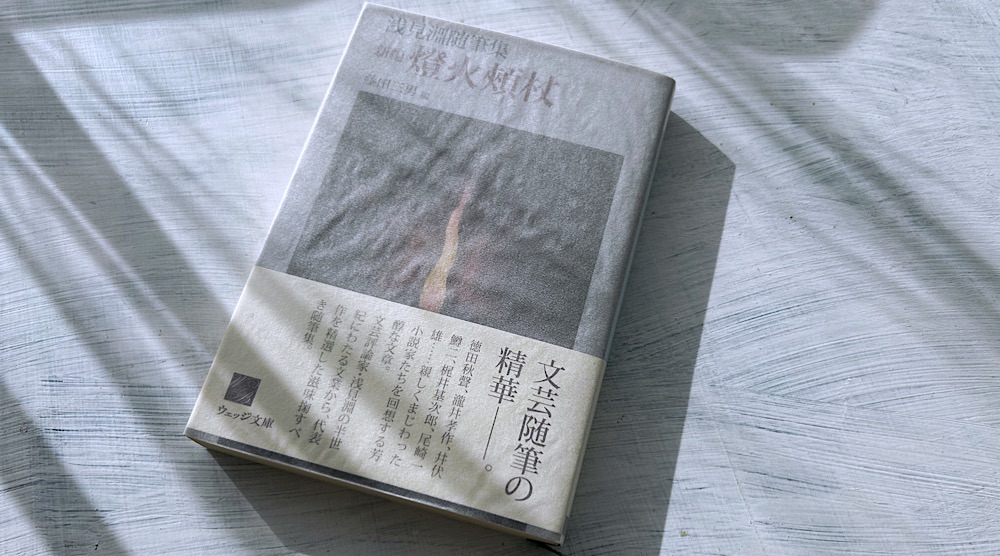




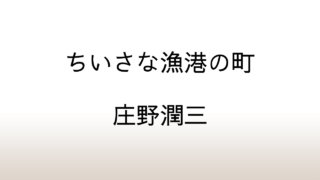
-150x150.jpg)









