福原麟太郎「変奏曲」読了。
本作「変奏曲」は、1961年(昭和36年)7月に三月書房から刊行された随筆集である。
この年、著者は67歳だった。
武蔵野の「野方の里」
「造本」という随筆の中で、福原麟太郎は、『変奏曲』について触れている(『この道を行く』所収)。
出版した人はうちの娘と目白で同級生であった吉川さんという若いおくさんである。雑誌の編集にいた経験で出版をしてみようということであったから取りあえず雑文を集めて提供し、ぼくは小型の本が好きなのですといったのが縁で、右のようなものが出来た。(福原麟太郎「造本」)
「うちの娘と目白で同級生であった吉川さんという若い奥さん」とあるのが、発行人の吉川志都子のことで、三月書房で人気の小型随筆集は、福原麟太郎のリクエストから始まったものらしい(ちなみに、学習院大学は「目白の杜」と呼ばれていた)。
「取りあえず雑文を集めて提供し」と本人も綴っているが、本書『変奏曲』には、実に様々のエッセイが収録されている。
タイトルから目につくのが「野方の里」だ。
福原麟太郎は、自分の生きる街を「野方の里」と呼んで愛した。
野方の里といっても、東京都中野区野方町一丁目のことで、その五七六番地に、この筆者が住まっているのである。その野方の里だ。(福原麟太郎「野方の里」)
福原さんが「野方の里」というと、野方町は、いかにも武蔵野の真ん中にある、良い雰囲気の田舎町に聴こえるが、そもそも「中野」とか「野方」という地名に、武蔵野の名残りがあると、福原さんは指摘している。
その野方の町外れの麦畑を眺める小さな家に越して来たのは昭和二十三年の八月であった。涼風が心持よく入って来た。夜になると、しいんとして、静かで、たよる人もない田舎へ来たという淋しさとともに、老夫婦がやっと生き延びて、どうやら永住的に自分たちの家へ住んだのだという、かくれ家の感じがあった。(福原麟太郎「野方の里」)
昭和23年というのは、福原さんが54歳だった年で、老夫婦と呼ぶには若すぎる気もするが、「老夫婦がやっと生き延びて」という言葉には、いかにも戦争を生き抜いてきたという戦後の実感がある。
おそらく誰もが「やっと生き延びた」時代だったのだろう。
「かすが野はけふはな焼きそわか草のつまもこもれり我もこもれり」という古い和歌を引用して、福原さんは、野方の里の住人となった時代のことを思い出している。
福原さんの随筆には、野方の里を散歩する話も多い。
私はスポーツ・シャツの上へプルオーヴァを着てブレザーを羽織り、すっかり春の若者のいで立ちで昨日は野方の郵便局へ小包を出しに行ったついでに、郵便局から田園の中を南へほとんど一直線に走っている道を高円寺の方へ歩いてみた。(福原麟太郎「春の日抄」)
「郵便局から田園の中を南へほとんど一直線に走っている道」とあるのは環状七号線のことで、高円寺に近くなったあたりの町通りの左側に、フランスの古書を不思議にたくさん持っている小さな古本屋があったらしい(いつの間にかなくなっていたが)。
こういう随筆を読んでいると、自分まで一緒に野方の里を歩いているような気持ちになって楽しい。
篭原観音という、小さな祠の前へ出た。いつもそこで合掌して拝む習慣である。その向いが中学校の運動場で、今日は休日だから町の青年たちが野球をしている。(福原麟太郎「土曜日曜」)
中野区立緑野中学校の角には、今も篭原観音が残っている。

この秋おやじの二十五周忌に郷里から上京した母が、いま八十八歳だが、毎月十七日その他の日にも時々、この小さな篭原観音へ花をもって詣っては、これはわたしには帯江の観音さまだといって拝んでいる。(福原麟太郎「帯江観音」)
「帯江観音」は、岡山県倉敷市の不洗観音寺にある観音様のことだろうが、近所の篭原観音が、福原家の人たちに愛されていた様子が伝わってくる、いい随筆だ。
野方の里で、福原麟太郎は、どのような暮らしをしていたのか。
私は、四十年東京に住んでも味噌汁というものをそんなに必要としない。いまは病気だから万事だめだが、健康の時は、朝飯はお茶漬である。夫婦とも、さらさらとかき込んでそれで終りである。浅づけか、塩こんぶか、福神漬があれば、おかずも充分である。(福原麟太郎「おさなき日々に」)
お茶漬けの味は、東京の人よりも「私たち西国人」がよく知っていると、福原さんは綴っている。
勉強するのに年齢は関係ない
福原麟太郎というと、やはり、読書に関する随筆におもしろいものが多い。
庄野潤三の名前が出てくるのは「『クランフォード』」という随筆だ。
庄野潤三氏の「ガンビア滞在記」を読んで、アメリカの片隅の小さな大学町での日常生活が何の奇もなくただ日記のように書いてありながら、その記録の面白さにつくづく感心したとき、すぐ思い浮んだのは、ギャスケル夫人の「クランフォード」という小説であった。(福原麟太郎「『クランフォード』」)
ギャスケル夫人の「クランフォード」は、1853年に発売された長篇小説で、岩波文庫の『女だけの町 クランフォード』(小池滋・訳)で読むことができる。
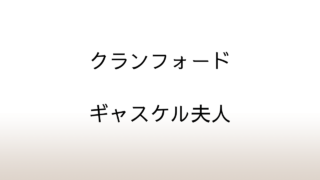
続いて「フィリップにも『小さき町にて』という短篇集があって同じような趣のものであるとこれは井伏鱒二氏から教えられた」とあるところまで含めて、この文章は興味深い。
フィリップもギャスケル夫人も、現代では、あまり話題になることが少ないからこそ、こういう古い書評は、逆に貴重で役に立つものだ(特に、自分のように時代遅れの小説を喜んで読んでいるような人間にとっては)。
森田たまも、福原麟太郎の評価の高い女性作家だった。
じっと坐り込んで随筆を書く。題材は、きもの、たべもの、季節に旅行、身辺のこと。磨かれた感覚、ふかぶかとした記憶、そして、なかんずく練り上げた描写。そうしてできた一篇は、いつのまにか、ちゃんとしたまとまりを備えて、ぴたりと隙がない。(福原麟太郎「『待つ』」)
これは、森田たまの二十冊目の随筆集『待つ』の書評だが、ほぼ絶賛と言っていい。
「彼女は、一生を、そういう随筆一本で通して来た。それは美事なものだ」とまで書くくらいだから、森田たまに対する福原さんの信頼は、相当に強固なものだったのだろう。
本書『変奏曲』で一番優れているのは、何と言っても表題作「変奏曲」である。
これは、島崎藤村の自伝的長篇小説『春』の感想を綴ったものだが、この作品中に登場する青年たちは、後に福原麟太郎が師事することになる英文学者たちの、若き日の姿だった。
私自身にとっては、私がその晩年をよく知っていたといってよい平田先生や戸川先生のお若いころの姿が実在の人のごとく写されているのを、なつかしく思うのである。モデルでも何でもよい。この人が若き禿木であり、若き秋骨であると思って読むのだ。(福原麟太郎「変奏曲」)
平田禿木や戸川秋骨のほか、馬場孤蝶や北村透谷らが登場する『春』(明治41年)は、明治後期に二十代を過ごした人々にとって、重要な青春小説だったらしいということに、僕は、福原さんの随筆を読んで初めて気づいた。
ともすれば、古典と思われがちな文学作品も、その頃には、瑞々しくて熱い血を感じる青春小説だったのだ(考えてみれば当たり前だけれど)。
平田先生の亡くなられたとき、島崎さんはとうとう弔問に来られなかった。そのとき私は告別式にくらい来て下さればよいにと思ったが、いま私も六十を半分も越してしまってみると、島崎さんの心持がわかるような気がする。つまり、もうみんな死ぬ年なのだ、ああ君がさきに行くのか、というような感じである。(福原麟太郎「変奏曲」)
青春の日の思い出は、やがて老境へと話題は移り、「焼香という儀礼など、あってもなくても友情には関係ないのである」という結論へと導かれていく。
平田禿木(享年71歳)も島崎藤村(享年71歳)も、亡くなったのは同じ昭和18年で、「ああ君がさきに行くのか」という言葉には、おそらく実感があったのだろう。
戸川秋骨は昭和14年に70歳で、馬場孤蝶は昭和15年に72歳で、それぞれ亡くなっているから、「つまり、もうみんな死ぬ年なのだ」という言葉にもリアリティがある。
そして、このようなお年寄りの人たちにも、熱い青春の日があり、その生々しい記録が『春』という長篇小説であったというところに、この随筆のポイントがある。
これは、もう書評という域を越えて、やはり随筆文学という一つの文芸作品だと思わないわけにはいかない。
ちなみに、戸川秋骨の名前は「銀座というところ」にも登場している。
私のただ一つ安んじてゆけるレストランはモナミであった。コーヒーを一杯のめるところは教文館の下の喫茶店しかなかった。ときどき映画の試写会が銀座であった。その帰りに、その喫茶店の椅子で一休みしていると、戸川秋骨先生が、よく花のごときお嬢さんがたに囲まれて、同じくコーヒーをすすっていられたりした。(福原麟太郎「銀座というところ」)
福原麟太郎の随筆集には、書評が多く含まれているので、昔の文学作品を読もうと思っている人には、大いに参考になると思う。
旅行文学というものは、田山花袋以後だめになったのかと思ったら、ちかごろ日本旅行文学選集、世界旅行文学選集のごときものが広く読まれているという。旅行記というのは美文で風景を写すのではなく、個人の覚え帖程度でも、十分面白いものだ。(福原麟太郎「旅行案内」)
1958年(昭和33年)には、修道社から『現代紀行文学全集(全10巻)』が発売されているから、当時は旅行文学というものに関心が高かったのかもしれない。
それから、英文学などの作品で、今まで読むべくして、読まなかったり、よく読んでいなかったりしたものを、ぽつぽつ読んでいる。これは罪ほろぼしのようなもので、いかにもよく知っているような顔をして、そんな本の話をして来た。(福原麟太郎「この空しき日々」)
福原麟太郎にして、「今まで読むべくして、読まなかったり、よく読んでいなかったりしたもの」があるというところに、我々庶民は勇気づけられる。
このとき福原さんは60代後半で、『チャールズ・ラム伝』のような晩年の大きな仕事は、この後に生まれることになる。
つまり、勉強には年齢なんて関係ないのだということを、この随筆集は教えてくれているわけで、そこに、老齢の作家のエッセイ集を読む意義がある。
人生の後半を、どのように生きていくべきかということを、福原さんは身近な随筆を通して、後進を行く人たちに教えてくれていたのかもしれない。
書名:変奏曲
著者:福原麟太郎
発行:1979/04/25
出版社:三月書房(ルビー選書)





















